注目すべき点を話そうか^^
(2015年12月29日 | 日記より)
氷に覆われていた時期から火山活動や地殻変動を再び活発化させ温暖な気候を取り戻した、
って言ったろ。
どうやらこの時期にシアノバクテリアとは違う生命(真核生物)が登場したらしい。
何よりも、過酷な環境でも生きられるシアノバクテリアが整えた環境に適応する生物ってことだよ。
けどそれはある限られた場所で登場したのか?
それとも世界中にほぼ同時期に登場したのか?
さらに、
二度目の冬眠から目覚めた時の
爆発的発生に見える生命の多様化(カンブリア紀の爆発)は何故か。
そしてさらに、
古代から現在の日常と、さらに未来に目を向けた時、
誰も知りえない空白の時間はどれだけあるだろうか^^
気にならない^^
まず始めに言っておくけど、
物語や学説や哲学は馬鹿にされるほど関心を引き寄せるお話はない。
(きっと今頃、多くの研究者がSTAP細胞を探しているだろうね^^)
始めに馬鹿にされなければまったく興味のない無味乾燥で無害なお話しだってことだよ^^
さぁ~元の話に戻そう^^
まず、
生命はある限られた場所で登場したのか?
それとも世界中にほぼ同時期に登場したのか?
これには地球誕生とともに構成された偶然の仕組み、
いずれは『自然の秩序』って言われる仕組みが関係してくるのだろうね。
『あるものがあるものと混じり合い、
あるものになる。』
鉄が酸化し錆びてしまようにね^^
『偶然と言えば偶然で、秩序といえば秩序のような仕組み』にのっとり、
長い時間をかけて混じり合ったものが、
(どのあたりで生命と呼べるかはわからない^^)
何世代もの時間を経てシアノバクテリアを登場させた。
きっと始めはほんの一画の局所的な登場だったと思うよ。
局所的な発生は小さなコロニー(ストロマトライト)をいくつか作っていった。
それとともに、地球は何度かお昼寝をするようになるだろうね^^
(このわけは、2015年12月29日 | 日記をもう一度読み直して)
何世代もの時間を経て過酷な世界でも適応することの出来る生命だから、
お昼寝中の地球環境でも絶えることはなかったと思うよ^^
むしろ再び訪れる温暖な時期には進化を遂げたと思うよ^^
何故かって?^^
温暖な気候に向かうときには、
とけた氷河に乗って外国へ移住するものが現れたっておかしくないだろ^^
そして、
辿り着いたころの環境が今まで住んでいたところの環境よりも、
多少でも違いがあるなら適応方法は変わってくるだろし、
他のバクテリアたちが占領していないとも限らないからね。
過酷な上に過酷な状況があったかもしれないよ^^
そしてこれは、
分布に関係して、
大量発生や衰退や絶滅にも関係するよ^^
お昼寝から覚め再び大量のガスを排出する地球は、
シアノバクテリア出す酸素と(メタン以外とも)化合してゆく。
それを何度も繰り返していくうちに、
『あるものがあるものと混じり合い、
あるものになる。』原理は増加してゆく。
そして、『偶然と言えば偶然で、秩序といえば秩序のような仕組み』で
別の生命を誕生させた。
でもこの生命は、
シアノバクテリアと地球が整えた世界でしか生きられない生命だ。
そしてこの生命は、
シアノバクテリアが(偶然か秩序か)移動してきた環境において
適応的だったか不利だったかということだけで
登場を限定したり、させなかったり多様であったりしただろうね。
結果として、
地球が眠りから覚めたと同時に
生命は偶然と秩序を増やすことから始め、
偶然と秩序からの移動を利用し、
偶然と秩序から選択されたものだけが利点を獲得した。
時間的にはランダムで、恵まれた(偶然と秩序のある)地域から順々に登場させたのだと、
思います^^

















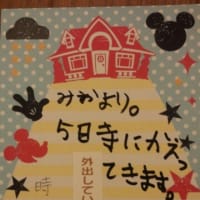


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます