不安とは、まさに現実に再現されたくない予測によるダメージである。その予測は、たいていが認識している観察経験と言語による方向づけに依存し恒常性を維持ているようだ。また、不安から逃れるための解決策も逆の意味で同様であり、異なる個体への関係を不安の一員とすることで解決策を導くことができる。つまり、不安から生じた感覚を他者に教育することにより恒常性を維持するのである。それは環境内(社風・学風・地方文化)で育まれたプライドと呼ばれる認知領土の中より確認された不安(攪乱)への合意を、条件とする。もちろん認知領土以外の場所からは予測は不可能であるものだから、合意条件は(ある意味)恒常的状態になる。それが歴史的・時間的に継続をすれば、所属の違いだけにも現実を揺るがす予測(たとえば戦国の世)は回避できなくなるのも当然の過程であろう。また、観察経験と言語による方向づけがわがままな機能を有している場合、環境は多数(部分)に分離し多数の独立した非政治的な環境を生み出すだろう。この場合、不安は不安とは理解されず(不安そのものではあるが)、分離した多数の部分によって構成される条件から特徴づけの行為と認識される。また、その他の独立したかのように思える特徴を攻撃することにより、環境を恒常的に維持する言説(方向づけ)を欠かすことのできない観察を余儀なくされる。解消されたはずの不安は自己を守るための反作用とし、その作用の維持を自己とするようになり場の過程の中で、散らばった部分の観察をダメージとする。そして、言説の環境が破壊されるまで、その円環に生命は続くことになる。その破壊とは、部分の環境のつながりに不安を感じるまでは、攻撃への対応をやめることができない自己への破壊である。
俺は、どうなんだろう・・・・?自分が何なのか?・・・・わからなくなってきた・・・・。でも俺は、この対象を壊さなくてはならない!ただ、わかるのは、「環境が破壊されれば生命の存在はなく、生命のないところには環境は存在できない」と、いうことだけだ。

















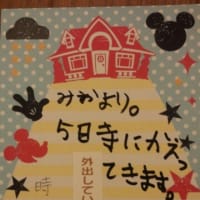


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます