では、新しいレンズで「施工管理工程表」を観るとするなら、まずニュートンの力学時代から続く「直線的・線的・計算的」ノウハウと、ヒエラルキー社会で教え備わった経験を一時、停止して観ることも必要となってくる。私が知る突貫工事の現場内で、分断さているものを探ると一番最初に目に付くのが「管理する側」と「管理される側」の行動だ。一方はニュートン力学の保持者。もう一方はローカル(スポット業者を含む)な部分、現場内の熟練された技術と経験の保持者。共に互いに繰り出す経験と分断思考が「カオス」を生み、そして互いに「カオス」と戦う戦士である。ニュートン力学の保持者は、平均化された細部は含まぬ線的な工程を作り出し完璧に行おうとし、初期値鋭敏性という性質に気付かぬまま工程の遅れをローカルな部分に突きつける。これを変化を知らない又は、恐れるニュートン力学の保持者は又は、組織は同じことを何度も繰り返す。一方、ローカルな部分、技術と経験の保持者は、経験による感とコミュニケーションを頼りに工程を予測する。全体から観て細部を見つけ出し、それも工程の一部として無視をしない。しかしながら、「管理する側」から与えられた工期(最近では工期短縮が目に付きあちらこちらに作業員を奪われ、しかもローカルな部分の若者が減ってきている)に間に合わさなくてはならない。ローカルな側は「管理する側」の古い時代の体系に、まるで戸惑っているようにも感じる。同じように「管理する側」も顧客に対し「出来ませんでした」とは言えない。互いのもつ、複雑な関係の中での共通とは何か?
《ここでニュートン力学とヒエラルキー社会で学んだものを一時、停止してみよう。》
互いに共通してかかえている問題は何か?それは作業員の数でも、しっかりとした作業でも、させる力でも、安定した工程でもない。孤立し閉じられた世界を創り出す断片化する負のエネルギーを全体の中で共通の意味を持つ正のエネルギーに変化させることにあるように思える。そのためにはまず、「管理する側」と「管理される側」の「自己再生」のために導くための「動機」が必要だ。そして、偽りのない「自由な情報」と「自由に歩きまわれるビジョン」と「個人の意味」が必要不可欠となる。そのことに餓えていることすら気付かない知識の中には断片化する記憶と文化があり、予測と制御に関わる仕事だけをしている。それの改善が必要ということだ。
餓えていることにすら気付けないのも十分な病理だ。実はその餓えがミソなのだが、たいていの人はそれを目の当たりにするまで避けて通り「秩序」を「安定」と信じている。餓えしのぎで、ある人が成功した知識と経験について知りたいと躍起になるが、実は成功した者は成功した理由を外乱の中の真実として語るだけで、実際の意味は知らせない、と言うか気付いないのだ。その語りの「10」の内「3」は話すが、残りの「7」は全体の内のローカルな部分に当たるため、つまりその時の「感」で動いているため話せないでいる。それよりも語れないのだ。例えば、目標を達成しようとし始に設定したものが行動の結果、計画にあったものとは違った結果となる。それは「予測」とは違い「感」で行動している時間が招く、「初期値鋭敏性」だ。だから、成功者まねして上手くいかないのが当たり前の現実だ。ある者のまねをしてその者に近づくことはできるが、その者になることは出来ない。しかし、その者の観念は知ることは出来る。後はどうやって「感」を育てるかだ・・・・。
ローカルな部分に触れずして全体は見えてこない。乱雑と外乱を恐れていては「感」を磨くことは出来ない。乱雑と外乱の真実を知る能力は、「感知器官」を育てるための重要な経験となる。小さな部分を知る能力の発達のために極めて小さいローカルな部分も知ることは、「全体」の中の必要性を生み出す。ある人にとっては奇跡かのように感じられる出来事になり、ある人にとっては文化に育て上げる実在する「モノ」となる。

















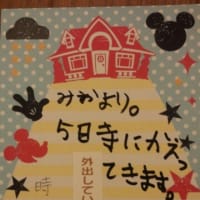


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます