男ジャム(その1)(宗谷支庁:サロベツ原野) (2007年8月17日)
Ⅰ 人 学ばざれば 即ち 道を知らず
さて、偶然号が、ここサロベツ原野に到着したときは夜。北緯ちょうど45度あたり。真夏だというのに夜はぐっと冷え、空気の透明さに磨きがかかる(やはり衣類は乾いたものにかぎる)。遮るもの、道ゆくものもほとんどなく、海は少し離れているのに耳元で響く。その夜は余力があり、小川のわきにテントを設営した。そして、さすがにここまで来れば川も清流であろうと、近くの水たまりで米を研いで就寝。
翌日は夜の晴れ上がりに反して霧。真っ白い中で目覚める。米を炊いている間、テントの周囲を歩くと、濃い白の中に鮮やかな色が見え隠れする。夢の続きのような色ながら、眼を見開くような清冽さ、ハマナスの紅い実や名前を持たない青い実が群生している。
さて、飯が炊けたので朝飯にしよう。コッヘル(鍋)のフタを明ける、勢いよく湯気があがる。その下には茶色い飯。あれ?炊き込み飯なんか作っていないぞ。一瞬、“こりゃ何じゃ顔”になるがすぐに合点。サロベツの植生はピートという植物残滓が重なっており、地面の基層は琥珀色。そして、川水もその琥珀色に染まっているのだろう。
「なーに、ピートと言っても、スコットランドじゃモルトと呼んで、スコッチ作りに利用しているぐらい。さぞかし、深い香りがするのだろう。」と少々期待して一口。すると口に拡がる“こりゃ何じゃ感”。ひどーい匂い。しかも深い。この匂いは何だか記憶あるぞ~、これは牛舎の匂いだ。当然、同じ水たまりで作ったみそ汁も牛舎の香りを漂わせ、ここに“サロベツ原野 暁の精鋭朝飯部隊”はあっけなく壊滅した。しかし、物事は簡単にがっかりしはいけない。「まあ、今日はパンがあるからいいや」と気分を切り替え、パンを取り出す。パンはあったが「あ、チーズとハムが無い。」探せど、探せど、出てこない。えーい面倒だ、とバックを逆さまに、するとバックからこんにちはと出てきたのは、お茶漬けの元、味噌、塩辛と干し昆布-----
うぇ~パンと一緒に食べたくないなー。
どうやら、別袋に入れていた洋食系素材は前日の宿泊先(天塩)のババア自殺騒ぎのどさくさに亡くしたようだ。ちなみにサロベツもここまで来ると、もはや食料店、レストランなど期待できない。「パンに塩辛つけて今日一日か」ここに来て、ようやくがっかりし、同時に教訓に背いた自分を責める。
教訓。そう、どさ日記と称する、この自転車旅行は、根性入ったこだわりやら自制的なルールなどきっぱりとない。が、ただ一つ「暗闇でメシを作るな」という経験則があった。
真夜中まで走り、疲れ切って、闇の中で炊事をすると色々な思い出ができる。今までの思い出から少し。
1.デスペラータ
パスタを作る時、塩味はソースにつけず、パスタにつけるのがおすすめだ。どういう訳だか味に落ち着きがでて、あれこれ複雑な味付けが不要となる。コツは、塩なんかケチんなよ、である。“死海のように濃くしな、つまむんじゃなくて、掴んでぶち込め!”とやる。そして、その夜も真っ暗闇の中、手探りでパスタを作ったものさ。夜空に広がるガーリックの香りが鼻腔をくすぐる。アンチョビは焦がさないように、出来上がりはきちんと手擦りのパルミジャーノをふって、できたぜ、芳しきスパゲッティ・アッラ・デスペラータ(絶望のパスタという意味らしい。由来不明)。一日の疲れなんてさっと料理して、その日のうちに食べてしまおうぜ。「いただきまーす」。フォークでかき上げ、かっ込む。
“う゛ほっ!”
何があったか分からない。が、口腔から喉にかけ、殴られたような感覚が走り、思わず、むせこむ。思い切りむせこむもんだからから、ほれ、スパゲッティ・アッラ・デスペラータは鼻腔まで侵入し、それがまたなんとも言えない痛みを鼻から脳天にまで広げる。
この激痛の正体はクエン酸。塩の瓶を闇でクエン酸の瓶と取り違え、コップ一杯強のクエン酸を全て鍋にぶちこんだのだ。クエン酸と言っても、コンビニで売ってるサプリ系の爽やかクンじゃないよ。味覚矯正用の添加物等をなぞ一切ない超硬派、純原粉野郎だよ。(疲労回復には心強い味方だが、まともなときに嘗めると、ちょびっとでも酸味というか、痛みが口の中を走る。)結局、鼻の中から脳天に達する痛みは数時間続き、次の一日はなにかしら集中力に欠けた。
2.私と生態系
まず、夜中に静かな湖畔に到着しましょう。夜の湖畔ほど神秘に近いものは、宇宙まで行かなければないような気もします。純粋な黒。漆黒の森に誰もいません、かすかな波音が安心のように満ちています。そのかすかな音の元、おや、中年が米を研いでいますよ、シャリシャリシャリ。中年は思いました「うーむ、米で良かった。これ小豆だと、確かそんな妖怪がいたような気がする。」などと、あまり妖怪と変わらないシチュエーションの中、中年は全く意味の無い安堵感で米を研ぎ終え、そして炊きました。
あらためて、夜はつややかに美しいものです。空間の底から滑らかな感覚の群が降りてきます。美しい沈黙、美しい風の触覚、美しい香り、あれ?少し臭いな~。それはそれ、湖だからね、飯を炊いた香りが少しぐらい泥臭くても我慢我慢。さあ、炊き上がったご飯を頂きましょうね「いただきまーす」。ふわりと箸ですくい、静かに口に入れる。と?
“生臭せぇー!“
噛めば噛むほど強まる生臭さ。何よこれ?それに飯の中に何か混じってるじゃないの。ぐにゅこりっとしたやつ。何よこれ?さあ、中年よ、悪い予感にひるまず確認しませう、己が今何と対面しつつあるのか。人はみな単に忘れているだけで、生態系から逃げることはできません。
そして、中年は朧な光の中で、飯粒をじっと見つめました。白い白いご飯の間に、黒い黒い大豆大の粒がびっしりと混じっています。もしや、もしや-----。中年は、その黒いモノをそっと掬い上げ、手のひらに置きました。大豆くらいの黒くて丸い粒。そして、その端には尻尾のようなものが縮れて付いています。そう、中年の予感は、いまここ、手のひらの上で「おたまじゃくし」という形で結実していました。
3.重力と恩寵
早朝から真夜中まで思い切り走り込み、文字通り精根尽き果て状態で止まることがある。そこが波立つ浜辺でも、危なかしい崖下でも、そこいらの田んぼの端っこでも関係ない。これ以上一漕ぎもできないというところで、バタと地面に寝ころぶ。爽快感この上ない。生きている恩寵のようなものまで感じる。が、若くない身にとっては疲労感もこの上ない。もう疲労回復には休憩ですむような時間ではぜんぜん足りなくなってしまった。つまりはその場で野宿ということなのだが、これがまた安易に宿るのだ。
まず、テントなぞ張る余力はないから、バックから荷物をぶちまける。そこからシートと寝袋を地べたに引いて寝ころぶ。続いて、寝ころんだまま、必要な物に手が届くようあれこれ、それなりに配置しなおす。独身寮時代の部屋か、開発途上国の露天商と似た姿になれば出来上がりだ。そして、寝ころんだまま、何か食べよう、ガサゴソ。けど、そういう時に限って、パンのようにすぐ食べられるものが無いのね。ちぇ、面倒くせー、ラーメンでも作るか。んで、寝ころんだまま、先ずウィスキーをガボッ。寝ころんだまま、コッヘルに水を入れ、ウィスキーをガボッ。寝ころんだまま、ガスに火を付け、ウィスキーをガボッ、ガボッ(俺って器用!!)。
程なく、アルコールが疲労感に染み渡る。寝ころんだ視線の先、天球の頂で星が動きだす。視線がゆっくり、大きく回り、宇宙も北極星を中心にゆっくり、大きすぎるほど回り出す。この大きな動きは、主観的にはアルコールに、客観的には万有引力にしたがう。ごちゃごちゃしたルールがないことの安らぎ。日常からの自己蘇生なんだな。さながら恩寵のような安らぎ。さあ、ラーメンが煮えた、スープを入れよう。そして、寝ころんだまま粉末スープを顔の上でピッ。すると粉末スープは重力に従いドサッと顔の上に落ちます。“うがっ”、目といい、鼻といい、欲しいままに散乱する粉末たち。そして、人間ですもの思わず跳ね上がります。すると次は、コッヘルがひっくり返り、煮えたラーメンが、手の届く荷物の上すべてにぶちまかれて完成です。

さて、このような“うーん”な記憶の数々が脳裏を巡り、自分の前には“パンドラの箱”からぶちまかれたように塩辛などが転がっている。何も考えたくない。ただ黙ってそれらを片づけようとバックを持ち上げた。すると、バックの底から
「開けてください、開けてください」
あれ、今のは?と中を見ると、それは希望という名の砂糖でした。
*
砂糖はドンと一袋(1kg)。荷物の重量を絞り、着替えさえ最小限に抑えている旅に、なぜこんな無駄な荷物があるのだ?と訝しがる方もおられるであろう。先ほど、どさ日記には根性入ったこだわりは無いと書いたが、実は、その他なこだわりならいくらでもある。その一つが、“どさ旅は可能な限り自給自足”というもの。今回はアルコールの自給自足にこだわった。つまり、人気の少ない道北では、いつ酒が切れてもおかしくない。ならば、アルコールなど自分で作れば良い!と砂糖と酵母菌を持ってきていたのだ(もちろん、毎回そんなことを繰り返すが、うまくいったためしはない)。
そして、砂糖を見た瞬間、それは先ほど草原に光っていた木の実と直感的に結びついた。
“ジャムだ”
そう、この不遇な朝飯に対する希望は今こそジャムとなって光る。もちろん、辛党な自分は、ジャムを作ったことはない。しかし、木の実をテキトーに潰して砂糖で煮れば、それはジャムである。そう確信した自分は、即座にヘルメットを籠代わりにして、木の実を集め始めた。ああ、眼の前には、希望の畑のように、紅い木の実が延々と拡がる。
(その2へ続く)











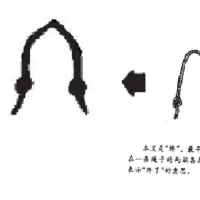



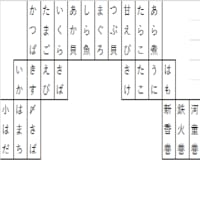
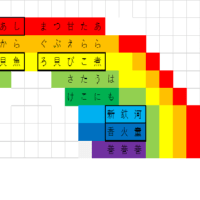
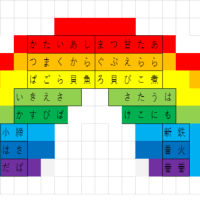


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます