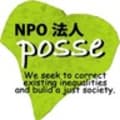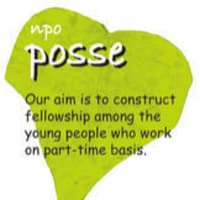5月10日に、市立の小学校教諭であった木村百合子さん(当時24歳)が自殺したのは仕事上のストレスによるうつ病が原因であるとして、公務災害の認定をご両親が争っている裁判の控訴審裁判の傍聴に行ってきました。
●事件の概要
亡くなった木村さんは、2004年に教員採用され、新任の教師として4年生のクラスを担当することになったのですが、発達障害をかかえる児童が授業中に暴れるといった問題に直面しました。保護者からは苦情が寄せられ、問題を一緒に解決すべき同僚、上司からは子供の目の前で叱られ、「お前の授業が悪いからクラスが荒れる」、「問題ばかり起こしやがって」、「アルバイトじゃないんだぞ」などと言われ支援を受けられず、木村さんは孤立無縁の状態に置かれてしまいました。さらに、授業の準備や教材の研究といった事務作業のために長時間の労働を強いられ、次第に心身ともに疲労し、木村さんは教師となって2ケ月余でうつ病を発症し、2004年の9月に焼身自殺されました。
木村さんのご両親は、木村さんの自殺の原因は仕事上のストレスによるうつ病が原因であり、公務員の労働災害に当たるとして、2004年の12月に地方公務員災害補償基金静岡支部に公務災害の申請をしました。しかし、同支部はその3年後に、パワハラという事実が無かったこと、初任者研修等で十分支援をしたこと、残業は月20時間程度であったことを根拠として公務外認定を行い、請求を棄却しました。再審査請求も棄却され、ご両親は公務外とされた処分の取り消しを求め、2008年に静岡地裁に提訴し、争いは法廷へと進んでいきました。
●裁判の経過
1審は3年余におよび2011年の12月に静岡地裁は「公務外災害認定処分取り消し」という木村さんのご両親側勝訴の判断を下しました。判決の中で、裁判所は木村先生が着任後わずか2ヶ月でうつ病に罹患したと認定した上で、「木村先生が担任していたクラスは、指導に困難を要する複数の児童らの問題が当初から顕在化し、数々の問題行動が発生していた」とし、多動性・衝動性を示す児童について「学級担任を勤める教師として通常担当するであろう手のかかる児童という範疇を超えた、専門的個別的な指導・対応を要する児童であるというべき」「新規採用教員に対し高度の指導能力を求めること自体酷」とし、木村先生は「苦悩しながらもできる限りの努力や責任感を持って同児童に対応していた」と評価しています。また支援体制については「こうした状況下にあっては当該教員に対して組織的な支援体制を築き、他の教員とも情報を共有した上、継続的な指導・支援を行うことが必要であるところ、本件全証拠をもってしても、かかる支援が行われたとは認められない」としています。このように静岡地裁は、木村さんが置かれていた状況について具体的な事実を丁寧に認定し、木村さんの負っていた業務の精神的負荷の大きさについても「上記公務は緊張感、不安感、挫折感等を継続して強いられる客観的にみて強度な心理的負荷を与えるものであった」として新任の教師の側に立った視点で評価しています。
この静岡地裁の判決に対して公務員災害補償基金側が控訴したのですが、今回傍聴したのはこの控訴審裁判です。
●東京高裁の様子
控訴審が開かれる東京高裁の808号法廷に行ってまず驚いたのが、傍聴を望む人の多さでした。裁判は基本的に平日に行われます。にもかかわらず、100名程度の傍聴希望者がおり、希望者全員が法廷の中には入れないという状態になっていたのです。私自身も裁判を直接傍聴することはできず、裁判の直後に開かれた報告集会で今回の期日でのやりとりを知るという状況でした。報告集会では、今回の裁判を担当されている弁護士の方々が法廷内でのやりとりや裁判所に提出した証拠資料についての解説をして下さいました。この報告集会も用意されていた会議室から人が出てしまうという状況の中で行われ、今回の裁判を支援している人の多さを感じさせました。
●教師の過労死は個人的な問題?
では、なぜ今回の裁判を支援する人が多く存在するのでしょうか。その理由は、木村さんが遭遇した問題というのが個人的な問題ではなく、教育の現場において現在広がっている問題であるというところにあります。平成20年度には、新採用の教師のうち304人の方が退職しているのですが、そのうち精神疾患をかかえて退職している人が88人もいるのです。
また、精神疾患により休職する教員は、この10年間で2,4倍になっています。
そして、うつ病を発症する教師が増加している背景には、膨大な事務作業をこなさねばならないことによる長時間労働、木村さんが遭ったような孤立化などを経験する教師が増えていることにあると思われます。
木村さんが直面したような問題を抱え、悩んでいる教師の方が少なからず存在しているというのが今の日本の教育現場の現状であり、そのことを原因に命を落としてしまう人もいるのです。
「木村先生に起きた悲劇を二度と繰り返させたくはない」、そういった思いが今回の裁判を支援している人々の根底にあるのです。そして、私たちも他人に起きた問題だとして無視するのではなく、この事件を契機として教育の現場で起きている問題を考え、それに対してどのように対処するかを考えいかなければならないのです。
●今回の裁判傍聴を通して……
最後に、今回の裁判傍聴を通じて私が特に感じたことを述べていきたいと思います。
報告集会の締めくくりとして、木村さんのご両親からのお話があったのですが、それが私にとって印象的な内容でした。どういった内容であったかというと、「つらいけれども、支援して下さる人たちがいるから、頑張って来られました」という旨の話でした。百合子さんを亡くされてから6年ほどの時が過ぎていますが、その間争いを続けるということを個人だけでやっていくというのは、困難なものです。木村さんのご両親が争いを継続できたのは、もちろん教育現場の問題をどうにかしたいという強い思いがあることもそうですが、争いを支援する人々がいたということも大きな要因であると思います。
POSSEには、労働の現場で起きている様々な問題の相談が寄せられていますが、そういった問題に個人だけで対処するというのは、どうすれば解決に導くことができるのかわからない、また、争いを解決しようにも個人でやるのが心細いといった理由で非常に困難なものです。そのため、問題を解決するために支援をしていく機関や組織が必要になってくるのですが、木村さんのご両親の話を伺って、支援の必要性について強く感じました。
私自身、POSSEのボランティアの活動に参加して1年が過ぎようとしていますが、この活動に参加する意義を、木村先生の裁判を通して改めて再認識しています。
控訴審の審理は今回の期日で終了しているので、次回の7月19日の13時15分からの裁判で控訴審の判決が下されます。東京高裁がどういった判断をするのか、その行方が注目されます。
大学4年生 ボランティア参加1年
木村裁判の支援団体です。
「故木村百合子さんの裁判を支援する会」
「静岡県の臨時教職員制度の改善を求める会」
ブログ→http://plaza.rakuten.co.jp/kodou/
「全国過労死を考える家族の会」
木村さんの日記や昨年の静岡地裁で勝利判決が出るまでの経緯が本になっています。








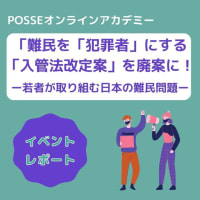

![[សំណើសុំការបរិច្ចាគ] សូមជួយគាំទ្រសកម្មភាពដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សិក្ខាកាមបច្ចេកទេសបរទេស។](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/a3/82f17015fc24605f66097c4d5d696457.png)