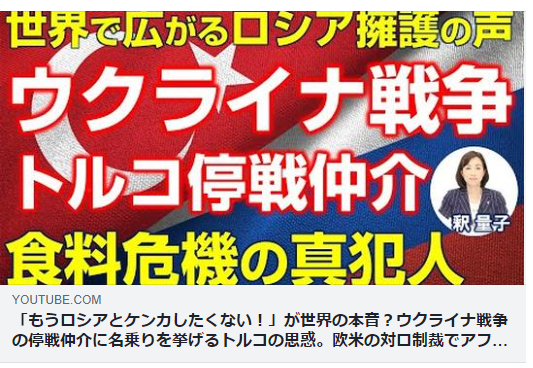
「もうロシアとケンカしたくない!」が世界の本音?ウクライナ戦争の停戦仲介に名乗りを挙げるトルコの思惑。欧米の対ロ制裁でアフリカの食料危機が深刻なことに。(釈量子)【言論チャンネル】
「もうロシアとケンカしたくない!」が世界の本音?
◆ウクライナの「停戦仲介」に名乗りを挙げたトルコ
ウクライナ戦争が開戦から4ヶ月半が経過しましたが、いま停戦の「仲介役」として本格的に名乗りを挙げ、世界から動向を注目されている国があります。
それが、東洋と西洋の狭間に位置する国トルコです。
3月から両国に停戦交渉の場を提供してきたトルコですが、5月30日、トルコのエルドアン大統領は改めて、ロシアのプーチン大統領、またウクライナのゼレンスキー大統領と電話協議し、両国の仲介に意欲を示しています。
それに合わせて、プーチン大統領にとって開戦後、初の外遊となるトルコ訪問について、ロシア大統領府は「準備している」ことを明らかにしました。
特に世界を危機に陥れている食料や肥料等の供給網の復旧、要するに、穀物、ヒマワリ油や肥料類などの輸出ルートが確保できるかどうか、という点が注目されています。
◆ロシアではなく、ウクライナ?黒海封鎖の真犯人とは
欧米側のスタンスとしては、侵略者ロシア・プーチン大統領が、ウクライナ産の穀物が輸出されないように、黒海に面した港湾を封鎖、「世界に深刻な食料不足を引き起こした」という一面的な批判を展開しています。
一方、プーチン大統領の言い分は真っ向から異なります。
今回の食料危機は「誤った欧米の経済制裁」が原因であり、港湾の封鎖についてはウクライナ側が「港の入り口に機雷をしかけた」と訴えています。これについてもウクライナ側は「ロシアの仕業」だと言っています。
戦場となり、交通インフラが極めて不安定なウクライナは難しいとしても、ロシアとしては国内で収穫された食料の輸出は開戦後も行いたかったはずです。
実際に、ロシア産小麦や大麦、ヒマワリ油などの生産地域は、コーカサス地方やロシア南部など、ウクライナ周辺地域に集中しているため、輸出の主力となる海上ルートは黒海経由となるのが、妥当でしょう。
そういう意味から、機雷によって自国の輸出ルートを自ら潰すとは考え難く、ロシアを悪役にするウクライナ(または西側)側の策略とも考えられます。
そんな中、ロシアと共同しながら、黒海に敷設された機雷の除去という大きな役割を担っているのが、トルコなのです。
ロシアのラブロフ外相は6月1日、サウジアラビアでの会見で「(トルコの)エルドアン大統領と会談した結果、発展途上国にとって必要不可欠な食料物資等(貨物)とウクライナの港の機雷除去を進める手助けをするという合意に達した」とトルコの貢献を、国際社会に報じています。
このように、ロシアと対立関係にあるNATOの一員として、黒海の交通管理という国際的に承認された役割を担いつつ、ロシアとの独自外交で、停戦仲介のメインプレーヤーを演じるトルコが存在感を放っています。
また、6月3日、プーチン大統領はウクライナ産の穀物に関しては、同盟国ベラルーシ経由でバルト海から海上輸送する案が「一番簡単で安価だ」と述べ、条件としてベラルーシの制裁解除を挙げました。
ベラルーシのルカシェンコ大統領も、バルト海の港から自国製品の輸出が出来るようになれば、ウクライナ産の穀物も運ぶ用意があると認めております。
欧米側の制裁が解除されれば、世界を苦しめている食料危機が、実質的に大きく軽減される未来が容易にイメージできます。
◆トルコが実質的に「世界大戦」化を防いでいる?
もう一つ、別の視点から見て、世界大戦に広がりかねない火種を、結果的にトルコが抑えているのが現状です。それがスウェーデンとフィンランドのNATO加盟への反対です。
5月29日、トルコのエルドアン大統領はこの両国のNATO加盟は「認められない」との認識を改めて示しました。
1か月以上、両国との協議を進めてきましたが、現時点ではトルコにとって「期待したレベルに達していない」と判断した模様です。
その一つの判断材料となるのが、5月下旬にトルコからスウェーデンに示されてきた「条件リスト」の中身です。
基本的には、スウェーデンが、テロ組織の隠れ蓑となって、武器支援や財政的支援を行っていることへの強い不満が表明されています。
特に、トルコではクルド人勢力の問題があります。
クルド人というのは、トルコやシリア、イラク、イランなど国を超えて住んでいる民族で、約3000万人いると言われます。このクルド人は自分たちの国を持ったことがなく、「国を持たない最大の民族」と呼ばれています。
1980年代に、トルコでは「クルド人など存在しない」と主張して、国内にいる少数のクルド人を弾圧しました。すると、クルド労働者党(PKK)がトルコ国内で武装闘争を開始し、死者が4万人を超えてしまいました。
しかし、クルド人は独立を果たすことができず、トルコにとっては「テロ組織」と危険視しています。
一方、シリアやイラクに横断して住んでいるクルド人たちが、アメリカや欧米から支援を受けてIS(イスラム国)に対して、勝利しました。その見返りに、クルド人たちはシリア北部で自治区を作って独立を果たそうとします。
これにはトルコが警戒し、2019年シリア北部に侵攻して、クルド人20万人ぐらいが家を失ったとされます。
非常に複雑な歴史があり、トルコは「条件リスト」で、スウェーデンがクルド系組織を支援していると指摘して抵抗しているわけです。
ただ、トルコのこの動きが、結果的に、戦争の拡大を防いでいると言っても過言ではありません。
万が一、ロシアと国境を接するフィンランド、そしてスウェーデンがNATOに加盟したら、プーチン大統領にとってはウクライナ同様、レッドラインを超えたと見做すはずです。
実際に、5月下旬、フィンランド国境にロシア軍部隊を増強しています。
そういう意味からみれば、結果的にトルコの反対が世界大戦への波及を防いでいることは確かです。
◆プーチンとエルドアンの不思議な絆
歴史的には、トルコは、クリミア戦争などで象徴されるように、隣国ロシアの南下政策には苦しめられてきた経緯があります。
現在進行形でシリアやリビアでは、ロシアと対立関係にもありますし、ウクライナにはトルコ製のドローン兵器を輸出してロシア軍と対峙したりもしています。
ところが、トルコ中東問題の専門家によると、「長年それぞれ国のトップを張り続けた、プーチン大統領とエルドアン大統領の間には、特別な絆、定期的に対話を重ねる信頼関係がある」と言われています。
エルドアン大統領に関する「指導者」としての評価は横に置きつつも、いま、核戦争につながりかねない世界大戦を未然に防いだほうがいい、という判断をしているのは注目されます。
◆アジア・アフリカで広がるロシア擁護の動き
実際、トルコから見た東方世界、中東・アジアに目を向ければ、「極悪な侵略者ロシア、可哀そうなウクライナを助ける欧米諸国」という日本のメディアにありがちなステレオタイプとは、全く異なった見方がされています。
例えば、ドバイを抱えるアラブ首長国連邦UAE、サウジアラビアといった伝統的な親米国が、トランプ政権からバイデン政権になってから、急速に距離を取りつつあります。
UAEに至っては、3月初旬に行われた国連安保理の「ロシアへの非難決議」で棄権票を投じ、ここまでアメリカ離れが進んでいるのかと、世界に衝撃を与えました。
UAEが誇る中東随一の経済都市ドバイは、経済制裁で苦しむロシア企業や富裕層にとって、うってつけの海外拠点となりつつあります。なんとドバイの不動産市場では「ロシア人マーケットがいま最も盛況」と言われています。
UAEの旧宗主国は英国なのですが、欧米諸国の対ロシア制裁に同調しないという姿勢をはっきりとさせています。(WSJ)
ようやく原油増産に応じたサウジアラビアも、米バイデン政権から再三の懇願は無視し続け、電話も出ないという状況で、ロシアと歩調を合わせてきました。
3月には、サウジアラビアと中国の間で、原油取引の一部を米ドルから中国元で決済するという取り決めの可能性が報じられました。
石油のドル決済こそ、ドル覇権の力の源泉なので、大きな流れです。米国から中露へのシフトが顕著です。
また、アフリカ諸国も、ロシアやウクライナに食料を依存している地域ですが、欧米側の肩を明確に持つ国はあまりないのが実情です。
6月3日、アフリカ連合の議長国セネガルのサル大統領がプーチン大統領とソチで会談を行い、「欧米の対ロ制裁でロシア産の穀物がアフリカに届かなくなっており、制裁が状況を悪化させた」と訴えています。
それに対してプーチン大統領は「ロシアは常にアフリカの側にあり、植民地主義との戦いでアフリカを支援してきた」と語っています。
更にインドは、安保理決議ではUAEと同じく棄権票を投じましたが、ロシアとは軍事装備上、切っても切れない関係があり、明確に欧米側に付くことは考え難いと言えます。
◆欧米諸国の中から噴出する「ロシアとケンカしたくない!」の声
最近になって、欧米諸国の内部からも、長引くウクライナ戦争や対ロ制裁について、「かえって自分たちの首を絞めかねない」と否定的な意見も多くなってきました。
ハンガリーは、EU加盟国ですが、NATOが5月4日にロシア産原油の輸入禁止を柱とした追加制裁を発動すると、これに強く反発しました。ロシア正教トップの総主教キリル1世への制裁もハンガリーの反対で見送られています。
ハンガリーはロシア産の原油がないと国が立ち行かなくなるので、制裁案を飲むなんてことは、「ハンガリー経済にとって核爆弾だ」というくらいの大打撃になるのは間違いありません。
ハンガリーのオルバン首相も、エルドアン大統領同様、プーチン大統領との個人的な信頼関係が強く、また宗教的・民族的な価値観など、EUという「外形的な枠組み」よりも、更に深いところでつながっているようです。
このように、欧米諸国も一枚岩ではありません。
停戦交渉についても、ドイツ、イタリア、フランスはロシアとの対話による和平を重視する一方、ロシア嫌いの英国やポーランド、エストニアなどバルト3国は「ウクライナの軍事的勝利が解決」と強硬路線を採り、EUに大きな亀裂が走っています。
米国では、対ロ制裁によるエネルギー価格の上昇などインフレ傾向が加速し、選挙には悪影響、もはや完全に逆効果になりつつあるようです。
米国が考える和平案の中には、ウクライナ保全の見返りに、NATOに対するウクライナ中立化や、クリミアやドンバスなどに関する対ロ交渉も議論の枠組みに、もう含まれていることが報道されてきました。
◆「欧米追従」を貫く日本、いつの間にか肩透かしを食らうかも
世界大戦にエスカレーションするか否か、緊迫する世界情勢の中で、「機を見るに敏」で立ち回る国際社会の中で、日本政府の「欧米追従」の姿勢は変わる気配を見せません。
バイデン政権がアフガンにおいて、20年間で8兆ドルも投じたのに手のひらを返して撤退してしまったように、いつの間にか肩透かしを食らい、割を食うのは日本だけ、という事態にもなりかねません。
地政学的に見ても、ロシアを敵に回して最も危険度が高いのは欧州のどの国よりも、中国・北朝鮮・ロシアの3ヵ国に囲まれた日本かもしれません。
日本が本来担うべきは、トルコのように東西文明の懸け橋にならんとする、もっと大きな役割であるべきです。
そのためにも、世界の行く末をよき方向にリードしていこうとする積極的でダイナミックな立ち回りこそ、日本に求められているのではないでしょうか。

執筆者:釈 量子
幸福実現党党首
。















