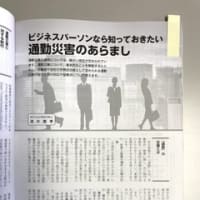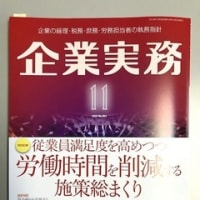特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。
令和元年9月1日から日本と中国との社会保障協定が発効しています。
まず社会保障協定とは何かということについて簡単な例をお示しします。
日本で勤務していて、日本の社会保険に入っている人が外国へ転勤になった場合、原則論をいうと日本の社会保険にも、転勤先の外国の社会保険にも加入し、日本と外国の両方の社会保険料を払います(要するに二重払い)。
両方の国の社会保険制度に加入して両方から給付が受けられれば良いですが、特に年金は長期にわたる加入が必要で、数年で日本に帰ってくる場合、外国でかけてきた年金保険料が掛け捨てになります。
社会保障協定が発効している国同士で、社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」を届け出ることにより、この二重払いと掛け捨てになってしまうことを防止しようというのが社会保障協定の趣旨です。
社会保障協定が発効している国へ転勤となった場合は、日本の社会保険に入っていれば、適用証明書を届け出ることにより転勤先の外国の社会保険に入る必要が(義務としては)なくなります。
日本との社会保障協定が発効しているのは20か国(令和元年12月現在)ですが、各国ごとに年金制度や協定の内容が違うので海外へ派遣する際は各国の内容を検討をお願いします。
スイスなどは1年で老齢年金の受給資格があるようです(出る年金の金額はわかりませんが)。
主要各国の年金制度(厚生労働省HP)
また、社会保障協定が発効している国同士では年金加入期間の通算という効果もある国も多いです。年金加入期間が通算されれば、一方の国の年金制度に加入していれば日本と相手国の両方で年金に加入していたことになります。
9月からの中国との社会保障協定は年金保険料の二重払いの防止のみです。従って日本から派遣された場合は中国の年金が、中国から日本へ来た方は日本の年金の資格が得られません。
9月より前から中国にいらっしゃる方は9月1日から協定発効日に中国へ派遣されたものとして取り扱われます。
協定相手国別の情報(中国)(厚生労働省HP)
なお、香港とマカオは中国側の制度の事情により9月からの社会保障協定の対象にはなりません。
令和元年9月1日から日本と中国との社会保障協定が発効しています。
まず社会保障協定とは何かということについて簡単な例をお示しします。
日本で勤務していて、日本の社会保険に入っている人が外国へ転勤になった場合、原則論をいうと日本の社会保険にも、転勤先の外国の社会保険にも加入し、日本と外国の両方の社会保険料を払います(要するに二重払い)。
両方の国の社会保険制度に加入して両方から給付が受けられれば良いですが、特に年金は長期にわたる加入が必要で、数年で日本に帰ってくる場合、外国でかけてきた年金保険料が掛け捨てになります。
社会保障協定が発効している国同士で、社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」を届け出ることにより、この二重払いと掛け捨てになってしまうことを防止しようというのが社会保障協定の趣旨です。
社会保障協定が発効している国へ転勤となった場合は、日本の社会保険に入っていれば、適用証明書を届け出ることにより転勤先の外国の社会保険に入る必要が(義務としては)なくなります。
日本との社会保障協定が発効しているのは20か国(令和元年12月現在)ですが、各国ごとに年金制度や協定の内容が違うので海外へ派遣する際は各国の内容を検討をお願いします。
スイスなどは1年で老齢年金の受給資格があるようです(出る年金の金額はわかりませんが)。
主要各国の年金制度(厚生労働省HP)
また、社会保障協定が発効している国同士では年金加入期間の通算という効果もある国も多いです。年金加入期間が通算されれば、一方の国の年金制度に加入していれば日本と相手国の両方で年金に加入していたことになります。
9月からの中国との社会保障協定は年金保険料の二重払いの防止のみです。従って日本から派遣された場合は中国の年金が、中国から日本へ来た方は日本の年金の資格が得られません。
9月より前から中国にいらっしゃる方は9月1日から協定発効日に中国へ派遣されたものとして取り扱われます。
協定相手国別の情報(中国)(厚生労働省HP)
なお、香港とマカオは中国側の制度の事情により9月からの社会保障協定の対象にはなりません。