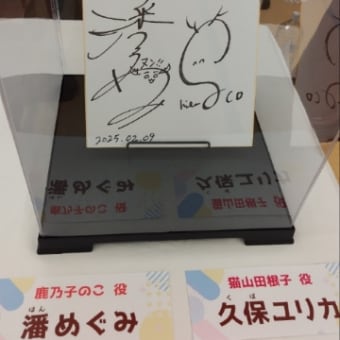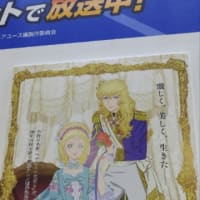制作者は一体何を考えているんだ、勉強して出直して来い、というアニメを2つ。
制作者の努力が空回りしたとか、やることなすことが裏目に出たとかであれば、可愛げもあるのですが、そんなレベルではなく。
世間的には好評みたいですけれどね。
●「ココロコネクト」
左から、太一(cv水島大宙)、姫子(cv沢城みゆき)、唯(cv金元寿子)、義文(cv寺島拓篤)、伊織(cv豊崎愛生)。
声優は、結構いい人を集めたんですけどねえ。

書こうと思えばいろいろと書けるしツッコミを入れられるのですが、時間もないし、何よりも見ていて馬鹿らしくなったので、概論だけ、書いておきます。
因みに、他のアニメ同様、原作は読んでいません。
本題の前に、余談を。
絵はあまり気にしない方ですが、それにしても、髪型以外はキャラの顔が皆な同じで、なおかつ、いい加減な線で書いているというのも、ここまでくると感心してしまいます。
また、このアニメ自体を「あらすじ」であると考えた方が良いのかも知れませんが、今後、そんなアニメを作られても困ります。
いくつか、ベタベタですが良い台詞はあるんですけどね。
で、本題です。
庵田定夏(あんだ さだなつ。1988年8月生、24歳。ライトノベル小説家。性別は不明らしい)さんのラノベが原作。
「ココロコネクト ヒトランダム」で2009年に第11回えんため大賞特別賞を受賞なので、このアニメの最初の「ヒトランダム」の話の原作は20歳かその前の作ということですね。
(因みに、ヒトランダム編の原作が本として刊行されたのは2010年1月、キズランダム編は2010年5月刊、カコランダム編は2010年9月刊、ミチランダム編は2011年1月刊。)
2人の男子、3人の女子の同級生の高校生5人の間に、龍善先生(cv藤原啓治)とかにのり移る謎の「ふうせんかずら」が面白いことを見るため(但し、話の流れからして、それは明らかに本心ではない)に起すアレコレを契機に、5人が心理的に成長していく話。
比較的シリアスな雰囲気で進み、時々ボケやツッコミというコミカルな要素も入れている、といった話。
○ 人格が入れ替わる「ヒトランダム編」(1~5話)、
○ 欲望が開放されてやりたいこと、抑えていたことをしたり言ったりしてしまう欲望開放が起きる「キズランダム編」(6~10話)、
○ 幼児期や小学生や中学生などの過去の自分に姿も性格も退行する「カコランダム編」(11~13話)、
がテレビで放送されたわけで、あと4話(ミチランダム編)あるらしいのですが、どう放送するのかは知りません。
始まった時の感想にも少し書きましたが(→7月29日のこれ)、いずれも、5人は簡単に悩みを話し過ぎですし、簡単に悩みが解決し過ぎです(いくつかを除いてどうってことない悩みなので、それを話すのは簡単でも良いのかも知れませんが、そうでもない悩みも簡単に話し過ぎです)。
具体的に描かなくても、いろいろあって、いろいろ考えてそうなったという描写や仕草や台詞らしきものがもっとあれば、あるいは、台詞はなくてもカメラーワークで様々な角度から写して間を取ったりすれば、あるいは、音楽で気持ちを代弁させたりすれば、つまり逡巡がもう少しあれば、行間の読みようもあるのですが、それすらもないので、解決も安易で唐突で底が浅すぎで、最初から最後まで「あらすじ」のような薄っぺらな話でした。
これらの設定自体にはベタな部分もありますが、心理面を重視した話であり、かなり面白くできそうなのに勿体ないです(もっと重い話にして世間的には不評になるか、もっとコメディにしてソフトな印象にするかでしょうけれど)。
で、本題の本題です。
制作者にも、視聴者にも、人の心や心理学を安直に考えられては困ります。
これから直接的な体験(実体験)を増やすのは大変でしょうから、原作者やこのアニメを作った人は、少なくとも、大学生以上向けの各種心理学の教科書的な本を10冊以上、純文学小説(芥川賞はこの分野)や大衆文学小説(直木賞はこの分野)を計50冊以上は読んで間接的な体験を増やして、なおかつ、良く考えてから出直してこい、という感じです。

取り敢えず、最低限、言いたいことは書きましたが、またまた余談です。
太一の「自己犠牲野郎」みたいなことは良くないことなので(最初は自分のためにしていることに気付かなかったが、姫子に言われて自分のために「自己犠牲」をしていることに気付いた)、参考に、「黄昏乙女アムネジア」のアニメの感想の中で、ボランティアは自分のためにもしていることを忘れてはいけないということを以前に少し書いたので、それを。
→7月1日の『「黄昏乙女アムネジア」の変なボランティア精神とアイデンティティ、「戦国コレクション」の感想』
●「あらしのよるに ~ひみつのともだち~」
人気の絵本(1994年刊)を原作とした、春夏の夕方の子供向けアニメ。結局、ちっちゃい話でした。
→7月7日の中間での感想「パイレーツ、あらしのよるに(ジャングル大帝レオも)の感想」
これは、子供には有害な話でしょう。
嵐の夜に雨宿りした真っ暗な小屋で偶然会い、偶然友達になって、楽しく密会を続けていた雄の狼のガブ(cv吉野裕行)と雌の子ヤギのメイ(cv釘宮理恵)は、結局バレて仲間から裏切り者と言われます。

(1) 裏切り者となった2匹はそれぞれ、羊のエサ場を聞き出して狩の成功率を上げるため、狼の狩場を聞き出して狼から逃げるため、仲間から言われて再会しますが、互いに相手(友達)を裏切ることが出来ずに、家族や仲間を裏切って2匹で逃げると。
となると、狼はエサ(ヤギとか)探しに今後とも苦労し、ヤギは狼から逃げることに今後とも苦労し、ということが続くわけですけれど。それは、これまでどおりということなので、ガブとメイを責めることは筋違いかも知れませんが。
(2) 裏切り者のガブを殺すために狼が追ってくるので、どこまでも逃げると。
2匹一緒だからつらくはなく、楽しいようですが。
(3) それ以前に親を狼に食べられたことを知ったメイですが、ガブと一緒に逃げると。
ガブが殺したわけではないので寛容な心というのはとても良いことですが、ガブもこれまで仲間のヤギを食べてきたんですけどね。
(4) メイと友達になってからはガブはヤギは食べないようですが、他の動物や魚は食べると。
(手塚治虫さんの名作、「ジャングル大帝レオ」におけるライオンとかの肉食動物は草を食べており、良い意味でも悪い意味でも、理想主義として徹底していましたけれど。)
これらは、特に(4)なんかは、「身内」、つまり自分の友達や家族とか身の回りの自分の手が届く範囲、自分に直接的に影響することは友達や仲間として強く守ったり関心を持ったりしますが、それ以外は「他者」として無関心で気にしないという心性が強く出ています。
それだけならまだしも、一般的に、その心性は、「身内」がちょっと文句を付けられただけでも、「身内」以外の他者を容易に敵に転じさせて、とても攻撃的になる心性でもあるわけであり。
半径1メートルとか、半径3メートルとか、そんな狭い範囲にしか関心が向かない、現代のあまりよろしくない傾向です。
このアニメ、夕方(テレビ東京、水曜、17:30から)に、つまり子供向けに放送するなんて、深夜に多い流血バトルアニメやエロアニメの何十倍も子供の教育上は有害だと思いますけどね。 (大人への成長のためには思春期に、親などへの隠し事や、いわゆる「親殺し」は必要ですが、それを描いたのだとしても、差し引きするとマイナス要素が多い。)
深夜とかで大人向けに放送して大人が見るなら、フィクションとして割り引いたりしながらとか、釘宮さんの声+時々の堀江由衣さんの声だとか、楽しみ方も自分で見つけられるでしょうけれど。
この話を子供向けに書いた原作者も、アニメにした側も、そこには気付いていないのでしょうかねえ。
【shin】