2013年2月 中国の政治経済―世界の動きⅣ
《政治》
○四川省成都で発行する月刊誌『看歴史』の2月号(台湾民主化の特集)の発行を当局が差し止め(13.2.1)。
○人事(13.2.5)。①外交担当の国務委員に楊潔簾外相(副首相級、総書記をトップとする党中央外字工作小組の秘書長を兼務)、外相に張志軍外務次官。⇒両方とも対米政策を長く担当、習近平指導部が対米関係重視の現れ。次期駐米大使に崔天凱対米政策担当の外務次官、次期国連大使に傳瑩アジア地域担当の外務次官。⇒これらの人事は対米外交の基本方針「新しいタイプの大国関係」(習近平)の共存共栄の追求、軍を除けば本音で交渉できる関係⇒1月の安保理での米国提出の北朝鮮制裁決議に賛成。②対日人事、次期駐日大使は未定、断る候補者が相次ぎ、駐韓大使の横滑りか。楊潔簾は9月の反日デモでは対日強硬路線で指導部の支持を得た。②国家副主席に李源潮共産党政治局員。共青団、政治局常務委員からはずれ政治局員に。次期大会での政治局常務委員昇格はほぼ確実。常務委員でない国家副主席は王震以来20年ぶり。
【習近平の対米姿勢は大国の共存、「軍を除けば」という共存関係には危うさ。対米では、釣魚台問題でも、北朝鮮問題でも、突っ張った対応はしていない。この対米での柔軟姿勢は何か。】
○中国国内でのチベット人の自殺者が09年以降で100人目に(2月3日)。
○中国の「民主の村」の広東省汕尾市鳥坎村で直接選挙で選ばれた指導部が苦境に。過去に幹部が開発業者に不正売却した土地の使用権の返還が停滞し住民が反発、村民委で辞職者が相次ぐ(13.2.17)。
【中国の民族問題は、必ず体制を揺るがす。】
○汚職摘発を本格化(13.2.23)。党や国有企業幹部の4000人に海外逃亡を防ぐために出国を禁止、内部調査に乗り出す。
○中国共産党第18回中央委員会第2回全体会議(2中全会)(26日)。全人代で決める行政改革案や人事案の最終調整へ。「独立王国」と批判される鉄道省(12年の総投資額は6000億元で現業部門は巨大な利権の巣。かつて人民解放軍が鉄道建設を担った関係で江沢民の影響大)の廃止、食品安全監督の強化など。銀行、証券、保険に分かれる金融監督部門の統合などは見送り。27の省庁は大きくは減らない。
《大気汚染など公害》
○北京の大気汚染は「PM2.5」(喘息や気管支炎を起こす直径2.5μmの微粒子)の大気中の濃度がWHO基準の20倍 (13.2.1)。北京市は企業の操業停止、公用車の利用削減、建設工事の中止を決定。日本企業も含まれる。
○大気汚染、中国内政の火種(13,2,4)。自動車の排ガス規制の遅れ、現行の「国3」(ユーロ圏の2000年導入のユーロ3に該当)から10年に排出基準が3倍厳しい「国4」に切り替える計画が進まず、最高指導部がエネルギー関連、規制組織の7割が石油業界代表などへの不満。
○中国政府は自動車燃料の品質基準を段階的に引き上げる方針を決定(6日 中国国務院の温家宝首相が主宰する常務会議)。現行の燃料基準は「国3」(硫黄含有量が150PPM)を14年末までに「国4」(50PPM)に引き上げ、17年までに「国5」(10PPM)に引き上げる。中国全土の大気汚染は自動車の排ガスが主因で市民の抗議の声、数千億円単位の負担を強いられる規制に反対している石油業界。
《経済景気指標》
○1月の製造業購買担当者景気指数PMI50.4(1日 中国物流購入連合会)。4ヶ月連続50を上回った。中国経済は減速をゆるめているものの、輸出の伸び悩みで勢いは力強さを欠いている。輸出向けの新規受注は1.5ポイント低下の48.5。
【PMIが4か月連続50を上回っている。】
○1月の貿易統計 (8日 中国関税総署)。輸出が前年同月比25.0%増加、輸入が28.8%増加と大きく伸びた。貿易収支は291億5千万㌦の黒字。
(分析 13.2.10)。①中国が12年、輸出と輸入を合わせたモノの貿易総額(3兆8667億㌦)で米国(3兆8628億㌦)を抜いて世界一に。輸出は09年にドイツを抜いて世界一。ただし、サービス分野を含めると米国と1兆㌦の差がある。②靴・繊維・家具などの労働集約型の「加工貿易」から通信機器・建機・自動車(12年に輸出100万台突破)などに。③貿易相手の多様化。01年(WTO加盟)には日米欧が貿易総額の半分から、12年には3分の1に。特に、10年発効のFTAを結んだASEANとは11年比10%増、すでに日本を抜いている。④貿易収支の偏り。12年は貿易黒字が2311億ドル、前年比48.1%増加⇒人民元の為替操作批判の高まり。また輸出の超過は構造的な問題。景気対策としてインフラ投資の積極化⇒過剰生産から輸出へ、貿易摩擦の激化。投資や輸出への依存からの脱出として内需拡大。サービス業拡大へ(深圳市での貸出金利の自由化)。
【中国の輸出は投資・過剰生産から。貿易構造問題がある。】
○1月の消費者物価指数CPI、前年同月比2.0%上昇(8日 中国国家統計局)。卸売り物価指数は1.6%低下。
○今年の春節(旧正月 9日~15日)の全国小売売上高、前年同期比14.7%増の5390億元(13.2.16)。個人消費はなお堅調だが、伸び率は前年より1.5ポイント低下。
○「点検 中国景気 下」、進まぬ構造改革。「労働集約」脱却遠く (13.2.16)。広東省は労働集約型で発展、付加価値の高い産業育成のモデルだが、産業高度化は一向に進まず、東莞市などの省内各地の政府が労働集約型の産業の温存を容認している。
【中国経済の構造的問題を自覚はしても、中国共産党と国家の政治体制ではそれを解決できない矛盾に陥っている。このギャップの大きさがまさに構造的問題としてある。】
○1月の世界からの中国への直接投資。前年同月比7.3%減の92億7千万㌦。(20日 中国商務省)。8ヶ月連続減少。日本からも20%減。対中投資は12年に3年ぶりに前年割れ。
○1月の主要70都市の住宅価格動向。前月比で上昇したのは53都市、前月比1都市減ったが上昇傾向は続いている(22日)。2月22日に不動産市場の引き締め策の強化を発表 (20日) 。
《人民元》
○中国と台湾の通貨の直接取り引きがまず台湾で始まった(6日)。現地の銀行が米ドルを介さずに台湾ドルを人民元に交換する業務が始まった。日本の3メガ銀行(みずほコーポレート銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行)も参入。台湾は香港のような人民元の一大取引市場を目指す。中国も台湾を優遇。中国は人民元経済圏の拡大を狙う。直接取り引きは、円、マレーシア・リンギッド、ロシア・ルーブルで行われている。
《経済摩擦》
○中国の通信機器・華為技術(ファーウエイ)とEU・米国・豪州などとの摩擦が激化(13.2.6)。EUは華為が中国の政府系金融機関の信用供与が補助金に当たると協議。米国は華為によるIT企業の買収を阻止、下院が政府調達から華為・中興通訳(ZTE)の排除を勧告。豪州は華為の高速通信事業への参加を拒絶。インドは華為・ZTEの通信機器湯謬を停止。華為は中国人民解放軍との関係疑惑。華為は通信会社向け機器を主力とするメーカーでは世界のトップに。
《経済政策》
○中国の最低賃金、10年で3倍に(13.2.7)。広東省が最低賃金の19%引き上げを決定、杭州市は月1550元(10年前の3倍)に、東莞・仏山・中山・珠海の各市は1310元。日本の自動車・部品メーカーの進出する広州市が全国最高に。広東省には日系企業3000社が進出。
○中国国務院は所得分配改革を推進する基本方針をまとめた(13.2.7)。高所得者への課税の徹底、不動産税の試行地域の拡大、遺産税の導入も検討。国有企業幹部の報酬管理の強化。
《過剰生産》
○世界粗鋼生産量の半分を占める中国の鉄鋼業が過剰生産の重荷に沈んでいる (13.2.11)。2012年に主要23社で赤字、合計は290億元。地方経済の屋台骨の鉄鋼メーカーを地方政府が下支えする構造問題(地方政府は国有鉄鋼メーカーを支援し金融機関も融資)。中国の粗鋼生産能力は12年で8億7300万トン、13年の粗鋼生産量は7億5千万トン、設備過剰解消には程遠い。
【中国の粗鋼生産は大規模であり半端ではない。その過剰生産は解決できない。】
《格差是正》
○格差是正の基本方針を明らかに (13.2.20 社説)。「収入分配制度の改革深化に関する若干の意見」という文書。一部の企業の給料が低すぎるのを解決するための業種別や地域別の労使協議の枠組み、国有企業幹部の報酬の管理と抑制のために国有企業の上納金を3年以内に5%引き下げ、資産課税の強化で不動産税や相続税の「徴収を始める問題の研究」など。
○国有企業に効率経営要求。経営幹部の評価基準を3年ぶりに見直す (13.2.20 国有資産監督管理委員会)。基準から売上高伸び率を削除し、新たに経営効率を問う基準(総資産回転率・売上高を総資産で割る)を設けた。売上高の増加を重視する従来基準が供給過剰を招いたとの反省から。委員会は中央企業(中央政府が管轄する企業)の幹部(董事長、総経理など)を定期的に経営成績をA~Eの5段階で評価、経営幹部が共産党幹部をかねるケースが多い。12年の中央企業の利益総額は前年比0.6%減少し、売上高は9.5%増加と国有企業は利益伸び悩みが鮮明。
○改革進展に地方の抜け穴(同上)。国有企業のM&Aは進まず。国有企業が中国の雇用の重要な担い手であり、地元政府の反対で削減できない。今回の評価基準の変更対象は中央企業で社数で圧倒的に多い地方政府出資の国有企業は対象外。地方政府系の企業の利益総額は15.8%減少したが,売上高は11.6%増加。
○不動産市場の引き締め策を強化。上海・重慶市で試行している不動産税(工程資産税の一種)の対象地域を拡大(20日 中国国務院、温家宝主宰の常務会議)。
○「反汚職」官製消費しぼむ(13.2.15)。中国景気の減速は12年10~12月に底入れした。回復の足取りは重い。1月のPMI製造業購買担当者景気指数は50.4で12月より0.2ポイント低下した。12年のGDPは7.8%成長。31の省・直轄市・自治区のうち13年の成長目標は沿海部の8~10%に対し内陸部の18地域は軒並み2桁成長だが9地域は12年の実績より1%以上引き下げた。
《真珠のネックレス戦略》
○パキスタン南西部グワダル港の港湾管理権を取得。ホルムズ海峡から400キロ、マラッカ海峡を通らずに、新疆ウイグル自治区からパキスタン経由で陸路中国へ原油を運ぶ(13.2.19)。インド洋の9カ国で港湾の建設・運営へ⇒9カ国はミャンマー、バングラディシュ、スリランカ、スーダン、タンザニア、モザンビーク、ケニア(東アフリカのハブ港候補のラム港)、サウジアラビア、パキスタン⇒中国海軍の寄港しやすい港へ。
○世界最大のEMS(電子機器の受託製造サービス)台湾の鴻海(ホンハイ)精密工業はiphoneの主力生産拠点・広州工場の生産拡大を凍結(13.2.21)。ホンハイの従業員は地元政府が集める仕組みだが、年初の20万人を14年をメドに40万人まで増やす計画だった。大原工場、深圳工場も従業員募集を中止。ホンハイは中国輸出の6%、従業員は160万人で中国景気の下押しの可能性。日本にも影響、1月の中国向けスマホ製造工作機械の受注額は9億円、昨年1月の151億円から急減。
【ホンハイは中国輸出の6%で従業員が160万人、この巨大さ!】
○遠心分離法のウラン濃縮技術の国産化に成功(22日 中国核工業集団)。これまではロシアからの技術移転に頼っていた。
【中国はこれまでウラン濃縮の遠心分離法技術を国産化していなかった。】
《政治》
○四川省成都で発行する月刊誌『看歴史』の2月号(台湾民主化の特集)の発行を当局が差し止め(13.2.1)。
○人事(13.2.5)。①外交担当の国務委員に楊潔簾外相(副首相級、総書記をトップとする党中央外字工作小組の秘書長を兼務)、外相に張志軍外務次官。⇒両方とも対米政策を長く担当、習近平指導部が対米関係重視の現れ。次期駐米大使に崔天凱対米政策担当の外務次官、次期国連大使に傳瑩アジア地域担当の外務次官。⇒これらの人事は対米外交の基本方針「新しいタイプの大国関係」(習近平)の共存共栄の追求、軍を除けば本音で交渉できる関係⇒1月の安保理での米国提出の北朝鮮制裁決議に賛成。②対日人事、次期駐日大使は未定、断る候補者が相次ぎ、駐韓大使の横滑りか。楊潔簾は9月の反日デモでは対日強硬路線で指導部の支持を得た。②国家副主席に李源潮共産党政治局員。共青団、政治局常務委員からはずれ政治局員に。次期大会での政治局常務委員昇格はほぼ確実。常務委員でない国家副主席は王震以来20年ぶり。
【習近平の対米姿勢は大国の共存、「軍を除けば」という共存関係には危うさ。対米では、釣魚台問題でも、北朝鮮問題でも、突っ張った対応はしていない。この対米での柔軟姿勢は何か。】
○中国国内でのチベット人の自殺者が09年以降で100人目に(2月3日)。
○中国の「民主の村」の広東省汕尾市鳥坎村で直接選挙で選ばれた指導部が苦境に。過去に幹部が開発業者に不正売却した土地の使用権の返還が停滞し住民が反発、村民委で辞職者が相次ぐ(13.2.17)。
【中国の民族問題は、必ず体制を揺るがす。】
○汚職摘発を本格化(13.2.23)。党や国有企業幹部の4000人に海外逃亡を防ぐために出国を禁止、内部調査に乗り出す。
○中国共産党第18回中央委員会第2回全体会議(2中全会)(26日)。全人代で決める行政改革案や人事案の最終調整へ。「独立王国」と批判される鉄道省(12年の総投資額は6000億元で現業部門は巨大な利権の巣。かつて人民解放軍が鉄道建設を担った関係で江沢民の影響大)の廃止、食品安全監督の強化など。銀行、証券、保険に分かれる金融監督部門の統合などは見送り。27の省庁は大きくは減らない。
《大気汚染など公害》
○北京の大気汚染は「PM2.5」(喘息や気管支炎を起こす直径2.5μmの微粒子)の大気中の濃度がWHO基準の20倍 (13.2.1)。北京市は企業の操業停止、公用車の利用削減、建設工事の中止を決定。日本企業も含まれる。
○大気汚染、中国内政の火種(13,2,4)。自動車の排ガス規制の遅れ、現行の「国3」(ユーロ圏の2000年導入のユーロ3に該当)から10年に排出基準が3倍厳しい「国4」に切り替える計画が進まず、最高指導部がエネルギー関連、規制組織の7割が石油業界代表などへの不満。
○中国政府は自動車燃料の品質基準を段階的に引き上げる方針を決定(6日 中国国務院の温家宝首相が主宰する常務会議)。現行の燃料基準は「国3」(硫黄含有量が150PPM)を14年末までに「国4」(50PPM)に引き上げ、17年までに「国5」(10PPM)に引き上げる。中国全土の大気汚染は自動車の排ガスが主因で市民の抗議の声、数千億円単位の負担を強いられる規制に反対している石油業界。
《経済景気指標》
○1月の製造業購買担当者景気指数PMI50.4(1日 中国物流購入連合会)。4ヶ月連続50を上回った。中国経済は減速をゆるめているものの、輸出の伸び悩みで勢いは力強さを欠いている。輸出向けの新規受注は1.5ポイント低下の48.5。
【PMIが4か月連続50を上回っている。】
○1月の貿易統計 (8日 中国関税総署)。輸出が前年同月比25.0%増加、輸入が28.8%増加と大きく伸びた。貿易収支は291億5千万㌦の黒字。
(分析 13.2.10)。①中国が12年、輸出と輸入を合わせたモノの貿易総額(3兆8667億㌦)で米国(3兆8628億㌦)を抜いて世界一に。輸出は09年にドイツを抜いて世界一。ただし、サービス分野を含めると米国と1兆㌦の差がある。②靴・繊維・家具などの労働集約型の「加工貿易」から通信機器・建機・自動車(12年に輸出100万台突破)などに。③貿易相手の多様化。01年(WTO加盟)には日米欧が貿易総額の半分から、12年には3分の1に。特に、10年発効のFTAを結んだASEANとは11年比10%増、すでに日本を抜いている。④貿易収支の偏り。12年は貿易黒字が2311億ドル、前年比48.1%増加⇒人民元の為替操作批判の高まり。また輸出の超過は構造的な問題。景気対策としてインフラ投資の積極化⇒過剰生産から輸出へ、貿易摩擦の激化。投資や輸出への依存からの脱出として内需拡大。サービス業拡大へ(深圳市での貸出金利の自由化)。
【中国の輸出は投資・過剰生産から。貿易構造問題がある。】
○1月の消費者物価指数CPI、前年同月比2.0%上昇(8日 中国国家統計局)。卸売り物価指数は1.6%低下。
○今年の春節(旧正月 9日~15日)の全国小売売上高、前年同期比14.7%増の5390億元(13.2.16)。個人消費はなお堅調だが、伸び率は前年より1.5ポイント低下。
○「点検 中国景気 下」、進まぬ構造改革。「労働集約」脱却遠く (13.2.16)。広東省は労働集約型で発展、付加価値の高い産業育成のモデルだが、産業高度化は一向に進まず、東莞市などの省内各地の政府が労働集約型の産業の温存を容認している。
【中国経済の構造的問題を自覚はしても、中国共産党と国家の政治体制ではそれを解決できない矛盾に陥っている。このギャップの大きさがまさに構造的問題としてある。】
○1月の世界からの中国への直接投資。前年同月比7.3%減の92億7千万㌦。(20日 中国商務省)。8ヶ月連続減少。日本からも20%減。対中投資は12年に3年ぶりに前年割れ。
○1月の主要70都市の住宅価格動向。前月比で上昇したのは53都市、前月比1都市減ったが上昇傾向は続いている(22日)。2月22日に不動産市場の引き締め策の強化を発表 (20日) 。
《人民元》
○中国と台湾の通貨の直接取り引きがまず台湾で始まった(6日)。現地の銀行が米ドルを介さずに台湾ドルを人民元に交換する業務が始まった。日本の3メガ銀行(みずほコーポレート銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行)も参入。台湾は香港のような人民元の一大取引市場を目指す。中国も台湾を優遇。中国は人民元経済圏の拡大を狙う。直接取り引きは、円、マレーシア・リンギッド、ロシア・ルーブルで行われている。
《経済摩擦》
○中国の通信機器・華為技術(ファーウエイ)とEU・米国・豪州などとの摩擦が激化(13.2.6)。EUは華為が中国の政府系金融機関の信用供与が補助金に当たると協議。米国は華為によるIT企業の買収を阻止、下院が政府調達から華為・中興通訳(ZTE)の排除を勧告。豪州は華為の高速通信事業への参加を拒絶。インドは華為・ZTEの通信機器湯謬を停止。華為は中国人民解放軍との関係疑惑。華為は通信会社向け機器を主力とするメーカーでは世界のトップに。
《経済政策》
○中国の最低賃金、10年で3倍に(13.2.7)。広東省が最低賃金の19%引き上げを決定、杭州市は月1550元(10年前の3倍)に、東莞・仏山・中山・珠海の各市は1310元。日本の自動車・部品メーカーの進出する広州市が全国最高に。広東省には日系企業3000社が進出。
○中国国務院は所得分配改革を推進する基本方針をまとめた(13.2.7)。高所得者への課税の徹底、不動産税の試行地域の拡大、遺産税の導入も検討。国有企業幹部の報酬管理の強化。
《過剰生産》
○世界粗鋼生産量の半分を占める中国の鉄鋼業が過剰生産の重荷に沈んでいる (13.2.11)。2012年に主要23社で赤字、合計は290億元。地方経済の屋台骨の鉄鋼メーカーを地方政府が下支えする構造問題(地方政府は国有鉄鋼メーカーを支援し金融機関も融資)。中国の粗鋼生産能力は12年で8億7300万トン、13年の粗鋼生産量は7億5千万トン、設備過剰解消には程遠い。
【中国の粗鋼生産は大規模であり半端ではない。その過剰生産は解決できない。】
《格差是正》
○格差是正の基本方針を明らかに (13.2.20 社説)。「収入分配制度の改革深化に関する若干の意見」という文書。一部の企業の給料が低すぎるのを解決するための業種別や地域別の労使協議の枠組み、国有企業幹部の報酬の管理と抑制のために国有企業の上納金を3年以内に5%引き下げ、資産課税の強化で不動産税や相続税の「徴収を始める問題の研究」など。
○国有企業に効率経営要求。経営幹部の評価基準を3年ぶりに見直す (13.2.20 国有資産監督管理委員会)。基準から売上高伸び率を削除し、新たに経営効率を問う基準(総資産回転率・売上高を総資産で割る)を設けた。売上高の増加を重視する従来基準が供給過剰を招いたとの反省から。委員会は中央企業(中央政府が管轄する企業)の幹部(董事長、総経理など)を定期的に経営成績をA~Eの5段階で評価、経営幹部が共産党幹部をかねるケースが多い。12年の中央企業の利益総額は前年比0.6%減少し、売上高は9.5%増加と国有企業は利益伸び悩みが鮮明。
○改革進展に地方の抜け穴(同上)。国有企業のM&Aは進まず。国有企業が中国の雇用の重要な担い手であり、地元政府の反対で削減できない。今回の評価基準の変更対象は中央企業で社数で圧倒的に多い地方政府出資の国有企業は対象外。地方政府系の企業の利益総額は15.8%減少したが,売上高は11.6%増加。
○不動産市場の引き締め策を強化。上海・重慶市で試行している不動産税(工程資産税の一種)の対象地域を拡大(20日 中国国務院、温家宝主宰の常務会議)。
○「反汚職」官製消費しぼむ(13.2.15)。中国景気の減速は12年10~12月に底入れした。回復の足取りは重い。1月のPMI製造業購買担当者景気指数は50.4で12月より0.2ポイント低下した。12年のGDPは7.8%成長。31の省・直轄市・自治区のうち13年の成長目標は沿海部の8~10%に対し内陸部の18地域は軒並み2桁成長だが9地域は12年の実績より1%以上引き下げた。
《真珠のネックレス戦略》
○パキスタン南西部グワダル港の港湾管理権を取得。ホルムズ海峡から400キロ、マラッカ海峡を通らずに、新疆ウイグル自治区からパキスタン経由で陸路中国へ原油を運ぶ(13.2.19)。インド洋の9カ国で港湾の建設・運営へ⇒9カ国はミャンマー、バングラディシュ、スリランカ、スーダン、タンザニア、モザンビーク、ケニア(東アフリカのハブ港候補のラム港)、サウジアラビア、パキスタン⇒中国海軍の寄港しやすい港へ。
○世界最大のEMS(電子機器の受託製造サービス)台湾の鴻海(ホンハイ)精密工業はiphoneの主力生産拠点・広州工場の生産拡大を凍結(13.2.21)。ホンハイの従業員は地元政府が集める仕組みだが、年初の20万人を14年をメドに40万人まで増やす計画だった。大原工場、深圳工場も従業員募集を中止。ホンハイは中国輸出の6%、従業員は160万人で中国景気の下押しの可能性。日本にも影響、1月の中国向けスマホ製造工作機械の受注額は9億円、昨年1月の151億円から急減。
【ホンハイは中国輸出の6%で従業員が160万人、この巨大さ!】
○遠心分離法のウラン濃縮技術の国産化に成功(22日 中国核工業集団)。これまではロシアからの技術移転に頼っていた。
【中国はこれまでウラン濃縮の遠心分離法技術を国産化していなかった。】















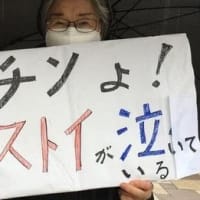




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます