安保法制整備骨格案を逐条批判する
(Ⅰ)戦後70年、自衛隊海外侵略戦争に踏み込む――この現実を全力で覆そう
3月18日、自公は集団的自衛権の行使容認の「安全保障法制整備の骨格」で合意した。あたかも公明党が自民党の暴走に歯止めをかけるかのような構図をデッチあげながら、実際は公明党が落としどころを誘導していくような猿芝居が、昨年の憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認の閣議決定過程に続き今回も繰り返された。
最近の世論調査(3.20~22、日経新聞・テレビ東京が共同実施)でも「集団的自衛権の行使可能の関連法案」に賛成31%、反対51%。「自衛隊の海外活動の拡大」は賛成43%、反対41%となっている。質問の文言で世論調査の結果は変わるが、この質問が「集団的自衛権」の具体的内容であり、「自衛隊の海外活動の拡大」の具体的内容である「自衛隊が海外で侵略戦争をすることに賛成ですか」という質問の文言に変えればもっと反対は増えるだろう。日経新聞の恣意的な質問でも反対は51%であり、憲法解釈変更での集団的自衛権行使容認が問題になって以降、反対は半数を超えている。
日経新聞はこの世論調査の結果に焦りを募らせ3月14日の社説で安倍政権に“情報不足・説明不足を何とかしろ”と助言している。これは反対派にもいえる。集団的自衛権行使容認の安全保障法整備の問題点をわかりやすく示し、闘う行動方針を示せていない。統一地方選挙の結果次第では全てが承認されたと片付けられかねない、階級闘争の主体的危機でもある。戦後70年にして安倍政権は自衛隊海外侵略戦争に踏み込むのだ。この現実を決してあいまいにしてはならない。全力で覆そう。
集団的自衛権の行使容認に関する安保法制整備の骨格は自衛隊の海外活動(海外派兵である)を広げるための五つの分野で合意した。
その具体的内容は、①外国からの武力攻撃に至らない「グレーゾーン」への対処では警戒などで一緒に行動する米軍などを守る。自衛隊法を改正。②「他国軍への後方支援」では周辺事態法改正と恒久法を新設、周辺事態法の地理的制約をなくし重要影響事態なら日本周辺以外でも後方支援できる。恒久法は日本の安全保障に影響がなくても国際協力の一環として他国軍隊への後方支援ができる。自衛隊を海外派遣しやすくする。③「人道復興支援」など国際貢献ではPKOだけでなく有志連合にも積極的に参加できるようにPKO協力法を改正し治安維持の任務も認める。④「集団的自衛権の行使」は武力行使の新3要件を満たす状況を新事態とし、自衛隊が防衛出動して他国軍を守れるすなわち戦争ができるように自衛隊法と武力攻撃事態法を改正する。⑤「邦人救出を含むその他の法改正」の5分野である。国会承認などの義務付けは協議する、というものである。
●自衛隊海外派兵を容易かつスムーズに
集団的自衛権とは自衛隊を海外に派兵することであり、戦争をすることであり、安全保障法制の整備とは自衛隊海外派兵を容易かつスムーズに行うための法整備なのだ。この点を何度も何度も繰り返し明らかにしていくことである。
またそれを阻止するための行動方針は、何よりも沖縄・辺野古での新基地建設阻止闘争を闘うことである。集団的自衛権の行使はまず米軍と自衛隊の共同行動・共同作戦で実施される。
4月28日の日米首脳会談に先立ってワシントンで日米防衛相・外務相の会合2プラス2で日米防衛協力の指針が改定され、集団的自衛権を行使できるとした自衛隊の具体的任務が決定される。この攻防の中心が辺野古新基地建設攻撃である。
●辺野古新基地建設と一体の攻撃
それだけではない。主権者である沖縄の民意を踏みにじり、足蹴にし、あろうことか面会を求める翁長雄志沖縄県知事を拒絶し、追い返した安倍、岸田、中谷とりわけ薄ら笑いさえ浮かべる官房長官・菅義偉の姿は侵略者の態度であり、沖縄を植民地として扱っているもの以外の何ものでもない。
3月23日の翁長知事の「腹は固めている」とした工事中止の決断に対して官房長官・菅は「この期に及んで……」と発言している。なんという言い草か。翁長知事の決断を受け、闘いを法廷だけで終わらせてはならない。法廷から引っ張り出すことだ。海上で、ゲート前で、辺野古の浜での大衆的阻止闘争を闘いぬこう。全国からから駆けつけることである。
辺野古に駆けつけられる人は駆けつけよう。自分が無理な人はカンパを集め代表を送ろう。辺野古と同時に普天間に配備されたオスプレイ訓練のために北部演習場のヘリパッド建設を体を張って阻止している沖縄・高江の闘いにも駆けつけよう。
重要なことはヤマトでの闘いである。沖縄での闘いに連帯してヤマトでの集団的自衛権行使を容認する安保法制整備、自衛隊の海外派兵を阻止する闘いを爆発させることである。沖縄での新基地建設に反対する闘いとヤマトでの自衛隊を海外に派兵する集団的自衛権行使容認の安保法整備に反対する闘いを一体のものとして進めよう。
(Ⅱ)先に侵略戦争、後で法改訂の暴挙
以下、「安全保障法制整備の具体的な方向性について」(骨格案)の批判である。
同骨格案の目次は
1.全般
2.武力攻撃に至らない侵害への対処
3.わが国の平和と安全に資する活動を行う他国軍隊に対する支援活動
4.国際社会の平和と安全への一層の貢献
5.憲法9条の下で許容される自衛の措置
6.その他関連する法改正事項
~となっている。
(1)「切れ目のない対応」とは自衛隊派兵のハードルを無くすもの
「1.全般」では「いかなる事態」にも「切れ目のない対応」を打ち出し、この「切れ目のない対応」を可能とする法整備として、「特に自衛隊の海外における活動の参加」を可能とする三つの方針を挙げている。
つまり「安全保障法制整備の具体的な方向性について」とは自衛隊の海外派兵を可能にする判断基準の3点(国際法上の合法性、国会の関与等の民主的統制、自衛隊の安全を確保)を示しているのだ。この基準・3原則は2月27日に公明党副代表・北側一雄が提唱し「北側3原則」と呼ばれ公明党が果たす悪質な役割を良く示している。
また安倍晋三が繰り返す「切れ目のない対応」とは何か外交上の事件が起こったときに「国際紛争の解決の手段」として「国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使を放棄する」という立場から外交的努力を尽くすのではなく、憲法9条を亡きものにし、どんな外交上の小さな事件でも自衛隊を派兵して対処するということなのだ。しかもその自衛隊海外派兵での対処の決定過程に民意や国会の意見を反映させることなく、法律に決めてあることなので「ある種自動的に」時の首相―内閣が判断し実行して行くとするものでもある。
まず「切れ目のない対応」があたかも「国民の命と平和な暮らしを守る」ために必要であるかのように記述しているが、「切れ目のない対応」とは自衛隊の海外派兵を実行する法律がないのでそれを作ろうという口実なのだ。自衛隊の海外派兵は憲法9条で禁止しているからないのは当然である。ない、のではなく、禁止しているのだ。この憲法9条を「切れ目のない対応」の一言で片付けている。
この一言で片付けられる憲法9条には「弱点」がある。それは国際紛争の解決の手段として「国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使」を放棄しているが、自衛権の保有と行使につけ込まれる隙が意図的に作られていた。この隙を埋めるためには戦争放棄ではなく戦争をこの世界からなくすために何をしなければならないのかを問題にしなければならない。憲法9条を守り抜くことは、戦争の放棄から戦争をなくす9条への飛躍が必要なのだ。
この骨格案で「海外派兵の基準」(国際法上の正当性、民主的統制、自衛隊員の安全を確保の3点)なるものを打ち出した。戦後70年の今日、侵略戦争への反省・二度と繰り返さないという決意がこの「海外派兵の基準」の3点に満たされているのか。とんでもない。国際法ほど曖昧なものはない。いや国際法は戦争を繰り返してきた現実の政治の反映、容認でしかない。国際法遵守は国際紛争を戦争に訴える、自衛隊を海外派兵することそのものであり、制限ではなく海外派兵の条件になる。国会承認などの民主的統制も危うい。すでにこの骨格案でも事後承認を押し付けている。自衛隊員の安全を確保とは危険な場所に近づかないのではなく武器のエスカレートでの安全の確保である。
(2)自衛隊が名実ともに武装した軍隊に
骨格案は第1に、「武力攻撃に至らない侵害」という「グレーゾーン事態」についての問題は武力攻撃に至らないのだから自衛隊が出動したり武器を使用したりする必要はないのだが、ここでは“演習などで一緒に行動している米軍が攻撃されたときに自衛隊は米軍を見捨てるのか”という論法で切り崩そうとしている。
自衛隊が武器防護のために武器使用ができる自衛隊法の規定を利用し、米軍の武器のためのみならず「わが国の防衛に資する活動」「わが国の防衛力を構成する重要な物的手段」を「武器などの防護」という範疇でくくり、自衛隊が武器を使用することができるとしている。万事がこのように屁理屈を持ち込んで現行法の拡大解釈で、それがどうしても無理の場合は新法を制定して自衛隊が武器を使用できる、戦争ができるようにするのだ。この屁理屈は自衛隊が戦争をすることをわかりにくくする手法である。
しかもその手続きは「国家安全保障会議の審議を含め内閣の関与を確保」でよいというのだ。内閣の決定で戦争を始めることができるようになる。
自衛隊法第7章(自衛隊の権限)に自衛隊の権限と武力行使についての規定がある。治安出動、警護出動、防衛出動、国民保護等派遣、海上における警備活動、海賊対処行動、弾道ミサイル等に対する破壊措置、災害派遣、在外邦人等の輸送、後方地域支援、防衛出動時における海上輸送の規制、捕虜等の取り扱い、部内の秩序維持に専従する者についての権限と武器使用~を定めており、95条に武器防護のための武器使用と自衛隊施設の警護のための武器使用を定めている。この安保法制整備の狙いは、武力攻撃に至らなくても自衛隊が武器使用できることを定めようというものである。
(3)自衛隊が米軍と共同して世界中で軍事行動
骨格案の第2は、「わが国の平和と安全に資する活動を行う他国軍隊に対する支援活動」である。周辺事態法(周辺事態に際してわが国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律)では朝鮮半島有事を念頭に、“放置すればわが国に直接の武力攻撃に至る恐れがある事態においては自国の領域でなくても軍事行動を起こすことができる”と定めている。朝鮮半島有事という地理的限定を含んでいる。それに対して今回の他国軍隊への支援活動は「わが国の平和と安全に重要な影響を与える事態」という周辺事態に代わる「新事態(重要影響事態)」を作り出し、地理的制限をとり払い、「日米安保の効果的運用に寄与」し新事態に対応して行動する米軍と他国軍を支援できるようにする。
実施に当たっての要件として「他国の武力行使との一体化(明確な憲法違反)を防ぐための枠組」「原則国会の事前承認」を挙げている。枠組なるものは具体的には不明であり、国会承認も原則であり、事後承認もあるということである。
(4)「他国軍隊に後方支援」は被侵略国人民を武装鎮圧するもの
骨格案の第3に「国際社会の平和と安全への一層の貢献」として、「国際社会の平和と安全のために活動する他国軍隊に対する後方支援を自衛隊が実施できる」ように新法を作り、国連PKOでの業務の拡大と武器使用の権限の見直し」を行い、「国連が統括しない人道復興支援活動」をできるようにする。
ここでも「国際社会の平和と安全」に貢献するために自衛隊を海外に派兵するということである。この骨格案の冒頭に「わが国が日本国憲法の下で平和国家として歩んできたこと」を変更し、すなわち憲法9条を拡大解釈し、“自衛のための武力の行使は権利としてあるが海外での武力の行使は禁止されている”としてきたこれまでの自民党の歴代内閣の立場を根底から覆し、自衛隊が「国際社会の平和と安定」を口実に海外で武力を行使する、戦争をできるようにするというのだ。
それは「活動する他国軍隊」に、すなわち活動とは戦争を行っている他国軍隊に後方支援ができるようにするのだ。軍隊の「活動」とは戦争なのだ。戦争をしている軍隊への後方支援は戦争活動そのものである。これは今までの自衛隊法の延長上では対応できないので新法を作る。
この新法の要件として挙げている4条件は何の歯止めにもならない。①「他国の武力の行使との一体化を防ぐ枠組み」をあげているが「活動する他国の軍隊に後方支援を実施する」ことがすでに他国の武力行使との一体化にもかかわらず一体化を防ぐ枠組があるとしたら、それは後方支援をやめること以外にない。②国連決議に基づくと「関連する国連決議」は国連憲章第51条が集団的自衛権の行使を認めている限り国連決議は軍事力の行使しか反映しない。③「国会の事前承認を基本」とはあくまでも基本であって例外、国会の事後承認、軍事の先行を認めるための口実でしかない。④「自衛隊員の安全確保」の最良の手段は武器を使用しないことである。それ以外は必ず安全確保のための武器使用を前提としている。
もう一つの「国際的な平和協力活動」への自衛隊派兵はPKO協力法の改正で対応するという。まずはPKOでの自衛隊の業務の拡大とは治安維持の活動とそれを遂行できる武器の使用である。警察官の治安の維持もイスラエルでは催涙ガスやゴム弾、音響弾などを使い火器も使われ、それどころか治安維持に出てくるのは正規軍と兵士である。自衛隊が治安雄維持に当たるということはイスラエルの軍隊と同じ行動をすることであり、規制された人々からの反撃を受けるのは当然である。
PKO5原則とは①紛争当事者間の停戦合意が成立、②紛争当時者が日本の参加に同意、③中立的立場を厳守、④以上の条件を満たさなければ撤収可能。⑤武器使用は生命防護のため必要最小限~の5点だが、政府は5原則の文言は変えないものの実質的に見直すとしている。
その内容は①安全確保ができれば停戦合意は必要ない(紛争当事者がいない地域での活動を想定)。②新たな任務に「治安維持」を加える。③「人道復興支援の一環として武器使用権限を拡大する」と3月6日に明らかにしている。「人道復興支援活動」とは現在米国が組織している対イスラム国への有志連合などをさす。この発動の要件も「PKOの参加5原則と同様の厳格な原則」として安倍政権はPKO5原則も改悪することを示唆している。
PKO協力法を改定し住民の保護などの治安維持を新たな任務として追加、任務遂行型の武器使用を認めるというのだ。
(5)「武力行使新3要件」は何でも集団的自衛権行使可能に
骨格案の第4は「憲法9条の下で許容される自衛の措置」とあるが、これが集団的自衛権行使容認のことである。この新しい安全保障法制の骨格案には集団的自衛権という文言は出てこない。自衛権の中に個別的・集団的自衛権は両方とも含まれるというように解釈を変更するというのが安倍政権の主張だからである。
そのやり方は「事態対処法、自衛隊法などに規定されている『武力の行使』の要件を精査し『新3要件』及び上記の考え方(昨年7月の閣議決定とその後の国会質疑)をそれらの条文に過不足なく盛り込む」というのだ。
武力行使新3要件とは①わが国またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある。②これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適切な手段がない。③必要最小限度の実力行使にとどまる。その3点である。
「過不足なく盛り込む」とは何のことはない。新3要件を満たせば集団的自衛権を行使できる、というように自衛隊法・事態対処法を改正するというのだ。そして集団的自衛権の行使できる事態を「新事態(重要影響事態)」として自衛隊が防衛出動、あくまでも防衛出動の法的体裁で合憲とするのだが、自衛隊が出動・海外派兵できるとするのだ。だから「新事態に対応する自衛隊の行動及びその際の武力行使」については「現行自衛法76条(防衛出動)及び第88条(防衛出動時の武力行為)によるもの」とするというのだ。これらは全て憲法9条を改悪するものであるが「解釈の変更」という形をとるかぎり、詭弁をもってするしかないのである。
3月3日の衆院予算委で、中東・ホルムズ海峡での自衛隊の機雷掃海が集団的自衛権行使の要件に該当するのか、が論議された。
民主党は木村答弁(1954年国会、当時保安庁長官)を引用し武力攻撃事態に海上封鎖が含まれるかはその危機の切迫性が「国民の糧道を断ち、生産物質を断つ。そうして日本を危殆(きたい)に陥らしめる」を引用しホルムズ海峡封鎖は「石油不足だけでは日本国民への死活的な影響は考えにくい。次元が違う」と質問した。首相・安倍晋三は「石油が突然ドンと遮断されると相当にパニックになる。そういう事態にも切れ目のない対応が必要」、「直ちに多くが餓死しなくても要件に当てはまらないとは考えていない」と答弁している。
機雷掃海が国連決議での集団安全保障措置で要請された場合も、新3要件を満たせば機雷掃海はできる、と安倍は答弁した。民主党の「次元が違う」論は逃げている。真正面から「石油の確保のために戦争をするのか」「資源のために再び戦争を繰り返すのか」と真正面から切り込んでいく以外にない。
(6)関連法もすべて改悪に
骨格案の第5は「その他関連する法改正事項」であり、そこでは①船舶検査活動では「周辺事態安全確保法の見直しに伴う改正を検討」すると共に「国際社会の平和と安全に必要な場合の船舶検査活動の実施について法整備を検討する」となっている。臨検時の武器使用は見送りという報道もあるが検討課題となっている。
②「自衛隊法の規定に基づく他国軍隊に対する物品・役務の提供」は米軍が「情報収集・警戒監視等具体的ニーズが存在する分野においても物品・役務を提供」できるように法整備する。
③「在外邦人の救出」では「武器使用を伴う在外邦人の救出」ができるようにする。在外邦人救出の事例としてハイジャック、在外公館が占拠、国外退避の日本人が取り囲まれる、連れ去られるなどをあげ、派遣先の領域国の同意が必要であり、イスラム国の人質事件は領域国の同意が満たされず救出は難しいとの認識を示している(3.2)。
また救出活動時は正当防衛ではなく任務を遂行するための威嚇射撃ができるように武器の使用基準を緩和する。
3月11日の与党協議で政府は武器使用を伴う邦人救出では武装勢力との交戦のリスクが高いので、自衛隊員の安全確保が前提となり、派遣の条件は領域国の権力が維持され同意があることで、具体的には武力紛争が発生していない、領域国の治安機関が治安維持に当たっている、を例示している。「交戦のリスクが高い」とはそのまま戦争に突入することもあるのであり、にもかかわらず「内閣総理大臣の承認」で可能としている。
④国家安全保障会議の審議事項がある。
以上が5月18日に自公が合意した「安全保障法制整備の具体的な方向性について」(骨格案)についての逐条批判である。
集団的自衛権の行使容認にかかわる安全保障法制の整備とは憲法9条を亡きものとし、自衛隊を再び海外に派兵し、戦争のできる国となるための法整備である。さまざまな口実を設けて先に侵略戦争に踏み切り、後で法改訂をしようとする暴挙である。このことに反対しよう。沖縄の闘いとヤマトでの安保法制整備阻止を自衛隊海外派兵阻止と一体のものとして闘おう。
2015年3月27日
博多のアイアン・バタフライ
(Ⅰ)戦後70年、自衛隊海外侵略戦争に踏み込む――この現実を全力で覆そう
3月18日、自公は集団的自衛権の行使容認の「安全保障法制整備の骨格」で合意した。あたかも公明党が自民党の暴走に歯止めをかけるかのような構図をデッチあげながら、実際は公明党が落としどころを誘導していくような猿芝居が、昨年の憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認の閣議決定過程に続き今回も繰り返された。
最近の世論調査(3.20~22、日経新聞・テレビ東京が共同実施)でも「集団的自衛権の行使可能の関連法案」に賛成31%、反対51%。「自衛隊の海外活動の拡大」は賛成43%、反対41%となっている。質問の文言で世論調査の結果は変わるが、この質問が「集団的自衛権」の具体的内容であり、「自衛隊の海外活動の拡大」の具体的内容である「自衛隊が海外で侵略戦争をすることに賛成ですか」という質問の文言に変えればもっと反対は増えるだろう。日経新聞の恣意的な質問でも反対は51%であり、憲法解釈変更での集団的自衛権行使容認が問題になって以降、反対は半数を超えている。
日経新聞はこの世論調査の結果に焦りを募らせ3月14日の社説で安倍政権に“情報不足・説明不足を何とかしろ”と助言している。これは反対派にもいえる。集団的自衛権行使容認の安全保障法整備の問題点をわかりやすく示し、闘う行動方針を示せていない。統一地方選挙の結果次第では全てが承認されたと片付けられかねない、階級闘争の主体的危機でもある。戦後70年にして安倍政権は自衛隊海外侵略戦争に踏み込むのだ。この現実を決してあいまいにしてはならない。全力で覆そう。
集団的自衛権の行使容認に関する安保法制整備の骨格は自衛隊の海外活動(海外派兵である)を広げるための五つの分野で合意した。
その具体的内容は、①外国からの武力攻撃に至らない「グレーゾーン」への対処では警戒などで一緒に行動する米軍などを守る。自衛隊法を改正。②「他国軍への後方支援」では周辺事態法改正と恒久法を新設、周辺事態法の地理的制約をなくし重要影響事態なら日本周辺以外でも後方支援できる。恒久法は日本の安全保障に影響がなくても国際協力の一環として他国軍隊への後方支援ができる。自衛隊を海外派遣しやすくする。③「人道復興支援」など国際貢献ではPKOだけでなく有志連合にも積極的に参加できるようにPKO協力法を改正し治安維持の任務も認める。④「集団的自衛権の行使」は武力行使の新3要件を満たす状況を新事態とし、自衛隊が防衛出動して他国軍を守れるすなわち戦争ができるように自衛隊法と武力攻撃事態法を改正する。⑤「邦人救出を含むその他の法改正」の5分野である。国会承認などの義務付けは協議する、というものである。
●自衛隊海外派兵を容易かつスムーズに
集団的自衛権とは自衛隊を海外に派兵することであり、戦争をすることであり、安全保障法制の整備とは自衛隊海外派兵を容易かつスムーズに行うための法整備なのだ。この点を何度も何度も繰り返し明らかにしていくことである。
またそれを阻止するための行動方針は、何よりも沖縄・辺野古での新基地建設阻止闘争を闘うことである。集団的自衛権の行使はまず米軍と自衛隊の共同行動・共同作戦で実施される。
4月28日の日米首脳会談に先立ってワシントンで日米防衛相・外務相の会合2プラス2で日米防衛協力の指針が改定され、集団的自衛権を行使できるとした自衛隊の具体的任務が決定される。この攻防の中心が辺野古新基地建設攻撃である。
●辺野古新基地建設と一体の攻撃
それだけではない。主権者である沖縄の民意を踏みにじり、足蹴にし、あろうことか面会を求める翁長雄志沖縄県知事を拒絶し、追い返した安倍、岸田、中谷とりわけ薄ら笑いさえ浮かべる官房長官・菅義偉の姿は侵略者の態度であり、沖縄を植民地として扱っているもの以外の何ものでもない。
3月23日の翁長知事の「腹は固めている」とした工事中止の決断に対して官房長官・菅は「この期に及んで……」と発言している。なんという言い草か。翁長知事の決断を受け、闘いを法廷だけで終わらせてはならない。法廷から引っ張り出すことだ。海上で、ゲート前で、辺野古の浜での大衆的阻止闘争を闘いぬこう。全国からから駆けつけることである。
辺野古に駆けつけられる人は駆けつけよう。自分が無理な人はカンパを集め代表を送ろう。辺野古と同時に普天間に配備されたオスプレイ訓練のために北部演習場のヘリパッド建設を体を張って阻止している沖縄・高江の闘いにも駆けつけよう。
重要なことはヤマトでの闘いである。沖縄での闘いに連帯してヤマトでの集団的自衛権行使を容認する安保法制整備、自衛隊の海外派兵を阻止する闘いを爆発させることである。沖縄での新基地建設に反対する闘いとヤマトでの自衛隊を海外に派兵する集団的自衛権行使容認の安保法整備に反対する闘いを一体のものとして進めよう。
(Ⅱ)先に侵略戦争、後で法改訂の暴挙
以下、「安全保障法制整備の具体的な方向性について」(骨格案)の批判である。
同骨格案の目次は
1.全般
2.武力攻撃に至らない侵害への対処
3.わが国の平和と安全に資する活動を行う他国軍隊に対する支援活動
4.国際社会の平和と安全への一層の貢献
5.憲法9条の下で許容される自衛の措置
6.その他関連する法改正事項
~となっている。
(1)「切れ目のない対応」とは自衛隊派兵のハードルを無くすもの
「1.全般」では「いかなる事態」にも「切れ目のない対応」を打ち出し、この「切れ目のない対応」を可能とする法整備として、「特に自衛隊の海外における活動の参加」を可能とする三つの方針を挙げている。
つまり「安全保障法制整備の具体的な方向性について」とは自衛隊の海外派兵を可能にする判断基準の3点(国際法上の合法性、国会の関与等の民主的統制、自衛隊の安全を確保)を示しているのだ。この基準・3原則は2月27日に公明党副代表・北側一雄が提唱し「北側3原則」と呼ばれ公明党が果たす悪質な役割を良く示している。
また安倍晋三が繰り返す「切れ目のない対応」とは何か外交上の事件が起こったときに「国際紛争の解決の手段」として「国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使を放棄する」という立場から外交的努力を尽くすのではなく、憲法9条を亡きものにし、どんな外交上の小さな事件でも自衛隊を派兵して対処するということなのだ。しかもその自衛隊海外派兵での対処の決定過程に民意や国会の意見を反映させることなく、法律に決めてあることなので「ある種自動的に」時の首相―内閣が判断し実行して行くとするものでもある。
まず「切れ目のない対応」があたかも「国民の命と平和な暮らしを守る」ために必要であるかのように記述しているが、「切れ目のない対応」とは自衛隊の海外派兵を実行する法律がないのでそれを作ろうという口実なのだ。自衛隊の海外派兵は憲法9条で禁止しているからないのは当然である。ない、のではなく、禁止しているのだ。この憲法9条を「切れ目のない対応」の一言で片付けている。
この一言で片付けられる憲法9条には「弱点」がある。それは国際紛争の解決の手段として「国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使」を放棄しているが、自衛権の保有と行使につけ込まれる隙が意図的に作られていた。この隙を埋めるためには戦争放棄ではなく戦争をこの世界からなくすために何をしなければならないのかを問題にしなければならない。憲法9条を守り抜くことは、戦争の放棄から戦争をなくす9条への飛躍が必要なのだ。
この骨格案で「海外派兵の基準」(国際法上の正当性、民主的統制、自衛隊員の安全を確保の3点)なるものを打ち出した。戦後70年の今日、侵略戦争への反省・二度と繰り返さないという決意がこの「海外派兵の基準」の3点に満たされているのか。とんでもない。国際法ほど曖昧なものはない。いや国際法は戦争を繰り返してきた現実の政治の反映、容認でしかない。国際法遵守は国際紛争を戦争に訴える、自衛隊を海外派兵することそのものであり、制限ではなく海外派兵の条件になる。国会承認などの民主的統制も危うい。すでにこの骨格案でも事後承認を押し付けている。自衛隊員の安全を確保とは危険な場所に近づかないのではなく武器のエスカレートでの安全の確保である。
(2)自衛隊が名実ともに武装した軍隊に
骨格案は第1に、「武力攻撃に至らない侵害」という「グレーゾーン事態」についての問題は武力攻撃に至らないのだから自衛隊が出動したり武器を使用したりする必要はないのだが、ここでは“演習などで一緒に行動している米軍が攻撃されたときに自衛隊は米軍を見捨てるのか”という論法で切り崩そうとしている。
自衛隊が武器防護のために武器使用ができる自衛隊法の規定を利用し、米軍の武器のためのみならず「わが国の防衛に資する活動」「わが国の防衛力を構成する重要な物的手段」を「武器などの防護」という範疇でくくり、自衛隊が武器を使用することができるとしている。万事がこのように屁理屈を持ち込んで現行法の拡大解釈で、それがどうしても無理の場合は新法を制定して自衛隊が武器を使用できる、戦争ができるようにするのだ。この屁理屈は自衛隊が戦争をすることをわかりにくくする手法である。
しかもその手続きは「国家安全保障会議の審議を含め内閣の関与を確保」でよいというのだ。内閣の決定で戦争を始めることができるようになる。
自衛隊法第7章(自衛隊の権限)に自衛隊の権限と武力行使についての規定がある。治安出動、警護出動、防衛出動、国民保護等派遣、海上における警備活動、海賊対処行動、弾道ミサイル等に対する破壊措置、災害派遣、在外邦人等の輸送、後方地域支援、防衛出動時における海上輸送の規制、捕虜等の取り扱い、部内の秩序維持に専従する者についての権限と武器使用~を定めており、95条に武器防護のための武器使用と自衛隊施設の警護のための武器使用を定めている。この安保法制整備の狙いは、武力攻撃に至らなくても自衛隊が武器使用できることを定めようというものである。
(3)自衛隊が米軍と共同して世界中で軍事行動
骨格案の第2は、「わが国の平和と安全に資する活動を行う他国軍隊に対する支援活動」である。周辺事態法(周辺事態に際してわが国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律)では朝鮮半島有事を念頭に、“放置すればわが国に直接の武力攻撃に至る恐れがある事態においては自国の領域でなくても軍事行動を起こすことができる”と定めている。朝鮮半島有事という地理的限定を含んでいる。それに対して今回の他国軍隊への支援活動は「わが国の平和と安全に重要な影響を与える事態」という周辺事態に代わる「新事態(重要影響事態)」を作り出し、地理的制限をとり払い、「日米安保の効果的運用に寄与」し新事態に対応して行動する米軍と他国軍を支援できるようにする。
実施に当たっての要件として「他国の武力行使との一体化(明確な憲法違反)を防ぐための枠組」「原則国会の事前承認」を挙げている。枠組なるものは具体的には不明であり、国会承認も原則であり、事後承認もあるということである。
(4)「他国軍隊に後方支援」は被侵略国人民を武装鎮圧するもの
骨格案の第3に「国際社会の平和と安全への一層の貢献」として、「国際社会の平和と安全のために活動する他国軍隊に対する後方支援を自衛隊が実施できる」ように新法を作り、国連PKOでの業務の拡大と武器使用の権限の見直し」を行い、「国連が統括しない人道復興支援活動」をできるようにする。
ここでも「国際社会の平和と安全」に貢献するために自衛隊を海外に派兵するということである。この骨格案の冒頭に「わが国が日本国憲法の下で平和国家として歩んできたこと」を変更し、すなわち憲法9条を拡大解釈し、“自衛のための武力の行使は権利としてあるが海外での武力の行使は禁止されている”としてきたこれまでの自民党の歴代内閣の立場を根底から覆し、自衛隊が「国際社会の平和と安定」を口実に海外で武力を行使する、戦争をできるようにするというのだ。
それは「活動する他国軍隊」に、すなわち活動とは戦争を行っている他国軍隊に後方支援ができるようにするのだ。軍隊の「活動」とは戦争なのだ。戦争をしている軍隊への後方支援は戦争活動そのものである。これは今までの自衛隊法の延長上では対応できないので新法を作る。
この新法の要件として挙げている4条件は何の歯止めにもならない。①「他国の武力の行使との一体化を防ぐ枠組み」をあげているが「活動する他国の軍隊に後方支援を実施する」ことがすでに他国の武力行使との一体化にもかかわらず一体化を防ぐ枠組があるとしたら、それは後方支援をやめること以外にない。②国連決議に基づくと「関連する国連決議」は国連憲章第51条が集団的自衛権の行使を認めている限り国連決議は軍事力の行使しか反映しない。③「国会の事前承認を基本」とはあくまでも基本であって例外、国会の事後承認、軍事の先行を認めるための口実でしかない。④「自衛隊員の安全確保」の最良の手段は武器を使用しないことである。それ以外は必ず安全確保のための武器使用を前提としている。
もう一つの「国際的な平和協力活動」への自衛隊派兵はPKO協力法の改正で対応するという。まずはPKOでの自衛隊の業務の拡大とは治安維持の活動とそれを遂行できる武器の使用である。警察官の治安の維持もイスラエルでは催涙ガスやゴム弾、音響弾などを使い火器も使われ、それどころか治安維持に出てくるのは正規軍と兵士である。自衛隊が治安雄維持に当たるということはイスラエルの軍隊と同じ行動をすることであり、規制された人々からの反撃を受けるのは当然である。
PKO5原則とは①紛争当事者間の停戦合意が成立、②紛争当時者が日本の参加に同意、③中立的立場を厳守、④以上の条件を満たさなければ撤収可能。⑤武器使用は生命防護のため必要最小限~の5点だが、政府は5原則の文言は変えないものの実質的に見直すとしている。
その内容は①安全確保ができれば停戦合意は必要ない(紛争当事者がいない地域での活動を想定)。②新たな任務に「治安維持」を加える。③「人道復興支援の一環として武器使用権限を拡大する」と3月6日に明らかにしている。「人道復興支援活動」とは現在米国が組織している対イスラム国への有志連合などをさす。この発動の要件も「PKOの参加5原則と同様の厳格な原則」として安倍政権はPKO5原則も改悪することを示唆している。
PKO協力法を改定し住民の保護などの治安維持を新たな任務として追加、任務遂行型の武器使用を認めるというのだ。
(5)「武力行使新3要件」は何でも集団的自衛権行使可能に
骨格案の第4は「憲法9条の下で許容される自衛の措置」とあるが、これが集団的自衛権行使容認のことである。この新しい安全保障法制の骨格案には集団的自衛権という文言は出てこない。自衛権の中に個別的・集団的自衛権は両方とも含まれるというように解釈を変更するというのが安倍政権の主張だからである。
そのやり方は「事態対処法、自衛隊法などに規定されている『武力の行使』の要件を精査し『新3要件』及び上記の考え方(昨年7月の閣議決定とその後の国会質疑)をそれらの条文に過不足なく盛り込む」というのだ。
武力行使新3要件とは①わが国またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある。②これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適切な手段がない。③必要最小限度の実力行使にとどまる。その3点である。
「過不足なく盛り込む」とは何のことはない。新3要件を満たせば集団的自衛権を行使できる、というように自衛隊法・事態対処法を改正するというのだ。そして集団的自衛権の行使できる事態を「新事態(重要影響事態)」として自衛隊が防衛出動、あくまでも防衛出動の法的体裁で合憲とするのだが、自衛隊が出動・海外派兵できるとするのだ。だから「新事態に対応する自衛隊の行動及びその際の武力行使」については「現行自衛法76条(防衛出動)及び第88条(防衛出動時の武力行為)によるもの」とするというのだ。これらは全て憲法9条を改悪するものであるが「解釈の変更」という形をとるかぎり、詭弁をもってするしかないのである。
3月3日の衆院予算委で、中東・ホルムズ海峡での自衛隊の機雷掃海が集団的自衛権行使の要件に該当するのか、が論議された。
民主党は木村答弁(1954年国会、当時保安庁長官)を引用し武力攻撃事態に海上封鎖が含まれるかはその危機の切迫性が「国民の糧道を断ち、生産物質を断つ。そうして日本を危殆(きたい)に陥らしめる」を引用しホルムズ海峡封鎖は「石油不足だけでは日本国民への死活的な影響は考えにくい。次元が違う」と質問した。首相・安倍晋三は「石油が突然ドンと遮断されると相当にパニックになる。そういう事態にも切れ目のない対応が必要」、「直ちに多くが餓死しなくても要件に当てはまらないとは考えていない」と答弁している。
機雷掃海が国連決議での集団安全保障措置で要請された場合も、新3要件を満たせば機雷掃海はできる、と安倍は答弁した。民主党の「次元が違う」論は逃げている。真正面から「石油の確保のために戦争をするのか」「資源のために再び戦争を繰り返すのか」と真正面から切り込んでいく以外にない。
(6)関連法もすべて改悪に
骨格案の第5は「その他関連する法改正事項」であり、そこでは①船舶検査活動では「周辺事態安全確保法の見直しに伴う改正を検討」すると共に「国際社会の平和と安全に必要な場合の船舶検査活動の実施について法整備を検討する」となっている。臨検時の武器使用は見送りという報道もあるが検討課題となっている。
②「自衛隊法の規定に基づく他国軍隊に対する物品・役務の提供」は米軍が「情報収集・警戒監視等具体的ニーズが存在する分野においても物品・役務を提供」できるように法整備する。
③「在外邦人の救出」では「武器使用を伴う在外邦人の救出」ができるようにする。在外邦人救出の事例としてハイジャック、在外公館が占拠、国外退避の日本人が取り囲まれる、連れ去られるなどをあげ、派遣先の領域国の同意が必要であり、イスラム国の人質事件は領域国の同意が満たされず救出は難しいとの認識を示している(3.2)。
また救出活動時は正当防衛ではなく任務を遂行するための威嚇射撃ができるように武器の使用基準を緩和する。
3月11日の与党協議で政府は武器使用を伴う邦人救出では武装勢力との交戦のリスクが高いので、自衛隊員の安全確保が前提となり、派遣の条件は領域国の権力が維持され同意があることで、具体的には武力紛争が発生していない、領域国の治安機関が治安維持に当たっている、を例示している。「交戦のリスクが高い」とはそのまま戦争に突入することもあるのであり、にもかかわらず「内閣総理大臣の承認」で可能としている。
④国家安全保障会議の審議事項がある。
以上が5月18日に自公が合意した「安全保障法制整備の具体的な方向性について」(骨格案)についての逐条批判である。
集団的自衛権の行使容認にかかわる安全保障法制の整備とは憲法9条を亡きものとし、自衛隊を再び海外に派兵し、戦争のできる国となるための法整備である。さまざまな口実を設けて先に侵略戦争に踏み切り、後で法改訂をしようとする暴挙である。このことに反対しよう。沖縄の闘いとヤマトでの安保法制整備阻止を自衛隊海外派兵阻止と一体のものとして闘おう。
2015年3月27日
博多のアイアン・バタフライ















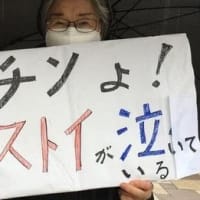




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます