いま左翼であることはどういうことか
絓 秀実 (文芸評論家)
水谷保孝+岸 宏一著『革共同政治局の敗北 1975~2014 あるいは中核派の崩壊』、池田信夫著『戦後リベラルの終焉 なぜ左翼は社会を変えられなかったのか』
『映画芸術』452号 Book Review から転載
2015年7月30日刊
「左翼」の定義は今や融解しているが、ここではとりあえず、一九六八年の世界的騒擾=革命(いわゆる「六八年革命」)を担った勢力と規定しておく。その意味では、『戦後リベラルの終焉』(以下、『終焉』と略)の池田信夫がサブタイトルで言う「左翼」(あるいは「戦後リベラル」)とはやや異なる概念である。日本の六八年「左翼」は、戦後思想あるいは戦後政治の総体を否定しようとした。まさに、「戦後政治の総決算」である。それゆえ、ここで言う「左翼」は水谷保孝・岸宏一の『革共同政治局の敗北』(以下、『敗北』と略)が論議の対象としている中核派を、一応は包摂する。しかし、両者がまったく無縁ではない、というところに、論ずべき「左翼」の複雑さもある。
日本の六八年革命の後期に生起した一九七〇年のいわゆる「七・七華青闘告発」は、現在ようやく、その重要性を歴史研究のなかでも認識されつつあるが、日本の六八年が六八年の世界性へと連なることを可能にした画期であった。そのことを詳述する余裕はここではないので、『革命的な、あまりに革命的な』など幾つかの拙著への参照を求めるにとどめる。六〇年安保において大衆的に登場したブント=全学連をはじめとする「新左翼」は、むしろ「戦後リベラルの」最左派であり、その意味で、ナショナルな存在であったが、そのナショナリズムが在日中国人・台湾人のグループ(華青闘=華僑青年闘争委員会)によって決定的に批判され、ナショナリズムからの飛躍を求められることになったのである。以後、新左翼総体は民族問題やフェミニズムなどのマイノリティー運動へとシフトすることになるが、それが単に新左翼のレベルにとどまらぬ広がりをもっていたことは、今日の在特会から従軍慰安婦の問題を一瞥するだけで了解されよう。
『敗北』の著者たちが属していた中核派は、華青闘告発をもっとも深刻に受け止めた政治党派であり、著者たちは一九七〇年の中核派の政治路線の変更に力を注いできた中心的な政治指導部であった。この政治路線は「血債の思想」と呼ばれた。しかし、『敗北』に詳述されているように、中核派はマイノリティー運動を重視するその路線を破棄して、古典的な(あるいは、サンディカリズム的な)労働運動路線へと再び大転換する。およそ二〇〇〇年代後半のことであり、この路線転換のなかで、著者たちは除名処分となる。
これは単に一新左翼政治党派内の問題にとどまらぬ、象徴的な出来事だったろう。『敗北』に従うかぎり、マイノリティー運動の重視、つまりさまざまな「差別」を問題にしていくほかない「血債の思想」に、労働者など一般党員は耐えられないというのが、労働運動路線への転換の背景にあった様子だからである。つまり、とりあえずその正負は問わず、在特会から「一般」中核派党員まで、差別問題は「ウザい」という心性が広がっていたことがうかがえる。在特会と、それに対するカウンターについては、多くの議論が必要だが、私見の及ぶところでは、中核派をはじめとする新左翼の反応が今一つ鈍い様子なのも、おそらくは、このあたりに理由があるのだろう。在特会に対向する「レイシストしばき隊」にしても、「ヘサヨ」を生み出した華青闘告発を「諸悪の根源」と見なしている。「ヘサヨ」は「ウザい」のである。
日本では華青闘告発が決定的端緒となったマイノリティー運動へのシフトは、「血債の思想」といった強い形を取ったというよりは、PC(ポリティカル・コレクトネス)と呼ばれるリベラリズムに吸収された。今や左翼といえばリベラルの同義と化してしまった感があるが、PCというレベルで言うなら、安倍首相でさえPCを否定できはしまい。ただ、「ウザい」と思っているだけであろう。この意味で、池田信夫の言とは異なって、左翼は社会を変えたのだが、確かにリベラルは終焉しているのである。
しかし問題は、なぜ今や左翼がリベラルの同義となってしまったのか、というところにある。奇妙なことに『終焉』も『敗北』もあまり重視していない様子なのだが、「左翼」がリベラルでしかありえなくなった契機は、言うまでもなく、ソ連邦の崩壊と中国の資本主義化である。六八年の「左翼」はおおむね「反スターリン主義」を標榜して、ソ連はもちろん中国にも否定的だった。しかし、対象が否定的であろうとそれらが存在するということは、「共産主義」というファンタスムを可能にしてくれたわけである。これは、池田の言う「戦後リベラル」においても同様であった。戦後リベラルは、ソ連なり中国なりが「平和勢力」だというファンタスムの上で可能であった。たとえ平和勢力だなどと本気で思っていなくても、である。しかも、逆説的なことに、ソ連邦の解体を促したのは、六八年の世界革命であったとも言えるのである。中国の資本主義化についても然り。
「共産主義」や「平和勢力」といったファンタスムが不可能な時に、左翼やリベラルであるとは、どういうことなのだろうか。それは、ジジェクの言葉を借りれば、「アルコール抜きのビール」で酔っぱらおうとすることである。あるいは、ノンアルコールビールだと知りながら、どこかにアルコールの破片が隠れていると言い募ることである。しかし、それは端的に欺瞞でしかないだろう。だとすれば、今なお「左翼」であろうとすれば、革命はビールを飲むことではないと見做すこと、つまり革命の概念をラディカルに変えることではないだろうか。
すが ひでみ◎沖島勲の死を悼む。
絓 秀実 (文芸評論家)
水谷保孝+岸 宏一著『革共同政治局の敗北 1975~2014 あるいは中核派の崩壊』、池田信夫著『戦後リベラルの終焉 なぜ左翼は社会を変えられなかったのか』
『映画芸術』452号 Book Review から転載
2015年7月30日刊
「左翼」の定義は今や融解しているが、ここではとりあえず、一九六八年の世界的騒擾=革命(いわゆる「六八年革命」)を担った勢力と規定しておく。その意味では、『戦後リベラルの終焉』(以下、『終焉』と略)の池田信夫がサブタイトルで言う「左翼」(あるいは「戦後リベラル」)とはやや異なる概念である。日本の六八年「左翼」は、戦後思想あるいは戦後政治の総体を否定しようとした。まさに、「戦後政治の総決算」である。それゆえ、ここで言う「左翼」は水谷保孝・岸宏一の『革共同政治局の敗北』(以下、『敗北』と略)が論議の対象としている中核派を、一応は包摂する。しかし、両者がまったく無縁ではない、というところに、論ずべき「左翼」の複雑さもある。
日本の六八年革命の後期に生起した一九七〇年のいわゆる「七・七華青闘告発」は、現在ようやく、その重要性を歴史研究のなかでも認識されつつあるが、日本の六八年が六八年の世界性へと連なることを可能にした画期であった。そのことを詳述する余裕はここではないので、『革命的な、あまりに革命的な』など幾つかの拙著への参照を求めるにとどめる。六〇年安保において大衆的に登場したブント=全学連をはじめとする「新左翼」は、むしろ「戦後リベラルの」最左派であり、その意味で、ナショナルな存在であったが、そのナショナリズムが在日中国人・台湾人のグループ(華青闘=華僑青年闘争委員会)によって決定的に批判され、ナショナリズムからの飛躍を求められることになったのである。以後、新左翼総体は民族問題やフェミニズムなどのマイノリティー運動へとシフトすることになるが、それが単に新左翼のレベルにとどまらぬ広がりをもっていたことは、今日の在特会から従軍慰安婦の問題を一瞥するだけで了解されよう。
『敗北』の著者たちが属していた中核派は、華青闘告発をもっとも深刻に受け止めた政治党派であり、著者たちは一九七〇年の中核派の政治路線の変更に力を注いできた中心的な政治指導部であった。この政治路線は「血債の思想」と呼ばれた。しかし、『敗北』に詳述されているように、中核派はマイノリティー運動を重視するその路線を破棄して、古典的な(あるいは、サンディカリズム的な)労働運動路線へと再び大転換する。およそ二〇〇〇年代後半のことであり、この路線転換のなかで、著者たちは除名処分となる。
これは単に一新左翼政治党派内の問題にとどまらぬ、象徴的な出来事だったろう。『敗北』に従うかぎり、マイノリティー運動の重視、つまりさまざまな「差別」を問題にしていくほかない「血債の思想」に、労働者など一般党員は耐えられないというのが、労働運動路線への転換の背景にあった様子だからである。つまり、とりあえずその正負は問わず、在特会から「一般」中核派党員まで、差別問題は「ウザい」という心性が広がっていたことがうかがえる。在特会と、それに対するカウンターについては、多くの議論が必要だが、私見の及ぶところでは、中核派をはじめとする新左翼の反応が今一つ鈍い様子なのも、おそらくは、このあたりに理由があるのだろう。在特会に対向する「レイシストしばき隊」にしても、「ヘサヨ」を生み出した華青闘告発を「諸悪の根源」と見なしている。「ヘサヨ」は「ウザい」のである。
日本では華青闘告発が決定的端緒となったマイノリティー運動へのシフトは、「血債の思想」といった強い形を取ったというよりは、PC(ポリティカル・コレクトネス)と呼ばれるリベラリズムに吸収された。今や左翼といえばリベラルの同義と化してしまった感があるが、PCというレベルで言うなら、安倍首相でさえPCを否定できはしまい。ただ、「ウザい」と思っているだけであろう。この意味で、池田信夫の言とは異なって、左翼は社会を変えたのだが、確かにリベラルは終焉しているのである。
しかし問題は、なぜ今や左翼がリベラルの同義となってしまったのか、というところにある。奇妙なことに『終焉』も『敗北』もあまり重視していない様子なのだが、「左翼」がリベラルでしかありえなくなった契機は、言うまでもなく、ソ連邦の崩壊と中国の資本主義化である。六八年の「左翼」はおおむね「反スターリン主義」を標榜して、ソ連はもちろん中国にも否定的だった。しかし、対象が否定的であろうとそれらが存在するということは、「共産主義」というファンタスムを可能にしてくれたわけである。これは、池田の言う「戦後リベラル」においても同様であった。戦後リベラルは、ソ連なり中国なりが「平和勢力」だというファンタスムの上で可能であった。たとえ平和勢力だなどと本気で思っていなくても、である。しかも、逆説的なことに、ソ連邦の解体を促したのは、六八年の世界革命であったとも言えるのである。中国の資本主義化についても然り。
「共産主義」や「平和勢力」といったファンタスムが不可能な時に、左翼やリベラルであるとは、どういうことなのだろうか。それは、ジジェクの言葉を借りれば、「アルコール抜きのビール」で酔っぱらおうとすることである。あるいは、ノンアルコールビールだと知りながら、どこかにアルコールの破片が隠れていると言い募ることである。しかし、それは端的に欺瞞でしかないだろう。だとすれば、今なお「左翼」であろうとすれば、革命はビールを飲むことではないと見做すこと、つまり革命の概念をラディカルに変えることではないだろうか。
すが ひでみ◎沖島勲の死を悼む。



















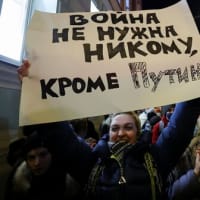
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます