友への手紙――「憲法改正に異議あり!」~天皇と戦争をめぐって
●憲法改正の是非が参院選の焦点に
参議院議員選挙が近づいてきました。7月21日投票の参院選は、まちがいなく今後の日本階級闘争の行く末を決する分岐点です。この選挙を契機にして「激動の時代」へと大きく動き出すでしょう。その最大の焦点が「憲法改正の是非」であり、世論は左右に大きく分裂していくものと考えています。まちがいなく時代は今、大きな分水嶺にさしかかっています。
以下、私なりに「憲法改正」問題について述べてみたいと思います。なお、ここで述べることは、昨年4月27日に発表された自民党改憲草案を資料としたものです。
●改憲問題の最大の争点は第1条にある
この間、改憲派、反対派の双方の主張・意見が出されています。が、私は何か腑に落ちません。納得できないというか、違和感を感じています。というのは、最大の争点を、双方とも触れていない、あるいは意図的に避けているように見えるからです。
最大の争点とは何か。言うまでもありません。国家の基本的あり方を規定した憲法第1章第1条です。憲法は、第1章第1条から第11章第103条までで構成されています。が、その中で、第1章第1条は特別な位置を占めています。それは、第1条が、国家の基本的在り方=統治形態を規定しているからです。憲法全文をその根底から、すべてにわたり規定し拘束するがゆえに、司法・行政・議会の3権の上に立つ概念だと私は考えています。
そこが大きく変えられようとしているのに、双方とも何も言わない。とりわけ改憲反対派の諸君です。賛成派が、これを焦点化したくないのは分かります(これについては後述します)。が、憲法学者・知識人・表現者・新旧左翼政党がまったく触れていない。反対意見はおろか、一元半句も言及していない。これは異常な事態であり、ありえないことです。
第9条(戦争放棄)、第96条(手続き条項)にかんしては、多くの方々が問題点を述べ、論陣を張っています。いわく。9条改憲は「軍事大国をめざすもの」、「戦争への一理塚」と。いわく。96条改憲で「手続き論を先行させるのはなぜか」、「何を変えるのかを、まずあきらかにすべき」と。その指摘はきわめて正しいし、重要な批判です。今後さらに9条改憲、96条改憲への批判を深めていかねばなりませんし、この点で反対運動の高揚と大衆運動の結集軸をつくっていかねばなりません。それを否定するものではありません。
しかし、1条批判をおろそかにしてよいはずがありません。否、1条改定の背景、そこに込められた日帝支配者階級の意図を分析・解明する作業を通して、9条改定の意味・全体像がよりいっそう浮かび上がってくると考えています。1条と9条。この両者は密接不可分の関係にあり、1条と関連づけて考えない9条論は、攻撃の凶暴さ、恐ろしさを見抜けず、9条と関連づけて考えない1条は、攻撃の全体像がぼやけてしまう。こう考えるからです。以下、その点を述べてみます。
●天皇の国家元首化にこだわる支配者階級
次の二つを読み比べてください。
【現行憲法】
第1章 天皇
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く
【自民党の憲法草案】
第1章 天皇
第1条 天皇は日本国の元首であり、日本国統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基く
先ほども述べたように、第1条は特別な条項です。国家の基本的在り方=統治形態を述べており、特別な意味をもちます。自民党改憲草案では、その第1条で、天皇の元首化が明記されている。これは非常に重要なことです。そして異なことに、その後に、象徴であるとも述べられています。「象徴天皇」と「元首天皇」を並列させている。あい反する・矛盾する概念を同時に用いる。これは文法上ありえません。
象徴天皇は自らの意思をもたない、非主体的存在です。意思も決定権ももちません。反して元首天皇は、主体的存在であり、自らの意思と絶大なる権力・影響力をもちます。象徴天皇は元首天皇たりえないし、元首天皇は象徴天皇ではない。両者正反対の意味をもつにもかかわらず、それを併記しています。ここに日帝支配者階級の苦悩がみてとれます。すなわち、“元首天皇といってもあまり変わりませんよ。これまでの象徴天皇の延長線上にあるのですよ”と言いたいのでしょう。争点をぼやかし、問題の所在を隠蔽しようとの意図がうかがわれます。姑息なやり方です。
なぜそこまでして、元首天皇にこだわるのか。日帝支配者階級の意図、そこにこめられた危機感と焦燥感、そして野望をみていきます。
●天皇と軍隊
近代史において、天皇はほとんど歴史の表舞台に登場していません。幕末~明治維新の激動期でもほとんど登場しませんでした。それほど影響力も存在感もなかったと言えます。唯一天皇が歴史に登場したのが、孝明天皇の死です。病死説、毒殺説の両論がありますが、「益御機嫌能被成為候(ますますご機嫌がよくなられました)」という内容の「御容態書」が提出されたその直後に死亡していること、さらには慶応2年1月25日死亡にもかかわらず、1月29日まで公表しなかった点からも、暗殺だと考えられます。天皇といえども、政治的に敵対すれば殺してもかまわない(「玉(ぎょく)を取る」の隠語で語られています)、それほど「権威も威厳もない」「軽い存在」だったようです。
その権威も威厳もない天皇が、後の1930年代の中国侵略戦争(日中戦争)時には、「神聖不可侵」にして「絶対無誤謬の現人神」の天皇へと変遷していくのですが、その必要性を痛感し、仕掛け人となった人物がいます。日本陸軍の創設者にして「国軍の父」と言われた山縣有朋です。彼は軍の創設者であるだけでなく、「天皇制と天皇制イデオロギー」の立案―導入―推進者だったと思われます。
転機になったのは1878年の西南戦争です。兵数においても火力・装備においても負けるはずのない政府軍が敗退します。この敗北の原因は何なのか? 反乱軍にあって政府軍にないものは何か? 明治政府の陸軍卿として陣頭指揮を執っていた山縣は考えました。そして行き着いた結論が、軍の士気―精神的支柱の有無です。旺盛な士気で鼓舞されている反乱軍に対し、しり込みし、算を乱して逃げる政府軍。前者にあって後者にないもの、それは死生観の有無だと考えたのではないでしょうか。
反乱軍は氏族階級であり、死生観として武士道(「武士道と云うは死ぬ事と見付けたり」『葉隠れ』)を有しています。対する新生政府軍にはそれがありません。武士道に匹敵する死生観を植えつける必要がある、山縣はこう考えたのでしょう。
西南戦争直後に山縣は即座に動きます。西郷自決で終焉したのが1878年9月4日。約40日後の10月12日に、陸軍卿・山縣有朋は全陸軍将兵に「軍人訓戒」を印刷配布しています。そこで「命令への絶対服従と規律の遵守」を求めています。この山縣起草の軍人訓戒をもとに、1882年1月4日「軍人勅諭」が発布されます。
前文で「「朕は汝ら軍人の大元帥なるぞ」と居丈高に恫喝し、続く主文において「義は山嶽より重く死は鴻毛より軽しと心得よ」と訓辞しています。すなわち、「忠義は重く、天皇のため、国のために命を捨てよ」と命じています。ここで初めて、「大元帥=軍の統帥権」が確立され、「国のために死ぬ天皇の軍隊」が誕生したわけです。
さらにこれだけでは不十分と山縣は考えたのでしょう。軍に召集する前の学校教育から天皇への忠誠を誓わせる必要があると考えました。1890年、山縣が総理大臣在任中に作成・発布した、「教育勅語」がそれです。そこでは教育らしきことはまったく語られていません。その内容は極端な皇国史観と天皇崇拝、そして愛国心の強要でした。
そのため、政府内部からも批判の声が続出しました。時の文部大臣・榎本武揚は抗議の辞職をし、内閣法制局長官・井上毅も反対しました。しかし山縣は、政敵を退け、総理の権限をもって力ずくで押し切りました。また、施行後も、反対が各地で起こり、翌1891年に、第一高等中学校教員・内村鑑三が拝礼拒否を行ったことは、ご存知のところです。
改めて言いますが、天皇制と天皇制イデオロギーは、あらかじめ存在したものではありません。ある一つの目的をもって、意図的、人為的に創り上げられたものです。それは、大日本帝国憲法(1889年公布、1890年施行)において、天皇の地位は万世一系の皇統を根拠として成立していると規定し、その究極的な根源は神勅にあるとし、したがって天皇は現人神の性格を有するとしたこと、そしてその大日本帝国憲法のもとに、軍人勅語と教育勅語、それに「国旗(日の丸)・国歌(君が代)」の3点セットを組み合わせることによって、一定の年月をかけて熟成されたものと言えます。
また、この過程で、軍歌も一定の役割を果たしたと思います。
日露侵略戦争中に作成された「戦友」では、「赤い夕日に照らされて 友は野末の石の下」と哀調をおびたメロデイと歌詞で「友」の死を悼み、悲しんでいます。しかし、その後、「友」の死を悲しむことはタブーになり、「戦友」も歌うことが禁止されていきます。そして中国侵略戦争に至り、軍歌は一変します。「同期の桜」では、「咲いた花なら 散るのは覚悟 見事散りましょう 国のため」となり、死を美化し、「国のために死のう」、「靖国の英霊と化し、死して護国の鬼とならん」となります。
軍歌「戦友」で、その死を悲しんでいたのが、軍歌「同期の桜」では死を美化し推奨する内容へと変わっていく。その背景に天皇制と天皇制イデオロギーがあることは明々白々です。
天皇制と天皇制イデオロギー、その実体としての「天皇の軍隊」が、どのようにして形成されていったのかがお分かりいただけたと思います。
●不正義の侵略戦争で死を強制するイデオロギーは何か
さて、話を現代にもどしましょう。「なぜ、今、元首天皇なのか(が必要なのか)」ということです。
その理由はただ一つ。山縣有朋が西南戦争で感じた危機感と焦燥感を、現日帝支配者階級が感じているからに他なりません。確かに自衛隊はある。しかし「有事にものの役に立つのか」との思いです。「サラリーマン軍隊」「免許取得軍隊」と揶揄されている自衛隊が、西南戦争時の政府軍のように、算を乱して逃げ出してしまわないかとの危惧です。
これは仮説・仮の想定ではありません。独島(日本呼称「竹島」)、釣魚台(同「尖閣列島」)をめぐる領土・領海権で韓国・中国と激しく争い、海上保安庁の巡視船では限界と言われている今日、海上自衛隊の出動―交戦はそう遠くないと考えています。事実、5月30日、自民党国防部会は、「新たな防衛計画大綱へむけての提案」を発表し、「島嶼防衛体制の強化=全自衛隊の海兵隊的機能の整備」と「敵基地攻撃能力の保持」を打ち出しました。
誇張ではなく、東アジアをめぐる現在の事態は一触即発の情勢だと言って過言ではありません。自衛隊の精神的支柱=死生感をいかにして育成するのか――この緊急にして不可欠の難題に対する答えが今回の「憲法改正」です。憲法第1条以外にも、天皇と愛国心、戦争へむけての条項が目につきます。
◎第3条 国旗および国歌 【国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする 日本国民は国旗および国歌を尊重しなければならない】
◎第5条 天皇の機能の拡大 【天皇はこの憲法の定める国事のみを行い→のみを削除】
◎第9条 集団的自衛権の行使 【交戦権はこれを放棄する→自衛権の発動を妨げるものではない】
◎第9条の2 国防軍の創設と軍事法廷 【国防軍に属する軍人その他の公務員が国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、国防軍に審判所を置く】
◎第66条の2 文民統制の破棄 【内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない→現役の軍人であってはならない】
これらの条文の頂点に立つのが第1条「元首天皇」なのです。
こう書いてくると、「そんなことあるまい。君の思い過ごしだよ」、「天皇制の復活なんてそんなに簡単ではないよ」との反論があるやかもしれません。確かに一朝一夕にしてできることではありません。時間がかかります。が、他国への侵略という不正義の戦争で、死を強制できるイデオロギーは「国家のため」しかなく、抽象的な国家を具現化できるのは、天皇しかいないのです。いかに現実と乖離しており、いかに一度破産したとはいえ、天皇と天皇制しか選択肢がないのです。その意味で、これは、支配者階級にとっても苦渋の選択であり、恐る恐るの決断だと思います。
しかしです。私が最も危惧するのは、自衛隊員の死を政治的に利用することです。こんな形で始まるのではないでしょうか。天皇(皇室)が、戦死した自衛隊員の家族を慰めるために訪問する。そして手を取り合って涙する。3・11東日本大震災の被災者を天皇(皇室)が訪問し激励したと同じように…。あの時、避難所を訪れ、手をとって歓談する天皇(皇室)を、マスコミは好意的に報じてきました。その時、民衆のなかに生じた一体感(「ああ、天皇陛下(皇室)が、われわれのことを心配して下さっている」との想い)を利用する。被災者と戦死者を同列に置き、その死を悼み涙する。
この演出に、われわれはどこまで抗しえるでしょうか。自衛隊員の死の政治的利用。これが「天皇の軍隊」復活の突破口になるように思います。
●問われているのは左翼
最後に。やはり戦後日本革命の敗北と、その負の遺産について述べなければなりません。
戦後革命では、アジア侵略戦争の最高責任者である天皇を断罪し、処罰し処刑することを闘いの課題にできませんでした。天皇制そのものを廃止する歴史的なチャンスをとらえて闘うことができませんでした。戦後革命の過程で、天皇の戦争責任が曖昧化され、象徴天皇としての延命を許してきました。戦前・戦中の歴史をきっぱりと清算することができなかったのです。そのつけを、ここにきて支払わされているとの思いです。
もう一つ。第1条にかんして。
憲法学者・知識人・新旧左翼諸政党が沈黙しているのが、やはり危機的です。とりわけ新左翼諸党派です。
1989年2月24日、昭和天皇の死去にともなう「大喪の礼」を弾劾し、「戦犯天皇糾弾」のシュプレヒコールで首都を席巻したかつての中核派、1990年11月22日の「大嘗祭」に対して全国各所で一斉に決起して闘ったかつての中核派は、一体どこに行ったのでしょうか。現在の中央派や関西派は、何をしているのでしょうか。「元首天皇」に関する記事は中央派・関西派の機関紙のどこにも見当たりません。早くも天皇制イデオロギーに絡め取られてしまったのか、それともこの攻撃を軽視しているのか。いずれにしても主体の危機です。
彼らがいかに「反戦」、「改憲反対」を叫ぼうとも、「天皇元首化反対」をスローガンを掲げないかぎり、まやかしであり、核心を射た批判にはなりえません。
もう一度第1条を批判的に読み返すことを、彼らに提案して終わりたいと思います。
2013年6月18日
竜 奇兵(りゅう・きへい)
追伸:
ここでは「元首天皇」を「天皇の軍隊」との関係で書いてみました。が、天皇制の凶暴さは、それだけにとどまりません。それに加えて、「天皇制と民族差別」の問題があると危惧しております。「万世一系の天皇」という皇国史観にもとづく天皇制イデオロギーが、「五族協和」の「大東亜共栄圏」づくりとして侵略戦争を正当化していったことは、周知の事実です。その中で、橋下徹大阪市長の数々の暴言がぎゃくに改めて浮き彫りにしたように、日本軍「慰安婦」制度による戦時性奴隷の犠牲が朝鮮・中国・アジアの女性たちに強制されたのでした。
それと密接不可分の「天皇制と差別主義・融和主義」の問題、「天皇制と沖縄、アイヌ民族」の問題があります。さらに、「天皇制と治安警察」、「天皇制と転向・階級性解体」の問題があり、「天皇制と軍隊内および民間右翼ファシスト」の問題、「天皇制=国家神道と宗教」の問題、「天皇制とマスコミ・文化」の問題、そして「天皇制と後発帝国主義経済体制」の問題などなど、天皇制攻撃のいずれも重要な諸側面を、トータリティーのある帝国主義論としてしっかりと見ていかねばなりません。
●憲法改正の是非が参院選の焦点に
参議院議員選挙が近づいてきました。7月21日投票の参院選は、まちがいなく今後の日本階級闘争の行く末を決する分岐点です。この選挙を契機にして「激動の時代」へと大きく動き出すでしょう。その最大の焦点が「憲法改正の是非」であり、世論は左右に大きく分裂していくものと考えています。まちがいなく時代は今、大きな分水嶺にさしかかっています。
以下、私なりに「憲法改正」問題について述べてみたいと思います。なお、ここで述べることは、昨年4月27日に発表された自民党改憲草案を資料としたものです。
●改憲問題の最大の争点は第1条にある
この間、改憲派、反対派の双方の主張・意見が出されています。が、私は何か腑に落ちません。納得できないというか、違和感を感じています。というのは、最大の争点を、双方とも触れていない、あるいは意図的に避けているように見えるからです。
最大の争点とは何か。言うまでもありません。国家の基本的あり方を規定した憲法第1章第1条です。憲法は、第1章第1条から第11章第103条までで構成されています。が、その中で、第1章第1条は特別な位置を占めています。それは、第1条が、国家の基本的在り方=統治形態を規定しているからです。憲法全文をその根底から、すべてにわたり規定し拘束するがゆえに、司法・行政・議会の3権の上に立つ概念だと私は考えています。
そこが大きく変えられようとしているのに、双方とも何も言わない。とりわけ改憲反対派の諸君です。賛成派が、これを焦点化したくないのは分かります(これについては後述します)。が、憲法学者・知識人・表現者・新旧左翼政党がまったく触れていない。反対意見はおろか、一元半句も言及していない。これは異常な事態であり、ありえないことです。
第9条(戦争放棄)、第96条(手続き条項)にかんしては、多くの方々が問題点を述べ、論陣を張っています。いわく。9条改憲は「軍事大国をめざすもの」、「戦争への一理塚」と。いわく。96条改憲で「手続き論を先行させるのはなぜか」、「何を変えるのかを、まずあきらかにすべき」と。その指摘はきわめて正しいし、重要な批判です。今後さらに9条改憲、96条改憲への批判を深めていかねばなりませんし、この点で反対運動の高揚と大衆運動の結集軸をつくっていかねばなりません。それを否定するものではありません。
しかし、1条批判をおろそかにしてよいはずがありません。否、1条改定の背景、そこに込められた日帝支配者階級の意図を分析・解明する作業を通して、9条改定の意味・全体像がよりいっそう浮かび上がってくると考えています。1条と9条。この両者は密接不可分の関係にあり、1条と関連づけて考えない9条論は、攻撃の凶暴さ、恐ろしさを見抜けず、9条と関連づけて考えない1条は、攻撃の全体像がぼやけてしまう。こう考えるからです。以下、その点を述べてみます。
●天皇の国家元首化にこだわる支配者階級
次の二つを読み比べてください。
【現行憲法】
第1章 天皇
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く
【自民党の憲法草案】
第1章 天皇
第1条 天皇は日本国の元首であり、日本国統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基く
先ほども述べたように、第1条は特別な条項です。国家の基本的在り方=統治形態を述べており、特別な意味をもちます。自民党改憲草案では、その第1条で、天皇の元首化が明記されている。これは非常に重要なことです。そして異なことに、その後に、象徴であるとも述べられています。「象徴天皇」と「元首天皇」を並列させている。あい反する・矛盾する概念を同時に用いる。これは文法上ありえません。
象徴天皇は自らの意思をもたない、非主体的存在です。意思も決定権ももちません。反して元首天皇は、主体的存在であり、自らの意思と絶大なる権力・影響力をもちます。象徴天皇は元首天皇たりえないし、元首天皇は象徴天皇ではない。両者正反対の意味をもつにもかかわらず、それを併記しています。ここに日帝支配者階級の苦悩がみてとれます。すなわち、“元首天皇といってもあまり変わりませんよ。これまでの象徴天皇の延長線上にあるのですよ”と言いたいのでしょう。争点をぼやかし、問題の所在を隠蔽しようとの意図がうかがわれます。姑息なやり方です。
なぜそこまでして、元首天皇にこだわるのか。日帝支配者階級の意図、そこにこめられた危機感と焦燥感、そして野望をみていきます。
●天皇と軍隊
近代史において、天皇はほとんど歴史の表舞台に登場していません。幕末~明治維新の激動期でもほとんど登場しませんでした。それほど影響力も存在感もなかったと言えます。唯一天皇が歴史に登場したのが、孝明天皇の死です。病死説、毒殺説の両論がありますが、「益御機嫌能被成為候(ますますご機嫌がよくなられました)」という内容の「御容態書」が提出されたその直後に死亡していること、さらには慶応2年1月25日死亡にもかかわらず、1月29日まで公表しなかった点からも、暗殺だと考えられます。天皇といえども、政治的に敵対すれば殺してもかまわない(「玉(ぎょく)を取る」の隠語で語られています)、それほど「権威も威厳もない」「軽い存在」だったようです。
その権威も威厳もない天皇が、後の1930年代の中国侵略戦争(日中戦争)時には、「神聖不可侵」にして「絶対無誤謬の現人神」の天皇へと変遷していくのですが、その必要性を痛感し、仕掛け人となった人物がいます。日本陸軍の創設者にして「国軍の父」と言われた山縣有朋です。彼は軍の創設者であるだけでなく、「天皇制と天皇制イデオロギー」の立案―導入―推進者だったと思われます。
転機になったのは1878年の西南戦争です。兵数においても火力・装備においても負けるはずのない政府軍が敗退します。この敗北の原因は何なのか? 反乱軍にあって政府軍にないものは何か? 明治政府の陸軍卿として陣頭指揮を執っていた山縣は考えました。そして行き着いた結論が、軍の士気―精神的支柱の有無です。旺盛な士気で鼓舞されている反乱軍に対し、しり込みし、算を乱して逃げる政府軍。前者にあって後者にないもの、それは死生観の有無だと考えたのではないでしょうか。
反乱軍は氏族階級であり、死生観として武士道(「武士道と云うは死ぬ事と見付けたり」『葉隠れ』)を有しています。対する新生政府軍にはそれがありません。武士道に匹敵する死生観を植えつける必要がある、山縣はこう考えたのでしょう。
西南戦争直後に山縣は即座に動きます。西郷自決で終焉したのが1878年9月4日。約40日後の10月12日に、陸軍卿・山縣有朋は全陸軍将兵に「軍人訓戒」を印刷配布しています。そこで「命令への絶対服従と規律の遵守」を求めています。この山縣起草の軍人訓戒をもとに、1882年1月4日「軍人勅諭」が発布されます。
前文で「「朕は汝ら軍人の大元帥なるぞ」と居丈高に恫喝し、続く主文において「義は山嶽より重く死は鴻毛より軽しと心得よ」と訓辞しています。すなわち、「忠義は重く、天皇のため、国のために命を捨てよ」と命じています。ここで初めて、「大元帥=軍の統帥権」が確立され、「国のために死ぬ天皇の軍隊」が誕生したわけです。
さらにこれだけでは不十分と山縣は考えたのでしょう。軍に召集する前の学校教育から天皇への忠誠を誓わせる必要があると考えました。1890年、山縣が総理大臣在任中に作成・発布した、「教育勅語」がそれです。そこでは教育らしきことはまったく語られていません。その内容は極端な皇国史観と天皇崇拝、そして愛国心の強要でした。
そのため、政府内部からも批判の声が続出しました。時の文部大臣・榎本武揚は抗議の辞職をし、内閣法制局長官・井上毅も反対しました。しかし山縣は、政敵を退け、総理の権限をもって力ずくで押し切りました。また、施行後も、反対が各地で起こり、翌1891年に、第一高等中学校教員・内村鑑三が拝礼拒否を行ったことは、ご存知のところです。
改めて言いますが、天皇制と天皇制イデオロギーは、あらかじめ存在したものではありません。ある一つの目的をもって、意図的、人為的に創り上げられたものです。それは、大日本帝国憲法(1889年公布、1890年施行)において、天皇の地位は万世一系の皇統を根拠として成立していると規定し、その究極的な根源は神勅にあるとし、したがって天皇は現人神の性格を有するとしたこと、そしてその大日本帝国憲法のもとに、軍人勅語と教育勅語、それに「国旗(日の丸)・国歌(君が代)」の3点セットを組み合わせることによって、一定の年月をかけて熟成されたものと言えます。
また、この過程で、軍歌も一定の役割を果たしたと思います。
日露侵略戦争中に作成された「戦友」では、「赤い夕日に照らされて 友は野末の石の下」と哀調をおびたメロデイと歌詞で「友」の死を悼み、悲しんでいます。しかし、その後、「友」の死を悲しむことはタブーになり、「戦友」も歌うことが禁止されていきます。そして中国侵略戦争に至り、軍歌は一変します。「同期の桜」では、「咲いた花なら 散るのは覚悟 見事散りましょう 国のため」となり、死を美化し、「国のために死のう」、「靖国の英霊と化し、死して護国の鬼とならん」となります。
軍歌「戦友」で、その死を悲しんでいたのが、軍歌「同期の桜」では死を美化し推奨する内容へと変わっていく。その背景に天皇制と天皇制イデオロギーがあることは明々白々です。
天皇制と天皇制イデオロギー、その実体としての「天皇の軍隊」が、どのようにして形成されていったのかがお分かりいただけたと思います。
●不正義の侵略戦争で死を強制するイデオロギーは何か
さて、話を現代にもどしましょう。「なぜ、今、元首天皇なのか(が必要なのか)」ということです。
その理由はただ一つ。山縣有朋が西南戦争で感じた危機感と焦燥感を、現日帝支配者階級が感じているからに他なりません。確かに自衛隊はある。しかし「有事にものの役に立つのか」との思いです。「サラリーマン軍隊」「免許取得軍隊」と揶揄されている自衛隊が、西南戦争時の政府軍のように、算を乱して逃げ出してしまわないかとの危惧です。
これは仮説・仮の想定ではありません。独島(日本呼称「竹島」)、釣魚台(同「尖閣列島」)をめぐる領土・領海権で韓国・中国と激しく争い、海上保安庁の巡視船では限界と言われている今日、海上自衛隊の出動―交戦はそう遠くないと考えています。事実、5月30日、自民党国防部会は、「新たな防衛計画大綱へむけての提案」を発表し、「島嶼防衛体制の強化=全自衛隊の海兵隊的機能の整備」と「敵基地攻撃能力の保持」を打ち出しました。
誇張ではなく、東アジアをめぐる現在の事態は一触即発の情勢だと言って過言ではありません。自衛隊の精神的支柱=死生感をいかにして育成するのか――この緊急にして不可欠の難題に対する答えが今回の「憲法改正」です。憲法第1条以外にも、天皇と愛国心、戦争へむけての条項が目につきます。
◎第3条 国旗および国歌 【国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする 日本国民は国旗および国歌を尊重しなければならない】
◎第5条 天皇の機能の拡大 【天皇はこの憲法の定める国事のみを行い→のみを削除】
◎第9条 集団的自衛権の行使 【交戦権はこれを放棄する→自衛権の発動を妨げるものではない】
◎第9条の2 国防軍の創設と軍事法廷 【国防軍に属する軍人その他の公務員が国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、国防軍に審判所を置く】
◎第66条の2 文民統制の破棄 【内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない→現役の軍人であってはならない】
これらの条文の頂点に立つのが第1条「元首天皇」なのです。
こう書いてくると、「そんなことあるまい。君の思い過ごしだよ」、「天皇制の復活なんてそんなに簡単ではないよ」との反論があるやかもしれません。確かに一朝一夕にしてできることではありません。時間がかかります。が、他国への侵略という不正義の戦争で、死を強制できるイデオロギーは「国家のため」しかなく、抽象的な国家を具現化できるのは、天皇しかいないのです。いかに現実と乖離しており、いかに一度破産したとはいえ、天皇と天皇制しか選択肢がないのです。その意味で、これは、支配者階級にとっても苦渋の選択であり、恐る恐るの決断だと思います。
しかしです。私が最も危惧するのは、自衛隊員の死を政治的に利用することです。こんな形で始まるのではないでしょうか。天皇(皇室)が、戦死した自衛隊員の家族を慰めるために訪問する。そして手を取り合って涙する。3・11東日本大震災の被災者を天皇(皇室)が訪問し激励したと同じように…。あの時、避難所を訪れ、手をとって歓談する天皇(皇室)を、マスコミは好意的に報じてきました。その時、民衆のなかに生じた一体感(「ああ、天皇陛下(皇室)が、われわれのことを心配して下さっている」との想い)を利用する。被災者と戦死者を同列に置き、その死を悼み涙する。
この演出に、われわれはどこまで抗しえるでしょうか。自衛隊員の死の政治的利用。これが「天皇の軍隊」復活の突破口になるように思います。
●問われているのは左翼
最後に。やはり戦後日本革命の敗北と、その負の遺産について述べなければなりません。
戦後革命では、アジア侵略戦争の最高責任者である天皇を断罪し、処罰し処刑することを闘いの課題にできませんでした。天皇制そのものを廃止する歴史的なチャンスをとらえて闘うことができませんでした。戦後革命の過程で、天皇の戦争責任が曖昧化され、象徴天皇としての延命を許してきました。戦前・戦中の歴史をきっぱりと清算することができなかったのです。そのつけを、ここにきて支払わされているとの思いです。
もう一つ。第1条にかんして。
憲法学者・知識人・新旧左翼諸政党が沈黙しているのが、やはり危機的です。とりわけ新左翼諸党派です。
1989年2月24日、昭和天皇の死去にともなう「大喪の礼」を弾劾し、「戦犯天皇糾弾」のシュプレヒコールで首都を席巻したかつての中核派、1990年11月22日の「大嘗祭」に対して全国各所で一斉に決起して闘ったかつての中核派は、一体どこに行ったのでしょうか。現在の中央派や関西派は、何をしているのでしょうか。「元首天皇」に関する記事は中央派・関西派の機関紙のどこにも見当たりません。早くも天皇制イデオロギーに絡め取られてしまったのか、それともこの攻撃を軽視しているのか。いずれにしても主体の危機です。
彼らがいかに「反戦」、「改憲反対」を叫ぼうとも、「天皇元首化反対」をスローガンを掲げないかぎり、まやかしであり、核心を射た批判にはなりえません。
もう一度第1条を批判的に読み返すことを、彼らに提案して終わりたいと思います。
2013年6月18日
竜 奇兵(りゅう・きへい)
追伸:
ここでは「元首天皇」を「天皇の軍隊」との関係で書いてみました。が、天皇制の凶暴さは、それだけにとどまりません。それに加えて、「天皇制と民族差別」の問題があると危惧しております。「万世一系の天皇」という皇国史観にもとづく天皇制イデオロギーが、「五族協和」の「大東亜共栄圏」づくりとして侵略戦争を正当化していったことは、周知の事実です。その中で、橋下徹大阪市長の数々の暴言がぎゃくに改めて浮き彫りにしたように、日本軍「慰安婦」制度による戦時性奴隷の犠牲が朝鮮・中国・アジアの女性たちに強制されたのでした。
それと密接不可分の「天皇制と差別主義・融和主義」の問題、「天皇制と沖縄、アイヌ民族」の問題があります。さらに、「天皇制と治安警察」、「天皇制と転向・階級性解体」の問題があり、「天皇制と軍隊内および民間右翼ファシスト」の問題、「天皇制=国家神道と宗教」の問題、「天皇制とマスコミ・文化」の問題、そして「天皇制と後発帝国主義経済体制」の問題などなど、天皇制攻撃のいずれも重要な諸側面を、トータリティーのある帝国主義論としてしっかりと見ていかねばなりません。















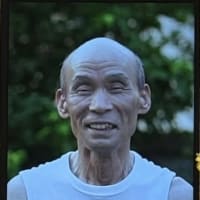










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます