
3月1日のことですが、ドローンを使って岡村天満宮の上空に揚がったり、あるいは蜂のように梅花の近くを飛んだりして動画を撮影することができました。当日は生憎、天気があまりよくなく、青空ではなかったのが残念でしたが、映像としてはいいものができたと思います。
今回のプロジェクトに関わった方々は次のとおりです。
ドローン操縦&撮影:髙梨智樹さん(スカイジョブ合同会社)
キャラクター原作/イラスト:遠藤望さん(Yocco18代表)
Yocco18ディレクター:坂口祐太さん(アンバサダーズジャパン株式会社)
映像制作:木村敬一さん(Squash yokohama japan)
助成:一般財団法人 地域創造
みなさまのご協力で出来上がった映像が、こちら。磯子区民文化センター杉田劇場のホームページから視聴できます。
さて、撮影当日のことですが、開始までに少し時間があったので、以前から気になっていた石碑の詳細を確認してきました。碑の名称は「杉山天満宮神楽殿社務所新築費寄附者芳名」です。
岡村天満宮なのに杉山天満宮とはどういうことなのでしょうか。この両社の関係は、磯子区民文化センター杉田劇場が発行した『壱十五(いそご)の神社と祭り』という調査・記録報告書の中に次にように書かれています。
『新編武蔵風土記稿』の岡村の項に記載されている三社は、村の鎮守の杉山明神社、太神宮、龍珠院持ちの天満宮。社伝によると、天満宮は、鎌倉時代の建久年間(1190~1199年)、鎌倉から移住してきた源頼朝公の家臣が、京の北野天満宮を勧請して祀ったということだ。杉山神社は、源頼朝公が鎌倉幕府安泰を願う鬼門除けとして祀った「七杉山神社」の一つだそうだ。明治43(1910)年に三社は杉山天満宮として合祀され、昭和5(1930)年には地名をとって岡村天満宮に改称し、現在に至っている。
つまり、現在の岡村天満宮は、明治43年から昭和5年までは「杉山天満宮」と言われていたことが分かります。この石碑は杉山天満宮の神楽殿と社務所を新築したときの寄付者名簿なのです。

石碑の裏面に各竣工年が彫られています。社務所は大正11年11月の竣工。神楽殿は大正12年3月に竣工していますが、それから半年で関東大震災が起き、どうやらそれで倒壊してしまったようで、大正14年8月に再建と記されています。
そして、この石碑は大正15年5月に建立されました。工費は10,572円と書かれています。

石碑の表面を確認しておきましょう。
一番上の段に並んでいるのは、すべて関内の料亭(25軒)です。右の2軒「千登世」、「八百政」は明治、大正時代における横浜の代表的な料亭でした。その他に「花月」、「末廣」、「わかな」などが載っています。この「わかな」というのは関内駅近くにある鰻の「わかな」でしょうかね。
その下には関外の料亭が46軒も並んでいます。そのあとにやっと磯子町の「幸楽」という名が出てきます。この位置にあるということは、当時、かなり有名だったのではないかと想像されます。そのあとに花咲町の料亭が3軒並んでいます。これは掃部山の花街にあったのでしょうかね。
それに続くのが伊勢佐木町にあった各商店。「港屋洋品店」、「杉林モスリン店」、「まからぬや」、「博雅亭」、「松坂屋喫茶店」、「木村パン店」、「亀楽商店」などなど。「博雅亭」というのはシウマイで有名なお店でした。「亀楽商店」は亀楽煎餅のことでしょうかね。
そしてその下の段に並ぶのは「魚河岸」関係。20軒が名を連ねています。それに続くのが蒔田、日本橋、神奈川の花街にあった料亭です。さらに眺めていくと、かつて屏風ヶ浦にあった「梅乃園」が出てきました。

昭和11年に発行された「大日本職業別明細図」に屏風ヶ浦海岸の様子が描かれています。「白旗」電停近くに「梅乃園」はありました。この料亭はその後、アパートになったようで、昭和34年の磯子明細図では「梅乃園荘」と表示されています。

さらに下の方を眺めていくと、関内・関外の商店や個人名が並んでいます。そして下から2段目に磯子区内の方々の個人名が書かれています。磯子町で1人、滝頭町で2人、地元岡村の方々が5人が寄附をしていたことが分かります。
一番下の段は世話人17人が載っています。その筆頭が畠山政吉です。この人が「八百政」の経営者で、齋藤岩吉は「千登世」の経営者でした。最後から2番目に載っている平林藤吉は魚河岸の人だったようで、磯子小学校が発行した『磯子の歴史』の中で、次のように紹介されています。
明治三十五年に中村町の小嶋萬吉、魚河岸の平林藤吉ほか数名が世話人となり、毎月二十五日の天神まつりを華やかに彩ろうと花柳界を中心に天神講をつくって参拝人を集めた。それからはあでやかな着物姿が目につくようになった。
この項目には「色天神」という見出しが使われています。岡村天満宮には、芸者衆や花街関係者が大勢参拝の来ていたことが分かります。ここの神楽殿と社務所を新築するにあたって、料亭や魚河岸の人たちが大勢、寄附をしていたことが納得できるのではないでしょうか。
byうめちゃん

















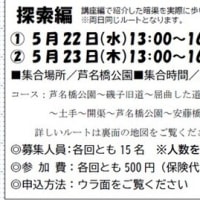


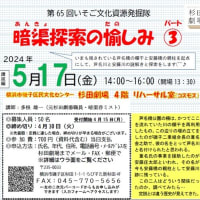

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます