動作的に考察すると、日本のあいさつの基本はお辞儀である。頭を下げる動作は、自分を相手よりも下げる謙譲の精神とも言える。なるほど、日本語には、尊敬語やら謙譲語やら、場に応じた多くに表現がある。ドイツの場合は、あいさつの動作は、日本とおよそ反対である。相手に対してあごを少し引き上げるような感じで「Gutentag」と言う。このとき、目線は相手からは決して離れない。
日本のあいさつは、お辞儀の時に相手に対して目線を下げる。ちょうど地面を向くような感じである。
このあいさつについての文化の違いについてのおもしろい話がある。
鳴門市にドイツ館がある。第1次世界大戦が始まると、日本は当時ドイツの租借地だった中国の山東半島にある青島を攻撃した。敗れたドイツ兵士約5.000人が俘虜となり、日本各地の収容所へ送られたが、その内、四国の徳島・丸亀・松山にいた約1,000人が1917(大正6年〉から192O年までの約3年間を板東倖虜収容所で過ごした。「バルトの楽園」という映画でも、紹介されているのでご存じの方も多いと思う。あるドイツ兵士が、すれ違う日本人がそのたびに深々と頭を下げ地面を見るので、そこに何かが有るのだと思い、通り過ぎた後に地面に目を近づけて見てみたら何もなかったという話。
東洋の文化が現代ほどヨーロッパに紹介されていない時代には、お辞儀をする習慣が非常に不思議な行為に見えたのであろう。
反対に、相手の目をじっと見ることは、日本では敵意を与えるためどちらかというと好まれないことである。
動作一つにも文化的な背景がある。日本のあいさつは、謙譲の精神に富んでおり、きちんと行えば大変美しい動作であると自信を持って言える。
日本のあいさつは、お辞儀の時に相手に対して目線を下げる。ちょうど地面を向くような感じである。
このあいさつについての文化の違いについてのおもしろい話がある。
鳴門市にドイツ館がある。第1次世界大戦が始まると、日本は当時ドイツの租借地だった中国の山東半島にある青島を攻撃した。敗れたドイツ兵士約5.000人が俘虜となり、日本各地の収容所へ送られたが、その内、四国の徳島・丸亀・松山にいた約1,000人が1917(大正6年〉から192O年までの約3年間を板東倖虜収容所で過ごした。「バルトの楽園」という映画でも、紹介されているのでご存じの方も多いと思う。あるドイツ兵士が、すれ違う日本人がそのたびに深々と頭を下げ地面を見るので、そこに何かが有るのだと思い、通り過ぎた後に地面に目を近づけて見てみたら何もなかったという話。
東洋の文化が現代ほどヨーロッパに紹介されていない時代には、お辞儀をする習慣が非常に不思議な行為に見えたのであろう。
反対に、相手の目をじっと見ることは、日本では敵意を与えるためどちらかというと好まれないことである。
動作一つにも文化的な背景がある。日本のあいさつは、謙譲の精神に富んでおり、きちんと行えば大変美しい動作であると自信を持って言える。













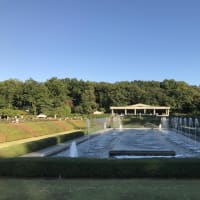




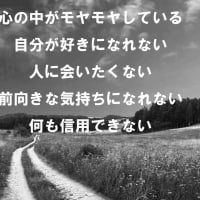



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます