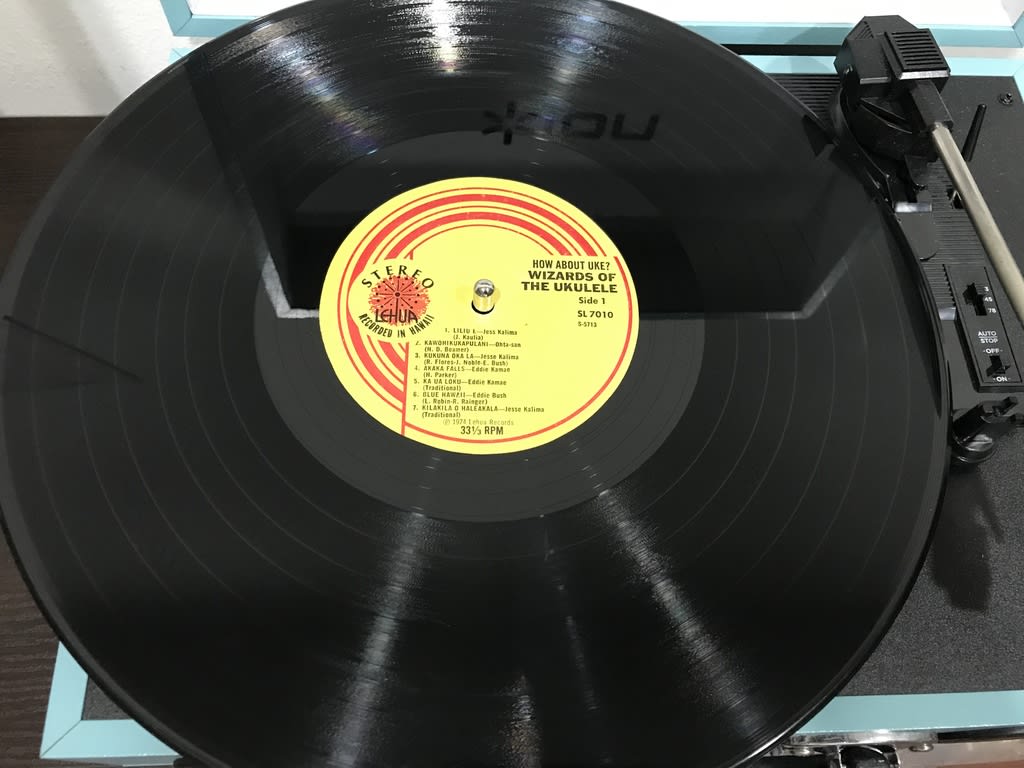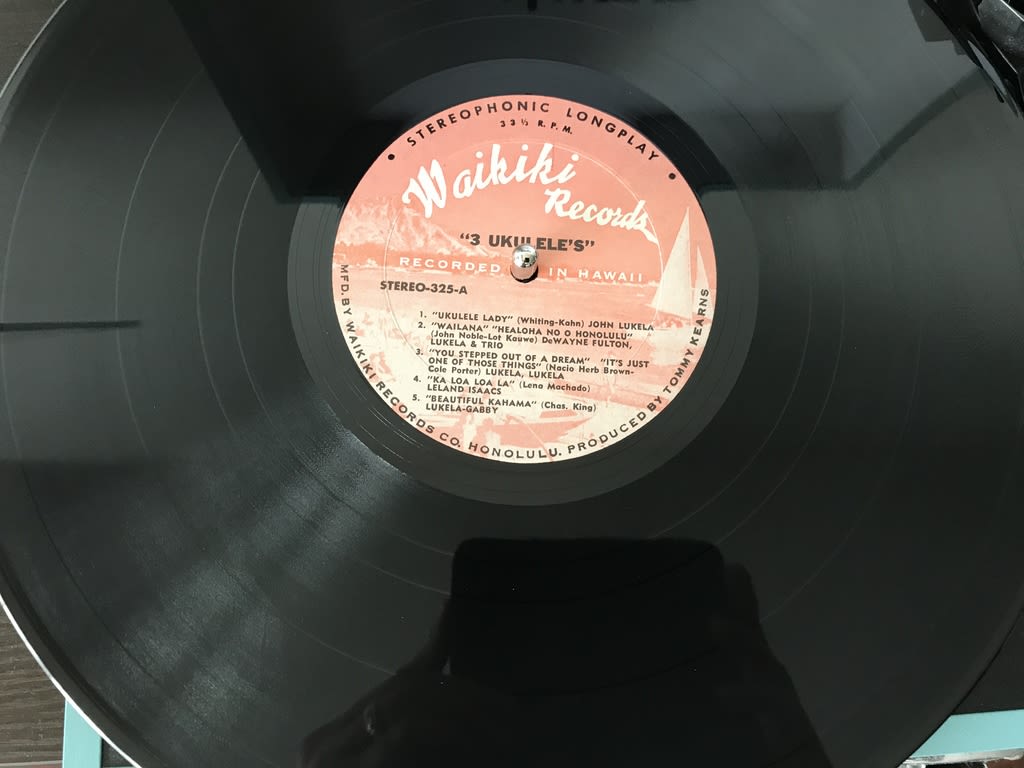8月の5週目となる今回の更新は、順番が前後してしまったが、ディスク未入手のため紹介できていなかったSurfside Recordsのオータサン盤を割り込ませる形で、拙稿の欠けていたカタログを補完したい。今月はオータサン以外のウクレレ奏者による音盤を特集したが、他にも紹介したいアーチストや音盤がまだまだあるため、それらについても今後また機会を設けて紹介してゆきたい。
さて本盤は制作年度が不明だが、カタログナンバー(SFS-108)から推測して1970年ないしは1971年の作品だろう。先に紹介済の「Plays The Theme From Hawaii Five-O (SFS-107)」と「 Stringed Out (SFS-109)」に挟まる同レーベルでの6作目。なおSurfside Recordsはオータサンの為に作られたHula Records傘下の傍系レーベルである為、関連アーチストによるアルバムとシングル数枚を除き、すべてオータサンの作品。
名義上はオータサンとThe Surfside Stringsなる楽団の共演という体裁になっているが、恐らくはパーマネントな活動実態のある楽団ではなかっただろう。なお同レーベルからの二作目で本作と同様に弦楽アンサンブルとの共演盤であった「Cool Strings And Ohta-San」ではライナーノーツに「Cool Strings」という楽団だと記載されていた。
同レーベルの諸作品にはこれまで見てきたように編曲や演奏で平岡精二や八木正生といった昭和の和製ジャズ・ミュージシャンが深くかかわっており、オータサンの初期キャリアにおいて重要な作品群であるばかりか、ハワイ=日本の音楽業界の交流史においても興味深い音源の宝庫といえるのだが、残念なことに同レーベルでの6作目となる本盤にもストリング・オーケストラをアレンジした編曲者がいたはずだがクレジットがなく不明となっている。
アルバムタイトルは副題に"Love Sounds from the Ukulele of Ohta-San and the Surfside Strings, playing love themes from 12 great shows"とあり、楽曲は映画や舞台劇から愛のテーマを集めたセレクションとなっている。サウンド的にはオータサン奏でるウクレレに弦楽アンサンブルを配したムード音楽。
A1 Love Story
A2 Sound Of Silence
A3 Theme de la Lecon Particuliere
A4 Bali Hai
A5 Theme From Sunflower
A6 Ebb Tide
A2 Sound Of Silence
A3 Theme de la Lecon Particuliere
A4 Bali Hai
A5 Theme From Sunflower
A6 Ebb Tide
B1 On A Clear Day
B2 Harbor Lights
B3 It Was A Good Time (Rosy's Theme from Ryan's Daughter)
B4 Theme from The Red Tent
B5 Treize Jours En France
B6 True Love Is Greater Than Friendship
B2 Harbor Lights
B3 It Was A Good Time (Rosy's Theme from Ryan's Daughter)
B4 Theme from The Red Tent
B5 Treize Jours En France
B6 True Love Is Greater Than Friendship
オータサンは60年代に軍隊を退役した時点ですでにウクレレ奏者としては一流の域にあったが、それに慢心することなくプロとして活動してゆくために故郷ハワイの学校で音楽理論を学び、またレコードデビュー後は日本から招かれた平岡精二や八木正生との音盤制作、また逆にオータサンが欧州に招かれアンドレ・ポップとのコラボレーションに至るまで、一流音楽人との仕事を通じて豊富な経験を積んだ結果、どのようなジャンル/趣旨の吹き込みセッションにも対応できるプロフェッショナリズムと音楽的な懐の広さを備えるに至り、ウクレレ奏者として前人未到である大量の音盤吹込み人生へと繋がってゆく。
これまで60年代から70年代までのオータサンの音盤を聴きながらこの偉大なヴァーチュオーゾの初期キャリアをなぞって来たが、9月からはまた隔週での通常更新ペースに戻り、1980年代以降からやがて『ウクレレの神様』とまで称されるに至る、果てしなく膨大なオータサン音盤世界の続きをじっくりと見てゆこう。

裏ジャケットは例によってポエム調の散文があるのみで吹込みに関する情報はほぼ皆無に近い。広告の記載によると、Surfsideでのオータサン全作品はカセットおよび8トラックでもリリースされていた事がわかる。

追記:日本のポリドール盤で『ロマンス/Herbert Ohta』(MR3172) と題した映画音楽集のLPが1971年にリリースされており、ジャケットデザイン含め一見全く別の作品のように見えるが大半の収録曲が本盤と重複する。帯には「来日録音」と明記されているものの、演奏は「サーフサイド・ストリングス・オーケストラ」名義ともなっていることから、筆者は未聴ながら本盤をベースにした日本編集盤ではないかと想像する。もし「来日録音」が事実なら逆にポリドールが日本で吹き込んだ音源をハワイのサーフサイドで流用した可能性もないとは言えないが、名義に「サーフサイド」とつくからにはやはりサーフサイド盤の本作がオリジナルと考えるのが自然な気もするが、どうか。なおポリドールは81年リリースのLP『The Waves and the Sun』(25MX2020)でもやはり「演奏:ハ-バート・オータとサーフサイド・オーケストラ」のクレジットで本盤との重複がある。