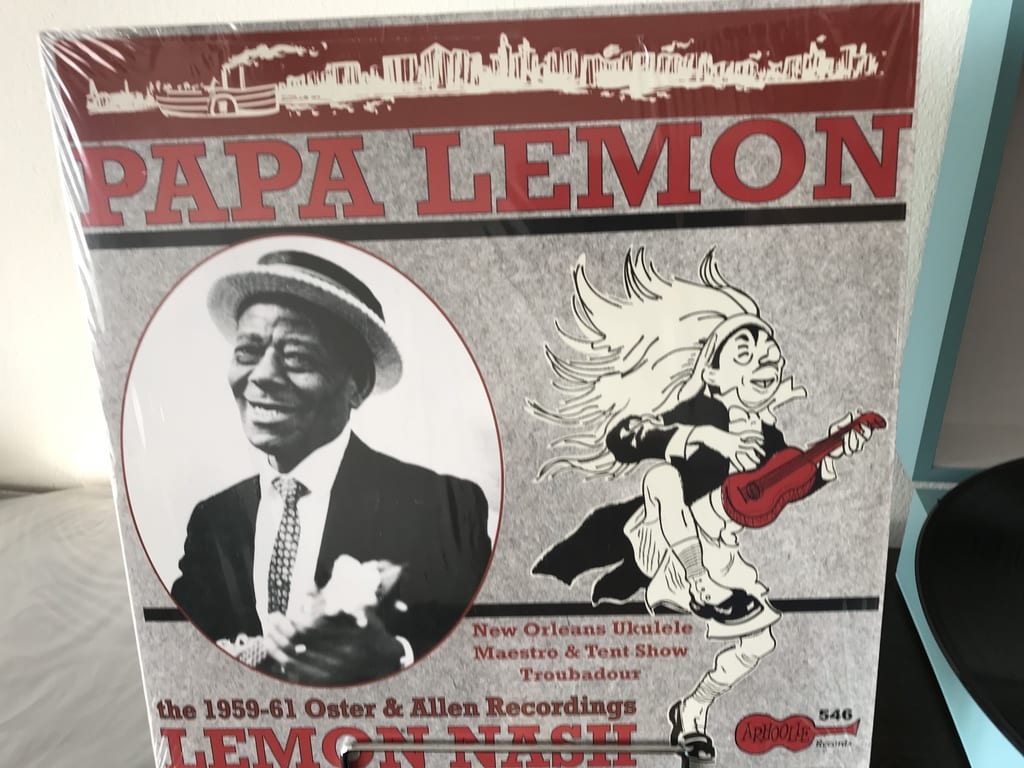
パパ・レモンである。日本の台所洗剤のアレは1966年発売だそうだが、こちらは1959年から1961年の間にニューオリンズのジャズ歴史研究家によって録音された数回のインタビューと演奏の記録を纏めたものだ。2013年にカリフォルニアのArhoolieというレーベルがCDとアナログLPでリリースした。このレーベルの親会社はSmithsonian Folkways。
パパ・レモンことLemon Nashはインディアンの酋長の羽飾りを付けてウクレレをかき鳴らし、1920年代にはブルースやジャズ小唄を歌い旅芸人に加わって旅をしたウクレレ芸人である。1898年生まれのルイジアナ州出身で、薬売りの一座や、巡回興業のボードヴィルやミンストレル・ショウなどで各地を巡り、50年代後半頃にニューオリンズに落ち着いたようだ。60年代後半にはまだニューオリンズで路上演奏を続けていたようだが、賑やかなブラスバンド演奏がひしめく合間に2曲ほど歌っては次の場所へ移動する、名もなき「グランパ(じい様)」として知られていたという。
ウクレレの原型となった楽器がポルトガル人によってハワイにもたらされたのは一説によれば1879年とも言われるが、アメリカ本土に広く紹介される機会となったのは1893年のシカゴ万博とされる。その後ハワイアンのレコード等と共にウクレレの販売も広まったようである。1920年のマーチン社におけるウクレレ生産本数は、ギターの二倍もの規模に達したというが、ウクレレは演奏が容易なうえに、構造上スイングするリズム感を表現しやすい楽器でもあって、当時のアメリカ流行歌との親和性は高かっただろう。
当時のいわゆる旅芸人の一座がどのようなものであったかはマイケル・ジャクソンとポール・マッカートニーがデュエットした「セイ・セイ・セイ」のPVでも抽象的にではあるが描かれていた怪しげな興業だが、現代アメリカのエンターテインメント産業(歌、手品などのショウ、コメディ、映画など)に繋がるルーツである。
A1 Bourbon Street Parade
A2 Papa Lemon's Blues
A3 Serenading With Frank Wagner
A4 Grave Digger's Blues
A5 Trouble With The Man
A6 What Was A Medicine Show Like?
A7 Bowleg Rooster, Duckleg Hen / Sweet Georgia Brown
A8 $25 A Night
A9 Nobody Knows You When You're Down And Out
A10 Anybody Seen My Kitty?
A11 Please Give Me Black And Brown
A12 Barrelhouse
A13 Let The Good Times Roll
A14 What A Friend We Have In Jesus
B1 Way In The Hee Hi Hoo
B2 We Played Anywhere
B3 I'm Blue Every Monday
B4 Stagolee
B5 The Battlefield
B6 Rabbit Brown
B7 If You Could Fight Like You Can Love
B8 Those Drafting Blues
B9 Spano's And Fox
B10 Nobody Knows The Trouble I've Seen
B11 Big Rock Candy Mountain
B12 The Jiggler Vein And The Raincoat
B13 Brownskin, Come And Go With Me
A2 Papa Lemon's Blues
A3 Serenading With Frank Wagner
A4 Grave Digger's Blues
A5 Trouble With The Man
A6 What Was A Medicine Show Like?
A7 Bowleg Rooster, Duckleg Hen / Sweet Georgia Brown
A8 $25 A Night
A9 Nobody Knows You When You're Down And Out
A10 Anybody Seen My Kitty?
A11 Please Give Me Black And Brown
A12 Barrelhouse
A13 Let The Good Times Roll
A14 What A Friend We Have In Jesus
B1 Way In The Hee Hi Hoo
B2 We Played Anywhere
B3 I'm Blue Every Monday
B4 Stagolee
B5 The Battlefield
B6 Rabbit Brown
B7 If You Could Fight Like You Can Love
B8 Those Drafting Blues
B9 Spano's And Fox
B10 Nobody Knows The Trouble I've Seen
B11 Big Rock Candy Mountain
B12 The Jiggler Vein And The Raincoat
B13 Brownskin, Come And Go With Me
ニューオリンズのA1に始まり、本格的なカントリー・ブルースや、A7「スイート・ジョージア・ブラウン」もあり、エリック・クラプトンもカヴァーしていたA9、ウクレレ・アイクも歌っていたB3など、ジャズ小唄とブルースを自在に行き来しながらウクレレを手に歌う。コード使いもなかなか多彩である。インタビューのパートでは、時折ガラス(酒瓶?)の音なども聞こえつつ、大きな声でまくしたてながら在りし日の旅芸人稼業の様子などを語ってもいる。
























