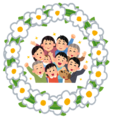法定相続情報証明制度が週明け29日・月曜から開始されます。
それにともなって、法務局のHPに(ようやく!?)解説のページが設けられました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
手続きは解説ページにあるように
①戸籍などの収集
②一覧図(相続関係図)の作成
③申出
の3段階です。
やはりネックになるのは①と②でしょうか。
②については、法務局も力を入れております。
いろいろなケースを想定してひな型を用意しています。
先日の法務局の説明会によると、申出された一覧図をPDFにして保管するのだそうです。
なので、基本的に記載内容に誤りがあった場合は、再提出なのだそうです。
資格者と一般の方では対応にある程度の差はあるかとは思いますが、一覧図(相続関係説明図)は慎重に作成する必要があります。
①の戸籍の収集については、現在の戸籍だけでは足りず、出生から死亡までの戸籍一式が必要になる点がポイントです。
一言でいえば簡単なのですが、不足なく取得しなければならず、取得のためにはある程度戸籍の記載内容を読み取る必要があるのでちょっとしたノウハウも必要です。
なので、法務局の解説ページをはじめ、戸籍の収集についてはどこの説明でもかなり大雑把に記載されているのが普通です。
相続登記や戸籍の集め方などの書籍を購入されれば別ですが、わざわざこの手続きのために本を1冊読むのも時間の無駄のような・・・
と思っていたところ、戸籍の収集についてとってもやさしく、しかもコンパクトに解説しているページがありました。
そこは、仙台家庭裁判所♪
裁判所にも家事手続きなどで戸籍一式を提出することが多いです。
それにしても、お役所の解説ページとしては群を抜いてわかりやすいと思います。
文章だけでなく、具体例も記載されています。
なので、これを見ていただければ、ある程度戸籍の収集はできるかと思います。
相続関係手続きにおける戸籍の入手方法Q&A
http://www.courts.go.jp/sendai/vcms_lf/205002.pdf
戸籍のたどり方
http://www.courts.go.jp/sendai/vcms_lf/205005.pdf
最後に、この法定相続情報証明制度は、相続登記の推進が一番の目的とのことでした。
不動産の名義が先代の名義のままになってる方は、この機会にぜひ名義変更の登記を行ってください!・・って法務局の方が一所懸命に広報してました!!(笑)
それにともなって、法務局のHPに(ようやく!?)解説のページが設けられました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
手続きは解説ページにあるように
①戸籍などの収集
②一覧図(相続関係図)の作成
③申出
の3段階です。
やはりネックになるのは①と②でしょうか。
②については、法務局も力を入れております。
いろいろなケースを想定してひな型を用意しています。
先日の法務局の説明会によると、申出された一覧図をPDFにして保管するのだそうです。
なので、基本的に記載内容に誤りがあった場合は、再提出なのだそうです。
資格者と一般の方では対応にある程度の差はあるかとは思いますが、一覧図(相続関係説明図)は慎重に作成する必要があります。
①の戸籍の収集については、現在の戸籍だけでは足りず、出生から死亡までの戸籍一式が必要になる点がポイントです。
一言でいえば簡単なのですが、不足なく取得しなければならず、取得のためにはある程度戸籍の記載内容を読み取る必要があるのでちょっとしたノウハウも必要です。
なので、法務局の解説ページをはじめ、戸籍の収集についてはどこの説明でもかなり大雑把に記載されているのが普通です。
相続登記や戸籍の集め方などの書籍を購入されれば別ですが、わざわざこの手続きのために本を1冊読むのも時間の無駄のような・・・
と思っていたところ、戸籍の収集についてとってもやさしく、しかもコンパクトに解説しているページがありました。
そこは、仙台家庭裁判所♪
裁判所にも家事手続きなどで戸籍一式を提出することが多いです。
それにしても、お役所の解説ページとしては群を抜いてわかりやすいと思います。
文章だけでなく、具体例も記載されています。
なので、これを見ていただければ、ある程度戸籍の収集はできるかと思います。
相続関係手続きにおける戸籍の入手方法Q&A
http://www.courts.go.jp/sendai/vcms_lf/205002.pdf
戸籍のたどり方
http://www.courts.go.jp/sendai/vcms_lf/205005.pdf
最後に、この法定相続情報証明制度は、相続登記の推進が一番の目的とのことでした。
不動産の名義が先代の名義のままになってる方は、この機会にぜひ名義変更の登記を行ってください!・・って法務局の方が一所懸命に広報してました!!(笑)