「國」は「大きい口+小さい口+戈」から、小さい内側の城壁を武力で守る為の大きな領域(城壁)を意味します。つまり、「國」は城を守る為の領土を意味します。
「国」は「口+玉」で、領地の中心に玉がいる事を意味します。「玉音放送」が天皇の肉声放送を意味するように、日本では「玉」は「天皇」をさし、外国の場合は「皇帝」をさします。
この意味からすると、本来の日本は「日本国」で、中共の支配地域は「中華人民共和國」と書けます。但し、今の日本は「ニホン國」で、江戸時代の日本は「にほん圀」かもしれません。
「城」は、日本では戦争が起きても戦うのは武士同士なので、城下町そのモノを守る必要が無く、城は一般に高台にあり城本体も高層構造になっています。つまり、城主は逃げ隠れせず、その地域で最も目立つところに住んでいると言えます。この事を「サヨク目線」で見ると、敵が攻めて来たら最初に城下町の人々が犠牲になり、それを天主閣から見張り、城主に危険が迫ると逃げ出す仕組みに見えます。
支那大陸では絶滅戦争が頻繁に起こる為、町そのものを城壁で囲み、國を守ります。これを「サヨク目線」で見ると、皇帝は住民の安全に気を配る心優しい人柄に見えるようです。しかし、実際は「南京事件」でも見られたように、「南京城」の町を守る城壁が破られると、住民は取り残され、自國兵は人民から必要なモノを略奪し逃走を図ります。
支那大陸の人民は支配者の所有物なので、単に城内に住んでいるだけであり、守られている訳では有りません。それどころか、城壁が破られる前に「皇帝」は逃げ出し、兵隊は皇帝を守る為に、大きく分けて三つの役割が与えられます。一つは「皇帝の守護隊」で近衛兵。二つ目は「敵と戦う兵隊」で戦闘員。三つめは「味方の兵隊が戦闘から逃げ出さないように見張る兵隊」で、これを督戦隊と言い挹江門事件(ゆうこうもんじけん)でも有名です。
挹江門事件は1937年の南京攻略戦の時に、「國民党軍」の戦闘員が城内に残っているのに督戦隊によって城門が閉ざされ、城壁を超えて逃げ出した「國民党」戦闘員が、同じ「國民党」の督戦隊によって1000名ほどが殺された事件(戦闘)です。これは、「国民党軍」ではなく「國民党軍」なので、起こるべくして起きた事件と言えます。
支那大陸の北京の北側には万里の長城があり、この城壁は元々は國境を示していました。この長城は支那大陸を北方蛮族から守る為の城壁で、長城以北は化外の地でした。但し、大清帝國の時代は支那を支配していた満州人の故郷であり、寧ろ逆に「漢民族」の立ち入りを制限していました。
大清帝國が滅亡した後に、(いくつもの)國民党が中華民國の立國宣言をし、満州に侵入し始めました。複雑な国際事情の中、関東軍は「満州国」を建国し、溥儀が皇帝におさまり「満州帝国」が一応成立しました。しかし、皇帝の溥儀は再度支那大陸を支配下に置く「満州帝國構想」を主張した為、混乱が拡大しました。
これらは、「国」と「國」の定義が定まっていない事と、武力侵略が標準であった国際情勢が、混乱の原因になったと思われます。単なる領域である「中華民國」を、世界は「中華民国」として、「国家」であると思い込んだからです。
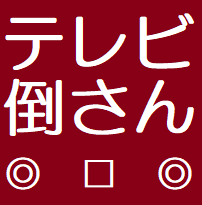










小平次です
敵が攻めて来たら最初に城下町の人々が犠牲になり、それを天主閣から見張り、城主に危険が迫ると逃げ出す仕組みに…、
めちゃ笑えます!
戦後の歴史学者は想像力が豊ですね!
ありがとうございました
日本は同じ轍を踏まないように、中東での関わり合いにも注意が必要だと思います。