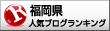北九州市の藤の名所・吉祥寺(きっしょうじ)に行きました。
例年と違い、花の先具合が早く薄紫色の藤は終わりに近く、
代わりに、白色、ピンク色の藤が満開になっていました。
白色の藤

ピンク色の藤と鐘楼
奥に鎮座していた祠?
薄紫の藤
例年、腰のかがめながら潜り抜けた藤は終わり、普通に歩いて潜れました。
上から見た藤
上から見ると花は全く見えず、全て緑色でした。
今年は、すべての花が早く咲いたようで、藤の花も同じでした。
今年も長く垂れ下がった藤の花を腰を屈めながら潜り抜けることができませんでしたが
ピンクと白の藤が満開で救われました。
コロナ禍の影響でようやく4年ぶりの藤まつりが開催されることになっていたのですが、
警察と地元自治会が造る実行委員会との安全対策について打ち合わせがうまくいかず、
中止になったことが残念です。
北九州市八幡西区にある吉祥寺は藤の花の名所です。
藤の花を透けて境内に降り注ぐ木漏れ日を見、長く垂れ下がったフジの花を腰を落とし
藤の香に包まれながら散策することはとても気持ちが良いです。
吉祥寺という名前は、東京にもありますね、10年前、さいたまに暮らしていたころ最も数多く遊びに行った街です。
この寺は「きちじょうじ」と読み、東京の吉祥寺と同じ呼び方です。
ところが、多くの方がこのあたりの地名「吉祥寺」を「きっしょうじ」と呼び、
自分も含み多くの方が寺の名前も誤って「きっしょうじ」と呼んでいるそうです。
面白いですね。
満開の藤
藤の香が漂う中、腰をかがめながら境内を散策します。
藤を通して境内を照らす木漏れ日に癒やされました。
白藤と紫色の藤
ピンクと薄紫の藤の花と山門
藤の花は薄紫の他、ピンク色があり山門と調和して落ち着きます。
吉祥寺の上から見ると藤の雲
上から太陽が燦々と降り注ぎ、木漏れ日となって藤の下にいる人々を照らしています。
鎮西上人と吉祥寺の藤棚
吉祥寺は1217年鎮西上人により家の跡地に難産で亡くなった母を弔うために開山されたそうです。
ご本尊は、腹帯を巻いた阿弥陀如来像で腹帯弥陀(はるびみだ)と呼ばれ、安産祈願に良いとされています。
**********************************************
吉祥寺公園の藤棚
公園はきっしょうじと呼び、吉祥寺に隣り合わせに並んでいます、こちらの藤の花は下がりが少なく少し早い感じです。
吉祥寺町の町並み
吉祥寺公園から吉祥寺町を見下ろします。
ツツジが綺麗でした。
吉祥寺公園の三重塔
藤の花の上に浮かぶように見えます、展望台です。
コロナ禍で例年開催される藤まつりは中止されました。
人手も少なく撮影には好都合でしたが、やはり寂しいものです。
来年は、なんとか祭りの中で苦労して撮影をしたいものです。