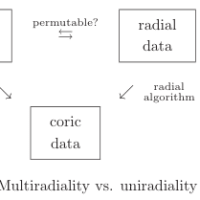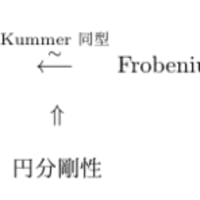少なくとも海外の経済学者の中で、*日本のためを思って*経済政策を提案している*唯一*の
存在だと、本ブログ筆者は認識している(「親日家」と言う事ではなく、*最も良い意味*での
「コスモポリタン」だと考えられる。∵世界各国に対して真に有益な政策提案をしているからだ)。
「*日本のためを思って*発言」していると判断する根拠の一つは、下記での「苦言」である。
# 「超帝国主義」∋ p.431
「日本は、アメリカがいかに顧客エリートを通して外国を支配しているかを示す、最も無様な
例のひとつである。日本の自動車産業やその他の産業がアメリカ市場に急速に進出したとき、
アメリカの外交官は日本の指導者たちに、1985年と1987年の自殺行為ともいえるプラザ合意と
ルーブル合意に同意させた。これらの協定は、アメリカが金利を上げる必要がないように、
そしてそれによって1988年の共和党の再選を脅かすことがないように、日本に金利を抑える
ことを義務づけた。」
i.e. ここでの「最も無様な例」という辛口表現は、真に心配していないと使えないだろう。
# かなり前に(「耕助のブログ」No.64,No.65で)同じ指摘をしている点も考慮している。
にも関らず、2023-11-22 時点で、彼の*数ある*著書の和訳出版は2つ、日本語WikiPedia の
項目すらないという状況。∴日本では「知る人ぞ知る」どまりで、知名度/重要性は低過ぎる。
取り敢えず、英語WikiPedia にある「主な主張」についての記述を和訳して見る。
その前に、下記の項目で「ポスト・ケインズ派」の経済学者に数えられている事を述べておく。
https://en.wikipedia.org/wiki/Post-Keynesian_economics
# 遺憾ながら、日本語WikiPediaの「ポスト・ケインズ派経済学」の項に彼への言及はない。
以下 https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Hudson_(economist) 冒頭部分の他、下記を和訳
「業績」⊃「古代近東における負債」、「国内債務と経済の債務デフレ」
「カール・マルクスとマルクス経済学に対する立場」、「作品紹介」(部分)
マイケル・ハドソン(1939年3月14日生まれ)はアメリカの経済学者で、ミズーリ大学
カンザスシティ校教授、バード大学レヴィ経済研究所研究員、元ウォール街アナリスト、
政治コンサルタント、コメンテーター、ジャーナリスト。Left Outが毎週制作している経済・
金融ニュースのポッドキャスト「ハドソン・レポート」に寄稿している。
シカゴ大学(学士、1959年)、ニューヨーク大学(修士、1965年、博士、1968年)を卒業後、
チェース・マンハッタン銀行で国際収支エコノミストとして勤務(1964-68年)。
ニュー・スクール・フォー・ソーシャル・リサーチの経済学助教授(1969-72年)を経て、
さまざまな政府機関や非政府組織で経済コンサルタントとして働く(1980年代-1990年代)。
ハドソンは、国内債務(ローン、住宅ローン、利子支払い)と対外債務の両方について、
債務の研究にそのキャリアを捧げてきた。^
その著作の中で、彼は一貫して、実体経済からの利益を上回る融資や指数関数的に増大する
債務は、政府にとっても借入国の国民にとっても悲惨なものである、という考えを提唱して
いる。なぜなら、それらは回転率から資金(使用者や賃借人への支払い)を洗い流し、財や
サービスを購入する資金を残さず、したがって債務デフレをもたらすからである。
ハドソンは、既存の経済理論、特にシカゴ学派は、レンティアと金融業者に奉仕し、現状に
代わるものがないという印象を強めるための特別な言葉を発展させてきたと指摘する。
偽りの理論では、現実経済への寄生的な負債は、会計上差し引かれる代わりに、国内総生産に
加算され、生産的であるかのように見せかけられる。
ハドソンは、消費者保護、インフラ事業への国家支援、労働者ではなく経済のレンティア部門に
課税することが、古典派経済学者の路線を今日において引き継ぐ事だと考えている。
2007年から2008年にかけての大不況の直前、2006年4月の『ハーパーズ』誌の記事で、
ハドソンはアメリカの住宅価格の暴落を予測した。
# ↑ 主流派経済学者は誰も予測できなかった。→故エリザベス女王の質問に絶句。^
^ 業績 ←英語原文
ハドソンは最初の著作を、金と外貨準備高とアメリカの対外経済債務という、彼の師である
テレンス・マッカーシー(マルクスの『剰余価値論』の訳者)が以前に詳しく扱ったテーマに
捧げた。金のふるい」と題された最初の論文で、ハドソンはベトナム戦争の経済的悪影響を
分析し、戦争がなくてもアメリカ経済はすぐに危機的状況に陥るという事実に注目した。
戦後のアメリカの福祉は、多くの場合、第一次世界大戦の終わりから第二次世界大戦の終わり
までの間に自ら作り出した「黄金の枕」で提供されていた(Youtubeでのマイケルの帝国講義
2021年4月と他の2021年録画講義による)。
アドルフ・ヒトラーに怯えた1934年以降、ヨーロッパ諸国は米国国債を買い始め、金と
外貨準備を米国の銀行に移した。1934年以降、米国の金・外貨準備高は74億ドルから1945年
には201億ドルに増加した。
ブレトンウッズ体制が構築され、その枠組みの中で国際通貨基金(IMF)が設立され、ドルが
金と同じ価値があることを保証する金プールが設立されると、資本は国外に流出し、
ヨーロッパに移動し始めた。
アメリカの財政赤字のうち軍事費が大きな割合を占めていたため、実効性には欠ける赤字拡大
防止努力として、アメリカは金の流通を制限する一方で、他方では外国の中央銀行がドルと
引き換えに金を受け取ることを認めなかった。このような政策は、偽善的だとヨーロッパの
銀行家に受けとめられた。しかし、彼らはその政策を不承不承受け入れた。それは、ドルを
下落させる事で彼らの製品が米国市場での競争力を失うことを恐れていたからだ。
ハドソンは、1960年から1968年までの米国の国際取引の金融支払-フロー分析において、
米国の輸出統計が、ある国の居住者から他の国の居住者への、いかなる支払いも伴わない
海外への移転が行われた物品の分類を誤って含んでいることを示した。
この種の物品の主なものは、米国が海外のエアターミナルで国際航空会社に航空機の部品や
コンポーネントを譲渡し、その航空機に取り付けることであった。
これらの移転は、保税の下で受入国に持ち込まれたため、輸入統計から除外された。そのため、
政府部門は1960年から1968年の間、主に軍事活動の結果として、支払い・フロー・ベースで
大幅な赤字となった。政府と民間のフローを混合した既存の会計システムでは、この問題と
格差の原因を示すことはできなかった。ハドソンはそのモノグラフの中で、米国の国際収支を
政府部門と民間部門に分ける試みを行った。^
1972年、ハドソンは第一次世界大戦後のアメリカ帝国主義形成の歴史をたどった
『超帝国主義』を出版した。
ハドソンの解釈では、超帝国主義とは、国家が自国以外のいかなる集団の利益も実現しない
帝国主義の段階である。
超帝国主義とは、国家が自国以外のいかなる集団の利益も実現しない帝国主義の段階であり、
それ自体、他国を植民地化し、ドル外交によって彼らを顧客国家にすることを完全に目的と
している。
ハドソンは、『A Financial Payments-Flow Analysis of U.S. International Transactions,
1960-1968』で概説した立場を引き継ぎ、第二次世界大戦後に形成された援助制度、世界銀行、
IMFを強調した。
アメリカの対外政治はすべて(抱き合わせの援助や債務を含め)、アメリカが新興の競争を
恐れる経済分野において、第三世界諸国の自給自足的な経済発展を抑制することを目的として
いた。同時にアメリカは、いわゆる自由貿易政策を発展途上国に押し付けた。この政策は、
アメリカ自身が繁栄を得るために利用した政策とは逆のものだった。
1971年、米国は金とドルを交換する権利を取りやめた後、外国の中央銀行に米国債を買わせた。
この収入は、連邦赤字と大規模な海外軍事支出の財源として使われた。資産、商品、負債調達、
商品、サービスの純余剰を提供する代わりに、外国は同額の米国債を保有することを余儀なく
された。これによって米国の金利が下がり、ドルの為替レートが下がって、米国製品の海外での
競争力が高まった。
ハドソンは、外国の中央銀行が財務省証券を購入するのは、為替操作ではなく、為替レートを
安定させるための正当な努力と見なす。外国の中央銀行は余ったドルを為替市場で売る事もでき、
そうすれば自国の通貨を強くできる。しかし、そうする事は購買力を高める一方で、貿易黒字を
継続する能力を低下させるという、ジレンマだと彼は言う。
彼は、将来的保証のない国外資産と引き換えられる、記帳上の負債増と財務省証券の発行は、
米国にとっては、財務省証券の償還を減価したドルで行う事を意味し、武力による略奪と同じ
ようなものと考えている。
彼は、国際収支の黒字国には為替レートを安定させる権利があり、産業がアメリカから債権国に
移っても、その結果生じる借款の返済を期待できると考えている。
ワシントン・コンセンサスは、国際通貨基金(IMF)や世界銀行に緊縮財政を促すものであり、
ドル支配のおかげでアメリカ自身は緊縮財政にさらされることはない、と彼は言う。ドル外交は、
他国を不公正な貿易や投資の対象とし、外国の資産や天然資源を奪うことを意図している。
これにはインフラを民営化させ、あわよくば底値で買収する事が含まれる。寄生的な金融手法
(欧米式の減税を含む)は、公正な状況を用意して各国の自立を促進するのではなく、その国の
余剰を最大限に奪い取り、経済的にアメリカと競う能力を損うために使われる。^
^ 古代近東における負債 ←英語原文
1980年代末、ハドソンは現代経済学の分野から離れ、古代メソポタミアに、現代の西欧金融に
おける諸慣行および諸概念の基礎を求める調査を行った。
彼が組織した長期経済動向研究所(Institute for the Study of Long-Term Economic Trends)
の支援のもと、1994年から2004年にかけて5回の会議を開催し、関連分野の第一線の学者を
集めてこのテーマを調査し、関連する最新の学問的成果を集約した著作として出版した。
この5つの会議は、以下に焦点を当てた:
「古代近東と古典世界における私有化」、
「都市化と土地所有」、
「古代近東における負債と経済再生」、
「経済秩序の創造(簿記、標準化、会計の発展)」
「古代世界における労働」
こうして積み重ねられた仕事は、さまざまな経済神話(例えば「市場と貨幣の起源は物々交換」や
「貨幣の起源は金属ないし硬貨」)を解体し、入念に文書化されたきわめて明白な事実に置き換えた。
借金との起源を調査した結果、最初に、そして圧倒的に早い時期に主要な債権者となったのは
青銅器時代のメソポタミアの神殿や宮殿であり、独自行動する個人ではなかったとわかった。
各地域の利子率は、生産性に基づいてではなく、その地域の計算システムによる分数の計算が
簡単になるように決められた。メソポタミアでは月に60分の1、後のギリシャでは年に10分の1、
ローマでは12分の1といった具合である。
貨幣の起源は、金属や物々交換や硬貨ではなく、簿記である。土地の所有権、抵当権、賃料、
賃金に関する考え方は、この文脈で生まれ、それによって決定された。
国家の自然な安定は、生産的な仕事をする自由で独立した労働者ができるだけ多くいることに
かかっている。個人負債が増加し、ある低い閾値を超えると労働者の生産性を低下させ始める-
たとえそれがエリート金融階級をより裕福にしたとしても。ジュビリーやクリーン・スレートの
宣言(訳注:いずれも「債務の(制度的な)帳消し」∴「徳政令」と類似。 訳し分けるならば、
例えば、後者を「債務の白紙清算」とすることなどが、考えられる。)
には、労働者の生産性を高め、より幸福にし、それによって経済を改善するという目的が
あった。ハドソンはこう述べている: 「1990年代初頭、私は自分なりの要約を書こうと
したが、聖書の債務帳消しの近東の伝統が確固たる根拠を持っていることを出版社に納得
させることはできなかった。20年前には、経済史家や多くの聖書学者でさえ、ジュビリー・
イヤー(「債務帳消しの年」)は単なる文学的創作で、ユートピア志向の現実逃避だと
考えていた。私は、「この慣習がますます詳細になっていくクリーン・スレート宣言の中で
証明されている」という思想への認知的不協和の壁にぶつかったのだ。」
デイヴィッド・グレーバーの著書『Debt: The First 5,000 Years』(2011年)は、ハドソンの
考えを参考にしている。
ハドソンと彼の同僚が集め、発表した文献的証拠によれば、古代近東では、借金が神聖視
された事はなく、むしろ神聖視されたのは、定期的な借金の帳消しであった。
社会の均衡を保つため、また軍務に服する自由民となる健全な農民階級を確保するために、
これには農民の負債も含まれ、奴隷使用人だけでなく自由民も永久的な負債による隷属から
解放された。
そうした債務の帳消しは、社会を不安定にすることはなく、むしろ長期的な社会的・経済的
安定を維持するために不可欠であった。
2000年代の初めから、ハドソンは架空の資本を膨張させ、実体経済から資金を引き揚げ、
債務デフレを引き起こすという問題に特別な注意を払っている。
彼は、金融と「金融化」が、アメリカとヨーロッパの生産能力を低下させるよう政治を誘導
する鍵であると述べている。
エリート金融階級は、非生産的な金融戦術や戦略から利益を得ている。彼らはこうした手法を
使って、チリ、ロシア、ラトビア、ハンガリーに危害を加えてきた。^
^ 国内債務と経済の債務デフレ ←英語原文
2000年代の初めから、ハドソンは架空の資本を膨張させ、実体経済から資金を引き揚げ、
債務デフレを引き起こすという問題に特別な注意を払っている。彼は、金融と「金融化」が、
アメリカとヨーロッパの生産能力を低下させるよう政治を誘導した鍵であると述べている。
エリート金融階級は、非生産的な金融戦術や戦略から利益を得ている。
彼らはこうした手法を使って、チリ、ロシア、ラトビア、ハンガリーに危害を加えてきた。
ハドソンは、寄生的で非生産的なレントシーキング金融は、産業と労働を、どれだけの富を
手数料、利子、減税によってそこから奪い取るか決めるためにのみ見ていると説く。
市場が求める生産と効率を高めるために資本を投下するのではなく、蓄積された富を複利で
融資する。こうすることで、国の借金は実質的な財の生産よりも速く膨れ上がる。
利息の複利化は当然、債務を増大させ、最終的には生産と労働が支払える以上の富を引き去る
ことを要求する。
労働と生産設備のコストを削減するためレンティアから税金を徴収し、その税収でインフラを
整備し生産効率を高めようとせず、アメリカの税制、銀行救済、量的緩和は、金融セクターの
利益のために労働者と産業を犠牲にしている、とハドソンはいう。
ハドソンによれば、1880年代には早くも銀行家とレンティアは、金融、不動産、独占の
非課税化と規制緩和を合理化する方法を模索し始めた。彼らは1980年代に「万人の所得は
働きに見合うもので、税を免れている不労所得などない」という新自由主義的なワシントン・
コンセンサスを確立することに成功した。
ハドソンは、新自由主義的なドル外交と金融化の世界的な成功は、すべての主要大学に
おける教育支援と密接に結びついていると強調する。彼はチリの話を引き合いに出す。
1973年に軍事政権がアジェンデ政権を打倒した後、チリにおけるシカゴ・ボーイズの最初の
行動のひとつは、シカゴ大学マネタリストの拠点であったカトリック大学以外のすべての
経済学部を閉鎖することであった。
その後、軍事政権はすべての社会科学系学部を閉鎖し、ラテンアメリカ全土で繰り広げられた
テロであるコンドル作戦で、自らのイデオロギーに批判的な人物を解雇、追放、殺害し、
アメリカ国内での政治的暗殺にまで拡大した。シカゴ・ボーイズが認識した事は、経済計画は
もっと中央集権的になるべきだが、政府の手から銀行家やその他の金融機関の手に移るべきだ
という考えに対する知的抵抗が生き残っている場所では、自由市場イデオロギーには、学校や
大学システムの全体主義的統制、報道機関と警察の全体主義的統制が必要だということである:
言い換えれば、自由市場イデオロギーは、あらゆる思想の自由に反対する政治的二重思考に
終わる。
アメリカ及び他国での自由市場イデオロギーの目覚ましい成功は、多くの点でマルクスを頂点と
する1800年代初頭からの古典的で保守的な経済思想の伝統を排除することによって達成された。
そうした経済思想は、経済学のカリキュラムから抹消されてしまった。
# ↑ 日本の経済学教育でも同様な状況。
ハドソンが信奉する現代貨幣理論 (MMT) は、経済学を純粋に数学として考える新自由主義者の
虚偽を示すことによって、支持を集めている。
# レンティア(不労所得{者、階級})への課税+社会の安定に必要な場合の「債務帳消し」の
# 重要性を強調する事は、他のMMT論者やポストケインズ派と異なる、ハドソン独自の論点。
# 例えば、今年中頃にロシアで実施された「破産申請要件緩和」は、ハドソンが想定している
# 社会の安定に必要な場合の「債務帳消し」の例と考えられる(∵破産者の債務は帳消し)。
# 破産後の「健康で文化的な最低限度の生活」への配慮も強化され、破産者が急増したとか。
# (返せそうにない借金を抱えた生活は、それだけ苦しいということだろう)。
# 「レンティアへの課税」の方は、これといった実例に心当たりがない。既存の税制の中だと
# 「固定資産税」、「相続税」などの、「レント(不労所得)への課税」という意味合いが
# ありそうな税の税率を上げるとか、「利子や配当への「源泉分離課税」」を原則やめるとか
# キャピタルゲイン(値上がり益)課税を強化するといった方向性になるだろうが、「労働者
# への課税を置き換える」というハドソンの想定に合う規模にするなら、何か抜本的新機軸が
# 税の定義と税実務上の技術の両方で必要になりそうな気もする(具体案は思いつかない)。
# そもそも所得ではなく、財産に課税するという案は、昔からあるのだが。超大金持ちだけを
# 対象にして、かなり低い税率にしても、金額は確実に十分大きくなるだろうし。^^;
# とは言え、「税」を考察対象の中心に含めるか否かは、筆者が経済学者評価で重視する点の
# 1つなので、ハドソンは「ポイント高い」^^;。^
^ カール・マルクスとマルクス経済学に対する立場←英語原文
ハドソンは自らをマルクス経済学者と自認しているが、カール・マルクスに関する彼の解釈は、
他の多くのマルクス主義者とは異なっている。他のマルクス主義者が今日の資本主義世界の
核心的問題として賃金労働と資本の矛盾を強調するのに対し、ハドソンはこの考えを拒否する。
ハドソンは、今日の破綻した経済の核心的な問題は、寄生的形態の金融であって、それは
「自由市場」を「非生産的な賃借料から自由である」という1800年代の本来の定義から変え、
「自由市場」をあらゆる規制と課税の引き下げ、国内外での資産剥奪を可能にするよう再定義
するものだと考えている。
ハドソンは、マルクスがあらゆる形態の封建的レントシーキングを排除することを望んでいると
理解する人々の味方である。
もしそれが奨励されるなら、新たな封建主義と99%の経済的農奴制をもたらすだけである。
古典派政治経済学者が論じた自由市場の本来の意味は、あらゆる形態のレントから自由な市場
であった。古典派政治経済学の要諦は、稼ぎのある生産的な経済活動と稼ぎのない非生産的な
経済活動を区別することであった。
ハドソンはまた、マルクスは楽観的すぎたと主張する。 歴史は資本主義が社会主義に進化する
という方向には進まなかった。1930年代以降、現代の資本主義は非生産的なレンティア階級に
よって支配されている。マルクスを含む古典派経済学では、階級としてのプロレタリアートは、
賃借料をできるだけ支払わない方がよいとされている。労働者の諸経費が少なければ、賃金を
低く抑えることができるからだ。これによって生産する商品の価格が下がり、国際市場での
競争力が高まる。これは、医療を政府が非営利で運営する公共コモンズとする論理でもある。
これによって労働者の賃金を下げることができる。
ハドソンは、このような地に足の着いた経済学的思考を、次のような新自由主義者の主張と
対比する:「あなたの家の値上がりを見てください!あなたは住宅投資で大儲けしているの
です!」(言い換え)。
非生産的な賃借、戦術、戦略は、米国を含むすべての国の自立性を低下させている。
このことは、債務帳消しや、労働者や生産活動にではなく、非生産的活動に課税するという
アイデアにつながる。
何もしないことの代償は大きい。野放しにすれば、ますます増加する負債の必要性とレントが
歴史を新しい封建制度に逆戻りさせる。そこでは、雇用主が医療費を支払い、住居を提供し、
労働者を永久に負債で囲い込む。
ハドソンの見解は、他のマルクス主義者の間では不評であり、時には激しく拒絶されることも
あるが、彼は、ほとんどのマルクス主義者は、マルクスがレントについて全く言及していない
『資本論』第1巻の先へ進んでいないと指摘する。
(指摘の背景を)説明しよう。マルクスと同時代の経済学者の間たちでは、非生産的レントの
有害性については幅広いコンセンサスが存在していたため、マルクスは第3巻まではレントの
問題を取り上げなかった。
(すなわち)『資本論』第1巻において、マルクスは、すべての商品がその価値で販売される
レントのない市場が存在すると仮定している。こうしてマルクスは、資本主義の搾取的性質と、
その根底にある矛盾としての労働と資本の二分法を推論する。
しかし、『資本論』第2巻と『資本論』第3巻において、マルクスはその仮定を緩和し、今日の
経済システムで観察されるものにはるかに近い別の矛盾を発見する。
『資本論』第3巻で、マルクスは、生産性と供給が消費力と需要よりも速いペースで増加する
傾向について論じている。
マルクスはまた、資本主義の非対称的な発展について研究し、学ぶにつれて、以前の考えを
修正した。その結果、マルクスは、工業先進国の低開発国に対する支配が、支配国の労働者
階級の革命的傾向をいかに阻害するかを理解し、最終的に革命的な論調を和らげた。
# 「1848年以降、マルクスはもはや政治的幻想に身をまかせることはなかった。」
# ↑ ウルリケ・ヘルマン著「スミス・マルクス・ケインズ」 p.154
# 「... われわれが現在グローバリゼーションと呼んでいるものは ... 諸問題をより大規模な
# 地理的領域に投企することによってそれらの諸問題を「解決する」一時的な回避 ....」
# ↑ デヴィッド・ハーヴェイ著「<資本論>入門」p.450 ^
^ 作品紹介 ←英語原文(Works)
著書
# 和訳が出版されているのは、下記2作品のみ。
Super Imperialism: 『超帝国主義国家アメリカ帝国の内幕』
Global Fracture: 『新国際経済秩序―世界経済の亀裂と再築』
# 下記3作品の「マイケル・ハドソン研究会」での和訳が現在も部分的に公開されている。
The Destiny of Civilization:「文明の命運」
Super Imperialism: 「超帝国主義(第3版)」
... and forgive them their debts:「... そして、彼らの債務を許せ」
# 前記「文明の命運」と下記作品、各々の紹介文が「耕助のブログ」にある。
The Collapse of Antiquity: 「古代の崩壊」^
更新履歴
2023-12-03 12:47 : 「古代近東における負債」、カール・マルクス...に対する立場」を更新