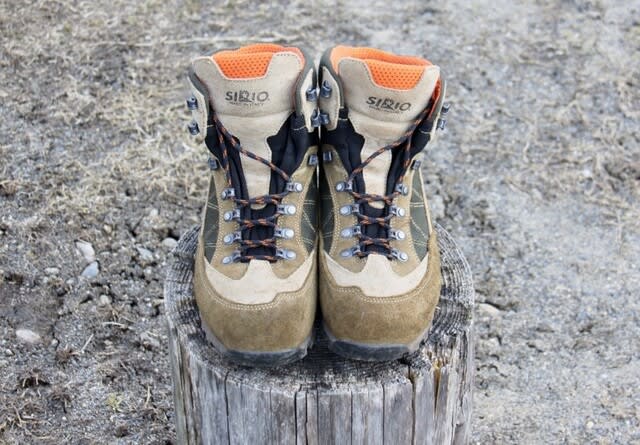2024年1月29日(月) 晴れ
茨城県北部には山々が拡がっているんですが、山と言っても一番高い八溝山で1,022mあとは500m前後の山でそれが折り重なりように連なっています。どちらか言えば低い山々なんですが、その一部に大昔海底火山だった影響で火山角礫岩で出来たゴツゴツした岩山がありまして、そこには滝が結構あります。全国的に有名な「袋田の滝」もその一つです。今回はそんな滝を散策に行きます。場所は「鍋足山」の西麓、東側は登山ルートが整備されているんですがこちら側は薄い踏み跡のけもの道のようなものがあるだけです。まずは沢沿いを歩きその薄い踏み跡を探しながら奥に進んで行きます。

氷結の滝-1
この沢床も固い火山角礫岩で出来ています。冬はほとんど流れがありませんのでここを遡上していきます。

氷結の滝-2
登山口から15分ほど進むとお目当ての「不動滝」に到着です。

氷結の滝-3
う~ん、残念ながらほとんど流れもなく氷結もしていません。いつもは両脇に何本も氷柱を作り真っ白く氷結しているんですが、暖冬の影響でしょうか残念です。

氷結の滝-4
当初氷結の滝を見た後滝を巻いて上部に抜け鍋足山山麓をトレッキングしようと思ったんですが、滝が氷結してないので予定変更して反対側の滝を見に行くことにします。

氷結の滝-5
左側のピークが鍋足山山頂、今回は山頂と右側のピークの間の滝を見に行きます。

氷結の滝-6
駐車スペースに車を停め15分ほど歩くと滝の案内板があります。今日は左側の「中ん滝」を目指します。

氷結の滝-7
急登を小一時間進むと「中ん滝」到着です。

氷結の滝-8
こちらは標高が高いせいか一部岩肌が白く氷結しています。

氷結の滝-9
近づいてみると一部が解けて水滴が滴り落ちていますが、何とかギリギリ氷結の滝を見ることが出来ました。

氷結の滝-10
これも温暖化の影響でしょうかひょっとしたら来年は見れないかも、寒いより暖かい方がいいんですが氷結の滝が見れなくなるのは何とも残念です。