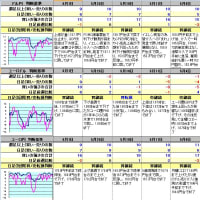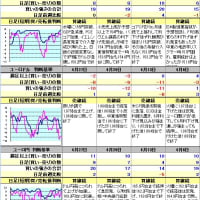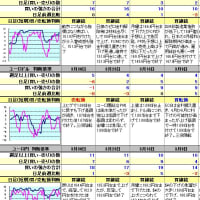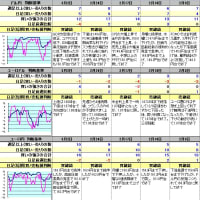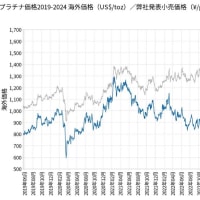毎週土曜日に為替トレンド確認のために個人的に行っているトレンド分析の2月3日分(1月2日~2月2日)。
分析結果と各ペア動きのまとめ
トレンド分析のサマリ部分(見方の説明は2020年2月3日の記事参照)。
分析結果と各ペア動きのまとめ
トレンド分析のサマリ部分(見方の説明は2020年2月3日の記事参照)。

各通貨ペアの日足チャート

出所:セントラル短資FX|為替チャート一覧
ドル円は年初の始値140.8円近辺を1月安値として上昇に転じた。元日の能登半島地震によって日銀の緩和解除の延期観測が広がったためだ。また1月4日公開のFOMC議事要旨では高水準の金利が当面維持されることが確認された。さらに1月5日の雇用統計では米雇用者の伸びが加速し、賃金は予想を上回る上昇で146円手前まで上げた。
ドル円は年初の始値140.8円近辺を1月安値として上昇に転じた。元日の能登半島地震によって日銀の緩和解除の延期観測が広がったためだ。また1月4日公開のFOMC議事要旨では高水準の金利が当面維持されることが確認された。さらに1月5日の雇用統計では米雇用者の伸びが加速し、賃金は予想を上回る上昇で146円手前まで上げた。
しかし、その後は米金利の動きを反映してすぐに反落し、1月9日には143.4円台まで下げた。雇用統計は後で下方修正されることが多く、過去11回中10回は下方修正だった。そのことを知っている市場関係者は、雇用統計を一時的な材料としてしか見ていないのだろう。
1月10日からは戻し始め、1月11日の消費者物価指数は伸びが加速し、予想を上回る上昇で146.4円台まで上げたが続かなかった。1月12日の生産者物価指数は前月比で3カ月連続の低下で利下げ観測が再び強まったが、下げも限定的で144.3円台止まりでまた戻し始めた。
1月16日にFRBウォラー理事が講演で利下げを急がない旨の発言をしたため
147円台へ上げ、翌17日には148.5円台まで上げた。その後は148円を挟んだ横ばいの動きが続き、1月19日の148.804円が1月高値だった。トレンド分析では1月20日に買転換となった。
1月31日のFOMCでは金利を据え置き、パウエル議長の記者会見では3月利下げの可能性は低いと発言したが、想定の範囲内だった。1月31日にニューヨーク・コミュニティ・バンコープ(NYCB)の株価が暴落し、米金利が大きく低下すると146円割れ寸前まで下げ、翌2月1日には145.8円台を付けた。2月1日のISM製造業景況指数は1年3カ月ぶりの高水準だったが影響はほぼなかった。
2月2日の雇用統計では雇用者数と賃金の伸びが予想外に加速し、ドルが急伸して一時148.5円台に達し、148.3円台で終わった。勢いを見れば週明けに1月高値の更新を期待できるが、前述のように雇用統計の効果の持続性には疑問があるところだ。
ユーロドルは1月2日の急落後、前半はやや上昇基調だったが、後半は下落基調だった。1月高値は1月2日の始値に近い$1.10433だった。トレンド分析では1月27日に売転換した。1月末に$1.08割れとなり、2月2日に$1.107805の安値を付け、$1.078台で終えた。
1月10日からは戻し始め、1月11日の消費者物価指数は伸びが加速し、予想を上回る上昇で146.4円台まで上げたが続かなかった。1月12日の生産者物価指数は前月比で3カ月連続の低下で利下げ観測が再び強まったが、下げも限定的で144.3円台止まりでまた戻し始めた。
1月16日にFRBウォラー理事が講演で利下げを急がない旨の発言をしたため
147円台へ上げ、翌17日には148.5円台まで上げた。その後は148円を挟んだ横ばいの動きが続き、1月19日の148.804円が1月高値だった。トレンド分析では1月20日に買転換となった。
1月31日のFOMCでは金利を据え置き、パウエル議長の記者会見では3月利下げの可能性は低いと発言したが、想定の範囲内だった。1月31日にニューヨーク・コミュニティ・バンコープ(NYCB)の株価が暴落し、米金利が大きく低下すると146円割れ寸前まで下げ、翌2月1日には145.8円台を付けた。2月1日のISM製造業景況指数は1年3カ月ぶりの高水準だったが影響はほぼなかった。
2月2日の雇用統計では雇用者数と賃金の伸びが予想外に加速し、ドルが急伸して一時148.5円台に達し、148.3円台で終わった。勢いを見れば週明けに1月高値の更新を期待できるが、前述のように雇用統計の効果の持続性には疑問があるところだ。
ユーロドルは1月2日の急落後、前半はやや上昇基調だったが、後半は下落基調だった。1月高値は1月2日の始値に近い$1.10433だった。トレンド分析では1月27日に売転換した。1月末に$1.08割れとなり、2月2日に$1.107805の安値を付け、$1.078台で終えた。
1月16日にECBが発表した今後1年間のインフレ期待の月次調査ではインフレ期待が著しく低下していて、過去1年半で最低の水準だった。それで利下げ期待が高まった。1月18日のダボス会議でのラガルド総裁の発言で、夏の利下げはあり得るとのことで、6月ごろの利下げ観測高まった。また1月25日のECB政策発表後のラガルド総裁の記者会見でも夏の利下げの可能性高いことが確認された。
ところが、2月1日のユーロ圏消費者物価指数で1月は予想上回る結果となり、利下げ観測が不透明になり、少し戻した。しかし2月2日の米雇用統計がよかっため、ユーロドルは下げて直近の安値を更新して終えた。
ユーロ円は1月2日に155.066円の1月安値を付けた後、1月中旬まで上昇基調で1月19日に161.864円の1月高値を付けた。トレンド分析では1月13日に買転換した。しかし、1月20日以降はユーロドルにつられて下げ基調となり、2月1日に158.0円台まで下げた。2月2日はドル円の上げとともに160円台に戻して終えた。
ユーロ円は1月2日に155.066円の1月安値を付けた後、1月中旬まで上昇基調で1月19日に161.864円の1月高値を付けた。トレンド分析では1月13日に買転換した。しかし、1月20日以降はユーロドルにつられて下げ基調となり、2月1日に158.0円台まで下げた。2月2日はドル円の上げとともに160円台に戻して終えた。
各国の動きとニュース
米国関連
1月4日 FOMC議事要旨公開
1月5日 雇用統計
1月11日 消費者物価指数
1月12日 生産者物価指数
1月16日 FRBウォラー理事講演
1月31日 FOMCとパウエル議長の記者会見
1月31日 ニューヨーク・コミュニティ・バンコープの株価暴落
2月1日 ISM製造業景況指数
2月2日 雇用統計
EU関連
1月16日 ECBが発表した今後1年間のインフレ期待の月次調査
1月18日 ダボス会議でのラガルド総裁の発言
1月25日 ECB政策発表後のラガルド総裁の記者会見
2月1日 ユーロ圏消費者物価指数
日本関連
1月23日 金融政策決定会合後の植田総裁の記者会見
新NISAの円安への影響
新NISA(つみたて投資枠)が始まって一番無難なeMAXIS Slim全世界株式(オルカン)に資金が集まってニュースになっていたが、類似の投信や米国のインデックス型も人気が高い。その分だけ、ドルを中心とした外貨需要が実需として現れる。2月2日の日経の記事だと月3250億円だそうだ。すぐに解約されるされることもないので、為替取引全体から見れば小さいがベースの部分としては一定の効果かある。
唐鎌大輔さんの解説記事
東日本大震災の後は円高になったが、元日の能登半島地震では緩和解除延期観測で円安に向かった。短期的には日銀政策や米金利動向ですぐに動くが、日本は過去10年余りで貿易赤字国としての地位が定着したので長期的には円安方向だという見方がある(以前から出ている構造的要因)。その辺りを解説してあるのが以下の記事。
米雇用統計での下方修正が多発
米雇用統計は後で下方修正されることが多いと上で書いたが、その辺りの解説記事。発表数値でアルゴリズム的に動くし、その後は金利動向で動くので後で修正されても相場への影響はほぼないが、実態は修正値に反映されている。