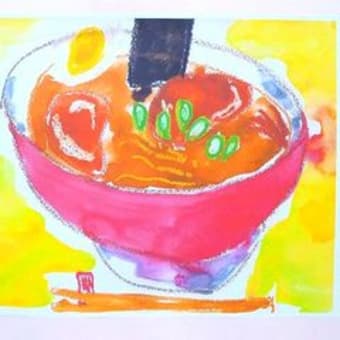4477.~要因を探る~
「知的障害・発達障害をもつ生徒さんの 個性と可能性を伸ばす!」: 造形リトミック・発達支援教室 Elephas(エレファース)
・・・明るく、楽しく、さわやかに・・・
~今日のElephasブログ:「工夫次第!」(8月22日)
おはようございます。津田沼教室の千山です。
Yくんと計算問題に取り組んでいます。
足し算の筆算、引き算の筆算、掛け算九九と簡単な割り算ができるようになりました、
けれども、足し算の時に引き算をしたり、掛け算と割り算をまちがえたりするなどのミスがみられました。
「これは何算かな」と、聞かれてから慌ててやり直すこともありました。
+、-などの記号に注意を払えていないことが原因と考えました。
そこで、一枚のプリントにいろいろな計算をのせて、+や-などの記号を赤で強調しました。
また、計算の前に「何算?」と声かけをしました。
繰り返すうちに、計算ミスをしなくなりました。
Yくんが自分できるようになるためにどういう授業をしたらいいか、これからも工夫したいと思います。
◇ワンポイント・メッセージ◇
誤答の場合、講師はその要因を探る必要があります。Yくん、記号の強調または計算前の声掛けで誤答が減ったということは、記号の理解に問題があったという訳ではなさそうですね。何故ならば、記号に注目すれば正答できるのですから。では要因は、不注意や焦り(とにかく終わらせればイイ)?それとも視知覚機能?・・・。教室の生徒さんの場合、後者である場合が多分にあります。記号の強調のみでの正答率を測ってみると良いですね。