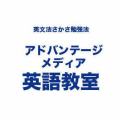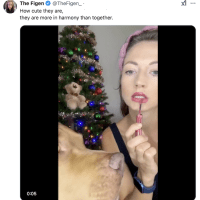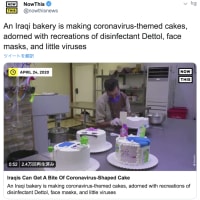こんにちは、アドバンテージ・メディア英語教室です。
今日もニュース英語で楽しく英文法を勉強しましょう!
今日もニュース英語で楽しく英文法を勉強しましょう!
本ブログの「第815回」で、輸送トラックから逃げ出したダチョウのニュースを取り上げました。
今度は農場から自由を求めて逃げ出し、町を走り回りました。その数なんと、80頭(羽)のダチョウ。ちなみに、ダチョウは時速約72キロ、高さは約2メートルあります。
今回は「「できた」を表す「was/were able to」」について、「CNN」をもとに解説します。
▷今日のテーマ
「できた」を表す「was/were able to」
▷今日の例文
例▷ The farmer was able to recover most of the ostriches with the help of the police.
訳例▷ その農夫は警察の助けもあって、ダチョウのほとんどを回収することができました。
▷今日のテーマ
「できた」を表す「was/were able to」
▷今日の例文
例▷ The farmer was able to recover most of the ostriches with the help of the police.
訳例▷ その農夫は警察の助けもあって、ダチョウのほとんどを回収することができました。

▷実際のニュース映像はCNN
▷解説
「〜することができた」という意味を表したい場合は、「was/were able to」を使うのが一般的です。
「can」の過去形である「could」にも「〜できた」という意味はあります。
しかし、「could」は仮定法の意味として使われることが非常に多いです。
「She could pass the exam.」という英文があります。
これは、「could」を「can」の過去形と考えると、「彼女はその試験に合格できた。」となりますが、実際にはそういう意味よりも「彼女はその試験に合格できるかもしれないね。」という仮定法による「推量・推測」の意味を表す場合の方が多いです。
ですのでもし、「合格することができた」と言いたいのであれば、「She was able to pass the exam.」とすると誤解がなくなります。
「今日の例文」でも「〜することができた」という意味で、「was able to」が使われています。
なお、「could」は「〜できた」という意味で使われることは少ないですが、「couldn't」は「〜することができなかった」という意味で普通に使われます。否定形の場合は「able to」をわざわざ使う必要はありません。
▷その他の単語
farmer: 農場主、農場経営者、農夫
recover: 回収[奪回]する、取り戻す
ostrich: ダチョウ
with the help of: ~の助け[援助]で[により]、~の助けを借りて、~の助力[協力・力添え]を得て[受けて]
▷今日の例文は「CNN」から
80 ostriches in China made a break for freedom...