私の音楽の思い出
燃ゆる瞳(H21.09.23)
♪いつかどこかで会った、そんな気がする、燃える瞳をした、あのかわいい娘~♪で始まる燃ゆる瞳という曲。
私の高校1年生の時、私の高校では、かなりマニアックに流行っておりましたので、私にとっては、とても懐かしい曲です。
原曲は、ボビー・ヴィーの燃ゆる瞳(The night has a thousand eyes)というアメリカン・ポップス。全米3位にまでなった曲。
少し調べたところ、スリーファンキーズが日本語版で、もゆる瞳という曲名でレコードを出しているとのことでした。
(当時の私の記憶には、スリーファンキーズがこの曲を歌っていたという記憶はありませんが)
日本語の訳詞をしたのは、私が調べた限りでは、確認できませんでしたが、おそらく、安井かずみさん(当時、みナみカズみというペンネーム)が訳詞したのではないかと思います。
後に、カーペンターズがこの曲をカバーしております。
1962年 The Night has a Thousand Eyes(燃ゆる瞳) 歌Bobby Vee 詞・曲Benjamin Weisman Dorothy Wayne Marilyn Garrett
1973年 The Night has a Thousand Eyes(燃ゆる瞳) 歌The Carpenters LP「Now & Then」に収録
Mercy,Mercy,Mercyという曲、知ってます?(H21.09.13)
私の大学生時代の知人で(数少ない、レコード会社に音楽ディレクターとして採用された人間)が、好きだと言った曲を思い出しました。
その曲はマーシー・マーシー・マーシー(Mercy,Mercy,Mercy)。ザ・バッキンガムズという米国のロックバンドが歌った。
(私としては、ロックバンドはビートルズのほうがよほど面白いし、曲もいいと感じていましたが)
この曲は、有名なジャズのキャノンボール・アダレーの代表作。(ジャズファンならば、きっと演奏を聞いたことがあると思います)
キャノンボール・アダレーのキーボード奏者ジョー・ザビヌルの作曲。翌年、ザ・バッキンガムズがカバーしてヒット。
1966年 Mercy,Mercy,Mercy 詞Larry Williams、Johnny Watson 曲Joe Zawinul 演奏Cannonball Adderley Quintet
1967年 Mercy,Mercy,Mercy 歌・演奏 The Buckinghams
ニコーフランシスはポップスのお手本だった(H20.07.12)
戦後最大のベビーブームと言われ、その後、団塊の世代と呼ばれた私達。その私達が、最もアメリカ文化に影響を受けたのは、音楽。それも現在では、オールディーズと呼ばれるようになったアメリカン・ポップスではないでしょうか。
そして、当時のアメリカン・ポップスの主役は、ポール・アンカ、ニールセダカ、コニーフランシスなどでした。
なかでも、コニーフランシスは、今考えても、特別に実力がありました。歌唱力、声量など、圧倒的なパワーの持ち主です。
私達の世代であれば、コニーフランシスのヒット曲は、何曲でも、すぐに思い出せると思いますが、私が一番好きな曲は何か、と改めて考えてみると、Follow the Boys(渚のデート)でしょうか。
コニーフランシスのデビュー当時は、声量がものすごく、はじけるような、力強さが溢れていました。それから4,5年後の、このFollow the Boysは、彼女の絶頂期にさしかかった、まさに、珠玉の一曲といえるものです
一般的には、先に発表した、Where the Boys Are(ボーイハント)のほうが有名で、かつ評価が高いかもしれませんが。
私は、どちらかと言うと、Follow the Boysが好きです。そして完成度も高いと思います。
1960年 Where the Boys Are(ボーイハント) Howard Greenfield詞、Neil Sedaka曲、Connie Francis歌
1963年 Follow the Boys(渚のデート) Ted Murray詞、 Benny Davis曲、Connie Francis歌
オーキャロルのアンサーソング、オー・ニール(H19.08.20)
先日、ニールセダカのオーキャロルのアンサーソング、オー・ニールという歌を聴きました。
ニールセダカ(Neil Sedaka)が、昔歌って大ヒットしたオーキャロル(Oh! Carol)は、キャロルキング(Carole King)をイメージして作ったという話しは、少し前に聞いていました。
しかし、ニールセダカは、私が小学生高学年の頃、恋の片道切符(One Way Ticket)が大ヒットして、知ったアメリカンポップスの大スターであり、
一方、キャロルキングは私が社会人になりたての頃、It's too lateが世界的にヒットしたシンガーソングライターであったため、
私の頭の中では、10年以上活躍した時代が違っていて、あまりピンときませんでした。
そして、今回、アンサーソングであるという、このオー・ニール(Oh! Neil)という曲を聴きましたが、これが相当ダメな曲でした。
キャロルキングが歌っているとのことでしたが、声はよくないし、歌も下手。さらに、あまりまじめに歌っているとも思えない印象です。
アンサーソングは、とかくパロディー的なものであることを考慮しても、あまり感じのよい曲とは聞えませんでした。
ニールセダカが活躍した時代には、女性ボーカルは、特に歌唱力のあるコニーフランシスやブレンダリーなどが大活躍した時期に近く、これに比べるとキャロルキングの歌は素人のようでした。(この約10年後には、女性シンガーソングライターの第一人者となる)
1959年 One Way Ticket(恋の片道切符) Hank Hunter詞、Jack Keller曲 Neil Sedaka歌
1959年 Oh! Carol(オーキャロル) Howard Greenfield詞、Neil Sedaka曲 Neil Sedaka歌
1960年 Oh! Neil(オー・ニール) Howard Greenfield、Gerry Goffin共作、Neil Sedaka曲 Carole King歌
1971年 It's too late Toni Stern詞、Carole King曲、Carole King歌 LP「Tapestly(綴れおり)」に収録
とても懐かしい曲Walking Back To Happiness(H19.05.05)
少し、前になりますが、ヘレン・シャピロ(Helen Shapiro)が歌うWalking Back To Happinessがラジオから聞こえてきました。
有名な、子供じゃないの(Don't Treat Me Like a Child)や悲しき片想い(You Don't Know)は、すぐに思い出せますが、この曲はすっかり忘れていたので、かえって、とても懐かしく聴きました。
子供じゃないのと悲しき片想いの2曲は、日本語の訳詞もついて、弘田三枝子さんが(今で言う)カバーして歌っており、さらに大ヒットしたので、とても有名なポップスとなりました。
しかし、Walking Back To Happiness(夢見る恋)はどういう訳か英語のままであったため、日本では、大ヒットとまではいきませんでした。
当時、私は中学1年生頃だったと思いますが、♪Walking Back to Happiness,woopah oh yeah yeah♪というフレーズがとても特徴的であり、何回も、小気味よく、また力強く、繰りかえされるフレーズでありました。
ただし、私達には、英語でどう言っているのかは、よく解らず、♪何とかかんとかハッピネース ウッツバーオ・イェーイェ♪と下校時に近所の子供たちと一緒に歌って帰っていたものでした。
私にとって、このヘレン・シャピロ(Helen Shapiro)とコニーフランシス(Connie Francis)はアメリカンポップスが好きになった原点ともいうべき女性シンガーです。(実際は、ヘレン・シャピロは英国人で英国でデビューしましたが、すぐにアメリカというか、世界進出しました)
1961年 Walking Back To Happiness Helen Shapiro(当時14才)歌 John Schroeder曲、Mike Hawker詞
映画「スーパーマン リターンズ」を観て思い出しました(H18.09.01)
先日、映画「スーパーマン リターンズ」を観ました。そこにでてきた印象的なシーンに、子供と男のピアノの連弾の場面がありました。
そして、そこで弾かれた曲を聴いて、急に、私の大昔の記憶が蘇りました。
正確には思い出せないのですが、中学生の頃、多分中学1年生の時であったと思いますが、1学年くらい上級生の男子生徒がいて、
突然、「この曲知ってる?」といって、ピアノで、シンプルな曲を弾きはじめました。
はじめは人差し指1本でピアノに単純なメロディーをゆっくり弾き始め、少しして私がそのメロディーを覚えて、弾き始めると、それにあわせて、その上級生がピアノで伴奏のコードを弾き始めるという、映画「スーパーマン リターンズ」のシーンと全く同じことがその時に起こりました。
(ただし、このことは、そんなに珍しい出来事ではなく、当時、少しピアノをやっていた者にとっては、流行りの行為だったのだと思いますが)
ほかのことは、あまり覚えておらず、すぐ目の前にピアノがあったことを考えると、多分、音楽教室に、放課後、私がいて、そこにその上級生がやって来たのだと思います。
そして、その上級生の男子生徒については、おぼろげながら思い出したことは、
名前も知りませんし、正確には、何学年上なのかも知りません。また、何故、私にだけ、話しかけたのかも、よくわかりませんでした。
しかし、当時、その男子生徒の同級生や下級生から、「シスターボーイ」と、よくからかわれていましたので、今でいうイジメにあっていたと思われます。
たしかに、色白で、背が高い、細身の男子生徒であったと思います。
それから、どのくらい経ったか(数か月後か、半年後くらいか)、その男子生徒のことは見かけなくなりました。多分、転校していったのだと思います。
この曲は、私に限らず、こうしたエピソードが多い曲であり、
(映画を観ている最中では、私でさえ、何故こんなに大切なシーンで、こんなにベタな曲を使うのか、と思いましたから)
確かに、洋楽の基本コードの基礎中の基礎でありますから、この曲のことは、けっこうみんな知っている、聞き覚えのある曲ではありますが、曲名までは、全く知りませんでした。
今回、調べてやっと分りましたが、曲名はHeart and Soulということでした。
1939年 Heart and Soul Hoagy Carmichael作曲、Frank Loesser作詞
ものすごく懐かしい名曲、My Special Angel(H16.12.09)
曲名も歌手も定かではないが、記憶に残る名曲というものがありますが
本日、ラジオからそんな一曲が流れました。
My Special Angelは、いつ聴き覚えたのか、私もはっきり思い出せません。
スローなロッカバラードですが、今や、ポップスのスタンダードな曲です。
調べてみたところ、なんと1957年に発表されておりました。
エルビス・プレスリーがデビューした翌年のことなので、
私があまり、記憶が定かではないのは当たり前かもしれません。
しかし、心に残る名曲であることは確かで、その後も、再ヒットしていたため、
本当に稀に、私が、耳にしていたことになります。
私の小学生高学年の記憶でもあり、高校生・大学生時代の思い出の曲でもあることになります。
1957年 My Special Angel Jimmy Duncan作詞・作曲 Bobby Helms歌
1968年 My Special Angel The Vogues歌
そよ風と私(The Breeze and I)(H16.05.11)
小学生から中学生になりたてのころ、本日のような、蒸し暑い夜に、どこからともなく聞こえてきた
洋楽が、そよ風と私(The Breeze and I)でした。その時のことを、非常に、印象的に憶えています。
この曲に、理由もなく、聞き惚れ、惹きこまれました。
日本の曲想にはありえない、大きな曲です。
洋楽のストリングスで聞いたのですが、何て素晴らしい曲だろうと、感心したものです。
(残念ながら、どのオーケストラの演奏であったかは、確認できません)
このThe Breeze and Iはキューバの作曲家,Ernest Lecuona が
1928 年に作曲した《アンダルシア》というピアノ組曲の第2番だそうで、
後に Al Stillman が英語の歌詞をつけたとのことです。
中学校の卒業謝恩会(H15.12.30)
中学校の卒業式の後、謝恩会をおこなう場合が多いと思いますが
私達の場合は、恩師と卒業生および父兄達の前で、クラス毎にいろいろな出し物を演じました。
他のクラスの出し物で、私のよく知らない1人の男子生徒が、やはり全く知らない2人の女性徒と
スティーブローレンスの悲しき足音(Foot steps)を英語で歌いました。
男性ボーカルにリズミカルな2人の女性バックコーラスをつけた演出は、天晴れでした。
それは、私が当時最も好きだった、アメリカン・ポップスの分野で、曲も大好きな1曲でありました。
本来であれば、その企画であれば、当然、私がリードボーカルを歌うべきだと、1人勝手に、思い込み、
そのため、「出し抜かれたな」と思った次第です。
(しかし、実際には、中学校生活で、そんなに、アメリカン・ポップスを好きだとは、
皆に、知られていたわけでもなく、私が、心の中で、思っていただけの話ですが)
さらに、もし、私がその時、Foot stepsを歌うチャンスがあったとしても、
女性2人のバックコーラスを付けることを、思いついたかどうか
後で友人に聞いたところ、その男子生徒は相当な秀才とのことでした。
(確かに、東京都立高校で1番有名な高校へ進学しました)
バックを付けていた女性徒の1人は、年の割には色っぽい感じで有名なのだ、とのことでした。
多分、その男子生徒には、兄または姉がいて、兄姉の入れ知恵もあったのだろうとは思いますが、
やはり、私にとっては、「やられたな」といった感じを強くもった、卒業式のあとの、ひとときでした。
1959年発表 Footsteps(悲しき足音) Steve Lawrence Barry Mann共作
歌Steve Lawrence 、
歌 飯田久彦、ダニー飯田とパラダイスキング
コパカバーナ(Copacabana)の原曲は?(H15.09.19)
私は、ある曲が流行り出すと、この曲はいつか、どこかで、聞いたことがある、と確信することがあります。
ある部分が似たフレーズといったものではなく、ほとんど全部、全く同じ曲であるといった場合が多い。
または、全てではないにしろ、主なメロディーまたはサビのメロディーが同じなどと感じることがあります。
この現象?は滅多にありませんし、深く追求する熱意もありませんでしたので、
真偽の確認はできず、ほとんどそのままになっていることが多いのですが。
こうした例は、特に有名な曲に多く、
バリーマニロウが歌ったコパカバーナやコニーフランシスのボーイハントなどがそうです。
まづ、考えられることは、本当に、昔流行った曲のリメイクである場合。
または、似た曲を後から発表してその曲のほうがよく売れてしまった場合などでしょうか。
しかし、私は、そう簡単に、曲を聴き間違えたりはしないと、多少のプライドをもっているつもり?ですので、
いつか聞き覚えのある曲が流行り出したときには、その都度、簡単には調べております。
そしてこれらの曲に関しては、全く判りません。
特に、コパカバーナについては、きっと、古い曲で、私が知らないだけだと思いますが、
原曲が見付けられておりません。
どなたか、ご存知でしたら、教えていただけないでしょうか?
ボーイハントについては、ニールセダカが作曲したことになっているので、私の勘違いなのでしょうか?
もっと大昔に聞いたようなメロディーだと思うのですが...
1961年 映画「ボーイハント」(Where The Boys Are)、歌、主演コニーフランシス(Connie Francis)
1978年 コパカバーナ(Copacabana)または(At The Copa)、歌バリーマニロウ(Barry Manilow)
月夜のボサノバって判ります?(H15.04.03)
中学校3年の頃、日本に初めてボサノバが紹介されました。(多分、本当に最初だと思います)
邦題月夜のボサノバという曲でFly me to the moonのことなんですが、
当時は日本人の歌手も歌ってました。
3拍子のためか、それほどノリのいい曲とは感じませんでした。
どうしてこのボサノバという音楽やリズムが世界的に流行だしたのか分かりませんでした。
その翌年には恋はボサノバというイーディ・ゴーメが歌った曲もでましたが、
(最初の印象がそれほどではなかったためか)
私はそれほど大した曲とは思いませんでした。
しかし、私が大学生になった頃には、ボサノバが洋楽界を席巻しており、アントニオカルロスジョビンや
セルジオメンデスの天下でした。
そして、イーディ・ゴーメがボサノバを歌ったレコードを聴くと、
恋はボサノバの時とは別人のように素晴らしく、ボサノバの名曲を歌っておりました。
One Note Samba Desafinado Moon Riverなどなど、私の好きな曲ばかりです。
今では、女性ジャズヴォーカルの一番好きな中の1人です。
1962年 Fly me to the moon 歌ジョー・ハーネル
日本では、月夜にボサノバ(私の記憶では月夜のボサノバ)歌中尾ミエ、月へ飛ぶ想いなど
1963年 Blame it on the bossa nova(恋はボサノバ) Eydie Gorme(イーディ・ゴーメ)
燃ゆる想い(H15.02.24)
やはり、高校1年生の頃、当時流行っていたポップスを演奏したり、歌ったりしていた私達は
大流行の曲よりは、マイナーヒットした、少し詳しい者でなければ、知らない曲を見付けてきては、
歌ったりすることを、互いに、自慢していました。
以前にも触れましたが、エルビス・プレスリーを歌わせると、抜群に上手い、先輩が
よく歌っていた曲を思い出しました。
燃ゆる想いという日本語の題名がついた、少しマイナー調の入った、ロックバラード。
この曲を歌っていると、皆聞き惚れて、彼の周りに集まったものでした。
1960年 発表 I'll go on loving you(燃ゆる想い) 歌Jamie Coe(ジャミークー)
ライブは怖い!(H14.08.28)
高校2年生の時、文化祭の前夜祭で、急遽、ムードを盛り上げるために
バンド演奏を依頼されたことがありました。(演奏の約30分くらい前に話しがきました)
全校生徒と、ほとんどの学校職員が、校庭に集まり、
(通常は、校長や教頭先生などが、朝礼をする場所です)
我々の音楽を期待していました。
しかし、本来、演奏する場所ではなく、音響も、スピーカーも音楽を流すには適当ではない状況でした。
さらに、現場の下調べもないまま、観衆の前で、手早くセットアップをしなければならなかったものですから
案の定、ギターアンプ用と、ベースアンプ用のコードがうまく音が出ませんでした。
少しして、1本だけは、音を出せる状態になりましたが、どうしても1本足りません。
全校生徒と多数の職員が待っているのですから、もう演奏を開始しなければなりません。
私は仕方なく、ベースの音の方をアンプに通さず演奏することを決めざるを得ませんでした。
(一般的には、ベースを残して、ギターを消すほうが良いと思いますが、
当時の私達のバンドレベルでは、
ポップスの歌の伴奏には、音程をリードするギターのほうが必要だったのです)
この苦渋の選択を極めて短時間に決めて、各メンバーに説明するのに、充分な時間もありませんでした。
ですから、私から、アンプを通さないで演奏するよういわれたメンバーは、大変傷つき、
演奏が終わってから、私が謝っても、そのことによる心の傷は、全く消えるものではありませんでした。
(あの状況では、そうしなければならなかったと、頭ではわかっても、当人の、心の傷は消えません)
ステージの出来具合は、さんざんなものでした。(少なくとも私は、そう感じました)
3曲ほど演奏したと思いますが、音量のバランスも悪く、
演奏が終わってから、先輩からも、伴奏の音のボリームが、よくなかったと、しかられました。
今、思い出しても、冷や汗がながれます。
大学1年生のとき聴いたConstant rain(H14.05.11)
ポピュラーな曲には、いつ聴いても、感動できる名曲もありますが、
聴く人の、状況や気分によって、効果が倍増する、ちょとした小曲もあります。
千葉県の御宿海岸で、海の家のアルバイトを、少ししたことがありました。
大学生の1年生の夏でしたが、学生のアルバイトが3人雇われていました。
(お互い全く知らない者同士でした)
その店で、かけるレコードは、私達が決められましたので、
その頃、流行っていたセルジオメンデスとブラジル66(Sergio Mendes & Brasil'66)のLPを中心に
ボサノバの曲を多く流していました。
一日中雨が降っている日もあり、そんなとき、聴いた
♪シャビィ・シューバアー♪で始まる、コンスタントレイン(Constant rain)は、まさに、
その日の、私の状況と合致して、とても気に入って聴いたものでした。
余談ですが、
オーナーは、売上が思ったほどでないため、アルバイトの1人にクビを言い渡しました。
3人のうち、私ともう1人は、少しギターが弾けるため、時々店でギターの弾き語りをしたこともありましたので
ギターの弾けない1人がクビを言われたのでした。
当時は、若くて、とても正義感の強かった私は、それなら、私も辞めるといって、
2人で東京へ戻って来てしまいました。(本当はひと夏の予定でしたが、一週間で帰ってきました)
クラリネットを教えてくれた中学生の時の先輩(H14.05.03)
私は中学生のとき、ブラスバンド部で、クラリネットを担当していました。
顧問の先生が力をいれていたため、私達の学校だけでなく、都内の中学校の運動会などによばれて、
演奏行進をしていました。
曲は、スーザ作曲の星条旗よ永遠なれなど代表的な行進曲ばかり、
他には、ワシントンポスト、錨を上げて、海兵隊など。
ブラスバンドは管楽器や打楽器など多くの種類の楽器がありましたが、
クラリネットにも第1クラリネット、第2クラリネット、曲によっては第3クラリネットまでの譜面があります。
第1クラリネットは難しく、かつ、やりがいのあるパートで、16分音符だらけの、ものすごく早い演奏が要求されます。
第2クラリネットは4分音符や8分音符が中心のパートです。メロディーを支えるベース的な役割でしょうか。
全く分からないクラリネットを1から教えてくれたのは、1年先輩でした。
とにかく、つきっきりで、昼休みと放課後に、練習するのですが、ていねいすぎるくらい、
よく教えてもらいました。
おかげで1年生のときから第2クラリネット担当で運動会などの行進には、何度もよばれて行きました。
2年生になると第1クラリネット担当で、馴れると第1クラリネットのほうが、断然面白いことも分かりました。
1年先輩のクラリネット担当はもう1人いて、その先輩も、ほんのたまに、私に練習をつけてくれました。
ただ、この人は、教え方がまったく逆で、ここは、こう吹くのだと言って、1回自分で吹いて、
あとは、私が吹くのを、だまってみているだけでした。
すこし後で気がついたのですが、その、そっけない教え方の先輩の方が、クラリネットの音自体は良く、
第1クラリネットは、その人が優先して担当していたようでした。
どちらかといえば、要領がよく、テキパキとしていて、顧問の先生にも評価されていたかも知れません。
(クラリネットは楽器自体で、音のよさは、かなり変わるので、本当は、要領よく、
学校にあったクラリネットで、よい音がする方を、先に確保してしまっただけかも知れません)
一方、私に熱心に教えてくれた先輩のほうは、努力型だったような気がします。
ですから、本当のところ、どちらが上手かったかは、判断できません。
ただ2人とも勉強はできたようで、
テキパキしたほうの先輩は、東京都立高校では、当時トップだった有名校へ進学しましたし、
私に熱心に教えてくれた先輩も、当時の学校群では2番目の高校へ進学しました。
(話が音楽から、かなり外れてしまい、申し訳ありません)
特に、私に熱心に教えてくれた先輩には、感謝しています。
ただし、当時は読めた譜面も、今はほとんど読めなくなってしまいました。
ジャニーギターをうまく歌える女子高生(H14.01.23)
ペギーリー(Peggy Lee)が1月21日に亡くなったとのことです。
もちろん代表作は、ジャニーギター(Johnny Guitar)。
今日、ラジオで何回かこの曲が流れました。
昔、思っていたよりは、若い声で、素朴なギターの音に、よく合っていると思いました。
1954年 米映画「大砂塵」の主題歌。作詞Peggy Lee、作曲Victor Young。
私の高校生時代、このジャニーギターを歌うと、ものすごく上手な女子高生がいたのを、思い出します。
低い、きれいな声が、よくのびて、文化祭などでは、必ずこの曲を歌ってました。
ただ、妙なことに、この曲以外は、それほどではなくて、結局、いつもジャニーギターでした。
当時のバンドは、コニーフランシス、ブレンダリー、ジュリーロンドンなどを中心とした
どちらかといえば、ポップスが主体のバンドでしたから、
本格的なジャズで、低音の女性ボーカルを、上手くひきだせるほどの技量は、バンド自体に無く、
原因はそのへんにあったかもしれません。
大学生の時、最も流行っていたのは、イパネマの娘(H14.01.15)
私が大学生になった時を、思い返すと、セルジオメンデスとブラジル66が流行り出した時期と、
以前書きましたが、
実際に、学生バンドの連中が、練習や演奏した曲といえば、イパネマの娘が圧倒的に多かったと
おもいます。
ですから、私も、この曲については、それなりの知識はあるつもりでした。
昨年末だったとおもいますが、NHKBSテレビで、「ボサノバの誕生、イパネマの娘」というドキュメンタリーの
ような、番組をやっており、途中からですが、惹きこまれて、観つづけてしまいました。
私が知らなかった、いくつかのエピソードが、大変興味深く、思わず、テレビを観続けてしまったわけです。
1.この曲は、曲が先にできあがっており、いい歌詞が、見つからず、
ジョアンジルベルトとアントニオカルロスジョビンが毎日のように、コパカバーナで相談していたとか
2.そこの海岸を通りかかった美人にみとれて、歌詞が、でき上がったとのことでした。
3.ジョアンジルベルトは、ボサノバギターの名手で、ポルトガル語にこだわり、原語でしか歌わなかったとか
4.英語が上手だった、アントニオカルロスジョビンが、アメリカでの録音の際、通訳をしていたとか。
5.レコード会社のプロデューサーは、英語でなければ売れないと主張したとか
ジョアンジルベルトの奥さん(アストラットジルベルト)が、急遽ボーカルを担当したことは、以前から知っていましたが
(かなり有名な話なので)
6.実際は、歌手志望で、どうしても歌わせて欲しいと言ったので、ジョアンジルベルトが、
アントニオに頼んだとか
(私は、彼女が素人っぽく歌ったので、1回だけで、あまり凝らずに、レコーディングを終えたとばかり思ってましたが)
7.実際は、英語のなまりがはげしくて、アストラットジルベルトの歌だけを、何回も取り直したとか
8.スタンゲッツの演奏をジョアンジルベルトが気に入らず、あんな大きな音は、ボサノバではないと
文句をいったとか
どれをとってみても、非常に興味深い、話でした。
高校生の時、早稲田大学ハイソサイティ・オーケストラを知る(H13.08.14)
私が高校1年生の秋に、大学の学園祭に行ったことがありました。
その頃には、バンドをやっていたので、大学生のバンドはどのくらいの実力なのかを確かめたくて、
出かけていきました。
早稲田大学の学園祭の期間中に行われたコンサートに行ったのですが、
その時、出演していたのが、早稲田大学ハイソサイティ・オーケストラでした。
インザムード、ムーンライトセレナーデなどを次々に演奏しました。
そして、このビッグバンドの、うまいことに感激するというよりは、
これらの、曲自体の素晴らしさを、強烈に感じました。
(もちろん、演奏がよくなければ、記憶に残りませんので、このビッグバンドは凄い実力であったと思います)
それまでも、ビッグバンドのよさは、映画「五つの銅貨」や、「ベニーグッドマン物語」で
知ってはいましたが、グレンミラーの曲の素晴らしさが、一番、印象に残りました。
その日のコンサートでは、他に、デュークエリントンや、カウントベイシーの曲も演奏されましたが、
私には、グレンミラーの曲が強く印象に残りました。
(この日に聴いた曲は、全て、うっすらとは、知っていて、全くはじめて聴く曲はありませんでしたが)
それ以来、ビッグバンドのよさを知ったことになります。
ところで、クレストフォーシンガーズのライブでは、ときどき、ムーンライトセレナーデを
コーラスで聴きますが、ビッグバンドに負けないほどの、素晴らしい迫力のある、コーラスと演奏です。
ペリーコモショーは毎週観ていました(H13.05.13)
あのペリーコモが亡くなったとのことです。
私が小学生から中学生になりたての頃、テレビでペリーコモショーを毎週観ていました。
細かくは覚えていませんが、ペリーコモがゲストとデュエットする時、誰とでも
(男性でも、女性でも、そして歌手だけでなく、当時の人気コメディアンとも)、
非常に仲良く、そしてなによりもきれいにハモるのに感心していました。
やはり、アメリカはレベルが段違いに高いことを、思い知らされたのを記憶しています。
It's immposible、And I love you so、South of the border、Begin the beguine、
Till the end of time、Some enchanted evening、Bali ha'i、By the Way
など歌っていたと、記憶に残っています。この頃の記憶も、
私がスタンダードジャズを好きになった、キッカケの1つかもしれません。
高校2年生の頃ビートルズがやってきた!(H13.02.11)
ビートルズの最初の映画「A hard day's night」の2001年春休みロードショーが決まったそうです。
1964年当時、「ビートルズがやって来る。ヤァ!ヤァ!ヤァ!」というキャッチフレーズで、
この映画の宣伝というか、ビートルズの紹介が、大ブームになり、社会的現象として、
ビートルズ旋風が日本にも上陸しました。
アメリカンポップスが好きだった私は、高校3年生の頃には、ビートルズも好きになりましたが、
決定的にBeatlesのファンになったのは、この映画を観てからでした。
(1964年8月の初公開当時は、あまりにも混んでいて、映画を観にゆく気になれない程の、大人気でした。
私は大学生になってから、この映画の再上映を、何回となく、観ました)
プロモーション映画としての役割もあったのでしょうが、なによりも、Beatlesの生活やステージ活動が
ストレートに描かれており、感動したのを覚えています。
中でも、一番好きだったのは、やはり彼らのライブ・ステージの場面です。
好きな曲は、数えきれませんが、I should have known betterやShe loves youは
映画のなかで光っていました。
小学生4年生の頃を思い出しました(H13.01.20)
今日、テレビで、昔、ウエスタンカーニバルに出ていたメンバーが集まった、2000年末コンサートの
様子を見ました。
そして、40年前のウエスタンカーニバルのことを思い出しました。
よく覚えていない部分もありますが、
当時、人気があったのは、山下敬二郎、ミッキーカーチス、平尾昌晃の3人です。
クレージーキャッツも出ていました。
そして、時代の記憶としては、サントリーの角瓶が、最高級のウイスキーだった、頃です。
森山加代子、坂本九、弘田三枝子なども、あとから加わったと、記憶しています。
当時、歌がうまかったのは、森山加代子と弘田三枝子です。
人気は、圧倒的に山下敬二郎でした。
今日、そのほとんどのメンバーが歌っているのを、見て、懐かしいのと同時に、
歌のうまいへたもあまり変わらないのだな、と再認識しました。
ただし、山下敬二郎のシェイクラトルアンドロールだけは、
最近、聞いたなかでは(といってもこの30年間、彼が歌ったなかでは)
一番よかったと思いました。(いつになく、気合をいれて、歌っていました)
そのほか、今日、出演していたのは、田辺靖雄、九重佑三子、田代みどり、飯田久彦、守屋浩、
佐野修、鈴木やすしさんなどでした。
高校時代(H12.08.17)
高校1年(といっても入学したての1-2ヶ月は、中学生の延長で、まだまだ子供だった頃)、
昼休みに校内放送から聞こえてきた、君は我が運命(you are my destiny)
は小学生・中学生時代聞きなれたポールアンカではなく、一体誰が歌っているのか、とても気になり、
聞き耳をたてました。
後で、判ったところによると、高校の軽音楽同好会のメンバーが勧誘を兼ねて、放送していたのです。
まだ子供だった、私には、驚くほど大人っぽい、そして、とても上手なボーカルに感激し、
さすがに、高校はレベルが高いと、思った記憶があります。
小・中学生時代、毎週アメリカンポップス(ポールアンカ、ニールセダカ、コニーフランシスが代表的)
を聞いていた私は、同じクラスの数人を誘って、その軽音楽同好会へ入ることにしました。
これが、小・中学生時代、どちらかといえば、スポーツ少年(野球少年)だった、わたしが、音楽を実際に
演奏する側に廻った、きっかけでした。
その同好会には、あの校内放送で聞いた素晴らしく上手なボーカルの先輩(当時3年生)が居ました。
彼は特にエルビス・プレスリーが上手く、他を圧倒していました。ギターはその先輩から教えてもらいました。
さらに、女性ボーカルでハスキーボイスの1年先輩も特に上手でした。当時ブレンダリー、コニーフランシス
ジュリーロンドンなどを歌っていました。
高校の文化祭になると、その特別上手な男性ボーカルと女性ボーカル2人がデュエットして
ポールとポーラのヘイ・ポーラを歌ったりすると、全校内中で盛り上がったものです。
その同好会でよく練習したり、演奏していた曲は
ハワイアンでは、小さな竹の橋の下で、南国の夜、月の夜は、珊瑚礁の彼方など
そのほか、霧のロンドンブリッジ、Too young、Diana、the Diaryなどなど、
当時の記憶では、エルビスの曲だけは、ほとんど上手く歌えなかった記憶があります。
本当の理由は、分りませんでしたが、やはりエルビス自身の歌唱力を、到底まねできなかったのと、
私が直接には、全盛期のエルビス・プレスリーを知らなかったからかもしれません。
私はどんな曲が好きだったのか?大学生時代(H12.06.25)
先日、クレストフォーシンガーズのリーダー内田典宏さんに、どんな曲がすきなのですか?
と尋ねられ、すぐには、答えられられなかったので、すこしづつここに、書き出してみようとおもっています。
以前にも書きましたが、本当は、無意識に大昔聴いたことのある、曲名もほとんど思い出せないような
スタンダード・ジャズをクレストフォーシンガーズがコーラスしている曲が好きなのですが、
あえて、意識的・直接的に私が聴いた曲を思い出しながら挙げてみます。
先日は、小学生時代のことを書きましたので、今回は大学生時代を思い出してみます。
私が大学生になりたての頃は、なんといっても、セルジオメンデスとブラジル66がはやりだした時期です。
私も、いままで聴いたことのない、この曲想には、かなりの衝撃をうけました。一体どういうものなのか、
世界は広いなと思ったものです。そしてセルジオメンデスのファンになりました。
衝撃をうけた曲は、マシュケナダ(Mais que nada)です。そしてそのほかのヒット曲の数々。
コンスタントレイン、フォーミー、ザ・ジョーカー、ディサフィナード、ワンノートサンバなど
その後、セルジオメンデスとバートバカラックが、今でいうコラボレートされていったと記憶しています。
バートバカラックも洗練された曲といった感じで、好きでした。
Close to you、I'll never fall in love again、Raindrops keep fall'in on my head、Look of love、
Walk on byなど
しかし、私には少しあまのじゃくなところがあるようで、あまりに綺麗に仕上がる曲は、
返って魅力が半減するようで、彼の後期はあまり聴かなくなりました。
小学生5-6年生の頃(H12.06.16)
よく考えてみると、私がなぜスタンダードジャズが好きになったか、明確な理由がある訳ではありません。
私がはじめて、音楽が好きになったのは、小学生5-6年生の頃、
アメリカのポップスのヒットチャートを毎週のように紹介していたラジオ番組を聴いて、
だんだん音楽が好きになっていったのだとおもいます。
その頃、はやっていたのは、コニーフランシス、ポールアンカ、ニールセダカでした。
私も、直接・意識的に聴いたこれらの曲は、まねして歌っていましたし、
現在でも、上手くはありませんが、歌えます。
スタンダードジャズは無意識にどこかで聴いていたものが、私のなかに残っていて、
それが今、クレストフォーシンガーズのようなすばらしいコーラスを聴くと、
懐かしさとともに、よみがえってくるのだとおもいます。
燃ゆる瞳(H21.09.23)
♪いつかどこかで会った、そんな気がする、燃える瞳をした、あのかわいい娘~♪で始まる燃ゆる瞳という曲。
私の高校1年生の時、私の高校では、かなりマニアックに流行っておりましたので、私にとっては、とても懐かしい曲です。
原曲は、ボビー・ヴィーの燃ゆる瞳(The night has a thousand eyes)というアメリカン・ポップス。全米3位にまでなった曲。
少し調べたところ、スリーファンキーズが日本語版で、もゆる瞳という曲名でレコードを出しているとのことでした。
(当時の私の記憶には、スリーファンキーズがこの曲を歌っていたという記憶はありませんが)
日本語の訳詞をしたのは、私が調べた限りでは、確認できませんでしたが、おそらく、安井かずみさん(当時、みナみカズみというペンネーム)が訳詞したのではないかと思います。
後に、カーペンターズがこの曲をカバーしております。
1962年 The Night has a Thousand Eyes(燃ゆる瞳) 歌Bobby Vee 詞・曲Benjamin Weisman Dorothy Wayne Marilyn Garrett
1973年 The Night has a Thousand Eyes(燃ゆる瞳) 歌The Carpenters LP「Now & Then」に収録
Mercy,Mercy,Mercyという曲、知ってます?(H21.09.13)
私の大学生時代の知人で(数少ない、レコード会社に音楽ディレクターとして採用された人間)が、好きだと言った曲を思い出しました。
その曲はマーシー・マーシー・マーシー(Mercy,Mercy,Mercy)。ザ・バッキンガムズという米国のロックバンドが歌った。
(私としては、ロックバンドはビートルズのほうがよほど面白いし、曲もいいと感じていましたが)
この曲は、有名なジャズのキャノンボール・アダレーの代表作。(ジャズファンならば、きっと演奏を聞いたことがあると思います)
キャノンボール・アダレーのキーボード奏者ジョー・ザビヌルの作曲。翌年、ザ・バッキンガムズがカバーしてヒット。
1966年 Mercy,Mercy,Mercy 詞Larry Williams、Johnny Watson 曲Joe Zawinul 演奏Cannonball Adderley Quintet
1967年 Mercy,Mercy,Mercy 歌・演奏 The Buckinghams
ニコーフランシスはポップスのお手本だった(H20.07.12)
戦後最大のベビーブームと言われ、その後、団塊の世代と呼ばれた私達。その私達が、最もアメリカ文化に影響を受けたのは、音楽。それも現在では、オールディーズと呼ばれるようになったアメリカン・ポップスではないでしょうか。
そして、当時のアメリカン・ポップスの主役は、ポール・アンカ、ニールセダカ、コニーフランシスなどでした。
なかでも、コニーフランシスは、今考えても、特別に実力がありました。歌唱力、声量など、圧倒的なパワーの持ち主です。
私達の世代であれば、コニーフランシスのヒット曲は、何曲でも、すぐに思い出せると思いますが、私が一番好きな曲は何か、と改めて考えてみると、Follow the Boys(渚のデート)でしょうか。
コニーフランシスのデビュー当時は、声量がものすごく、はじけるような、力強さが溢れていました。それから4,5年後の、このFollow the Boysは、彼女の絶頂期にさしかかった、まさに、珠玉の一曲といえるものです
一般的には、先に発表した、Where the Boys Are(ボーイハント)のほうが有名で、かつ評価が高いかもしれませんが。
私は、どちらかと言うと、Follow the Boysが好きです。そして完成度も高いと思います。
1960年 Where the Boys Are(ボーイハント) Howard Greenfield詞、Neil Sedaka曲、Connie Francis歌
1963年 Follow the Boys(渚のデート) Ted Murray詞、 Benny Davis曲、Connie Francis歌
オーキャロルのアンサーソング、オー・ニール(H19.08.20)
先日、ニールセダカのオーキャロルのアンサーソング、オー・ニールという歌を聴きました。
ニールセダカ(Neil Sedaka)が、昔歌って大ヒットしたオーキャロル(Oh! Carol)は、キャロルキング(Carole King)をイメージして作ったという話しは、少し前に聞いていました。
しかし、ニールセダカは、私が小学生高学年の頃、恋の片道切符(One Way Ticket)が大ヒットして、知ったアメリカンポップスの大スターであり、
一方、キャロルキングは私が社会人になりたての頃、It's too lateが世界的にヒットしたシンガーソングライターであったため、
私の頭の中では、10年以上活躍した時代が違っていて、あまりピンときませんでした。
そして、今回、アンサーソングであるという、このオー・ニール(Oh! Neil)という曲を聴きましたが、これが相当ダメな曲でした。
キャロルキングが歌っているとのことでしたが、声はよくないし、歌も下手。さらに、あまりまじめに歌っているとも思えない印象です。
アンサーソングは、とかくパロディー的なものであることを考慮しても、あまり感じのよい曲とは聞えませんでした。
ニールセダカが活躍した時代には、女性ボーカルは、特に歌唱力のあるコニーフランシスやブレンダリーなどが大活躍した時期に近く、これに比べるとキャロルキングの歌は素人のようでした。(この約10年後には、女性シンガーソングライターの第一人者となる)
1959年 One Way Ticket(恋の片道切符) Hank Hunter詞、Jack Keller曲 Neil Sedaka歌
1959年 Oh! Carol(オーキャロル) Howard Greenfield詞、Neil Sedaka曲 Neil Sedaka歌
1960年 Oh! Neil(オー・ニール) Howard Greenfield、Gerry Goffin共作、Neil Sedaka曲 Carole King歌
1971年 It's too late Toni Stern詞、Carole King曲、Carole King歌 LP「Tapestly(綴れおり)」に収録
とても懐かしい曲Walking Back To Happiness(H19.05.05)
少し、前になりますが、ヘレン・シャピロ(Helen Shapiro)が歌うWalking Back To Happinessがラジオから聞こえてきました。
有名な、子供じゃないの(Don't Treat Me Like a Child)や悲しき片想い(You Don't Know)は、すぐに思い出せますが、この曲はすっかり忘れていたので、かえって、とても懐かしく聴きました。
子供じゃないのと悲しき片想いの2曲は、日本語の訳詞もついて、弘田三枝子さんが(今で言う)カバーして歌っており、さらに大ヒットしたので、とても有名なポップスとなりました。
しかし、Walking Back To Happiness(夢見る恋)はどういう訳か英語のままであったため、日本では、大ヒットとまではいきませんでした。
当時、私は中学1年生頃だったと思いますが、♪Walking Back to Happiness,woopah oh yeah yeah♪というフレーズがとても特徴的であり、何回も、小気味よく、また力強く、繰りかえされるフレーズでありました。
ただし、私達には、英語でどう言っているのかは、よく解らず、♪何とかかんとかハッピネース ウッツバーオ・イェーイェ♪と下校時に近所の子供たちと一緒に歌って帰っていたものでした。
私にとって、このヘレン・シャピロ(Helen Shapiro)とコニーフランシス(Connie Francis)はアメリカンポップスが好きになった原点ともいうべき女性シンガーです。(実際は、ヘレン・シャピロは英国人で英国でデビューしましたが、すぐにアメリカというか、世界進出しました)
1961年 Walking Back To Happiness Helen Shapiro(当時14才)歌 John Schroeder曲、Mike Hawker詞
映画「スーパーマン リターンズ」を観て思い出しました(H18.09.01)
先日、映画「スーパーマン リターンズ」を観ました。そこにでてきた印象的なシーンに、子供と男のピアノの連弾の場面がありました。
そして、そこで弾かれた曲を聴いて、急に、私の大昔の記憶が蘇りました。
正確には思い出せないのですが、中学生の頃、多分中学1年生の時であったと思いますが、1学年くらい上級生の男子生徒がいて、
突然、「この曲知ってる?」といって、ピアノで、シンプルな曲を弾きはじめました。
はじめは人差し指1本でピアノに単純なメロディーをゆっくり弾き始め、少しして私がそのメロディーを覚えて、弾き始めると、それにあわせて、その上級生がピアノで伴奏のコードを弾き始めるという、映画「スーパーマン リターンズ」のシーンと全く同じことがその時に起こりました。
(ただし、このことは、そんなに珍しい出来事ではなく、当時、少しピアノをやっていた者にとっては、流行りの行為だったのだと思いますが)
ほかのことは、あまり覚えておらず、すぐ目の前にピアノがあったことを考えると、多分、音楽教室に、放課後、私がいて、そこにその上級生がやって来たのだと思います。
そして、その上級生の男子生徒については、おぼろげながら思い出したことは、
名前も知りませんし、正確には、何学年上なのかも知りません。また、何故、私にだけ、話しかけたのかも、よくわかりませんでした。
しかし、当時、その男子生徒の同級生や下級生から、「シスターボーイ」と、よくからかわれていましたので、今でいうイジメにあっていたと思われます。
たしかに、色白で、背が高い、細身の男子生徒であったと思います。
それから、どのくらい経ったか(数か月後か、半年後くらいか)、その男子生徒のことは見かけなくなりました。多分、転校していったのだと思います。
この曲は、私に限らず、こうしたエピソードが多い曲であり、
(映画を観ている最中では、私でさえ、何故こんなに大切なシーンで、こんなにベタな曲を使うのか、と思いましたから)
確かに、洋楽の基本コードの基礎中の基礎でありますから、この曲のことは、けっこうみんな知っている、聞き覚えのある曲ではありますが、曲名までは、全く知りませんでした。
今回、調べてやっと分りましたが、曲名はHeart and Soulということでした。
1939年 Heart and Soul Hoagy Carmichael作曲、Frank Loesser作詞
ものすごく懐かしい名曲、My Special Angel(H16.12.09)
曲名も歌手も定かではないが、記憶に残る名曲というものがありますが
本日、ラジオからそんな一曲が流れました。
My Special Angelは、いつ聴き覚えたのか、私もはっきり思い出せません。
スローなロッカバラードですが、今や、ポップスのスタンダードな曲です。
調べてみたところ、なんと1957年に発表されておりました。
エルビス・プレスリーがデビューした翌年のことなので、
私があまり、記憶が定かではないのは当たり前かもしれません。
しかし、心に残る名曲であることは確かで、その後も、再ヒットしていたため、
本当に稀に、私が、耳にしていたことになります。
私の小学生高学年の記憶でもあり、高校生・大学生時代の思い出の曲でもあることになります。
1957年 My Special Angel Jimmy Duncan作詞・作曲 Bobby Helms歌
1968年 My Special Angel The Vogues歌
そよ風と私(The Breeze and I)(H16.05.11)
小学生から中学生になりたてのころ、本日のような、蒸し暑い夜に、どこからともなく聞こえてきた
洋楽が、そよ風と私(The Breeze and I)でした。その時のことを、非常に、印象的に憶えています。
この曲に、理由もなく、聞き惚れ、惹きこまれました。
日本の曲想にはありえない、大きな曲です。
洋楽のストリングスで聞いたのですが、何て素晴らしい曲だろうと、感心したものです。
(残念ながら、どのオーケストラの演奏であったかは、確認できません)
このThe Breeze and Iはキューバの作曲家,Ernest Lecuona が
1928 年に作曲した《アンダルシア》というピアノ組曲の第2番だそうで、
後に Al Stillman が英語の歌詞をつけたとのことです。
中学校の卒業謝恩会(H15.12.30)
中学校の卒業式の後、謝恩会をおこなう場合が多いと思いますが
私達の場合は、恩師と卒業生および父兄達の前で、クラス毎にいろいろな出し物を演じました。
他のクラスの出し物で、私のよく知らない1人の男子生徒が、やはり全く知らない2人の女性徒と
スティーブローレンスの悲しき足音(Foot steps)を英語で歌いました。
男性ボーカルにリズミカルな2人の女性バックコーラスをつけた演出は、天晴れでした。
それは、私が当時最も好きだった、アメリカン・ポップスの分野で、曲も大好きな1曲でありました。
本来であれば、その企画であれば、当然、私がリードボーカルを歌うべきだと、1人勝手に、思い込み、
そのため、「出し抜かれたな」と思った次第です。
(しかし、実際には、中学校生活で、そんなに、アメリカン・ポップスを好きだとは、
皆に、知られていたわけでもなく、私が、心の中で、思っていただけの話ですが)
さらに、もし、私がその時、Foot stepsを歌うチャンスがあったとしても、
女性2人のバックコーラスを付けることを、思いついたかどうか
後で友人に聞いたところ、その男子生徒は相当な秀才とのことでした。
(確かに、東京都立高校で1番有名な高校へ進学しました)
バックを付けていた女性徒の1人は、年の割には色っぽい感じで有名なのだ、とのことでした。
多分、その男子生徒には、兄または姉がいて、兄姉の入れ知恵もあったのだろうとは思いますが、
やはり、私にとっては、「やられたな」といった感じを強くもった、卒業式のあとの、ひとときでした。
1959年発表 Footsteps(悲しき足音) Steve Lawrence Barry Mann共作
歌Steve Lawrence 、
歌 飯田久彦、ダニー飯田とパラダイスキング
コパカバーナ(Copacabana)の原曲は?(H15.09.19)
私は、ある曲が流行り出すと、この曲はいつか、どこかで、聞いたことがある、と確信することがあります。
ある部分が似たフレーズといったものではなく、ほとんど全部、全く同じ曲であるといった場合が多い。
または、全てではないにしろ、主なメロディーまたはサビのメロディーが同じなどと感じることがあります。
この現象?は滅多にありませんし、深く追求する熱意もありませんでしたので、
真偽の確認はできず、ほとんどそのままになっていることが多いのですが。
こうした例は、特に有名な曲に多く、
バリーマニロウが歌ったコパカバーナやコニーフランシスのボーイハントなどがそうです。
まづ、考えられることは、本当に、昔流行った曲のリメイクである場合。
または、似た曲を後から発表してその曲のほうがよく売れてしまった場合などでしょうか。
しかし、私は、そう簡単に、曲を聴き間違えたりはしないと、多少のプライドをもっているつもり?ですので、
いつか聞き覚えのある曲が流行り出したときには、その都度、簡単には調べております。
そしてこれらの曲に関しては、全く判りません。
特に、コパカバーナについては、きっと、古い曲で、私が知らないだけだと思いますが、
原曲が見付けられておりません。
どなたか、ご存知でしたら、教えていただけないでしょうか?
ボーイハントについては、ニールセダカが作曲したことになっているので、私の勘違いなのでしょうか?
もっと大昔に聞いたようなメロディーだと思うのですが...
1961年 映画「ボーイハント」(Where The Boys Are)、歌、主演コニーフランシス(Connie Francis)
1978年 コパカバーナ(Copacabana)または(At The Copa)、歌バリーマニロウ(Barry Manilow)
月夜のボサノバって判ります?(H15.04.03)
中学校3年の頃、日本に初めてボサノバが紹介されました。(多分、本当に最初だと思います)
邦題月夜のボサノバという曲でFly me to the moonのことなんですが、
当時は日本人の歌手も歌ってました。
3拍子のためか、それほどノリのいい曲とは感じませんでした。
どうしてこのボサノバという音楽やリズムが世界的に流行だしたのか分かりませんでした。
その翌年には恋はボサノバというイーディ・ゴーメが歌った曲もでましたが、
(最初の印象がそれほどではなかったためか)
私はそれほど大した曲とは思いませんでした。
しかし、私が大学生になった頃には、ボサノバが洋楽界を席巻しており、アントニオカルロスジョビンや
セルジオメンデスの天下でした。
そして、イーディ・ゴーメがボサノバを歌ったレコードを聴くと、
恋はボサノバの時とは別人のように素晴らしく、ボサノバの名曲を歌っておりました。
One Note Samba Desafinado Moon Riverなどなど、私の好きな曲ばかりです。
今では、女性ジャズヴォーカルの一番好きな中の1人です。
1962年 Fly me to the moon 歌ジョー・ハーネル
日本では、月夜にボサノバ(私の記憶では月夜のボサノバ)歌中尾ミエ、月へ飛ぶ想いなど
1963年 Blame it on the bossa nova(恋はボサノバ) Eydie Gorme(イーディ・ゴーメ)
燃ゆる想い(H15.02.24)
やはり、高校1年生の頃、当時流行っていたポップスを演奏したり、歌ったりしていた私達は
大流行の曲よりは、マイナーヒットした、少し詳しい者でなければ、知らない曲を見付けてきては、
歌ったりすることを、互いに、自慢していました。
以前にも触れましたが、エルビス・プレスリーを歌わせると、抜群に上手い、先輩が
よく歌っていた曲を思い出しました。
燃ゆる想いという日本語の題名がついた、少しマイナー調の入った、ロックバラード。
この曲を歌っていると、皆聞き惚れて、彼の周りに集まったものでした。
1960年 発表 I'll go on loving you(燃ゆる想い) 歌Jamie Coe(ジャミークー)
ライブは怖い!(H14.08.28)
高校2年生の時、文化祭の前夜祭で、急遽、ムードを盛り上げるために
バンド演奏を依頼されたことがありました。(演奏の約30分くらい前に話しがきました)
全校生徒と、ほとんどの学校職員が、校庭に集まり、
(通常は、校長や教頭先生などが、朝礼をする場所です)
我々の音楽を期待していました。
しかし、本来、演奏する場所ではなく、音響も、スピーカーも音楽を流すには適当ではない状況でした。
さらに、現場の下調べもないまま、観衆の前で、手早くセットアップをしなければならなかったものですから
案の定、ギターアンプ用と、ベースアンプ用のコードがうまく音が出ませんでした。
少しして、1本だけは、音を出せる状態になりましたが、どうしても1本足りません。
全校生徒と多数の職員が待っているのですから、もう演奏を開始しなければなりません。
私は仕方なく、ベースの音の方をアンプに通さず演奏することを決めざるを得ませんでした。
(一般的には、ベースを残して、ギターを消すほうが良いと思いますが、
当時の私達のバンドレベルでは、
ポップスの歌の伴奏には、音程をリードするギターのほうが必要だったのです)
この苦渋の選択を極めて短時間に決めて、各メンバーに説明するのに、充分な時間もありませんでした。
ですから、私から、アンプを通さないで演奏するよういわれたメンバーは、大変傷つき、
演奏が終わってから、私が謝っても、そのことによる心の傷は、全く消えるものではありませんでした。
(あの状況では、そうしなければならなかったと、頭ではわかっても、当人の、心の傷は消えません)
ステージの出来具合は、さんざんなものでした。(少なくとも私は、そう感じました)
3曲ほど演奏したと思いますが、音量のバランスも悪く、
演奏が終わってから、先輩からも、伴奏の音のボリームが、よくなかったと、しかられました。
今、思い出しても、冷や汗がながれます。
大学1年生のとき聴いたConstant rain(H14.05.11)
ポピュラーな曲には、いつ聴いても、感動できる名曲もありますが、
聴く人の、状況や気分によって、効果が倍増する、ちょとした小曲もあります。
千葉県の御宿海岸で、海の家のアルバイトを、少ししたことがありました。
大学生の1年生の夏でしたが、学生のアルバイトが3人雇われていました。
(お互い全く知らない者同士でした)
その店で、かけるレコードは、私達が決められましたので、
その頃、流行っていたセルジオメンデスとブラジル66(Sergio Mendes & Brasil'66)のLPを中心に
ボサノバの曲を多く流していました。
一日中雨が降っている日もあり、そんなとき、聴いた
♪シャビィ・シューバアー♪で始まる、コンスタントレイン(Constant rain)は、まさに、
その日の、私の状況と合致して、とても気に入って聴いたものでした。
余談ですが、
オーナーは、売上が思ったほどでないため、アルバイトの1人にクビを言い渡しました。
3人のうち、私ともう1人は、少しギターが弾けるため、時々店でギターの弾き語りをしたこともありましたので
ギターの弾けない1人がクビを言われたのでした。
当時は、若くて、とても正義感の強かった私は、それなら、私も辞めるといって、
2人で東京へ戻って来てしまいました。(本当はひと夏の予定でしたが、一週間で帰ってきました)
クラリネットを教えてくれた中学生の時の先輩(H14.05.03)
私は中学生のとき、ブラスバンド部で、クラリネットを担当していました。
顧問の先生が力をいれていたため、私達の学校だけでなく、都内の中学校の運動会などによばれて、
演奏行進をしていました。
曲は、スーザ作曲の星条旗よ永遠なれなど代表的な行進曲ばかり、
他には、ワシントンポスト、錨を上げて、海兵隊など。
ブラスバンドは管楽器や打楽器など多くの種類の楽器がありましたが、
クラリネットにも第1クラリネット、第2クラリネット、曲によっては第3クラリネットまでの譜面があります。
第1クラリネットは難しく、かつ、やりがいのあるパートで、16分音符だらけの、ものすごく早い演奏が要求されます。
第2クラリネットは4分音符や8分音符が中心のパートです。メロディーを支えるベース的な役割でしょうか。
全く分からないクラリネットを1から教えてくれたのは、1年先輩でした。
とにかく、つきっきりで、昼休みと放課後に、練習するのですが、ていねいすぎるくらい、
よく教えてもらいました。
おかげで1年生のときから第2クラリネット担当で運動会などの行進には、何度もよばれて行きました。
2年生になると第1クラリネット担当で、馴れると第1クラリネットのほうが、断然面白いことも分かりました。
1年先輩のクラリネット担当はもう1人いて、その先輩も、ほんのたまに、私に練習をつけてくれました。
ただ、この人は、教え方がまったく逆で、ここは、こう吹くのだと言って、1回自分で吹いて、
あとは、私が吹くのを、だまってみているだけでした。
すこし後で気がついたのですが、その、そっけない教え方の先輩の方が、クラリネットの音自体は良く、
第1クラリネットは、その人が優先して担当していたようでした。
どちらかといえば、要領がよく、テキパキとしていて、顧問の先生にも評価されていたかも知れません。
(クラリネットは楽器自体で、音のよさは、かなり変わるので、本当は、要領よく、
学校にあったクラリネットで、よい音がする方を、先に確保してしまっただけかも知れません)
一方、私に熱心に教えてくれた先輩のほうは、努力型だったような気がします。
ですから、本当のところ、どちらが上手かったかは、判断できません。
ただ2人とも勉強はできたようで、
テキパキしたほうの先輩は、東京都立高校では、当時トップだった有名校へ進学しましたし、
私に熱心に教えてくれた先輩も、当時の学校群では2番目の高校へ進学しました。
(話が音楽から、かなり外れてしまい、申し訳ありません)
特に、私に熱心に教えてくれた先輩には、感謝しています。
ただし、当時は読めた譜面も、今はほとんど読めなくなってしまいました。
ジャニーギターをうまく歌える女子高生(H14.01.23)
ペギーリー(Peggy Lee)が1月21日に亡くなったとのことです。
もちろん代表作は、ジャニーギター(Johnny Guitar)。
今日、ラジオで何回かこの曲が流れました。
昔、思っていたよりは、若い声で、素朴なギターの音に、よく合っていると思いました。
1954年 米映画「大砂塵」の主題歌。作詞Peggy Lee、作曲Victor Young。
私の高校生時代、このジャニーギターを歌うと、ものすごく上手な女子高生がいたのを、思い出します。
低い、きれいな声が、よくのびて、文化祭などでは、必ずこの曲を歌ってました。
ただ、妙なことに、この曲以外は、それほどではなくて、結局、いつもジャニーギターでした。
当時のバンドは、コニーフランシス、ブレンダリー、ジュリーロンドンなどを中心とした
どちらかといえば、ポップスが主体のバンドでしたから、
本格的なジャズで、低音の女性ボーカルを、上手くひきだせるほどの技量は、バンド自体に無く、
原因はそのへんにあったかもしれません。
大学生の時、最も流行っていたのは、イパネマの娘(H14.01.15)
私が大学生になった時を、思い返すと、セルジオメンデスとブラジル66が流行り出した時期と、
以前書きましたが、
実際に、学生バンドの連中が、練習や演奏した曲といえば、イパネマの娘が圧倒的に多かったと
おもいます。
ですから、私も、この曲については、それなりの知識はあるつもりでした。
昨年末だったとおもいますが、NHKBSテレビで、「ボサノバの誕生、イパネマの娘」というドキュメンタリーの
ような、番組をやっており、途中からですが、惹きこまれて、観つづけてしまいました。
私が知らなかった、いくつかのエピソードが、大変興味深く、思わず、テレビを観続けてしまったわけです。
1.この曲は、曲が先にできあがっており、いい歌詞が、見つからず、
ジョアンジルベルトとアントニオカルロスジョビンが毎日のように、コパカバーナで相談していたとか
2.そこの海岸を通りかかった美人にみとれて、歌詞が、でき上がったとのことでした。
3.ジョアンジルベルトは、ボサノバギターの名手で、ポルトガル語にこだわり、原語でしか歌わなかったとか
4.英語が上手だった、アントニオカルロスジョビンが、アメリカでの録音の際、通訳をしていたとか。
5.レコード会社のプロデューサーは、英語でなければ売れないと主張したとか
ジョアンジルベルトの奥さん(アストラットジルベルト)が、急遽ボーカルを担当したことは、以前から知っていましたが
(かなり有名な話なので)
6.実際は、歌手志望で、どうしても歌わせて欲しいと言ったので、ジョアンジルベルトが、
アントニオに頼んだとか
(私は、彼女が素人っぽく歌ったので、1回だけで、あまり凝らずに、レコーディングを終えたとばかり思ってましたが)
7.実際は、英語のなまりがはげしくて、アストラットジルベルトの歌だけを、何回も取り直したとか
8.スタンゲッツの演奏をジョアンジルベルトが気に入らず、あんな大きな音は、ボサノバではないと
文句をいったとか
どれをとってみても、非常に興味深い、話でした。
高校生の時、早稲田大学ハイソサイティ・オーケストラを知る(H13.08.14)
私が高校1年生の秋に、大学の学園祭に行ったことがありました。
その頃には、バンドをやっていたので、大学生のバンドはどのくらいの実力なのかを確かめたくて、
出かけていきました。
早稲田大学の学園祭の期間中に行われたコンサートに行ったのですが、
その時、出演していたのが、早稲田大学ハイソサイティ・オーケストラでした。
インザムード、ムーンライトセレナーデなどを次々に演奏しました。
そして、このビッグバンドの、うまいことに感激するというよりは、
これらの、曲自体の素晴らしさを、強烈に感じました。
(もちろん、演奏がよくなければ、記憶に残りませんので、このビッグバンドは凄い実力であったと思います)
それまでも、ビッグバンドのよさは、映画「五つの銅貨」や、「ベニーグッドマン物語」で
知ってはいましたが、グレンミラーの曲の素晴らしさが、一番、印象に残りました。
その日のコンサートでは、他に、デュークエリントンや、カウントベイシーの曲も演奏されましたが、
私には、グレンミラーの曲が強く印象に残りました。
(この日に聴いた曲は、全て、うっすらとは、知っていて、全くはじめて聴く曲はありませんでしたが)
それ以来、ビッグバンドのよさを知ったことになります。
ところで、クレストフォーシンガーズのライブでは、ときどき、ムーンライトセレナーデを
コーラスで聴きますが、ビッグバンドに負けないほどの、素晴らしい迫力のある、コーラスと演奏です。
ペリーコモショーは毎週観ていました(H13.05.13)
あのペリーコモが亡くなったとのことです。
私が小学生から中学生になりたての頃、テレビでペリーコモショーを毎週観ていました。
細かくは覚えていませんが、ペリーコモがゲストとデュエットする時、誰とでも
(男性でも、女性でも、そして歌手だけでなく、当時の人気コメディアンとも)、
非常に仲良く、そしてなによりもきれいにハモるのに感心していました。
やはり、アメリカはレベルが段違いに高いことを、思い知らされたのを記憶しています。
It's immposible、And I love you so、South of the border、Begin the beguine、
Till the end of time、Some enchanted evening、Bali ha'i、By the Way
など歌っていたと、記憶に残っています。この頃の記憶も、
私がスタンダードジャズを好きになった、キッカケの1つかもしれません。
高校2年生の頃ビートルズがやってきた!(H13.02.11)
ビートルズの最初の映画「A hard day's night」の2001年春休みロードショーが決まったそうです。
1964年当時、「ビートルズがやって来る。ヤァ!ヤァ!ヤァ!」というキャッチフレーズで、
この映画の宣伝というか、ビートルズの紹介が、大ブームになり、社会的現象として、
ビートルズ旋風が日本にも上陸しました。
アメリカンポップスが好きだった私は、高校3年生の頃には、ビートルズも好きになりましたが、
決定的にBeatlesのファンになったのは、この映画を観てからでした。
(1964年8月の初公開当時は、あまりにも混んでいて、映画を観にゆく気になれない程の、大人気でした。
私は大学生になってから、この映画の再上映を、何回となく、観ました)
プロモーション映画としての役割もあったのでしょうが、なによりも、Beatlesの生活やステージ活動が
ストレートに描かれており、感動したのを覚えています。
中でも、一番好きだったのは、やはり彼らのライブ・ステージの場面です。
好きな曲は、数えきれませんが、I should have known betterやShe loves youは
映画のなかで光っていました。
小学生4年生の頃を思い出しました(H13.01.20)
今日、テレビで、昔、ウエスタンカーニバルに出ていたメンバーが集まった、2000年末コンサートの
様子を見ました。
そして、40年前のウエスタンカーニバルのことを思い出しました。
よく覚えていない部分もありますが、
当時、人気があったのは、山下敬二郎、ミッキーカーチス、平尾昌晃の3人です。
クレージーキャッツも出ていました。
そして、時代の記憶としては、サントリーの角瓶が、最高級のウイスキーだった、頃です。
森山加代子、坂本九、弘田三枝子なども、あとから加わったと、記憶しています。
当時、歌がうまかったのは、森山加代子と弘田三枝子です。
人気は、圧倒的に山下敬二郎でした。
今日、そのほとんどのメンバーが歌っているのを、見て、懐かしいのと同時に、
歌のうまいへたもあまり変わらないのだな、と再認識しました。
ただし、山下敬二郎のシェイクラトルアンドロールだけは、
最近、聞いたなかでは(といってもこの30年間、彼が歌ったなかでは)
一番よかったと思いました。(いつになく、気合をいれて、歌っていました)
そのほか、今日、出演していたのは、田辺靖雄、九重佑三子、田代みどり、飯田久彦、守屋浩、
佐野修、鈴木やすしさんなどでした。
高校時代(H12.08.17)
高校1年(といっても入学したての1-2ヶ月は、中学生の延長で、まだまだ子供だった頃)、
昼休みに校内放送から聞こえてきた、君は我が運命(you are my destiny)
は小学生・中学生時代聞きなれたポールアンカではなく、一体誰が歌っているのか、とても気になり、
聞き耳をたてました。
後で、判ったところによると、高校の軽音楽同好会のメンバーが勧誘を兼ねて、放送していたのです。
まだ子供だった、私には、驚くほど大人っぽい、そして、とても上手なボーカルに感激し、
さすがに、高校はレベルが高いと、思った記憶があります。
小・中学生時代、毎週アメリカンポップス(ポールアンカ、ニールセダカ、コニーフランシスが代表的)
を聞いていた私は、同じクラスの数人を誘って、その軽音楽同好会へ入ることにしました。
これが、小・中学生時代、どちらかといえば、スポーツ少年(野球少年)だった、わたしが、音楽を実際に
演奏する側に廻った、きっかけでした。
その同好会には、あの校内放送で聞いた素晴らしく上手なボーカルの先輩(当時3年生)が居ました。
彼は特にエルビス・プレスリーが上手く、他を圧倒していました。ギターはその先輩から教えてもらいました。
さらに、女性ボーカルでハスキーボイスの1年先輩も特に上手でした。当時ブレンダリー、コニーフランシス
ジュリーロンドンなどを歌っていました。
高校の文化祭になると、その特別上手な男性ボーカルと女性ボーカル2人がデュエットして
ポールとポーラのヘイ・ポーラを歌ったりすると、全校内中で盛り上がったものです。
その同好会でよく練習したり、演奏していた曲は
ハワイアンでは、小さな竹の橋の下で、南国の夜、月の夜は、珊瑚礁の彼方など
そのほか、霧のロンドンブリッジ、Too young、Diana、the Diaryなどなど、
当時の記憶では、エルビスの曲だけは、ほとんど上手く歌えなかった記憶があります。
本当の理由は、分りませんでしたが、やはりエルビス自身の歌唱力を、到底まねできなかったのと、
私が直接には、全盛期のエルビス・プレスリーを知らなかったからかもしれません。
私はどんな曲が好きだったのか?大学生時代(H12.06.25)
先日、クレストフォーシンガーズのリーダー内田典宏さんに、どんな曲がすきなのですか?
と尋ねられ、すぐには、答えられられなかったので、すこしづつここに、書き出してみようとおもっています。
以前にも書きましたが、本当は、無意識に大昔聴いたことのある、曲名もほとんど思い出せないような
スタンダード・ジャズをクレストフォーシンガーズがコーラスしている曲が好きなのですが、
あえて、意識的・直接的に私が聴いた曲を思い出しながら挙げてみます。
先日は、小学生時代のことを書きましたので、今回は大学生時代を思い出してみます。
私が大学生になりたての頃は、なんといっても、セルジオメンデスとブラジル66がはやりだした時期です。
私も、いままで聴いたことのない、この曲想には、かなりの衝撃をうけました。一体どういうものなのか、
世界は広いなと思ったものです。そしてセルジオメンデスのファンになりました。
衝撃をうけた曲は、マシュケナダ(Mais que nada)です。そしてそのほかのヒット曲の数々。
コンスタントレイン、フォーミー、ザ・ジョーカー、ディサフィナード、ワンノートサンバなど
その後、セルジオメンデスとバートバカラックが、今でいうコラボレートされていったと記憶しています。
バートバカラックも洗練された曲といった感じで、好きでした。
Close to you、I'll never fall in love again、Raindrops keep fall'in on my head、Look of love、
Walk on byなど
しかし、私には少しあまのじゃくなところがあるようで、あまりに綺麗に仕上がる曲は、
返って魅力が半減するようで、彼の後期はあまり聴かなくなりました。
小学生5-6年生の頃(H12.06.16)
よく考えてみると、私がなぜスタンダードジャズが好きになったか、明確な理由がある訳ではありません。
私がはじめて、音楽が好きになったのは、小学生5-6年生の頃、
アメリカのポップスのヒットチャートを毎週のように紹介していたラジオ番組を聴いて、
だんだん音楽が好きになっていったのだとおもいます。
その頃、はやっていたのは、コニーフランシス、ポールアンカ、ニールセダカでした。
私も、直接・意識的に聴いたこれらの曲は、まねして歌っていましたし、
現在でも、上手くはありませんが、歌えます。
スタンダードジャズは無意識にどこかで聴いていたものが、私のなかに残っていて、
それが今、クレストフォーシンガーズのようなすばらしいコーラスを聴くと、
懐かしさとともに、よみがえってくるのだとおもいます。










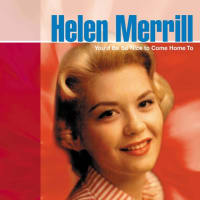




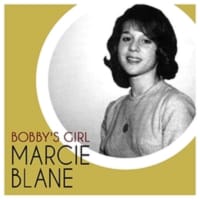





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます