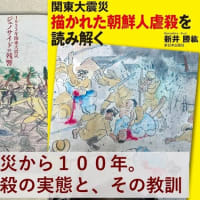「毒親」であった事実を暴露した娘に対しツイッターで「未だに娘の北朝鮮ぶりは健在です」とツイートする西原理恵子。
さらに西原理恵子の息子 西原雁治を名乗るツイッターアカウントが見つかり、妹の鴨志田ひよを「ゴリラみてえな顔」とツイート。
https://news.allabout.co.jp/articles/o/43911/p5/
「毎日かあさん」西原理恵子さんの娘による”毒親告発”で、日本の子育てSNS界隈が凍りついた件

「お母さんは、私が泣いて嫌がっても作品に描いた」
おそらく、日本の子育てエッセイ漫画の唯一にして無二の巨星であり、2010年代を代表する国民的大ヒットを遂げた『毎日かあさん』(毎日新聞出版)。毎日新聞紙上での15年の長期連載は子育て真っ只中にあった日本中の母たちから涙ながらの共感をさらい、「卒母」という印象的な言葉とともに終了したのは、今からちょうど5年前の2017年6月26日のことだった。
作者である漫画家の西原理恵子さんは、連載終了を前に、当時こんなコメントを残している。「娘が16歳になり、経済的支援以外、お母さんとしての役割は終わった」「子育て終わり、お母さん卒業、各自解散(笑)」。だが、そのモデルとなった家庭の実像は、漫画通りの面白おかしく切なくのどかな姿などしていなかったのだと、私たちは知ることとなった。
作中では「ぴよ美」と呼ばれ、幼い頃からファンにその成長を見守られてきた西原さんの娘が、これまで非公開だった実名ツイッターアカウントとブログを公開した。母による精神的・身体的「虐待」、いじめ、登校困難、整形やリストカット、精神科への通院、1人暮らしとアルバイト生活、15年前に他界した父の名字へ改名した事実などを彼女の視点から告白し、「お母さんは、私が泣いて嫌がっても作品に描いた」「なぜ書いて欲しくないと言ったのに、私の個人情報を世間へ向けて書き続けたのか」と母を責めた内容が明るみに出たのである。
それまで、『毎日かあさん』後半では母である西原さんのユーモラスな筆致によって「反抗期」「口もきいてくれなくなった」と描かれるままに、あのぴよ美ちゃんも大きくなって、と無邪気に受け止めていたファンにはショッキングなニュースであり、先週のSNSはその話題で大荒れに荒れた。そして「子どものプライバシーを、親がSNSなどで公開する罪」について、皆が一斉に考えた。
西原さんは、無頼派の麻雀漫画『まあじゃんほうろうき』やバブル期のグルメ文化を毒っ気たっぷりにちゃかした『恨ミシュラン』、アダルトな話題たっぷりの『できるかな』、元夫で戦場ジャーナリストであった故・鴨志田穣さんと世界各地を回った『鳥頭紀行』、リリカルな絵本『いけちゃんとぼく』、半自伝的な金銭哲学の『この世でいちばん大事な「カネ」の話』など多数の著作を持ち、エッセイ漫画作家として、また一時期は講演やテレビ番組でも活躍。近年は、「Yes、高須クリニック!」の国民的整形外科医ともいえる高須克弥氏と事実婚関係にあることでも知られている。
『毎日かあさん』は彼女の漫画家キャリアの中でも出色の代表作であり、アニメ化や映画化に加え、文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞、手塚治虫文化賞短編賞、日本漫画家協会賞参議院議長賞などの大きな賞はこの作品で授与された。国民的な人気と影響力を持つ作品であっただけに、実の娘による暗い告発が社会へ与えた衝撃は、決して小さくなどなかった。
「西原理恵子」という生き方
西原理恵子さんという作家は、無礼と無頼を身上とする、珍しい作家だ。武蔵野美術大学卒の実力を携えながらもエロ雑誌の挿絵書きとしてキャリアを開始。稼いだお金をギャンブルと酒に派手に注ぎ込んでギリギリの暮らしをし、それを作品に赤裸々に描いた。独特な線や色使いと手描き文字でつづられる作品メッセージは強くリリカル、かつエモーショナルで、「西原理恵子の世界観」は大手リベラルメディア人や、活字媒体を好む比較的エリート層の読者に熱烈に支持された。
当時、出版社や広告代理店の人間が発したという「女性の無頼は西原だけでいい」「お前は生い立ちがこじれてるからいいよな」などの言葉には、西原理恵子というまねのできない作家に対する、エリートの羨望(せんぼう)が顔を出す。アル中父の暴力、高校訴訟の経験、ギャンブルによる金銭問題や税務署との攻防、戦場ジャーナリストとの結婚、アルコール依存症によるDV、離婚、復縁、夫のがん闘病に死別と、西原さんはプライベートの出来事を隠さず作品化し、それはまさに「生きる私小説作家」という深く暗い業でメシを食い続けてみせるとの、強い意志の具現化でもあった。
その彼女が『毎日かあさん』で自らの家庭生活を作品にし、国民的「母さん」になったのは、もちろん作家として十分に戦略的な選択だった、と本人が作品中で述べている。女性ではない誰かが「女性活躍推進」という言葉をどこかで言い出す前から、上京した女の子が1人でどう男性に搾取されたりされなかったりしながら生きていくか、自分で稼いで生き残っていくか、「男と女が寝たら子どもができるんだよ」「地元の女たちはそうやって、無責任な男たちの尻拭いに振り回されて生きて埋もれた」「だから自分の腕で食える女になれ」と強烈に発信してきた張本人が西原さんだ。
西原作品が2000年代以降の女性に与えた影響は大きい。老若の女性の中に無数の崇拝者が生まれ、特に出産育児を経験した女性には絶大な人気があった。母親当事者である彼女は、女性の「母」の顔にとどまらず「妻」「女」としての顔も描いた。彼女の描く子育ては、どこかの大学の先生やナントカ博士が教えるような子育て理論の正解ではなく、日常の大小の出来事全てに愛憎があり、その向こう側に喜びがあり、生きていてよかったと必ず思えるカタルシスを生んだ。彼女が子育てのカタルシスを作品に描いたからこそ、「サイバラ後」の子育てエッセイ漫画というジャンルが開けたのだ。
子育てSNS界隈が凍りついた
出版界は第2、第3のサイバラを探した。新しい人材は、自分の時間に制限があるために断片的な発信しかできない、子育て中の母親たちと親和性の高いSNSであるTwitterの中から生まれることが多かった。「面白おかしい子どもとのやりとり」「子どもの笑える発言」といった無邪気な投稿の数々からアマチュアの漫画家やライターがスカウトされ、出版に至る。プライバシーに疑問の残るものも数多くあったが、SNSでの面白おかしい子育て投稿の延長線上にバズや作家デビューの可能性を見た「子育てアカウント」は、男女の出産育児を奨励する時代背景も手伝って、加熱した。子育ては、SNS上での一大ジャンルとなったのである。
だから「ぴよ美」ちゃんの告発がネット上で騒がれた途端、子育てアカウントが一斉に沈黙した。
始まる批判。「SNSで呑気に子どものプライバシー晒す親たちって毒親」「自分の承認欲求のために子ども晒していいね稼いで」「おむつ姿や失敗や言い間違えが可愛いって笑うけれど、それを見知らぬ人々に晒された子どもが同じように感じるとは限らない」「ネットではいろんな危険だって生じる。親としての自覚あるの?」。
そして反省。「今まで自分がしてきたことが、子どもを傷つける可能性なんて考えたこともなかった」「無意識のうちに、自分が毒親になってた」「もう自分の子どものこと書くのやめよう」「投稿控えます」。写真や投稿が消されたり、アカウントが公開から非公開(鍵垢)へ変更されたり。今回の件は、2000年代以降の、実に日本らしくのどかだった匿名SNS子育てカルチャーに走った激震であるといえる。
作家とはそもそも狂気の職業であり、作家の子どもは「狂気の下で育つ」
ネットとは、容赦のない悪意の沼でもある。西原さんの国民的作家としての成功の影には、サイレントなアンチの存在もあった。特にネットでの言論に積極的な高須院長憎し派が、ここに便乗。「西原批判」「西原キャンセル」が解禁、「男を踏み台にしてのし上がって行った女。もともとあの人には疑問があった」「言動をよく考えれば、本当は表には出せないような人」「みんなが思っているような聖人ではないのに、騙されてきた」と始まった。
私は『恨ミシュラン』以来30年以上にわたるファンとして、西原さんが聖人だなどと思ったわけはなく、ゲスの極みである作品群の動機はずっと「憎い」「悔しい」「苦しい」の感情だったように感じてきたし、それらが昇華していくカタルシスが、彼女の作品を読み続ける理由でもあった。だから彼女が鴨ちゃんの死を乗り越えた先でドクター高須と一緒になったとき、それが誰であるかとか経緯がどうだとかは超越して、「ああ、もうこの人(西原さん)はあの暗い感情を原動力に作品を描かずともよくなったんだ」と思い、心から彼ら2人を祝福した。西原さんは、あるインタビューで漫画家仲間に「なんかねえ……私、やっと幸せになったよ」と述懐している。「彼女としては」狂気の執筆生活の先に、幸福はあったのだ。
作家はみんな、その存在からして狂気の人々。私が以前インタビューした芥川賞や直木賞受賞作家たちは、なるほどこんなふうに浮世離れしているから創造的な文章を書くのだな、というよりも書くしかないのだな、と納得させられる異様なオーラを静かに放っていたし、みんな「小説執筆中は作品の中に生きているから、本当の生活なんかどうでもいい、子どものこともどうでもいい」「小説家なんてみんな不幸ですよ」「幸せな結婚なんて書いても3行で終わっちゃうから、本にならないんだよ」と口々に語った。
そんな作家の子どもたちは、彼らから生を受けた時点で、どこかその狂気の共犯関係とならざるを得ない、大きく重たいものを背負ってしまっているのかもしれない。檀一雄の『火宅の人』しかり、椎名誠の『岳物語』しかり、特に私小説作家の子どもたちは、思春期に親と激しい衝突をするし、自分のことをネタにされる限り、衝突するのが健全なのだろうとも思う。
私小説は、作家にとって自分だけでなく、周囲の人間の身を切る「禁じ手」でもあり、私小説での記述をめぐるトラブルは古今東西、枚挙にいとまない。活版印刷文化で、本を読む人が限られていた時代ですらそうだったのだから、ほぼ情報垂れ流しで丸見えの様相を呈するネット時代には、一層リスクが高くなっているということでもある。
「子どもが親に勝手にその成長をSNSに投稿されない自由」も?
西原さんの娘が公開したブログを知ったネットユーザーは、西原さんや娘にどういう感情を持っていようと関係なく、「いったい、自分の知らない何が書かれているのか」と好奇心からブログに殺到した。私を含め、『毎日かあさん』を読んできた読者はそれぞれに「◯◯年にはこういうことがあった」「こういう母だった」「こういう子だった」「だからこんなことが起こった」と答え合わせをした。
だが、ふと気づく。本人と会ったこともない無数の読者が、ネットでああでもないこうでもないと、勝手に「心配」「ジャッジ」する。そんなことがなぜ可能なのか。それは、母の作品という形で、「おかしゃん」と母サイバラに笑顔を向け、「おかしゃん、どこー」と母を求めて泣く幼少期の彼女について描かれ著述された材料が、確かに世間のあちこちに散らばっているからだ。
実際、私たちは西原さんの娘のことを知りすぎている。彼女は私たちのことを何も知らないのに。
「新聞や雑誌に、自分のことが描かれている」「周りの大人が、みんな自分のことを知っている」「そのせいで、友達にからかわれたりいじめられたりする」。そのアンバランスすぎる非対称は、幼い少女にとって恐怖だっただろうと、ようやく気づくのである。私たちは彼女が抱える恐怖や葛藤に気づかなかった。サイバラ家は、みんなそれを受け入れて楽しく暮らしているのだろうと思っていた。私たちは、西原さんが描くままにのんびりとおかしく豊かなサイバラ家の日々を消費し続けたのだ。
西原さんのケースに限らない。「息子愛」「娘愛」から、無邪気すぎる親のフィルターを通して世間へ共有された子ども本人のプライバシーについて、日本は今考え始めている。「子どもが了承したから大丈夫」? そもそも親と子どもの関係には力学的な傾斜があるのに、その潜在的な暴力性を自覚しない親が子どもから一方的に調達した「了承」はどれほど信頼に足るものだろう? 本当の物語は、子どもの中にだけずっと流れている。今後のネット社会では「子どもが親に勝手にその成長をSNSに投稿されない自由」というのも、議題に上がってくるのかもしれない。
河崎 環プロフィール
コラムニスト。1973年京都生まれ神奈川育ち。慶應義塾大学総合政策学部卒。子育て、政治経済、時事、カルチャーなど幅広い分野で多くの記事やコラムを連載・執筆。欧州2カ国(スイス、英国)での暮らしを経て帰国後、Webメディア、新聞雑誌、企業オウンドメディア、政府広報誌など多数寄稿。2019年より立教大学社会学部兼任講師。著書に『女子の生き様は顔に出る』『オタク中年女子のすすめ~#40女よ大志を抱け』(いずれもプレジデント社)。