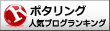2022/11/9(水) 晴
今日の最高気温22°今日も好天の自転車日和、「野外で食べるごはんはおいしいね」と言ったところ妻がおにぎりを握ってくれたので、それを持って午前11時半からポタリングに出る。
目的地は、熊本市西区の城山(47m)・御坊山(29m)とする。
往路は、熊鹿ロードを南進し井芹川沿いを下り、高橋で坪井川を渡り、城山西登山口を目指す。
先ずは、城山(写真1参照)に登る。写真は帰路に西側から撮ったもの。

西登山口の案内看板(写真2参照)の所から登る。ここで城山が重箱読みで「じょうやま」と読むことを知る。坪井川沿いの道を右折してこの道に入り、その先を左に折れ、東方向から南方向へと廻り込み込む。

そこに墓地と水道局の配水池があり、その傍の林(写真3参照)がこの山の最高点のようである。

この林の西側に、熊本市指定史跡「城山古墳一の塚」の石柱(写真4参照)がある。林全体が塚状をしているので、全体が古墳と云う認識でいいと思うが、全体をフェンスで囲ってあるので三角点の確認はできない。

城山を南側に下り、西区役所西方向にある御坊山(写真5参照)に移動する。

御坊山南東に小島阿蘇神社(写真6・7参照)の鳥居があり、100段ほどの石段が山頂社殿まで続く。


鳥居左側に由緒書(写真8参照)には、「御坊山(おんぼうさん)(御宝山)
この海抜二十三メートル、周囲約三百メートルの鬱蒼とした小高い山は、大昔は海中に浮かぶ小島であり、「小島」地域の語源となる山です。古くよりこの山には人が住んでおり、山頂に神社の拝殿前からは弥生時代前期(紀元前四~紀元前三世紀ごろ)の甕棺が三基発掘されています。
平成一七年四月一日環境保護地区として指定されています。
小島阿蘇神社
・・・室町時代末期の嘉吉三年(1443年)六月の白川大洪水の時、御神輿一基が御坊山に流れ着いているのを村民弥七郎が発見し、御神輿を開けてみると阿蘇神社二の宮の御神体であったので、俄かに村民と話合い山頂に社殿を鎮祭したと伝えられ、以後小島地域の産土神として崇敬を受けています。
御神体が流れ着いた時、その御神輿の底には御神体を守るようにびっしりと鯰が付いていたので、この地域では昔から鯰は神の使いされ食べない習慣があります。
皮膚病にもご利益があり美肌の神様として、また地震・事故などの災難除けの神様としても有名です。」とある。

鳥居前には道を挟んで天満宮(写真9参照)が鎮座する。曽我神社は南側山裾に鎮座する。

若干走り足りないような気分に、熊本港(写真10参照)まで足を延ばす。
トイレ休憩をして14時に帰途に就く。復路は往路を逆に辿る。

15時半に帰宅する。今日も無事だったことを天に感謝する。
熊本(自宅)18km→熊本港18km →熊本(自宅)
総所要時間4時間(実3時間) 総計36km 走行累計51,284km
山歩所要時間1(実0.5)時間 歩行した標高差約40m+20m