玉名市横島町の龍神宮等巡礼
2024/5/13(月)晴
最高気温26°午前は薄曇りだったが晴れた日になった正午からポタリングに出る。
目的地は、今年の干支の龍を祭神とする玉名市横島町の九番龍神宮、共栄龍神宮、横島の龍神宮とする。
熊鹿ロードを北へ走り、県道31から国道208を走り、木葉駅前を通り玉名市田崎から県道170・176を通る。自宅を出発して約2時間、今回は伊倉南八幡宮(写真1参照)境内で持参したサンドイッチで昼食とする。
写真を撮っている時丁度お参りする人がいた。お参りした後、北八幡宮の鳥居を潜られたので、両方にお参りされるのかと思う。
坂を下り県道1に出て、国道501を西進し501から左折して、Google Mapに最初に龍神社と表示された場所は田圃の中で、社や祠は見当たらない。止む無く、次の九番龍神宮(写真2参照)に移動する。
境内には、「九番龍神宮改築記念」碑と由緒書(写真3・4参照)がある。
由緒書には、「九番開住吉神社。九番開は安政六年(1859)有吉将監立愛により築造されたその面積約六十七町余である。その新地鎮護の神としてこの地に海神を祀った。祭神は大綿積神である。勧請は安政七年(1860)新地築造主の有吉家により勧請された。最初は石祠で祀ってあって今神殿の裏にある古い石祠が当時の物といわれている。九番地区でも社殿造営の話が出て服部宗次郎木村市三郎等の肝煎で明治十三年十月二十日(1880)元の社殿を造営した。拝殿の天井には百人一首の歌絵を画いてあるのが見事であったが破損がひどく昭和三十五年頃歌絵の上に天井板を打った。九番開では(1974)を百年祭と言って居るがこれは明治七年に九番開で死者九名を出す大潮害を蒙ったその復旧を記念して大祭を行った時から数えた年次と思われる。お宮の紋所は立四ッ角である。・・・」とある。

九番龍神宮を後にして南に走り、明治20年代から40年代にかけて築造された「国指定重要文化財旧玉名干拓施設」の、堤防沿いに鎮座する共栄の龍神宮(写真5・6参照)を拝する。

共栄の龍神宮を後にして北進し、菊池川が近い横島の龍神宮(写真7・8参照)を拝する。ここも旧菊池川がその分流河川堤防跡と思われる地形の傍に鎮座する。

帰路の途中、平地部から坂を上がり中分線の道路との交差点の角に、「歴史と史跡の伊倉」(写真9・10参照)の掲示板がある事に気付いたので写真に撮る。
「伊倉のあゆみ」には、「金峰山系の裾の流れが幾個の丘となり、海近く伸びて尽きる所、ここ伊倉の台地にいち早く人々が生活の拠点を築いた。伊倉は丹倍津(にべの津)といって、昔朝廷への献上品や肥後の産物を大阪、京都方面へ移出する菊池川の川口に発展した要港として栄えた。
その後、朝鮮、中国との海上交通も開け、大阪から移住する者も多かった。従ってこの港に関連する地名(船津、唐人町、住吉)遺跡等が現存している。
奈良時代には、南北両八幡宮が創建され、報恩寺の建立があり、地方文化の中心となって伊倉の特色を発揮するようになった。南北朝時代には菊池勤皇軍の海軍基地となり、その頃から伊倉丹倍津はますます繫栄した。この時代正平3年(1348年)には伊倉五山制が確立し、そのひとつ、唐人町の桜井山安住寺境内地には、かつて唐人が船をつないだという樹齢700年以上の大銀杏がある。これを「唐人船つなぎのイチョウ」といい県指定の天然記念物となっている。
さらに、室町時代には、遠く南方との貿易も始まり、経済の発展にともない文化も進展し、伊倉は経済的文化的に最も華やかで豊かな地域となった。
のちに、加藤清正が菊池川下流に干拓地造成の為、天正17年(1589年)より慶長10年(1605年)にかけて河道を変更し堤防を構築したので伊倉港は消滅したが、小田手永会所が片諏訪に設けられ、穀倉地帯小田郷の中心地としての地位を確かなものにした。
文政11年2月(1828年)には、肥後の国学者林桜園先生が伊倉に私塾を開設され、明治初期から中期にかけて木下助之竹・添進一郎・国友古照軒・岡松真守・松尾常人・内田三左衛門・山戸多十郎・山戸憲次郎・野田藤造等の諸先生によって次々に伊倉に私塾が開かれた。
近郷の村々より来学するもの多く、伊倉の子弟もまた向学の気風高まり、進学者多数、社会の各方面に幾多の人材が輩出し活躍した。それが日本の文化開花に果たした役割は大きく〔文教の地伊倉〕の名声は高まっていった。その伝統は今も脈々と受け継がれ、町勢が衰えた現在においても、この歴史的文教の風土を愛し、教育に対する地域の関心は高く、次代を担う子供達に期待する夢は大きい。
太平洋戦争時には、伊倉台地の下に太刀洗陸軍航空隊の飛行場が建設され、多くの人が労役に従事した。戦争末期にはアメリカ軍のグラマン戦闘機がたびたび来襲し{歴史と史跡の町}伊倉も戦火にさらされた。
近縁は、都市への人口流出と急速な車社会の進展で、古い町並みの伊倉は衰退を余儀なくされた。しかし、市民生活において文明のほずみが目立ってきた昨今、新たな視点にたち、安全、快適、利便性を「まちづくり」の基本に据え、21世紀においても、存在感のある確かな町として生き残れるよう努力しなければならない。」とある。ここを最後として帰途に就く。

17時半に帰宅する。今日も無事だったことを天に感謝する。
熊本(自宅)34km→共栄の龍神宮33km→熊本(自宅)
総所要時間6時間(実5時間) 総計67km 走行累計59,045km

自転車で探訪した史跡・文化財等の記録です。一部山行の記録もあります。
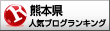

最新の画像もっと見る
最近の「肥後国(熊本)の神社」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- 熊本から山と自転車のブログ索引(28)
- ウォーキング(92)
- トレッキング(72)
- 日帰り登山・ハイキング(40)
- 残しておきたい自転車日記(50)
- 自転車で低山登山(25)
- 自転車で花(63)
- 自転車で紅葉(25)
- 自転車で宇土半島(18)
- 公園・湧水・名水(44)
- 歴史公園・資料館・博物館(29)
- 熊本の名勝・天然記念物(43)
- 熊本の近代史跡・文化財(39)
- 西南戦争史跡(32)
- 肥後国の近世史跡・文化財(67)
- 肥後国(熊本)の石橋(42)
- 放牛石仏(地蔵)(30)
- 肥後国の六地蔵(50)
- 加藤清正遺跡等(55)
- 肥後国の中世史跡・文化財(60)
- 肥後国の中世城跡(26)
- 肥後国(熊本)の仏閣(41)
- 肥後国(熊本)の神社(94)
- 肥後国の古代史跡・文化財(48)
- 肥後国の古墳(144)
バックナンバー
人気記事

















