さて、まず小林=益川模型によるペンギン過程とはどんなものだったのか復習しましょう。
中性B中間子のB⁰とは反bクォークとdクォークからなる中間子ですが、ここでは分かりやすさのためにbクォークと反dクォークからなる反B⁰についてお話ししましょう。その反B⁰が崩壊するにあたってbクォークから仮想W粒子が飛び出るという反応が起こると考えられています。それは湯川秀樹がπ中間子出現の際に仮定したようなプロセスで生じます。ここでbクォークがW粒子のエネルギーを受けてtクォークにまで遷移すると考えてその確率因子を計算するのが小林=益川模型なのです。
W粒子のエネルギーではtクォークにまで遷移するにはエネルギーが足りません。
そこで小林=益川模型ではかつてニールス・ボーアが行ったような「微小領域ではエネルギー保存が成り立たなくなる」と考えて言い訳にするということをします。結果としてtクォークにまで遷移する確率因子は虚数となるのですが気にしないという幾分なりとも苦しい考え方なのです。
ここに標準理論による説明の第一の難点が存在していると考えます。
次に、湯川のプロセスで仮想粒子としてW粒子が出現したとすると、その湯川時間は0.819×10^-26sになってしまうのですが、それではtクォークが崩壊するいとまがないという第二の難点が出てきます。同様の難点がユニバーサルフロンティア理論では片付いたからというわけではありませんが、この難点は致命的だと思われてなりません。このようにしてユニバーサルフロンティア理論による説明のほうがずーっと精緻だということを示すことができました。
どうでしょうか?
中性B中間子のB⁰とは反bクォークとdクォークからなる中間子ですが、ここでは分かりやすさのためにbクォークと反dクォークからなる反B⁰についてお話ししましょう。その反B⁰が崩壊するにあたってbクォークから仮想W粒子が飛び出るという反応が起こると考えられています。それは湯川秀樹がπ中間子出現の際に仮定したようなプロセスで生じます。ここでbクォークがW粒子のエネルギーを受けてtクォークにまで遷移すると考えてその確率因子を計算するのが小林=益川模型なのです。
W粒子のエネルギーではtクォークにまで遷移するにはエネルギーが足りません。
そこで小林=益川模型ではかつてニールス・ボーアが行ったような「微小領域ではエネルギー保存が成り立たなくなる」と考えて言い訳にするということをします。結果としてtクォークにまで遷移する確率因子は虚数となるのですが気にしないという幾分なりとも苦しい考え方なのです。
ここに標準理論による説明の第一の難点が存在していると考えます。
次に、湯川のプロセスで仮想粒子としてW粒子が出現したとすると、その湯川時間は0.819×10^-26sになってしまうのですが、それではtクォークが崩壊するいとまがないという第二の難点が出てきます。同様の難点がユニバーサルフロンティア理論では片付いたからというわけではありませんが、この難点は致命的だと思われてなりません。このようにしてユニバーサルフロンティア理論による説明のほうがずーっと精緻だということを示すことができました。
どうでしょうか?










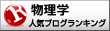








そのことは小林=益川模型によるペンギン過程が間違いであることを証言し得る根拠ではないでしょうか?