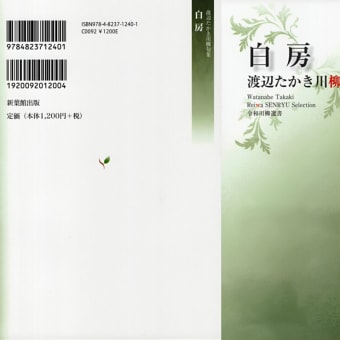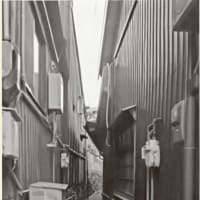□本日落語一席。
◆五代目柳家小さん「粗忽長屋」(衛星劇場『衛星演芸招待席』)。
※口演情報不明。
あらためて五代目小さんの「粗忽長屋」を聴くと、今や多くの落語家が演るこのネタの源流なのだなとよくわかる。粗忽者の噺を演るときに振るマクラの小噺まで、五代目小さん流なのだなと。
長屋の者どうしが言いあいをする夫婦喧嘩の小噺、いや、実は夫婦喧嘩でなく、一方が近所の犬を追い払っていたとか、よく見た人が前にいるが、誰だか忘れたところ、尋ねてみると、「おまえの親父だ」という落ちになる噺とか。ちなみに、五代目小さんは「親父でなく」「兄貴」で演っていた。誰がこれを「親父」にかえたのだろう。
また、本編もほぼほぼ寸分違わず今の落語家は型を継承している。とくに、行き倒れを見て熊五郎が「顏が長いような気がする」と言うと、八五郎が「夜露にあたって伸びたんだ」と返すクスグリも、この五代目小さんがもとになるのかと思えたが、どうなのだろう。
ちなみに、明治の三代目柳家小さんは、「長へ面ん成ったなア。目が窪んで頬がこけて小鼻が落ちて真ッ白けに成つちまつた」と熊五郎が言ったのに対して、とくに八五郎は何も言い返していない(『口演速記 明治大正落語集成』による明治28年の速記)。
それと、演者はわからないが、昭和36(1961)年刊の金閣社版『増補 落語全集』によると、ここのところ、「オヤオヤ、大変面が長くなつたなァ」(熊)、「南風が吹いたんで、自然と伸たんじャなえかい」(八)となっている。夜露じゃなくて、南風というのがおもしろい。こんなふうに演られていた時代もあったのかと。
してみると、夜露はやはり五代目小さんが演り出したものか。これを誰もがおもしろいクスグリだとばかり数十年も継承され続けているというのは、やはり落語が伝統芸能ということになるのだろうか。
◆五代目柳家小さん「粗忽長屋」(衛星劇場『衛星演芸招待席』)。
※口演情報不明。
あらためて五代目小さんの「粗忽長屋」を聴くと、今や多くの落語家が演るこのネタの源流なのだなとよくわかる。粗忽者の噺を演るときに振るマクラの小噺まで、五代目小さん流なのだなと。
長屋の者どうしが言いあいをする夫婦喧嘩の小噺、いや、実は夫婦喧嘩でなく、一方が近所の犬を追い払っていたとか、よく見た人が前にいるが、誰だか忘れたところ、尋ねてみると、「おまえの親父だ」という落ちになる噺とか。ちなみに、五代目小さんは「親父でなく」「兄貴」で演っていた。誰がこれを「親父」にかえたのだろう。
また、本編もほぼほぼ寸分違わず今の落語家は型を継承している。とくに、行き倒れを見て熊五郎が「顏が長いような気がする」と言うと、八五郎が「夜露にあたって伸びたんだ」と返すクスグリも、この五代目小さんがもとになるのかと思えたが、どうなのだろう。
ちなみに、明治の三代目柳家小さんは、「長へ面ん成ったなア。目が窪んで頬がこけて小鼻が落ちて真ッ白けに成つちまつた」と熊五郎が言ったのに対して、とくに八五郎は何も言い返していない(『口演速記 明治大正落語集成』による明治28年の速記)。
それと、演者はわからないが、昭和36(1961)年刊の金閣社版『増補 落語全集』によると、ここのところ、「オヤオヤ、大変面が長くなつたなァ」(熊)、「南風が吹いたんで、自然と伸たんじャなえかい」(八)となっている。夜露じゃなくて、南風というのがおもしろい。こんなふうに演られていた時代もあったのかと。
してみると、夜露はやはり五代目小さんが演り出したものか。これを誰もがおもしろいクスグリだとばかり数十年も継承され続けているというのは、やはり落語が伝統芸能ということになるのだろうか。