
図はPLL(フェーズ ロックド ループ)による「FM復調」の原理を示しています。オペアンプを理解していれば一目瞭然ですね。
VCO(Voltage Controlled Oscillator)は「V/Fコンバータ」であり、入力電圧に比例して出力周波数が変化します。よってVCOの出力は入力信号の周波数と位相が一致し(同一波形であり)、VCOの入力(オペアンプの出力)が復調された信号波形になります。
すなわちこれもオペアンプの核心部。ネガティブフィードバックする限り必ずプラス入力端とマイナス入力端の値は一致するということです。もしVCOの代わりに抵抗を取り付けたら、プラス入力端、マイナス入力端、オペアンプの出力の3か所の波形がすべて同じになりますね。
関連記事:オペアンプとは何か? 2007-09-02
VCO(Voltage Controlled Oscillator)は「V/Fコンバータ」であり、入力電圧に比例して出力周波数が変化します。よってVCOの出力は入力信号の周波数と位相が一致し(同一波形であり)、VCOの入力(オペアンプの出力)が復調された信号波形になります。
すなわちこれもオペアンプの核心部。ネガティブフィードバックする限り必ずプラス入力端とマイナス入力端の値は一致するということです。もしVCOの代わりに抵抗を取り付けたら、プラス入力端、マイナス入力端、オペアンプの出力の3か所の波形がすべて同じになりますね。
関連記事:オペアンプとは何か? 2007-09-02
















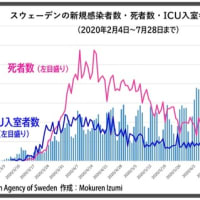









(^^)
コンスタントにレスできないこともあると思いますが、必ず見ておりますので。
ありがとうございます。
また時間見つけて参考にして作ってみます。
またカキコさせていただくと思いますがよろしくお願いします。
私も内容的にはほとんど理解していないのですが、このサイトあたりはどうでしょうか?何らかの参考になれば。
http://u111u.info/kAqJ
当方、若干不規則な時間ですみません。
そうですね。
現在はトリマコンデンサとコイルでの自励発信です。
ご質問の件ですが、実は私もPLLにさほど詳しいわけではないんです。たまたま仕事でFM変調された信号(有線)を専用PLLデバイスで復調したのですが、その時にPLLのメカニズムになるほどと思い、この記事にした次第です。
それで、ご紹介のNJM2035のデータシートを見てみたのですが、ステレオの音声信号をFMコンポジット信号に変換するデバイスのようですね。FMステレオトランスミッターも初耳だったんですが、Web検索してカーステ用として良く知られてるんですね。
改造の目的は、NJM2035で作ったFMコンポジット信号をFM変調して飛ばしたいということでしょうか?
失礼します。
このたび、自励発信の機種をPLL制御発信に変更を目論んでいます。
ICはNJM2035を使っており、このICの8番、9番から出力させた信号を何とかPLL制御発信できないかなんですが、簡単な回路ご存知でしたらお教えくださいませんか。
はじめてにもかかわらず厚かましいですが、よろしくお願いいたします。
きっと本質がわかるかと思います。
アナログが得意なホロンさんですから怖いものなしです^^;
ゲルマラジオ->1石ラジオ->スーパーラジオ->アンプ、なぁ~んてやってきた私がいきなりロジックで「???」で壁になり、マイコンやりだしたら「!!!」で進んで、CPLDで「???」で、PCプログラマになってからようやく「!!!」です。
同じ過程を踏めばクリアできますよ、たぶん。
私も全部わかっているワケではないと思います。でも、それをもとにして想像して理解できるものってあると思います。それをカギ分ける元となる力がつくかなぁ~?って・・・。
きっと見える世界が変わるのではないかと・・・。
Windows上でCBuilderを使うようになってから見え方が変わってきました、私の場合。
今、すこしだけ興味あるのはXBOXかな?(以前からすこぉ~しだけあったのですけど・・・)
PCでDirectXをすこしでもカジれば、なんとか入り込めるかも?
XBOXなんて、とうの昔にハードは凍結しちゃいましたが・・・。
世間はAndroidばっかですが、そういうのは興味ないんで・・・。別の「アンドロイド」のほうしか興味ないですけど(笑)。
(^^)
というわけでHDLとやらも関係のない低次元の話です。
「ABEL」のようにアセンブラでもいいですから・・・。
同じ様な仲間内や職場とかいろんなところで技術的な話がでたときに「なんだ、まだクラゲか?HDLも知らんのか?」ってあきれられないように!
HDLのほうがはるかに早く目的を達成できます。
ロジックシンボルで設計していたことなんて忘れてしまう、というか戻れなくなります。
C言語とかObjectPascalとか扱えるくらいの技量は必要になります。
慣れるにはPC上でのコンパイラのほうが圧倒的に効率いいです。
一番小さいCPLDのキットでもあれば充分です。
実際に使わなくても、他は想像つくようになりますし、大見栄(笑)を切れるようになりますよ、絶対!(私がそう!)
※ほとんど出番のない手持ちのXilinxのCPLDスタータキットはそのために残っているようなものです・・・。
まさに「デジタル」は「万人向け」の素質を持った方式だと思います。
いままで、それで苦労させられた業界は、それに関する苦労は少なくなったことでしょう!
それ以上に、クォリティに関することはよりシビアになるでしょうけど・・・。
もう、そういう「戦争(?)」には一切関わらなくても生きていける私です(笑)
※ボチボチHP更新してました・・・。
「シングルコンバージョン」という場合もありますが・・・。
そういうワケで当然のことながら「ダブルコンバージョン」もあります。
周波数が極端に高い場合は、まず間違いなく「ダブル」です。
BS・CSチューナーがそうですね!
10Ghz帯を(パラボラ)アンテナで受けて、ダウンコンバータで1GHzまで落とす・・・ここで1次中間周波となり、チューナー側でおなじみの10.7MHz・・・ってそいれはアナログ時代の話(ただし、アメリカ方式)。
あと、「ダブルコンバージョン」だったのは、古~いラジオで「三菱・ジーガム」っていうのを使っていたことがあって、そいつもそうでした。しかもVFO搭載だったのでSSBが受信できました・・・って、アマチュアバンド聞いて、何がタノシーねん!ってところです。
ま、そんなところで、いまどき、何の役にも立たないと思うけど・・・。
とりあえず、「ラジオもオールデジタル化」が白紙になって「ホッ」としているところ・・・。
なにはともあれお仕事ごくろうさん。僕はもう数か月バイト生活で適当に流してるけど、ktの仕事ぶり見てると猛烈サラリーマンだったころの自分が懐かしいなあ。
ホロン,kaoaruさんの知識の幅広さ,すごいな。スーパーヘテロダイン,ちょっと勉強したよ。ダイレクトコンバージョン方式とZero-IF方式の受信機を勉強したときに,受信機のスタンダードとして・・・・しかし,勉強になるなぁ~ 近いうちに,質問させてくださいな。
あっ,そうそう,ktは,皆さんより年下でした。今年で46歳です。一番年下なのに,タメ口,ごめんね!
(^^)
FRは楽しいそうですね。しかし4WDの方が速いとか。テクニックが必要らしいですけどね。まあこの歳の私にはもはや無縁の世界ですが。私は170馬力のFFのアクセラでも十分すぎます。
私、目(心の目?)では見えないですけど、気配を感じたところありました。カミさんといっしょになるまえに入ったホテルがそうでした。私は気になってしょうがなくて、すぐに出ました。
俗に言うパワースポットならばいいのですが、「ミステリーゾーン」と言われる場所はあぶないです。
横浜に住んでいたときに、そういう仲間といっしょのいバイクで、そういうスポットをめぐったこともありましたが・・・かなりヤバイところありました。
私ねぇ~、外でカメラ持つと変なの写ることがタマにあるんです。だから、風景とったりすることしないんです。
こわかったのは線路のガード下の壁から親子らしき人影(?)がでてくるところが写ったことがありました。それは今の職場のすぐ近くなんです。
そういうワケで、ちゃんとしたカメラなんてないほうがいい私でした^^;
※八王子城跡、かなりやばそうですね!テレビで見たこと有りますが・・・人がたくさん自害したところって、やっぱりなんかあるものだと思います。
クルマの件ね、まわりもそういう人たちがいっぱいいて・・・って、そういう中に入り込んでいっしょになってワイワイやってました^^;
そういう人たちといっしょになって、フロントストラット分解してコイルスプリング交換したりしたんですよ!なんせ、集まるのは「表向きタイヤショップ」、実はカーショップでしたから、スプリングコンプレッサもあったりして・・・。
RX7のツインターボ(ブリッツ)のヤツとか、カマロRSをチューンしたヤツとか・・・シートにグッと押さえつけられる強烈な加速感・・・すごかったです!
クルマはやっぱり・・・FRが楽しい!
さて、kaoaruさんもホントに多芸多才な人ですねえ。(^^)
「走り屋」さんでしたか。私が今一緒にパワーアンプを組んでいる30歳の相棒も最近まで走り屋をやっていて、スカイラインGT-Rをフルチューンして1000馬力だそうです。高速道路を走ると350km/hを超えるそうです。チューニング費用も1000万円を超えたそうですが。
筑波山は「霊山」なのですか。霊的なもの感じる感性は私にもあると思うのですが、私は基本的に唯物論者ですので、まったく気にならないというか無関心ですね。もちろんロジックで否定することはできないですけどね。私の真逆が嫁さんです。だから家族ではパワースポットなどによく出かけますよ。私一人カーステを聴きながら、参拝に行った家族を待つというのが常ですね。
当時はそういうの意識してなかったと思うけど、よくまぁ毎晩ひとりで走っていたよなぁ~!
「裏筑波スカイライン」から中腹あたりで「廃レストラン跡」があるハズですが、あそこは強烈な「霊場(?)」です。
だって、筑波城があったはずの場所ですから・・・。
「筑波」っていうのは、もともと「城主の名」だったようで、「川島の合戦」で敗れたときに全滅していると思われます。
親父から「先祖は飯炊き」という話を聞いた記憶があります。
おそらく「筑波城の勝手口」を出入りしていたと想像するわけですが、今生き残りがここにいるワケですから(笑)、命からがら逃げ切れたのでしょうね!
「筑波城」のあったあたりから麓までは地元の人じゃないとわからないような道があるんですよ!
まぁ、そういうのも、先祖の導きだったんだろうと思っています。
そのような夢を2年くらい前にみたことがありますが、先祖が教えてくれたものと、思い込んでおります。それはそれでいいのではないかと・・・。
当時、こんなこと知ってたらむやみに近づいていなかったですよ、おそらく。
わかっているのは、親父が3代目で私が4代目!あくまでも紙の上での話。現在初代としているそれ以前のことはわかりません。これだけわかっていれば充分です。
これももっともな話ですが、「民主党」もきれいごとばかりならべるだけで、何も身にならなかった・・・これが一番の元凶でしょう!
だから「マニフェストなんてはずかしくていえない」っていう言葉には笑っちゃいました!
これだけ悪い就労条件の中で「愛」とか「恋」とか(「SEX」とか)夢中になれるのは若者だけなんでしょうね、たぶん。
かくいう私も「定時間内だけ」ですよ、ヒーコラしてんのは。4年前くらい前までは平気で100時間以上の時間外をやってました。そのころは90キロ以上あった体重もいまや80キロに収まって、標準体重で、体脂肪率も20%ないかな?多くても16~17くらいかな?
歩くことが増えたので、自然とこうなりました。1日に少なくても1時間は歩きますんで・・・。
クルマが1台だと、使いまわしを工夫しないとね・・・。
ウチの息子も自動車学校に通い始めたので、この先どうなることやら・・・。就職内定しているのでそれはいいのですが、免許が必要なんで間に合うのかな?
「もう間に合わんぞ!」と言ったのはワタシ!
しかもねぇ~、よしゃぁ~いいのに「マニュアル」だって!
まぁ、私はマニュアルもATも左ハンドルもOKなんでどぅってことないのですけど、はじめてでいきなりマニュアルなんてねぇ~!無謀だな~って思っています。
でも、クルマはマニュアルでFRのほうが断然いい!そう思います。かつて、ケンメリやジャパンを乗り回していたし。カウンターをあてる、なんてのはFRじゃないとねぇ~!
22になる直前だったと思ったけど、毎晩のように「筑波山」を初代ミラージュで攻めて(いるつもり?)いました。
足回りはラリー用のコイルスプリングでカヤバのガスショックを装着して、マフラーはトラスト。キャブにまでは手が回わんなかった、予算不足で・・・。
22~23くらいで茨城をひきあげることになり、週末は先輩とよくストリップ見に行ったなぁ~!
私がいた会社に「高校の10年先輩」がいたのですよ!
今はストリップなんてほとんどないですよねぇ~!
そういえばなんかの旅行で「女体盛り」ってのを体験したことを思い出した!何の旅行だったか思い出せないけど、「わかめ酒」っていうの、ほんとにはじめてみたよなぁ~!
と、これも、今となっては単なる思い出に過ぎないのですが・・・。
今はそんないい話はないと思いますよ!
なんせ、みんな稼ぎのためにヒーコラしていますから、そういう余計なほうに気を回せないハズですから・・・。
お分かりだとは思いますが・・・。
「ユーのイングリッシュはプアね」はやはり、彼女に好感をもたれてなかったということでしょうねえ。(;;)。20代前半とおぼしき可愛い人でしたがねえ。別に悪さをした覚えもないのですが、顔が気に入らなかったのかな?でも仕事はちゃんとしてあげたので喜んでましたよ。(^^)
ほう製造ラインで多数の女性に迫られましたか。私なら喜んでみなさん全員を嫌というほどかまってあげますが。でも私は鼻の下がすぐ伸びるので、下心見え見えで引かれてしまうでしょうねえ。
ほう、これは目から鱗。エレクトーン教室いいですねえ。若い女の先生とお近づきになれるではないですか。個人レッスンがいいですね。(^^)。鍵盤楽器は私も好きで、やはりピアノかな。学生時代に音楽室のピアノを借りてベートーヴェンの「月光」を練習して1楽章だけ弾けるようになりましたよ。ほぼ1年かかりましたが。
これ、実際に自分で具体的なモノを作ってみればわかります。
PICマイコンでやったとき、アプリケーションのオリジナルはPIC16C268でやっていたものを移植したのですが、ハードウェアスタックがまったく違っていたために全くの作り直しになってしまったのです。
そういうワケで自分で詳細を理解できていないとできなかった・・・。
このやりかた、積分なくしては成り立たんのです。シグマあってのデルタなんです。
まぁ、見方によっては「スロープ積分」の親戚と言えなくもないのですが・・・。
「積分してから差分にフィードバック」これに気づいたときにプログラムを完成することができ、トラ技で採用されたワケです。
やってみないとわからないこと、多いです。
まぁ、私は「座学」では退屈になるほうなんで、すぐ実行に移すほうでしたが・・・今は情けないかな?おそらく、当時の私が今の現実をみたらガッカリするかも?
「ユーのイングリッシュはプアね」
これは、あんまり好感もたれてなかったのが原因でしょうね!特に、相手が女性となればなおさら・・・。見下されていた・・・そういう風に感じました。
その逆(?)というか、こういう体験あるんです。
製造ラインって女性が多かったのですよ!当時の横浜って、既婚者でもね、垢抜けしているのかどうかよくわかんないですけど、いつも「間に合わない人」にかまっていると、他の人たちからね、不満の声が・・・。
どうも、「私もかまってほしい」ということらしい!
う~ん、むずかしいモンだ!って25~26の私は悩みましたよ!
まぁ、みんなに声掛けるようにするしかない!って感じでしたか・・・。既婚者って言っても上限は30代くらいでしたんで、若いですよねぇ~!
おそらく、そん時がイチバンたくさん女性と話をしなければいけなかった時期だったかもしれません。
次にたくさん女性がいた場所・・・それはヤマハの教室に通っていたころかな?28~30くらいまでだったと思いますが、やはりキャリアのある人とそうでない人といろいろでした・・・。
インストラクタに教えてもらうのですけど、もちろん女性です。このインストラクタとも冷戦状態になった経験がある私でした^^;
何の教室かって?いや、聞いてない、聞いてない(笑)!
エレクトーンの教室だったのです。「ハーモニーパーク」ってやつで、鍵盤楽器ってまったくわからなかったし、シンセの教室がなかったので、とりあえず「お試しレッスン」受けたらそのまま「ハーモニーパーク」に引き込まれてしまった・・・という状況!
キレイな女性が沢山いましたんで・・・^^;
私も外国人と仕事をした経験がありますが、最初は台湾の半導体工場でした。クリーンスーツを着て女性社員と一日付き合いましたが、最後に「ユーのイングリッシュはプアね」などと言われて、ガックリ。向こうの人たちはみんなホントに英語に堪能で、劣等感にさいなまれてしまいました。日本の英語教育はいまだにまったくダメですねえ。
さてデルタシグマ変調ですが、私のこの記事をご覧ください。
http://blog.goo.ne.jp/commux/e/863567476d14e53b696f530bf75f9bf4
やはり動作的に考えるとデルタシグマがフィットしているように思えるのですが。
オリジナルドキュメントを和訳したやつもそうなっているかと思います。
「デルタシグマ」っていう呼び方をするのは日本くらいなんじゃないでしょうか?
つまり、デルタという記号の次にシグマの記号をそのまま続けて読んだ・・・海外ではそのように書いて「シグマデルタ」と読むようです。文献関係はみんなそのように書かれていますね。
動作から言ったら、積分(シグマ)して差分(デルタ)をフィードバックして、HIGHをカウントするのですから、海外の文献のほうが正しいんじゃないでしょうか?
オーディオに興味があったものなら誰でも知っていると思います。あと、スタントンとか・・・。
「シグマデルタ」というのは、日本人の誤訳が原因だと思います。海外では「デルタシグマ」という言い方をするようです。
専門用語のオンパレードだと、普通の通訳では役に立ちません。
私の経験では、「筆談でも通用する」んですね、エンジニアどうしだと。
専門用語は英語やドイツ語が大半です。だから、普段使っている単語が発音ちがってたって通じちゃうんですね、これが。
そういうことを26くらいのときに体験しました。1週間大変でしたけど・・・。
ドイツ生まれのアメリカ人で、コカコーラが大好きな人でした。
ポリバリコンでチューニングするAMラジオはその昔、電気のでの字も知らない頃にキットで何台か作りましたよ。なかなか鳴らないんですよこれがまた。「トラッキングエラー」「トゥイート」「デジマースコープ」、知らない言葉ばかりですねえ。東京にいたころ「ダイナベクター」というカートリッジの会社でバイトしてたので、レコード針の「トラッキングエラー」はしょっちゅう話題にしていました。
PICでデルタシグマ変調しちゃうんですか。でAD変換してしまう。すごいですねえ、尊敬しちゃいます。しかしアナデバは「シグマデルタ」って言いますよね。なんででしょうね?動作を考えるとデルタシグマだと思いますが。
「VFO」「SSB」?????(^^;
「人生の残りもあと少し」?相対的見れば「まだまだこれから」とも言えそうです。この先、何に遭遇するかはわかりませんものね。願わくば、また何かが新しく始まってほしいと思う私です。
実はこれ、省略したのです。
もちろん、「和」のほうもあるのです。
SSBって聞いたことありますか?
キャリアで変調を掛けると、キャリアの上と下、両方に同じイメージでできるのです。
下側を「下側波」、上側を「上側波」と言って、SSBではそのどちらかを使って電波として送信します。だから、キャリアがないのです。
どうやって復調するか?
キャリアに相当するものを受信側で用意するのです。
一般的にはそれを「VFO」と言っています。
SSBのメリット・・・それはキャリアを送信しないために送信電力を極端に抑えることができます。
デメリットはもうおわかりですよね?
受信側でキャリアに相当するVFOを用意しなきゃイカンということで、こいつの安定度が問題になります。
アマチュア無線をやられている方はご存知の内容です。
まぁ~、SSBなんて「AM変調」でしか使えんけどねぇ~!
ちなみに「アナログ方式のテレビ用電波」はVSBという方式だったのですよ!
キャリアと上側波(じょうそくは)の一部をカットして、帯域を6MHzに抑える方式なのです。
テレビ信号をまともにAM変調すると8MHzの帯域が必要なのです。
テレビの音声信号はFM変調です。しかも、キャリアのカラクリは・・・巧妙です。インターキャリア方式といって、キャリアがないのです。フフフ・・・おもしろいでしょ?
このあたりはメンドくさいかもしれません。
でも、現在も使われているモノだったら考えてもムダじゃないですよね?
FMステレオ放送なんてどうでしょう?
LとRを平衡変調かけるのですね、キャリアは38kHzです。そのための19kHzパイロット信号がFMの場合は重畳されていて、受信側ではその19kHzを元にして38kHz復調をするんですよ!
このしくみについては、高校時代に自分でやっていたのでわかっていました。オーディオマニア時代だったのですね、あの頃は・・・。
高校生ともなると他の連中はナンパしにいったりしてたり、デートしたりしてようですが、私にはそのようなものにまったく縁がなかったので、時間をこういうモノに掛けていたワケで、そのせいでこんなに偏った人間になってしまった・・・そういうコトじゃないですかね?
人生の残りもあと少し。
未来も希望も今後の展望も何もないかもしれません。
今まで生きてきた後片付けの時間・・・それがこれからの時間なんじゃなかろうか?そう思ってこの2~3年過ごしてきているこの頃です。
これって、年齢の割に「老けた内容」ですよね?おそらく。
ということで8ビット~10ビット程度の精度でいいのなら、PICマイコンのほうが安上がりです。
しかもADコンバータも内蔵していない12F509という割り込みもないチップでやっちゃうワケです。
それで「デルタシグマ(ほんとはシグマデルタ)方式」でやったのが前にカキコした内容ですね!
こぉ~んなこと書いていると、実にスラスラと内容が出てくるんですけど、世間一般の話になるとなぁ~んも出てきません。
長いことやってきているから、染み付いているのでしょうね!
だから、いまさら「浮世」のことを気にしたって、もう~遅すぎる、あんたはそのままいくしかないのだよ!ってな感じですか・・・。悲しいものですねぇ~!
これは驚きです!
今やチューナー部分に着眼する人がいないんじゃないでしょうか?
2周波を混ぜると、その差がうねりになって出てきます。それを「ヘテロダイン」と呼んでいるのですが、日本の中波ラジオですと、その周波数は450kHzです。アメリカバンドは455kHzです。
たとえば、新潟放送BSNが1116kHzだとしたら、ラジオの局発(これがローカルオシレータと呼んでいる部分)はそれよりも450kHz高い1116+450=1566kHzの周波数になる、ということなんです。
この1566kHzをVCOにしてPLL制御すれば、周波数をジャストで指定できることになるわけです。
昔はこれが夢のまた夢みたいな話で、ポリバリコンでチューニングするようなラジオばっかりでしたけど、今は逆にそういう仕様にラジオのほうが便利です。分周にしばられた9kHzステップなんてないわけですから。
こういう部分を書いた書籍を出しても売れないからでしょ?たぶん。
まぁ、私は仕事でやってた時期があるんで、いまさらそういう本はいらないですけど・・・。
ラジオの調整なんて製造ラインに並んでたくさんやりましたよ!主に調整をやるところの指導にあたっていたものですから・・・。
あと、ラジオとかやりだすと「トラッキングエラー」というものにブチあたることになります。こいつもなかなか悩ましいのです。
さらにAMラジオの場合、450kHzの中間周波の2倍にあたる900kHzで「うなるような音」が出ます。「トゥイート」って呼ぶ現象なんですけど、これも実に悩ましい!
それから、前に「スペアナ」の話がありましたけど、FFTアナライザと根本的に違うのは、横軸にあたる周波数をスイープさせるということで、現在「スペアナ」と呼ばれている製品でそういうモノは存在しないかと思います。
スイープジェネレータとオシロスコープをXYモードで使えば「スペアナもどき」なんですけど・・・。デジマースコープって知っていますか?あれはそのために使うものなんです。
ヤフオクなんかで「オシロスコープ」と勘違いして出品しているのを見かけますけど・・・。
こういうのを書き始めるとキリないですね・・・。
だから「浮世離れ」している・・・と言われたことがある私でした!
「国有時代は、それはそれはよかった」という話は私も中にいてよく聞きました。民営化してとんでもないものになった...。まさにその通りです。郵政なんかも同じですね。まだ完全に民営化されたわけではないけど、それでも今すでに中はぐじゃぐじゃのようですよ。
おやお仲間ですか。(^^)しかもEchoとは。これも拘りのひと箱ですね。でもいまじゃ探すのが大変じゃないですか?私のヘビーは筋金入りですからマイルドセブンスーパーライトを日に2箱超えますよ。
さてVFコンバータですが周波数パルスをカウントすればADコンバータになりますよねえ。
”一般的に言われる「PLL制御によるVCO」というのは、基準波とVCOの出力を比較してそのエラー電圧をVCOの制御電圧としてフィードバックすることを指します”
お!これって私のこの記事の説明そのものですね。ならばタイトルを「PLLの原理」とするよりも、「PLLによるVCO」とした方が的確なんでしょうね。具体的にはVCOを実現するためにバリキャップなどを使っていると。(テレビ、ラジオ)。どうやら「分周」が一つの大きなキーワードのようですね。「スーパーヘテロダイン」ですか、その昔名前は何度となく聞いたことがありますが、その正体を知らずして現在に至ってますねえ。というのも、最近の電気の本にはほとんど書いてない。「ラジオの製作」や「初歩のラジオ」が無くなってしまったのも、現在を象徴してるんでしょうねえ。
VFコンバータってAD変換器にも使えるのですよ!
で、一般的に言われる「PLL制御によるVCO」というのは、基準波とVCOの出力を比較してそのエラー電圧をVCOの制御電圧としてフィードバックすることを指します。
だから、電圧で発振周波数を可変できるものすべてがVCOなわけですが、ラジオとかテレビチューナーとかは「バリキャップ」とか「可変容量ダイオード」を使って構成したローカルオシレータをVCOにして選局を可能にしているワケです。
このあたりは「横浜・シントム(今はもうないです)」に勤務していたときに、まいにちおつきあいしてました。アメリカ向けBSチューナーの製造ラインを担当したのが勉強になりましたか・・・。
DDSっていうのがありますね?
これ使うと分周する必要がないのでいいんです。
でも、普通、コスト面で基準波を分周するために1Hz単位まできっちりとは指定できないのが現実です。
ラジオ・テレビの周波数割り当て表の周波数をよくごらんになればわかるかと思います。AMラジオってなんで9kHzステップなの?っていう疑問は「分周」にそのワケがあるのです。
それ以前に、「スーパーヘテロダイン方式」というものが前提なので、それを知らない方はそこからはじめないと理解しがたい内容となりますが・・・。
このあたりの話は「座学」でも充分に楽しめる(?)モノだと思います。
自分で書いてて思ったのです、やっぱり、イロイロやりすぎていたのかなぁ~?の感じた次第。
よくもまぁ、こんなにパカパカと内容がすぐに出てきたモノだ・・・でも、今はもう役に立たない状況にいますけどねぇ~、プログラマだし・・・。
国有時代は、それはそれはよかったのでしょうね!民営化でとんでもないものになってしまった・・・それはなんとなくわかります。
民営化になってから、親父と仕事をしてたことがあるという人と話す機会がありましたんで・・・。
コネがないとね、保線区のままで一生を過ごすハメになるわけです。というわけで、親父はコネで茨城から新潟まできたんですね、保線区も脱出して改札業務にまで・・・。
それはさておき、いまは「バイト」なんですか?ん、じゃ、私と同じですねぇ~!
しかもスモーカーまで同じです。昔は「ヘヴィー」そのものでしたが、今は1箱あけるかどうか?になっちゃってます。「Echo」ですけど・・・。
20代の頃と同じタバコなんだよねぇ~!
20代、実は親父の故郷「筑波山の麓」の近くに住んでいたのですよ!なんたる巡り合わせでしょう!まぁ、「縁」ということですね!
いろいろあって、思い起こせば「セカセカ」と過ごしてきた人生だったような気がします。寿命が短いのはそれのせいじゃないでしょうか?干支が「ねずみ」ですし(笑)!
kaoaruさんと私の歳はやはり非常に近接しているようですね。私の方が少し上かもしれない。早期退職が55歳ならそうです。
歴代61~62とはまた、あまりにも若すぎますねえ。健康と体力には私も自信はありませんが(ヘビースモーカーですし)、前職の垢がようやく落ちてきたので、もう少し生きたいなあ。
「旧J○R」もそうです。
これの場合は、中央を隠蔽したらモロ、そのまんまだなぁ~!(わざとそうしたんだけど・・・笑)
私の亡父は、そこで働いていました。電気関係は畑違いでしたけどね、親父の場合。
新潟駅の改札とかに親父がいると、なんかはずかしかった・・・。
今現在、私は親父がそこを早期退職した歳です。61で亡くなったんで、私もあとすこしかなぁ~?
歴代61~62に亡くなっている家系です。それは事実なんです。相続関係の都合で家系図作ってもらったんですけど、持っているのは私です・・・。
日本最初の原発、東海一号機が動いたのが1960年代後半。その時から311まで、私はすっかりテレビや新聞に洗脳されて原発は必要不可欠なものと思い込んでいました。ところが事故後いろいろ調べてみると、原発などなくても電力はまったく不足しない。原発のランニングコストが一番高い、つまり発電機としての性能は最低です。唯一原発にしかできないこと。それは、プルトニウムが取れるということなんですねえ。
「裏の世界の力」というものは、「表の力」がある以上、常に作用している。まったくその通りですね。
自分のところの非を1つでも認めると関係ないものまでみんな責任をかぶせられるからです。そういうところなんです。
そういう世界なんです。
「旧○○鉄工」の仕事ってそうなんです。
原発の電源用ディーゼルエンジンはそこのヤツです。「もんじゅ」のもそうです。
一部、そういう関係の仕事ありましたんで・・・。
プログラマと言えど、組み込み系だとそういうモノに関わることもありますね!
「ホントのことは何一つない」と思って聞いてましたけど・・・私はね!だから驚きもなかった。
「裏の世界の力」というものは、「表の力」がある以上、常に作用しているモノなのです。そういうモンです。
秋葉原はアキハバラであって、アキバという言い方は私もなじめません。言ったこともありませんね。かつて千葉に住んでいたころにはよく出かけた街でしたが。フロッピーディスクのプロテクト外しが趣味でしたか。やはりすごいですね。私はもっぱらマジックコピーのファイラーでした。(^^)
浮世離れというと、私はいままさに浮世を離れてしまいたい心境ですよ。福島原発事故の嘘を重ねた政府発表、マスコミ報道が発端でしたかねえ。
フロッピー自体のことは知識としてもっていても、もう役に立つことはないでしょう・・・多分ね!(例外はもちろんありますけどね!)
FMは単純にクロックとデータをシリアル化したものとかけあわせたものです。ここでいうクロックがキャリアになるわけです。別な言い方をすると「広帯域FSK」とでもなるのでしょうか?
細かいことはもう忘れましたが(^^;)、LOWレベルやHIGHレベルが連続した場合にビット反転させるのがMFMの特徴だったかと思います。
いずれも「復調」というのは「クロック」と「データ」に分けて弁別できる・・・ということです。
「弁別」という言葉を使いましたが、それを担うのが「データセパレータ」というヤツです。
秋葉原(アキバという言い方はなじめない私です^^;)に買いに行ったりしたこともありました。
CQ出版から出ていた「フロッピーディスクのすべて」とかももちろん買いました。
当時は「プロテクト外し」が趣味のようになっていましたね!
FDCというのはカウンタのバケモノです。
そういう意味ではCRTCと紙一重かもしれません。
FDDのモータが回らなくなったもので、手で回してシリアルデータが出てくるのをオシロスコープでトリガかけて観測したこともありましたよ!
そういう、バカなことしかやることがなかったのです・・・まさに「浮世離れ」ですか・・・。
単精度から倍精度、2DD、2HDとフロッピー全盛のころ、まだ20代だった私はそれを使うのが精いっぱいで、自分でディスクドライブをコントロールするなど思いもよらなかったし、スキルも当然にもありませんでした。歳月を経て心の故郷に帰ってきたような心境ですねえ。
CDのアルゴリズムにPLLの核心部ありということですね。VHDとはなんと懐かしい。カラオケ用のヴィデオディsスクとしてよく使われていたような記憶がありますが、すぐに消滅しました。あれはいったい何だったんでしょうねえ。
レーザーディスクはアナログのFM変調なんで除外されますが、デジタル方式のディスクはCDで理解しておくと応用が利くかと思います。
そういえば、VHDというレアなディスクを使っていた時期もあった!それではじめて買ったディスクが「浜田麻里」の「ブルーレボリューション・ツアー」の収録だった。それでファンになったんだよねぇ~!
それはさておき、CDやDVDもディスクですから、フォーマットや変調など、元をたどればフロッピーディスクにたどり着くわけですね。それ以前は磁気テープになりますよね。
kaoaruさんの資料庫のどこを探せば、和文PDFにお目見えできるのでしょうか?これでFMやMFMの何たるかがわかれば、ありがたいことです。
ただ、手法がデジタルなので詳細に入ると違うことになってしまうのですが・・・。
これを理解するには「フロッピーコントローラ」のFMやMFMを調べると早道です。
クロックとデータの重畳方法が所謂変調器とはやりかたがまったく違うんです。
EFMというのはMFMから発展した手法であった、と見ることができます。
これで、古いFDCのデータシートをひもとく意味も出てきますね^^;
私のところで和文のPDFを置いてますんで持っていってみてくだされ!
古いマイクロコンピュータの知識だけでも、こういうことができますね!だから、私は「オジサン」なのですよぉ~^^;
昔っから「女性」には縁がなかったけどねぇ~!(って、それは関係ないか^^;)
ここのサイトによるとEFM変調は読み取りエラーを是正するのが目的のようですね。
http://home.impress.co.jp/magazine/dosvpr/q-a/0006/qa0006_3.htm
このEFM変調を復調するときにVCOが必要になるわけですね。ということはEFM変調すると結果的に周波数変調したのと等価になるということでしょうかねえ?
カー用CDの製造ラインを担当したときに勉強したんです。
CDはご存知のようにEFM変調という方式で8ビットから14ビットに変換するテーブルで復調するわけですが、クロックとデータに分離するときにVCOが基準になるのです。
初期のCDプレーヤは16キロバイトのRAMにデータを先読みしつつデコードして音声信号に変換されるのですが、当時はそれだけで大変な技術だったワケです。
VCOですのでもちろんPLL制御です。
当時のサーボ系はアナログサーボだったんで広帯域のオペアンプをサーボアンプに使用していました。
現在はデジタルサーボしかありませんけど・・・。
仮にアナログであってもVCOの技術は今でも役に立つのです。だから勉強して損はないと思いますよ!
さてVCOですが、わたしは大胆にも「VCOとはVFコンバータ」だと断定したわけですが、実際どうなんでしょうねえ?
kaoaruさん,ホロンといい,リアルタイムのコメントだな。LINEみたいですね。(私は使っていませんが ^^;)
実は周波数シンセサイザの設計で,VCOだけ担当したことがあります。決まった回路があって,それほど設計に苦労は無かったけど,評価で温特の苦しめられた記憶があります。低温側です。
PLL全体の勉強が不足しています。オールディジタルが主流(?)ですよね。何か良い書物でもありますか?
PLLについては私はほんとに無知なのですが、そもそもFM変調が周波数変調(FSK)であることは一般によく知られていますよね。で、周波数変調された信号をどうやれば復調できるのかと考え始めたのがきっかけです。そしてkaoaruさんにもお話しましたが、ふと思いついたのかこの記事に添付している図です。「なんだ簡単じゃないか」とね。VCOがキーワードであることも知ってはいました。
しかし実際には簡単ではなくオペアンプを組み合わせて作れと言われてもたぶん私にはできないでしょう。ん?ホントにできないかな?一度やってみようかな。(^^)
しかしWebの質問サイトなどで「どうしても位相をロックできなくて困っている」という質問などもたくさんありますね。かなり難しいのは確かなようですね。
比較対象を分周するかどうかでも違ってきますし、弁別にアナログ・ラグリードフィルタ方式とかデジタルか?ってことでも違うし・・・。
まぁ、もっとも、今はDSPで処理しちゃうのが最先端ですけどね!
廉価版のPLL方式ラジオなら分周方式です。AMの9kHzステップというのはそこから決めたものですし・・・。
そして、そういう専用のマイコンが存在するところもその意味合いですが、そういうことにとらわれてしまうと自由な発想ができなくなる、そういうモノですしね・・・。
kaoaruさん含め,議論を深めませんか?
しかし広大なネット上の情報はむしろ毒リンゴの方が多いかも知れませんね。その中からキラリと光る宝物を見分けるのは、かなりのスキルが必要ですね。
私のブログのすべての記事もただのメモですよ。備忘録のようなものです。と言っても、昔の記事は自分で書いておきながら、いま読み返すとすぐには理解できないものや、大嘘を書いてたりするものもありますね。だから突っ込んでくださる方は大歓迎です。
(^^)
歳と共に「興味」や「感受性」が薄れていくのは仕方がありませんが、願わくば大切にし続けたいですね。
見てましたかぁ~、いやいや・・・これはどうも・・・。逆に恐縮してしまいます。
私のところはブログでもないし、そういう仕掛けを作っていません。ただのメモです。
でも、いろんなことに「興味を示せる」のはいいですよね!
「三角波をキャリアにしてアナログ信号を載せるとどうなるか?PWMになぁ~るじゃあ~りませんか!」
なるほどお、そうですよね。こういうシンプルな話ほど奥が深くておもしろいですね。分かっているようで実は分かっていないことも多いです。
kaoaruさんのサイトにも何度かお邪魔して、その膨大な情報量に圧倒されてしまいました。興味深い話がてんこ盛りですね。コメントを残そうとも思ったのですが、要領が分からず諦めました。
ともあれ、今後ともよろしくお願いします。m(_ _)m
いや、そういうモンなんです。
デジタルだろうとアナログだろうと「変調」の定義が意味するところは同じなのです。ただ、それに気づいてしまった・・・それだけのことなんですよ!
アナログ信号を三角波で変調・・・いやいや間違い!三角歯・・・じゃなくて三角波をキャリアにしてアナログ信号を載せるとどうなるか?
PWMになぁ~るじゃあ~りませんか!
ってな感じですかね?
実際には「変調」っていうほど大袈裟な話ではなく、コンパレータの入力が三角波と入力信号というただそれだけの話です。
でも、これはPLLとは直接関係ない話・・・でした。
PLLについては、私はいままでほとんど接する機会がなく、FM変調を復調するときに使うものだろうと、漠然と思ってきた次第です。そもそも高周波の経験が今までほとんどありませんでした。
ところが最近、XR2211というFSKデモジュレタICを使用している機器に接する機会があり、見事にFM復調している様子を見て感心してしまいました。
で、いったいどうやって復調してるんだろうと布団の中で考えながら、ふと思いついたのが添付のブロック図です。「なんだ、簡単じゃないか」てな感じでね。
(^^)
何か変ですかねえ...?
この分野はあまり興味を示す人がいないのかな?
身の回りはPLLだらけなのになぁ~?
ラジオだろうと地デジだろうと「チューナー部」のローカルOSCはみんなPLL制御してるし・・・。
とてもメンドくさかったのは、昔の仕事でスーパーインポーズのクロスカラーを解決するのにPLLでGenLockをかけてやろうと、東芝のTC5018でやっきになって実験してたっけ!
結局はPLLにしないで、緻密な4FSC(14.31818MHz)の調整にしたのです。トリマコンデンサだけで済むので、コストがとても安くつきました・・・。でも、不満でしたけどねぇ~!
まぁ、昔のことなんで、フィルタはもろアナログ!CとRでラグリードでした。今じゃ通用しない話ですけどねぇ~!
今や当たり前となっているPLL、つきつめてみませんか?
でも、誰も興味もたんかなぁ~?