2022年度熊取町予算編成にあたっての要望書
熊取町長 藤原 敏司 殿
2022年1月14日
日本共産党熊取町会議員団
坂上 巳生男・江川 慶子・ 鱧谷 陽子
貴職の日頃のご精励に敬意を表します。新型コロナウィルスのオミクロン株が世界中で猛威を振るっており、日本においても感染者が急激に増加し続けています。大変厳しい社会・経済状況が続く中で、熊取町は職員一丸となってワクチン接種の体制を整え、緊急生活・経済支援策を3次、4次と継続的に打ち出すなど、住民のいのちとくらしを守る立場で職務を遂行されていることは大いに評価するところです。
しかしながら、一方で住民の声を十分に聞かないまま西保育所民営化を断行し、コロナ禍における町制70周年事業に多額の予算を費やしたことは、禍根を残すものと言わざるをえません。
次年度以降も財政状況の厳しさは続くと思われますが、2022年度予算編成にあたり、蓄えられたふるさと応援基金を有効に活用しながら、住民の安全を守り、くらし・福祉の向上を図る町政の実現を願い、以下の項目について要望致します。
(一)地方財政の拡充を国に求め、民主的な町政運営、平和に役立つ町政をすすめる
1)憲法の民主的・平和的条項と地方自治法の目的・任務を厳守し、「地方分権」を本来の趣旨にそって、住民のくらしに活かす立場を貫く。地方自治を破壊する「道州制」の導入や広域都市圏構想に反対する。
2)会計年度任用職員制度や保育・幼児教育無償化による地方自治体の負担増については、地方交付税措置等によって担保するよう、国に強く求める。また、地方交付税の財源保障、財政調整機能を堅持するよう国に求める。「税と社会保障の一体改革」に反対し、消費税5%への軽減を求める。
3)行革のありかたを抜本的に見直す。
①職員削減計画は中止する。②煉瓦館・公民館など生涯学習施設は直営を維持する。③町立保育所の位置づけを明確化し、民営化計画を見直す。④窓口業務の民間委託は行わない。⑤ごみ袋など、料金値上げはしない。
4)ふるさと応援基金を有効に活用し、防災や子育て支援の拡充、コロナ対策など積極的活用を図る。
5)各種審議会等の委員公募を広げ、女性の登用をいっそうすすめる。会議、及び会議録は公開とし、会議録は要点筆記を改め、審議内容がわかるものとする。
6)住民や住民諸団体との意見交換を積極的に行い、「みんなが主役」のまちづくりに反映させる。計画策定段階からの住民参加を促進し、「自治基本条例」を制定する。
7)①「核兵器の廃絶と軍縮を願う平和都市宣言」の町として、核兵器禁止条約への参加を政府に求める。戦争展・戦争史跡見学などの行事を拡充し、非核宣言自治体協議会への参加など平和のとりくみをつよめる。
②憲法九条改悪を許さず、米軍普天間基地の無条件撤去、辺野古新基地建設の即時中止、戦争法(安保法制)の廃止、日米地位協定の抜本的見直しを国に求める。
8)男女共同参画プランを具体化し、子育て支援の充実、利用しやすい相談体制、講座開催による啓発活動など、積極的施策を行う。
9) 職員は必要に応じて計画的に採用し、防災・福祉サービス充実に努める。保育士・保健師など恒常的な職務は正職員を基本とする。サービス残業が発生しないよう、職員体制を整える。女性職員の勤務条件については、機械的な男女平等に陥らないよう、母性保護の観点から十分な配慮をする。職員が安心して働けるよう、休憩室の設置など職場環境の改善に努める。
10)常勤特別職職員の退職手当については一般職員に準ずることを原則とする。
11)工事・物品などの入札・契約については、公正性・競争性・透明性を確保すると同時に、工事の品質管理、下請け業者への指導を徹底する。第三者機関による入札・契約の執行状況のチェックを厳正に行い、談合の再発防止、公正な入札・契約制度の確立に努める。
(二)福祉・医療を充実し、住民のいのちとくらしを守る
1)府に「緊急小口資金」の貸し付け限度額の引き上げ・要件の緩和を求める。新型コロナ対応特例貸し付けの期限延長を国に求める。固定資産税などの公租公課に負担能力のない住民に対して町独自
の減免・減額措置を行う。
2)統一保険料の押し付けには反対し、国保会計への国庫負担の抜本的引き上げを国に求める。一般会計からの繰り入れを増やすなど、国保料の軽減に努める。国保料減免規定を住民に広く知らせ、多
子減免の創設など、新たな負担軽減策を国・府に求め、町としても検討する。一部負担金減免制度
のお知らせを広報紙等で実施し、生活困窮者の受診抑制を防ぐ。加入者の納付相談を丁寧に行い、
資格証明書の発行や差押えはしない。
3)インフルエンザワクチン接種に町独自の補助を実施する。
4)◎新型コロナ感染症対策としてのPCR等検査体制の強化のために、保健所、医師会、医療機関とも連携しつつ、町独自の検査推進体制を拡充する。
5)◎新型コロナ対応の国保料減免など、住民負担軽減につながる制度の周知を徹底する。
6)後期高齢者医療制度については、資格証明書発行などの事態が発生しないよう相談体制をつよめ、脳ドック補助が受けられるよう改善する。
7)水道・下水道料金など町の公共料金の値上げをせず、低所得世帯や福祉施設等への福祉減免制度を導入する。
8)①介護保険は、国の負担割合、介護報酬の引き上げなど、制度の改善を国に求め、町独自の保険料減免制度を拡充する。利用料減免制度を創設する。②要介護認定は、審査会の公正性を確保し、生活実態を反映した認定基準で判断する。③地域包括支援センターが役割を十分に発揮できるよう、町として公的責任を果たす。④国による利用者負担割合の引き上げ、ケアプラン有料化などの制度改悪に反対し、利用者の生活を支える地域包括ケアシステムの確立、介護サービスの拡充に努める。
9)介護予防の施策を推進し、サービスの質と量の確保に努める。そのための財源保障を国に求める。非営利のNPO法人などによる民間の地域福祉活動への支援を強める。
10)高齢者・障がい者・乳幼児など災害時要配慮者、避難行動要支援者の生活実態を正しく把握し、要配慮者支援・「見守り」をつよめる。
11)「熊取ふれあいセンター」が、名実ともに町の保健・福祉・医療サービスの中核施設となるよう、必要な職員の配置、土日開館など機能の充実に努める。会議室の音響(音の反射)を改善する。
12)老人福祉センターの改築を行い、入浴施設も整備する。
13)老人憩いの家は、町としての管理を継続し、老朽化した施設の耐震診断・改修を順次行う。高齢者の人口増に対応した施設の拡張(増築)も行う。
14)「障害福祉計画」の実施にあたっては、障害者の実態や制度改革などをふまえた具体化を行い、障害者施設の設立・運営が円滑に行われるよう支援を強める。障害福祉に関わる相談体制を強化する。公共施設、交通施設などのバリアフリー化をすすめる。
15)地域福祉推進の拠点である社会福祉協議会への財政支援、体制拡充を図り、精神保健福祉など、ボランティア養成講座を充実させる。
16)シルバー人材センターがその役割を十分に発揮できるよう、最低賃金に見合う単価の引き上げ等、町としての支援を強化する。 国・府に対して補助の増額を要求する。
17)中学卒業までの子ども医療費無料化の実施を国・府に求め、一部負担金の撤廃を府に求める。町の子ども医療費助成を高校卒業まで引き上げる。
18)町立保育所の安易な統廃合・民営化はしない。保育士を計画的に採用し、正職保育士の比率を高める。「3歳児配置改善加算」を活用し、保育士配置基準を見直す。給食の自園調理方式を検討する。
19)民間保育所の保育条件が十分に保障され、安定した運営ができるよう、町として必要な指導・援助を行う。私立幼稚園に対する就園補助など、支援を充実させる。
20〉「実費徴収に係る補足給付事業」を活用し、保護者の負担軽減をはかる。副食費無償化を継続する。
21)学童保育事業は、「NPO熊取こどもとおとなのネットワーク」との合意事項や協議を尊重する。現状の質を低下させず、子どもたちの安全といきいきとした放課後・働く親の権利が保障されるよう、財政支援・環境整備につとめる。大規模化に対応した施設整備、運営費の拡充を図り、指導員の処遇改善をすすめる。
22)ホームスタート事業、「つどいの広場」事業、ファミリーサポートセンター事業については行政の責任を明確にし、さらなる支援を行う。コロナ禍で住民生活が苦しくなる中、子ども食堂・フードバンクへの支援をつよめる。
23)子育て放棄・虐待など、子育てに関する「相談事業」を支える職員体制を更に充実させる。
24)「町営葬儀」は、委託業者には条例厳守を指導し、委託内容についても住民の意見をよく聞き検討・改善する。住民要望をふまえて、永楽墓苑に「合葬墓」の設置を検討する。
(三)緑豊かで、安全・便利・快適なまちづくりを
1)東日本大震災や熊本地震、大阪北部地震、多発する台風災害、豪雨災害の教訓に学び、「熊取町地域防災計画」を抜本的かつ実践的に見直す。
①地域ごとの自主防災マニュアル、避難所運営マニュアルの作成を積極的に支援する。
②避難所となる学校体育館へのエアコン設置、非常用電源など施設整備をすすめる。
③公共施設の耐震補強工事を早期に実施し、非常用電源や蓄電設備を整備する。
④豪雨災害を最小限に抑えるため、水路、河川、盛土造成地などの点検を強化する。
⑤防災行政無線の「聞き取りやすさ」を改善し、ジェイコム端末設置の補助を検討する。
2)原子力発電からの撤退と自然エネルギー中心への転換を国に求め、町として「原発ゼロ宣言」を行う。町内の原子力事業所・核物質取り扱い施設による事故の危険から住民を守る体制を整える。①国に原子力防災のための財源保障の強化をもとめる。②熊取町は、四施設に対して、安全対策の取り組み状況について定期的な報告を求めると共に、必要に応じて立ち入り調査を行う。③町職員の安全教育及び住民への科学的知識の啓発など、国と共に実施する。④住民参加の安全監視体制、住民によくわかる情報公開を行う。⑤原子力事業所の耐震性の強化など、地震防災対策を再点検する。
3)乱開発から住環境を守るため、ガケ地、急傾斜地の開発・建築の禁止、緩衝緑地設置の義務づけ、十分な駐車場の確保、開発途中の防災・安全対策など、開発指導要綱の規制を強化し、厳正な適用と開発指導の体制をつよめる。無秩序な住宅開発を抑制、公園や緑地・歩道を計画的に配置する。
4)永楽ゆめの森公園は、夏場の日陰、水遊び場の設置など住民要望に応えた改善をすすめる。
奥山雨山自然公園など既存公園の改修、維持管理(安全対策)に力をつくす。
5)まちづくりや開発事業については、過去の開発事業での教訓・問題点を生かして対処するとともに、「都市計画審議会」への公募委員の採用など住民参加をすすめる。町は、「開発者負担の原則」を厳しく適用する。
6)ひまわりバスは、利用者・住民の声をよく聞き、熊取駅への乗り入れ、フリー乗降制の拡大など、「改善」をすすめる。料金の無償化を継続する。
7)道路計画は、子どもから高齢者まで安心して歩ける道を増設することを第一目標とする。歩行者・自転車の安全を優先した交差点改良、歩道・路側帯の整備、路側帯のカラー化、横断歩道など路面標示の更新、歩道の段差解消、障害物撤去など交通安全対策をすすめる。住宅地内の大型車通り抜けを禁止する。生活道路については、住民の安全を第一に、町の管理・管理外にかかわらず、補修・舗装などの要望について積極的に対応する。
8)国・府に対して、岸和田南海線の事業促進、外環状線の全線4車線化、(旧)国道170号線の歩道整備、大久保東交差点の改良を強く要望する。熊取駅東交差点の改良をすすめる。「滑橋」の拡幅、歩行者安全対策を府に求める。
9)小型不燃ごみについては資源ごみのルートで収集できるよう改善する。再生利用できる粗大・不燃ごみのリサイクルを具体化する。可燃・粗大ごみ、産業廃棄物の不法投棄に対する監視・対策を強める。
10)公害企業の進出を認めず、公害は発生源で規制する。騒音・大気汚染についての監視・測定体制を強める。中小企業の公害防止のため、資金・技術・移転などの援助を行う。住宅に隣接する事業所の騒音・振動・悪臭に対する、町独自の対策を強める。
11)住吉川・雨山川の改修を府に求め、見出川など町内主要河川の改修事業を促進する。
12)下水道整備の事業費を増やし、整備を促進する。国・府の補助の充実・維持管理等への補助対象の拡大を求める。
13)町独自の「環境基本条例」を制定し、自然環境・生活環境の保全に関する行政・事業者・町民の責務を定める。
(四)ゆきとどいた教育をすすめ、文化・スポーツの振興をはかる
1)「日の丸」「君が代」のおしつけや、政治権力の学校教育への介入など一切の圧力を許さず、憲法の平和・人権・民主主義にそった教育をすすめる。町長は教育行政に介入せず、教育委員会の独立性を守る。学校間競争を激化させ、教師の負担をふやす大阪府のチャレンジテストに反対する。
2)教職員定数の改善を国に強く求め、町の予算で35人以下学級を拡大する。不登校・いじめ・学校内外での暴力・非行の根絶へ全教師、教育関係者が一体となって対処し、教師の増員、加配継続を府に求める。保護者、地域との交流をいっそう深め、協力共同の体制をつよめる。
3)トイレの洋式化、体育館のエアコン設置など学習環境を整える。生理用品をすべての女子トイレに設置する。印刷機や用紙など備品、消耗品費を十分に確保する。老朽化した給食施設の更新、エアコン設置をすすめる。
4)教材費・需用費を拡充し、クラブ活動費など父母負担の軽減をはかる。就学援助制度を父母に知らせ、その適用範囲を拡大する。就学援助の所得基準を維持する。学校給食無償化を継続する。
5)給食の民間委託については、安全性と契約内容が守られているか厳しく点検し、守られない場合は、直営に戻すことも含め再検討する。
6)子ども達の安全な環境を確保出来るよう、通学路や生活地域の危険箇所を点検し、対策をはかる。深夜のコンビニなど、子どもたちに悪影響をあたえる場所についての指導をつよめる。
7)小中学校の支援教育については、教師の増員・介助員の継続雇用など体制を整えて、すべての障害児に教育を保障することに努める。LD、ADHD等発達障害に関する研修を充実させる。
8)児童・生徒と父母の実情をよくつかみ、教師・父母・子どもたちの悩みに応える教育相談体制をととのえる。臨床心理士や発達診断のできる専門職を拡充する。
9)学校図書館司書は週5日勤務とし、待遇改善をはかる。必要な図書費を確保して学校図書館を充実する。
10)熊取図書館が町づくりの中核施設としての機能を維持できるよう、図書費を増額し、必要な職員を確保する。
11)文化・スポーツ団体が、いきいきと活動・交流できる場を配慮し援助する。煉瓦館のコミュニティ支援ルームについては利用者の意見を良く聞き、効果的な活用を図る。煉瓦館講義室の音響(音の反射)を改善する。コットンホール等の集会施設に難聴者用磁気ループを設置する。
公民館の大規模改修、町民会館ホールの建て替えにあたっては、利用者の要望を積極的に採用し、
エレベーター設置等、あらゆる年齢層、障がい者の利便性に配慮した設計とする。
12)ひまわりドームの指定管理者による運営については、利用者の意見が反映され、安全で利便性の高い施設になるよう、指導・監督する。シャワー施設など、利用者の声を聞いて改善する
(五)地元商工業・農業を守り発展させる
1)国・府に対し、地域産業と中小零細企業の救済と振興・雇用の安定などに実効性のある不況対策を求める。町としての緊急雇用対策・若年者就労対策をすすめる。町内金融機関に対し、商工業者・農業者への融資の確保を申し入れる。
2)「熊取町産業振興ビジョン」の具体化へ職員を配置し、商工業者・農家・消費者の声をよく聞き、推進へ努力する。産業活性化の固定資産税優遇策については、対象業種の拡大を検討する。産業活性化基金による制度融資の、農業者への拡大を検討する。◎新型コロナの影響で経営不振に陥っている事業者への独自支援策を継続・拡充する。
3)町内商工業者の経営相談に積極的に対応し、熊取町商工会等と連携してその解決に努める。制度融資の融資枠・利子補給の拡充に努める。
4)町が行う小規模事業や施設の修復は、町内零細企業・一人親方に優先して発注する。分割発注を広げるなど、地元業者の受注機会を確保する。国と府に対しても町内で行う事業については地元業者に発注するよう求める。
5)町の発注する事業については、下請け業者に対して価格・支払い条件など適切な契約がなされるよう指導を強める。公契約条例の制定について、近隣市との協同も含め具体的に検討する。
6)日米貿易協定やRCEP協定にはきっぱり反対し、日本の経済主権・食料主権を守ることを国に求める。
7)米価暴落に対する支援策を国・府に要望し、町の支援策も検討する。
8)国・府の制度を活用して、農業用水路・農道など営農環境の整備をすすめる。
9)家族農業を守り、後継者が希望の持てる所得補償・価格保証など支援策の強化を国に求め、後継者の育成と休耕地対策を講じる。
10)引き続き鳥獣被害対策をすすめ、被害対策補助金の個人への適用、猟友会の後継者育成など支援強化を行う。
11)農業収益や小作料を上回る不当な固定資産税の評価と課税をやめ、生産緑地制度の早期実施をはかり、農と緑のあるまちづくりをすすめる。農地に対する相続税納税猶予制度の農業用施設などへの対象拡大を国に求める。
12)農業用軽油の課税免除制度の恒常化を国・府に求める。
13)農と緑のある町づくりをすすめる。「防災農地契約」、「都市農地課税減免」などの導入を検討する。
14)学校・保育所給食については、「食育推進基本計画」による地場産30%、国産80%に照らした状況を確認し、近づける。産地直売所など地場産の販路開拓を進め、都市近郊農業の振興を図る。











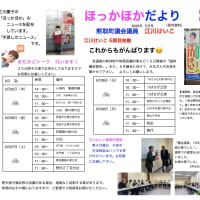

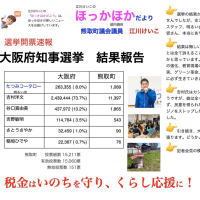





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます