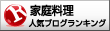最近意識して読書量を増やしている関係で,アマゾンなどを使用することも多くなってきました。この本面白そう,とか思うとクリック一つで3日もすれば手元に届いているのですから,便利というかなんというか。
それだけでも買いすぎてしまいそうなのに,そのうえ,わざわざ注文して1冊だけというのもなあ,と不要な員数合わせで目についた本を合わせて注文してしまう傾向があります。
「逆転の発想」と感心したのは,そうやって注文した本のうちの1冊に載っていた話です。
本は中年のための自転車入門みたいな本です。坂道で自転車のギアをどう使うかという問題です。
前に2枚,後ろが8枚でしたっけ。それだけでも16段ギアということになるのかな。坂道が急になってくると,フロントのギアを軽い方に変えて,そうするともう残りは8段だけ。坂道の続き具合を見ながら,少しずつギアを軽くしていくのです。
もうあと2枚しかない。もう少し我慢せねば,と必死に立ち漕ぎをしてみたり。
で,この問題には結構以前に,自分なりに結論はだしていたのです。ネットで買った1万円の重たいくせに一応折りたたみという自転車で柏崎原発の辺りの坂道や長岡から山古志に抜ける峠を登っていたころかな。そうやって残りの枚数を気にするのはいっしょですが,
最後の1枚を使い切ったら,あとは降りて休む。そのあと乗りたくなかったら押して歩く。
当たり前の話ながら,そう覚悟を決めてしまうとうんと楽になりました。
でも,その本に書いてあったことは同じ局面で発想が違うのですよ。
坂道のはじめから一番軽いギアにして,いくらなんでも軽すぎるという状態から状況に合わせたギアにだんだん重くしていく。
というものでした。
うん,これはすごい。逆転の発想だ。といたく感激したものでした。
「ただし失敗例かも・・・」と思うのは,実際試してみたら,毎日のように走るコンビニまでのコースでさえ,それは1番軽いところから2段くらいは重くできますが,すぐに脚力は限界。また軽くして,結局普段だったら登り切れるよりも軽いギアでかろうじてという結果。発想としては非常に良いと思うのですが,私がヘタレなだけでしょうか。
ところで,写真はコンビニまでのお買いものの途中の風景。このところ見かけなかったので,もうステーキになってしまったのかなと思っていたら,まだお元気そうだったので,自転車をとめて撮影でした。