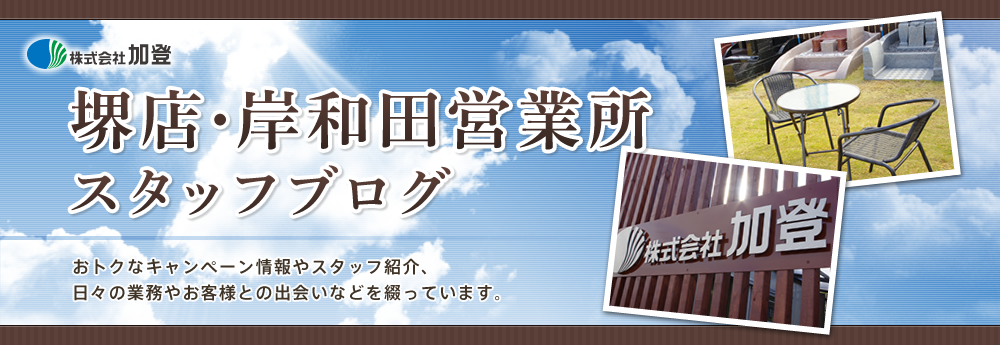地方の初盆@高知県
by |2017-07-17 13:31:43|
こんにちは、【鉢ヶ峯】加登堺店のマサキです。
祖母の初盆があり、高知県安芸市へ7月15日に行って参りました。
※余談ですが安芸市は昔阪神1軍のキャンプ地だったところです。

なぜ7月かというと下記をご参考下さい。
「2017年(平成29年)お盆とお盆休み。期間はいつからいつまで? 地域によって日程が異なるって本当?」はこちら
高知県なのか、安芸市がなのか、お寺がなのかははっきりとはしませんが、勝手に安芸市が旧暦の祀りなのかな?と思っております。
「新盆(初盆)」には何をするの? 服装やお布施、香典(御提灯料)、香典のお返しは?
お客様から一周忌と初盆を日が近いので同じ日に考えているんですけど、出来ますかね?なんて質問をよくお受けいたします。
実際関西では多く同じ日に行われてもいるようですが、
うちの曹洞宗のお寺では「一周忌より初盆を特に大切にするので、一緒にしてはならない。」
というお返事を頂きました。お寺様によって考え方や作法は違いますので、安易に考えずに必ず確認をした方が良いようです。
精霊棚や作法も少し独特でした。
「新盆(初盆)」の時期・読み方は? 盆棚(精霊棚)などどんな準備が必要?」はこちら

こちらがうちの精霊棚です
まず棚はスダレを使うように指示を受けました。
1段目 水棚(※1)に位牌を祀り左右に1対櫛に麩を飾り付けます。
2段目 本膳と果物、お菓子を飾ります。(写真には写ってませんが)透明な器に田芋の葉やキャベツレタスの葉を敷き、その中に洗米と茄子やニンジンを賽の目にしたものを混ぜた水の子(※2)と呼ばれるものを用意いたします。
3段目 左は海のモノとしてわかめ、素麺を、右には実りのモノとして野菜を飾ります。
真ん中には精霊馬です。よく見かける茄子(牛)ときゅうり(馬)で故人が足の速い馬で帰ってきて、足の遅い牛でゆっくり帰られるといわれます。
オクラやピーマンなども使って賑やかしてとうちでは言われました。そして16日には川へ流します。
精霊棚以外には

精霊棚の横の提灯以外にも、飾りました
これはお盆が終わるとお寺へ持参し焚き上げして頂きます。良くないものがつくからと説明を受けました。
それと玄関では

迎え火として松明(たいまつ)を燃やします

カワラケ台(※3)というものです
参拝者はまずしきみに水を捧げ、燈心を取り、火をつけカワラケ(皿)に置きます。
※1 水棚とは、お盆にご先祖様と餓鬼仏様(供養されていない仏様、無縁仏様)をお祀りし、供養する祭壇です。
※2 水の子とは、餓鬼仏様の供養に飾るもので細かく刻むのは、餓鬼の喉が針のように細いからであり、水に浸すのは、餓鬼が食べ物を口に運ぶと燃えてしまうからだそうです。お寺様も式中に庭に出て水の子を撒き、式後には川に流しました。
※3 カワラケ台に関してはあまりくわしくお伺いできなかったのですが、カワラケとは素焼きの皿のことで同じく餓鬼仏様の供養するもののようです。
故人様と一緒について帰ってくる餓鬼仏様を供養する事を重視した祀り方に感じました。

川に流す水の子

?
こちらは最後にお寺様から頂いたもので、名称は聞けなかったのですが「オンカカ カビサンマエイ ソワカ」と唱えながら川へ流すようにとの事です。
なかなか作らないといけないものも多いので用意が大変ではありましたが、所作が供養の形に繋がる例はとても多いと思いますので、これからも何でもかんでも簡略とせず継承していきたいものです。
【鉢ヶ峯】加登堺店の詳細はこちら
祖母の初盆があり、高知県安芸市へ7月15日に行って参りました。
※余談ですが安芸市は昔阪神1軍のキャンプ地だったところです。

なぜ7月かというと下記をご参考下さい。
「2017年(平成29年)お盆とお盆休み。期間はいつからいつまで? 地域によって日程が異なるって本当?」はこちら
高知県なのか、安芸市がなのか、お寺がなのかははっきりとはしませんが、勝手に安芸市が旧暦の祀りなのかな?と思っております。
「新盆(初盆)」には何をするの? 服装やお布施、香典(御提灯料)、香典のお返しは?
お客様から一周忌と初盆を日が近いので同じ日に考えているんですけど、出来ますかね?なんて質問をよくお受けいたします。
実際関西では多く同じ日に行われてもいるようですが、
うちの曹洞宗のお寺では「一周忌より初盆を特に大切にするので、一緒にしてはならない。」
というお返事を頂きました。お寺様によって考え方や作法は違いますので、安易に考えずに必ず確認をした方が良いようです。
精霊棚や作法も少し独特でした。
「新盆(初盆)」の時期・読み方は? 盆棚(精霊棚)などどんな準備が必要?」はこちら

こちらがうちの精霊棚です
まず棚はスダレを使うように指示を受けました。
1段目 水棚(※1)に位牌を祀り左右に1対櫛に麩を飾り付けます。
2段目 本膳と果物、お菓子を飾ります。(写真には写ってませんが)透明な器に田芋の葉やキャベツレタスの葉を敷き、その中に洗米と茄子やニンジンを賽の目にしたものを混ぜた水の子(※2)と呼ばれるものを用意いたします。
3段目 左は海のモノとしてわかめ、素麺を、右には実りのモノとして野菜を飾ります。
真ん中には精霊馬です。よく見かける茄子(牛)ときゅうり(馬)で故人が足の速い馬で帰ってきて、足の遅い牛でゆっくり帰られるといわれます。
オクラやピーマンなども使って賑やかしてとうちでは言われました。そして16日には川へ流します。
精霊棚以外には

精霊棚の横の提灯以外にも、飾りました
これはお盆が終わるとお寺へ持参し焚き上げして頂きます。良くないものがつくからと説明を受けました。
それと玄関では

迎え火として松明(たいまつ)を燃やします

カワラケ台(※3)というものです
参拝者はまずしきみに水を捧げ、燈心を取り、火をつけカワラケ(皿)に置きます。
※1 水棚とは、お盆にご先祖様と餓鬼仏様(供養されていない仏様、無縁仏様)をお祀りし、供養する祭壇です。
※2 水の子とは、餓鬼仏様の供養に飾るもので細かく刻むのは、餓鬼の喉が針のように細いからであり、水に浸すのは、餓鬼が食べ物を口に運ぶと燃えてしまうからだそうです。お寺様も式中に庭に出て水の子を撒き、式後には川に流しました。
※3 カワラケ台に関してはあまりくわしくお伺いできなかったのですが、カワラケとは素焼きの皿のことで同じく餓鬼仏様の供養するもののようです。
故人様と一緒について帰ってくる餓鬼仏様を供養する事を重視した祀り方に感じました。

川に流す水の子

?
こちらは最後にお寺様から頂いたもので、名称は聞けなかったのですが「オンカカ カビサンマエイ ソワカ」と唱えながら川へ流すようにとの事です。
なかなか作らないといけないものも多いので用意が大変ではありましたが、所作が供養の形に繋がる例はとても多いと思いますので、これからも何でもかんでも簡略とせず継承していきたいものです。
【鉢ヶ峯】加登堺店の詳細はこちら