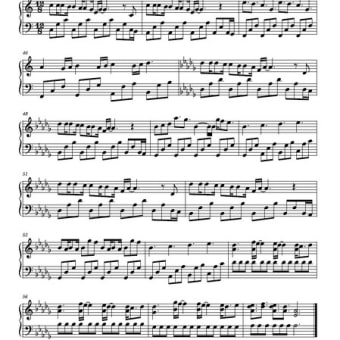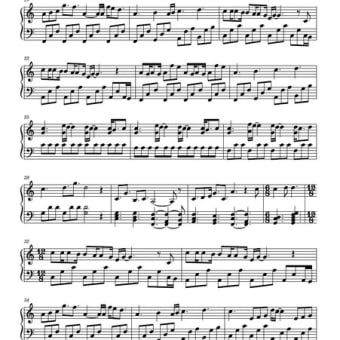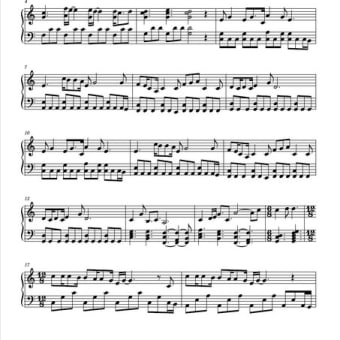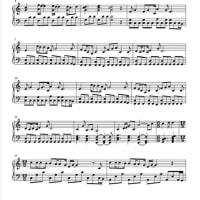スパコン開発凍結を論じている。
スパコン騒動についてわかりやすく書かれているが、
記事自体の主旨については疑問がある。
> 巨額の研究費を受けている研究者は、もう一度、人類や社会への
> 貢献という観点から、研究プロジェクトのあり方を見直し、
> その期待される成果について、市民社会に向けて、説得力をもった
> メッセージを出すべきである。
誰かがこうしたメッセージをもっともっと出すべきだ、
ということには完全に同意するが、
現場の研究者にそれを求めるのは損失が大きいと思うのだ。
それでなくても現場で活躍する優秀な研究者ほど、
プロジェクトの推進会議や評価用資料の作成などで
疲弊しているのが現状だろう。
特に、最近の科学技術の世界は
一刻を争う厳しい競争社会であり、
そんな呑気なことをやっていては確実に負ける。
従って、上記のようなメッセージを出すべき人は、
研究者ではなく、プロジェクト運営側だろう。
たとえば、JSTやJSPSに科学広報担当官やリエゾン担当者を
必要な数だけ置いて、そうした人々が、
必要に応じて研究者をインタビューするなりしながら、
きっちりと説明できるようにすればよいのではないか?
なぜそれができていないのか?
現状では、官僚や大企業の研究開発職をしていた人が
天下ったり天上がったりして、
そうした法人でプロジェクト管理の仕事をしていることが多い。
そういう人は、ある程度の年齢にも達していて、
新しい知識をしっかり吸収して説明するような仕事は
最初からあきらめている場合が多い。
具体的に何をしているかというと、
会議のロジスティックスとか、資料の適当な取りまとめ
(コピーして束ねる)などで、
あまり、専門的な知識が必要となる仕事ではない。
そうではなくて、もっと若いポスドククラスの人で、
科学広報の道に興味がある人を採用して育てれば、
人件費的にも、効果的にもずっと得だと思うのだが・・・
そういう人が歳をとったらどうするか?
より上級、大規模なプロジェクトの担当になってゆく道、
各種報道メディアの科学技術担当になる道、
地域や学校に密着した科学広報、普及を担当してゆく道、
くらいだろうか・・・
科学広報・普及全体の水準向上にもなるだろう。
そもそも、博士号を取ったからといって、
必ずしも研究職や大学教員になる必要は無いと思うのだ。
たとえば米国では、ファンディング組織などでたくさんの
博士号取得者が働いている。
プログラマと同じで、研究者の生産性は
人によって最大100倍くらいは違うだろう。
そして、新しいことの発見は基本的に厳しい競争社会である。
ある事柄について二番手はありえない。
研究者を志して博士号を取ったとしても、
研究者として一流にはなれない人が出るのはやむをえないことだ。
そういう人を無理やり研究者にしても、
引用されない論文や使われない特許、
冴えない学生が生産されるだけだ。
それよりは、早い段階で路線を変えて、
もっと社会の役に立つ仕事をしたほうが
本人のためにも良いと思う。
何度でもくり返すが、
真に優秀な研究者に研究広報の資料や
評価対応の資料を作成させるのは、
優秀なプログラマに営業させるようなもので、
ものすごい資源の無駄だ。
競争の激しいところほど、
適切な分業が重要になると思う。
最新の画像もっと見る
最近の「雑感」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事