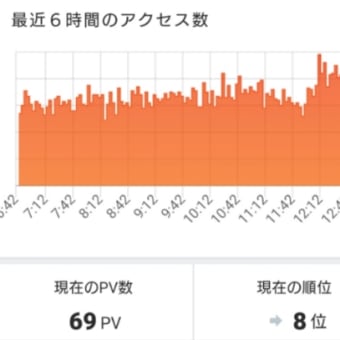北村紗衣 著『お嬢さんと嘘と男たちのデス・ロード ジェンダー・フェミニズム批評入門』文藝春秋/Kindle 版。ジェンダー、フェミニズム的な視点で映画や文学作品、事象を批評したエッセイなどをまとめた一冊。発売は今年の6月で、買ったのは8月10日。面白かったんだけど読むのに1ヶ月以上かかってしまった。
***
意図的にも無意識にも作品に表れている作家や監督のジェンター視点を、作品からすくい上げて指摘しているようなところが面白い。
企業の論理が人間性(特に女性)を圧殺する『アパートの鍵貸します』や、「男らしさの虚構性」を暴くタランティーノ映画、翻訳ものを映画化したうまさが冴える韓国映画『お嬢さん』など、具体的なストーリー解説もありわかりやすく楽しく読めた。ただ、批評とは関係なくこれらの映画をほとんど観れていない自分に若干落ち込んでしまうときもあり。
一方、『お嬢さん』の原作『荊の城』やブロンテ姉妹、ジェーン・オースティンなど、かつて読んだことがある小説の批評は素直に楽しく読めたかな。とくにオースティンの小説について、こう書いてあったのがすごく納得。
オースティンの恋愛小説は世界的に人気があるが、それは愛のために全てを擲つ情熱が描かれているからではない。人生でとんでもなく不愉快な相手と結婚しないよう気をつけつつ、金欠状態に陥らないためにはどうすればよいのか、ということを面白おかしく描いているところが人々の興味をそそるからだ。p162
で、「結婚は大変なビジネス」とか、「結局結婚するのだが、家父長主義的な結婚を極力避ける『ジェーン・エア』」といった論考になるほどなと。結婚が唯一のキャリアパスだった時代の小説だが、けっこうつい最近まで(もしかしたらいまも)変わらない面はあったかもしれない。
「ロミオとジュリエット」にスピード婚については、当時の社会規範が強く影響していたという指摘があり、私たちはジュリエットのような悲劇をつくらないために頑張らなきゃいけない、というポジティブな提言をしているところもよかった。
そのほか
「批評は独立した芸術なので面白ければ作品分析に妥当性がなくてもオッケー」(要約)「優生思想と接近したフェミニズム」「自分があるコンテンツから選ばれたというファンの感覚を表現した映画」「帝国と化すファンダム」
などなど、興味深く納得したり感心したり。とても真似できるものではないけれど、少しでもこういう鋭い切り込みで文章を書けるようになると良いなあと憧れる。