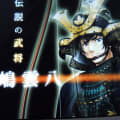前回ブログ記事の続きです。
関ヶ原の戦いの史跡巡りで、
岐阜県の垂井に出かけました。
まず南宮大社に参拝します。
関ヶ原の戦いの時、南宮大社のあたりは
西軍に属した外交僧、安国寺恵瓊の陣が
置かれていたと伝えられています。
神社の建物は戦火で焼失しました。

南宮大社の建物は、江戸時代になって、
徳川家により再建されています。
手水舎には、季節の花が色鮮やかに浮かび、
夏の期間、境内は風鈴が飾られています。
とても美しい神社という印象でした。
明治維新まで、この南宮大社と一体だった
神宮寺、真禅院にも立ち寄りました。
南宮大社からゆるやかな坂を登っていくと、
だいたい10分ぐらいで到着です。

このお寺は1300年もの歴史を持つお寺で、
開基は行基菩薩と伝えられています。
平安時代、平将門が乱を起こした時、
乱を速やかに鎮めるご祈祷をするよう
朝廷からこのお寺に依頼がありました。

そこでお寺の20人の僧が、四天王の秘法で
祈祷したところ、無事、乱が鎮まったとか…。
こんな不思議な霊験談が伝えられています。
関ヶ原の戦いの時は、南宮大社と同様、
兵火にかかり、建物は焼失しました。

やはり江戸時代、三代将軍家光の時代、
建物は再建、復興されたそうです。
古びた薄暗いお堂の中は、ひっそり静か…。
蝋燭に灯された火が揺れ、線香の香りが
漂っていて、信仰の寺らしい雰囲気でした。
ここまでやって来る人はほとんどなく、
華やかな南宮大社とは別世界のようです。
境内の樹木を渡る風がさわやかで、
ほっとするような静けさに包まれています。

南宮大社から朝倉山真禅院あたりには、
関ヶ原の戦いに参戦した武将の陣跡を
いろいろ見つけることができました。
南宮山に陣を構えたのは西軍の武将たち…。
安国寺恵瓊、毛利秀元、吉川広家です。

実は、吉川広家は密かに東軍と内通し、
毛利家を守るために和睦交渉を重ね、
戦いが始まっても軍を動かしませんでした。
吉川広家は最前線に陣どっていたので
その背後にいた西軍の武将は戦えずに、
関ヶ原の戦いは終わってしまったようです。

実際は、西軍の武将はいろいろな事情で、
戦わないで”見てるだけ”だったところが、
案外多いですね。それに気が付きました。
毛利秀元などは、南宮山頂の陣まで
ハイキング…。戦わずにのんきにお弁当を
食べていた(?)…との伝説もあるのです。
もちろん、後の世の創作に近いですが、
実際は、敵に調略されていたのでしょうね。

垂井駅には”戦国武将ロッカー”があった…!
残念ながら、”大嶋雲八のロッカー”はない…。
ほとんど戦闘に参加しなかった島津軍は、
西軍が敗走した後、敵に囲まれていました。
その中を今まで温存していたパワー全開、
猛烈な勢いで戦いながら、敵のど真ん中を
駆け抜けて、撤退していきました。
よく知られる話なのですが、このように
”見ていただけ”だった西軍の武将が、
みんな必死に戦ったら、関ヶ原の戦い、
勝敗はどうなっていたのでしょうか…?

ちなみに、わずか1500人(諸説あり)で
参戦していた西軍の島津義弘は、
「もし、うちの軍に5000人の兵がいたら、
この戦い、勝てたかもしれないなぁ~。」
…と3度も言ったと、伝えられています。
いや、島津家はお家騒動でドタバタしていて、
”5000人の兵”を関ヶ原に送ることが
難しかったという現実がありました。

”関ヶ原の戦い”での東軍の勝利は、
小早川秀秋の裏切りによるもの…。
…と、世間では言われています。
しかし、着陣しても見ているだけ…。
いろいろな理由があって、実際は
戦わなかった、いや戦えなかった
西軍の武将達がたくさんいたから…。
…と、いう理由もアリなのではないかしら…?