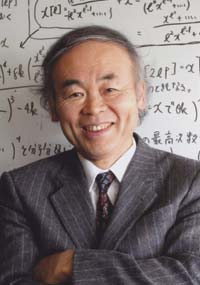- 正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現【Yahoo!ブログ 】さんの記事、長いので、抜粋して紹介させていただきます。(それでも長い…デス)

父親がアメリカ人で、家族全員が英会話ができ、小学生のときに外国人から英語教育を受けていたが、小学生の頃から今日に至るまで英語で話すことができないウエンツ瑛士は、日本の小学校での英語教育について、「何かが奪われるリスクも考慮すべき」と苦言を呈する。
http://www.sankei.com/smp/premium/news/141220/prm1412200003-s.html
【日本の議論】「英語」は本当に必要なのか 早期教育化の流れの中で大学関係者から漏れる「英語不要論」
2014.12.20 18:00、産経新聞
文部科学省の中央教育審議会で、子供たちが実用的な英語を学ぶ環境づくりを進める議論が本格的に始まった。平成28年度にも改定される新学習指導要領では、小学生高学年から教科として導入される見通しだ。高校でも討論や交渉力を高める方針が示されている。だが、英語教育の“抜本的改革”は過去幾度となく繰り返されながら、子供たちに英語力が身についたとの実感が乏しいのも事実。改めて考えてみたい。英語って本当に必要なのか-。
■「英語を話す必然性はないと思っている」と直言する短大関係者も
文科省は12月2日、「英検」や「TOEFL(トーフル)」などの民間資格試験を、大学入試に活用できるかどうかを検討する有識者会合を立ち上げた。席上、活用の是非とは別に、有識者から日本の英語教育そのものへの根本的な疑問が相次いだ。
「現在の日本の段階では、英語を話す必然性はないと思っている」
短期大学関係者を代表して出席した日本私立短期大学協会副会長の奥田吾朗委員はこう述べ、英語力の向上が短大生の生活に差し迫った課題ではないことに言及した。.
全国公立短期大学協会副会長の中村慶久委員も英語教育の改革を「えらく遠い話のように感じる」と話した。短大教育が医療や福祉、保育などの分野の比重を高める中で、英語教育の推進に対する教育者側の感覚的な違和感ともいえる。.
■子供は英語学習をどう受け止めているか
■中高生の半数…「英語使うことない」
子供たち自身は、英語学習をどのように受け止めているのだろうか。
ベネッセ教育総合研究所が今年3月に全国の中高生約6200人を対象にアンケートを行ったところ、中高生ともに9割以上が「仕事で英語を使うことがある」など社会生活での英語の必要性を感じていることが分かった。
一方で、「自分自身が英語を使うイメージがあるか」と尋ねたところ、中学生の44%、高校生の46%が「英語を使うことはほとんどない」と回答。調査を担当したベネッセ教育総研の加藤由美主任研究員は「日本の大部分の子供たちは教室の外に出れば、英語を使う環境にないのが現状。ただし、メディアなどにより『英語が必要』という意識はある」と説明する。
さらに学校での授業内容についても、中高の約8~9割が「英文を日本語に訳す」「単語の意味や英文の仕組みについて先生の説明を聞く」と回答するなど、受け身的だ。一方で、授業で自分の考えなどを英語で話す機会は中学2年の55%をピークに、学年が上がるごとに低下。高校3年の時点で26%にとどまっており、「授業での学びと、英語を使うことにも大きなずれがある」(加藤主任研究員)のが現状だ。
■財界は「企業が語学教育せざるを得ない」と嘆く
だが、教育界の英語教育熱は高まる一方だ。文科省が進める改革では、「読む」「書く」「聞く」「話す」-の4技能をバランス良く盛り込んだ実用的な学習環境づくりが喫緊の課題とされ、議論が進んでいる。.
12月2日の文科省の有識者会議では「(英語教育の)必然性はない」と述べた奥田委員らに対し、財界側から出席した日本経済団体連合会(経団連)の教育問題委員会企画部会長の三宅龍哉委員が「ビジネスにおいては必然性は高い。社員を海外駐在などへ送り出す際、(企業が)語学教育をせざるを得ない現状だ」と正反対の意見を述べた。
こうした実用的な英語力の必要性は、昭和30年に当時の日本経営者団体連盟(日経連、現経団連)が「会話力を身につける」などと要望を出すなど、これまで幾度も繰り返されてきている。なぜ、英語力は身につかないのか。.
元大学入試センター教授の小野博・福岡大客員教授(コミュニケーション科学)は「授業づくりの前提に、学習内容の差別をしないという平等主義があった。そのため、学校に習熟度別など効率的な英語取得法が取り入れられてこなかった」と指摘。その上で「社会情勢の変化により日本企業のアジア進出がさらに拡大したり、逆に移民を受け入れるなど、今後日本社会は変化を余儀なくされる可能性が高い。英語は必ず必要になる」と断言する。
■専門家は「能力や希望に応じた多様な学習の場を」と指摘
.
立教大は、平成28年度の一般入試から「英検」などの民間資格試験の活用を他大学に先駆けて決めた。塚本伸一副総長は「卒業生にその力量を身につけさせるためにも高度な英語教育は欠かせない」と話す。
立教大では平成20年、より実戦的な英語を学べる「異文化コミュニケーション学部」を新設すると、教養英語中心の文学部英米文学科の志願者が激減し、新設学部に人気が集中した。塚本副総長は「学生が求めていたものが教養としての英語ではなく、ツール(道具)としての英語だということが分かった」と語る。英語を遠いものと感じる生徒らがいる一方、英語を積極的に身につけたいと考える層も薄くはない。
塚本副総長は「高校進学率がほぼ100パーセントとなる中、(高校などの英語教育に)一律の基準を設けるのは無理があるのではないか」と疑問を呈する。.
小野名誉教授は「外交官や通訳など高度な英語力が必要とされる人たちと、アジアへ向かうビジネスマンらとでは、求められる単語数や発音などは自ずと異なる。それぞれの能力や、将来の希望などに応じた多様な教育の枠組みを作っていくことが大切だ」と指摘している。
>12月2日の文科省の有識者会議では「(英語教育の)必然性はない」と述べた奥田委員らに対し、財界側から出席した日本経済団体連合会(経団連)の教育問題委員会企画部会長の三宅龍哉委員が「ビジネスにおいては必然性は高い。社員を海外駐在などへ送り出す際、(企業が)語学教育をせざるを得ない現状だ」と正反対の意見を述べた。
経団連の三宅龍哉は「ビジネスにおいては必然性は高い」と主張するが、それは一部のビジネスマンにとって必要なだけだから今までどおりに必要な企業が語学教育をすれば良い。
義務教育において、全ての日本人児童に対して英語早期教育を受けさせる必要性とは全く関係のない主張だ。
必要な企業が必要な人材に対してのみ、ビジネスの実戦で使える英語教育をすれば良いだけの話だ!
私自身は、中学校から英語の授業を受けて大学卒業までは読み書きだけの英語教育を受け、大学を卒業してからも暫くは海外旅行以外で英語を使うことは全くなかったものの、30歳を過ぎてからビジネス(証券会社)で英語を使う必要が生じたために会社の費用でイギリスで3か月間の語学研修を受け、あとは独学とビジネスの実戦の中で英語を勉強した。
経団連に所属するようなグローバル大企業の社員なら、私などよりももっと若いうちから語学研修を受けて海外に送り出され、更にビジネスの実戦の中で英語力を付けていくのだろうが、今までどおりで何が悪いのか?!
経団連の主張は、一部の社員に必要な英語教育の費用を自分たち大企業が負担せずに、国民に負担させようとする利己主義に他ならない。
しかも、小学校での英語教育が、ビジネスの実戦で役立つとは到底考え難い。
>元大学入試センター教授の小野博・福岡大客員教授(コミュニケーション科学)は……「社会情勢の変化により日本企業のアジア進出がさらに拡大したり、逆に移民を受け入れるなど、今後日本社会は変化を余儀なくされる可能性が高い。英語は必ず必要になる」と断言する。
おいおい、冗談じゃない!
この小野博という馬鹿は、「日本が移民を受け入れるために、日本人は小学校から英語を学習しろ」と言っている!
どうして日本が移民を受け入れるために、全ての日本人小学生が国語(日本語)や算数や体育などの授業を減らしてまで、英語の授業を受ける義務を負わせられなければならないのか?!
そんなことなら移民を受け入れなければ良いだけの話であって、日本が支那や朝鮮やフィリピンやブラジルなどから来る移民のために、小学校で日本人が国語や算数の授業を減らしてまで英語を学習する必要なんて、これっぽっちもない!
それと、「日本企業のアジア進出がさらに拡大」とか言っているが、それについても上述したとおり、必要な企業が必要な人材にだけビジネスの実戦で使える英語教育をすれば良いだけの話であり、全ての日本人小学生に国語や算数の授業を減らして英語の授業を受けさせる理由とはならない。
小野博は、マジキチ理論を展開するな!

「日本が移民を受け入れるために、日本人は小学校から英語を学習しろ」とマジキチな主張をする小野博
>小野名誉教授は「外交官や通訳など高度な英語力が必要とされる人たちと、アジアへ向かうビジネスマンらとでは、求められる単語数や発音などは自ずと異なる。それぞれの能力や、将来の希望などに応じた多様な教育の枠組みを作っていくことが大切だ」と指摘している。
だから、それは上述したとおり、必要な役所や企業が必要な人材にだけ仕事の実戦で使える英語教育をすれば良いだけの話であり、全ての日本人小学生に国語や算数の授業時間を減らしてまで英語教育を受けさせる必要なんて全くない。
しかも、小学校での英語教育が、外交官や通訳にとっては勿論のこと、アジアへ向かうビジネスマンにとっても、それほど役立つとは思えない。
小学生の時点では、自分がアジアへ向かうビジネスマンになるなんて分からないのが普通であり、大人になってアジアに向かうビジネスマンになる可能性が高まってから英語を勉強すれば十分だ。

下村博文文部科学相
昨年、文部科学省が、小学校3年生から英語教育を開始する方針を固めた。
下村文部科学相も、小学校1・2年生から英語教育を実践している研究開発学校が相当数あると述べ、今後、英語学習の早期開始を検証して行くと話した。
しかし、小学校3年生から英語を始めても、将来の英語力は殆ど変らない。
むしろ、小学校3年生から英語の授業を導入するために、国語や算数や体育などの授業時間が減らされるわけだが、その損失の方が計り知れないほど遥かに大きい!
なぜ、小学校で国語や算数などの授業を犠牲にしてまで役に立たない英語の授業をするのか?!
日本人を滅ぼすためとしか考えられない。
小学校での英語教育は、「ゆとり教育」に替わる日本人愚民化政策だ!
せっかく長年にわたる文部科学省による「ゆとり教育」が日本人愚民化政策だったことに気が付き「ゆとり教育」が終了すると思ったらら、文部科学省は今度は「英語早期教育化」、「小学3年生から英語教育」で、日本人愚民化政策を続けるということだ!
現実的には、高校生とか大学生になってから、あるいは就職した後に英語を本気で勉強し始めても、十分に高度な英語を使う職業に就くことは可能だ。
日本人にも、20歳を過ぎてから英会話を習い始めて英語を使ってビジネスをしているビジネスマンや、英語の論文を読み書きしてノーベル賞などの栄えある賞を受けている学者が山ほど居る。
逆に小学校から英語を勉強しても、大人になって全く英語を話せない生き証人も枚挙に暇がない。

例えば、タレントのウエンツ瑛士だ。
ウエンツ瑛士は、父親がアメリカ人で、母親が日本人であり、日本育ちの日本国籍だ。
ウエンツ瑛士以外の家族は、全員が英語で会話をしていた。
さらに、ウエンツ瑛士は、小学生のときに外国人から英語教育を受けていた。
しかしながら、ウエンツ瑛士は、外国人から英語教育を受けていた小学生の頃から、今日に至るまで英語を話すことができるようになった例(ためし)がないという。

はっきり言って、小学校の英語教育なんて無駄なのだ。
無駄だけならまだ諦めも付くが、小学校の授業に英語を導入することによって、国語や算数や体育などの授業時間を減らされることによる損失は計り知れないほど大きい!
やはり、小学校の英語教育は、日本人の子供の国語や算数や体育の授業を減らして、日本人を愚民化させるための政策となる。
小学校の英語教育など、日本の子供たちや日本にとっては、むしろ弊害の方が大きいと考えるべきだ。
http://news.livedoor.com/article/detail/8812025/
ウエンツ、早期の英語教育に苦言
●平成26年5月5日のテレビ番組で、ウエンツ瑛士が早期の英語教育に苦言を呈した
●小学生のころから教育されたのに英語が話せない自身の経験から、意味がないと主張
●また、「興味をもて」という現行の英語教育のあり方を批判した
ウエンツ瑛士、小学校からの英語教育に苦言 「興味を持てって言われることは、一番子どもが興味持てない」「可能性が広がるっていうのもあるかもしれないですけど、何かが奪われるリスクも」
2014年5月8日 17時10分 トピックニュース
5日放送のテレビ朝日系バラエティ「言いにくいことをハッキリ言うTV ゴールデン未公開SP」で、ウエンツ瑛士が現在の英語教育について考えを語った。
同番組は、世間に言いにくい極論をゲストが紹介し、爆笑問題ら番組出演者が議論をするというもの。みずのメソッド・イングリッシュ・ランゲージ・スクール(MELS)主宰の英語講師、水野稚(みずのゆか)氏は「公立の小学校の正規の授業で英語教育を導入することには意味がない」と主張した。父親がアメリカ人で、なおかつ小学生のときに外国人から英語教育を受けたウェンツは、現在も英語が話せないことを理由に、水野氏の主張を「大賛成」とバックアップした。
水野氏は「子供の発達過程において、ある年齢を過ぎると、言語や行動の学習能力が衰えていく」という、アメリカの学者・エリック・レネバーグが唱えた「臨界期説」を持ち出し、「これが早期英語教育の科学的な根拠として採用されていた」と英語教育が導入された背景を説明。
続けて「臨界期説」の間違いを指摘した研究例などを挙げ、と「20歳から英語を勉強した人でも上手になっている、という研究もある」などと、早くからの英語教育の必要性に疑問を呈した、。
一方、東進ハイスクールの英語講師・安河内哲也氏は「早い時期に(英語を)始めるとチャンスが増えませんか」「やっぱり小学校から始めた子のほうがプロフェッショナルになっていく」と水野氏の意見に反論。英語学者の唐須教光氏も「敏感な時期っていうのは、小学生の時期ですよ」と、これを支持した。
これにウエンツは「俺、小学校からやって実際しゃべれてないっすからね」と水野氏の意見に同調。さらに「もっと言うと、父親がアメリカ人ていうアドバンテージがあったにも関わらずですよ」「小学校でやるよりもさらに小さい頃から(英語に)触れているわけですよ。だから触れるってのは、俺はそんなに関係ないと思う」と、早期英語教育に異論を唱えた。
さらに、水野氏が早期英語教育が原因で英語を嫌いになる子どもが増えていることを指摘すると、ウエンツはこれに補足する形で「他の教科って『学ばせる』ためなんです。英語だけは『興味持て』っていう学ばせ方なんですよ」「興味を持てって言われることって、子どもって一番興味持てない」と小学生からの英語教育に苦言を呈した。
その後も出演者らは白熱した議論を繰り広げたが、最後にウエンツは「小さい頃から(英語を)始めれば、好きな人も増えるかもって。もちろん可能性は広がるっていうのもあるかもしれない」と認めつつ、小学校英語が科目になることについては「何かが奪われるリスクももうちょっと考えた上で」と慎重論を唱えた。
上記の番組に出演して中心的に議論した、みずのメソッド・イングリッシュ・ランゲージ・スクール(MELS)主宰の英語講師・水野稚(みずのゆか)と、東進ハイスクールの英語講師・安河内哲也は、後日、さらに議論をした。
非常に長い議論なので、ポイントだけ抜粋して掲載する。
http://toyokeizai.net/articles/-/39987
論争勃発! 小学校の英語教育は意味がない!?
日本の英語教育を変えるキーパーソン 水野 稚(1)
安河内 哲也 :東進ビジネススクール講師
2014年06月18日テレビ番組「侃侃諤諤」「言いにくいことをハッキリ言うTV」(テレビ朝日系)で、英語教育について2回にわたり大議論を巻き起こし、スタジオとお茶の間を騒然とさせた安河内哲也と水野稚が、もう一度、東洋経済オンラインで場外乱闘。まさに犬猿の仲ともいえるこの2人は、今度こそ、着地点を見つけられるのか?
企業英語研修講師の水野稚と東進ビジネススクール講師の安河内哲也
水野 稚(みずの・ゆか)
Mizuno Method English Language School(MELS)代表
企業英語研修講師、大手英会話学校講師を経て、青山学院大学で国際コミュニケーション学修士号を取得。東京大学大学院博士課程にて英語教育政策を研究。在籍中にオックスフォード大学大学院へ留学し、応用言語学および第二言語習得専攻にて修士号を取得。現在は「みずのメソッド」を伝える教室を銀座と吉祥寺で展開しているほか、慶応大学や上智大学で教鞭を執り、「All About(オールアバウト)」の英語学習ガイドとしても人気を博す。単に「英語が話せる」だけでなく、国際教養人としてのマナーや、日本文化を発信するための英語力の習得を目指す指導法を採り、世界を目指す学生や一流のビジネスパーソンからの信頼も厚い。近著に『これだけで聞き取れる!英語リスニングたった3つの秘密の法則』(Gakken)がある。
<iframe src="http://rcm-fe.amazon-adsystem.com/e/cm?t=deliciousicec-22&o=9&p=8&l=as1&asins=405304104X&ref=qf_sp_asin_til&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
(一部抜粋)
水野:小学校の英語教育導入のそもそもの目的は、英語でコミュニケーションをしようという態度を養うということですよね。
そうなると、むしろ正確な英語の音声というよりは、外国人と会って、実際にコミュニケーションをとることが目的だったはずで、インターネットやタブレットをいくら使ったところで、今までのカセットテープやCDを使った授業とさほど変わりはなくて、結局はリアルなコミュニケーションに関する教育というのは、外国人教師に来てもらいやすい都市部などに集中してしまい、注目に値する変化というのは起こらないのではないかと思います。
音声を徹底的に鍛えたいということが目標ということであればわかるのですが、そもそもの目標・目的に安河内先生がおっしゃっていることは合致しないのではないですか。
それとオリンピックに関してですが、オリンピックというのは世界中がスポーツでつながる祭典です。経済的に豊かでも貧しくても、どの国もとにかく参加しようと。ですから、入場行進のときも「こんにちは」や「ようこそ」とそれぞれ自国の言葉で行進してもらってるはずです。
そういう場であるオリンピックを英語漬けにするというのは、そもそものオリンピック精神に反します。以前の東京オリンピックのときにも英会話ブームになった歴史もあります。オリンピックと小学校での英語教育をつなげるのは、どうかと思います。
水野:日本語もできず、外国語を学ぶ大変さもわからず、ただ英語ができるネーティブだからといって、教育学の資格もなく言語学も知らない人に、大事な初期教育を委ねるというのは、理解に苦しみます。
水野:でも、英語だけがどうしてそんなに特別扱いなのですか? 社会とか理科とか体育とか音楽とかありますが。そんなにまでして予算をつぎ込んで小学校で英語教育を行って、いったい日本の子どもたちをどうしたいのかという、哲学と理念が見えてこないのです。
水野:もうひとつ、やればできるようになる前提でお話をされていますが、算数でも理科でもどの科目でも、できる子とできない子と出てきますよね。安河内先生のお話では、英語だけはたくさんやればできるようになる、とおっしゃっているように聞こえるのですが。
水野:とはいっても、世の中の親御さんたちは、かなり色めき立っているのではないでしょうか。
安河内:そこは私も危険だと感じています。
■「すぐ話せるようになる」という世間の誤解
水野:今回のこの対談のポイントのひとつは、小学校のうちから英語をやることがなぜいいのか、ということに対する世間の誤解を解くことでもあると思うのです。小学校のうちからやっておけば「話せるようになるからいいんだ」と思っている人は、きっと多いと思いますよ。
安河内:それは違いますね。小学校でやったからすぐに話せるようになるわけではありませんね。
水野:それは違うんだと、もっとはっきり言ったときに、はたして世論が今の文科省の方針にYESと言うかどうかは、わからないですよね。自分が思っている、それぞれが思っている英語教育をやってくれると、きっと世間はおのおのが思い描いているのだと思います。
安河内:確かに私もそれは感じています。現在だと8年間、小学校低学年からの導入が実現したときには10年間の英語教育が終了したときに、平均的にどれくらいの英語力が達成されているのかというビッグビジョンが、人によって違う。このビッグビジョンを統一しないで、小学校での話ばかりをすると、誤解を招いてしまいますね。このビッグビジョンの目標とする到達点を明確にしていかなければなりません。
http://toyokeizai.net/articles/-/39987
小学校で勉強しても話せるようになりません
日本の英語教育を変えるキーパーソン 水野 稚(2)
安河内 哲也 :東進ビジネススクール講師
2014年06月25日
企業英語研修講師の水野稚と東進ビジネススクール講師の安河内哲也
(一部抜粋)
水野:小学校で英語を勉強させたってしゃべれるようになんかなりませんよと、ちゃんと言ったほうがいいんですよ。
水野:その特性を問うのは、中学生からではなぜ遅いのかということが、私は納得がいかないのです。
水野:小学校(5、6年生)から英語を導入したことによって、かえって英語嫌いの子どもが増えているというふうに聞いていますが。
水野:では、型を教えている今の中学校英語教育に、先生のおっしゃる「自動化訓練」を加えれば、事は足りるのではないですか。小学校の段階で、日本語もまだ固まっていない段階で、そんな高度なことを全員に求めるのは酷ですよ。
水野:今の時点でも、小学校の英語教育を学校で始めるとなってから、いろんな教育産業が動いていますよね。そういう動きが世論を形成して、「うちの子にもやらせないと遅れてしまう」「学校教育だけでは足りないかもしれない」という親心に付け込むことになっていませんか。
安河内:それがよい指導ならばやることに意味がないとは思いませんが、やはり英語だけが加熱しすぎることはよくはありませんね。
水野:今までの歴史を振り返れば、加熱してるのですよ、毎回。戦後もブームがあり、前回の東京オリンピックでもブームになり、英会話ブームが繰り返し繰り返し来ていて、来るたびに加熱し、その都度、ブームは終わっているのです。
http://toyokeizai.net/articles/-/41384
英語はいつから始めるのがベスト?
日本の英語教育を変えるキーパーソン 水野 稚(3)
安河内 哲也 :東進ビジネススクール講師
2014年07月02日
(一部抜粋)
安河内:水野先生は東大やオックスフォード大で勉強して、今は英語を教える仕事をされています。いわゆる英語の達人です。それで英語は中学からやればいいと言われていますが、ご自身は何歳くらいからどのようにして英語を学び始めたのですか?
水野:私は小中高はすべて公立の学校に通いましたから、特別な英語教育を受けたわけではありません。帰国子女でもありませんし、オックスフォード大学に留学したのは、大学の教員になった後です。特に英会話学校にも通っていたわけでもありません。ですから、独学の部分が多かったと思うのですが、私は、英語の達人では全然なくて、自分に必要な英語力を、ある程度、身に付けた人間ということです。
私の場合、難しい論文を全部読めるとか、すらすら書けるとか、海外の高校生向けのドラマを見て全部わかるとか、そういうことではありません。ただ、必要なものに絞っているのです。
では、どうして英語の発音なり、リスニングがある程度、できたかというと、これは向き不向きだと思っています。
■いつ始めるのがベストか
安河内:水野先生、話はがらっと変わるようなんですが、ズバリお伺いします。「じゃあ、どうすれば、子どもたちは英語ができるようになるのか」。これが親御さんたちもいちばん知りたいことだと思います。
「小学校でやらなくていいんです」と先生はおっしゃる。じゃあ、いつ始めて、今の公教育の枠組みの中でどのようにやっていけば、私たちの子どもはできるようになるのかと、これをぜひお聞かせいただきたい。
水野:始める時期ですが、いつがベストかというのは研究がされていないのです。英語を外国語として勉強することが、小さい頃のほうがいいとか悪いとかというのは、科学的根拠を示す前の研究がほとんどなされていない。文部科学省が国家政策として行うものに対して、ほとんど研究がなされていないということ、どうするのがいいのかまだわからない段階で踏み切ることが、まず問題があると言わなければなりません。
それを踏まえての個人的見解としてお聞き願いたいのですが、私は英語を始める年齢は、現状と同じ中学校からでいいと思います。
水野:言語的な距離感もありますよね。
安河内:それもあると思うのですが、では、韓国はなぜできるのか。言語的な距離感でいえば、日本語と韓国語は英語とは同じく対極にあるのにです。
水野:日本語と韓国語は近くて、対極に英語があるんですよね。韓国が英語ができるというのは、TOEFLの点数でおっしゃっているのですか。
安河内:TOEFLの点数は、韓国のほうが日本より受験者数は多いにもかかわらず高いということがあります。
水野:韓国の場合には徴兵免除ということがあるので、本気度が違いますよ。留学していたら軍隊に入らなくていいとなると、モチベーションはものすごい。
安河内:モチベーションの差が国民的英語力の差を生んでいる、と。
水野:でも、英語に対するモチベーションが低いということは、幸せなことですよ。テレビ収録(テレビ番組『侃々諤々』『言いにくいことをハッキリ言うTV』)でも言いましたが、夏目漱石も「それはいいことだ」と言っているのです。「独立国になった証拠だ」と。自分たちの言葉で英語を教えたり科学技術を教えたりというのは、独立国として自分たちの教育を自分たちの手に委ねられている、これは幸せなことである、と。
http://toyokeizai.net/articles/-/41385
オックスフォード卒の私は小学校英語に反対
日本の英語教育を変えるキーパーソン 水野 稚(4)
安河内 哲也 :東進ビジネススクール講師
(一部抜粋)
安河内:日本の国立大学、ほとんどの入試が“学者を育てるための問題”を出しているんですよね。その問題を解く人の中で、実際に学者になる人がどれだけいるのか。ほとんどの人は営業や製造に携わったり、グローバルビジネスをやったり、別の仕事に就くのに。
水野:ただ、国立大学の使命としては私は、それもいいんじゃないかと思うんですけど。
■子ども英語教室に通わせても、できるようにならない
安河内:親御さんたちに私がいちばん言いたいのは、子ども英語教室に週に1時間通っても、英語は「できる」ようになるはずがない、ということ。
水野:それ、共同声明として出しましょう。
水野:本音は結局、自分ができなかったから子どもにはできるようにさせたいというのと、小さな頃からの投資は回収したい。そういうことじゃないですか。心の底から子どもの立場に立ってると言えますかね。
安河内:現在の日本では、そんなに英語は必要ないかもしれません。でも、たとえば20年後くらいには必要になってるんじゃないかと、親は心配している部分も大きいと思います。
(略)
ただ、英語を絶対視して、英語ができないからうちの子はダメな人間だと決めつけるのはいけないと思います。ときどき「英語ができる人=すごい人」「英語ができない人=凡庸な人」という価値基準が見られますが、英語というのは人間の持っているたくさんの能力の単にひとつのもので、たったそれだけで人を裁くなんて、ありえないですよ。そういう点では、英語だけがあまりにも重視されすぎるのは、おかしいです。
水野:小学校から導入したら、ますますそれが加速するのではないですか。小学校から導入するほど重要になってくるんだと勘違いしませんか。
安河内:そこを正しく啓蒙していく必要があると思います。
水野:社会の一部の人だけ英語ができればいい、それはわかっているのですが、その一部の人にうちの子にはなってほしい、というのは親の勝手な願いですね。
水野:教育によって、たとえば一発逆転ができると考えるのは、親ならばアリだと思うんですよ。私も最初から東大、オックスフォードなわけではなく、最初は短大出です。それで1年、銀行員をしていました。そのときに世の中から受ける扱いが嫌で、これはトップとかセンターに行かないとダメだなと思って、東大やオックスフォードに行ったのです。
でもね、答えはないんですよ。親が知りたい答えはない。それは親御さんたちもわかっている。でも、もしかしたら、親御さんたちは、少しでも本音を言ってくれる専門家を探してる、ということですかねぇ。できないかもしれないと思っているところに、「楽しくやれば英語だってできるよ」と言われると、決心が揺らぐじゃないですか。希望は持たせられないかもしれないですけど、勉強ができない子はしなくていい、というのも、私は教育の大事なところだと思います。
だから、英語教育は、皆に必要なわけではない!と、できなくても構わないんだ!と主張します。これを言ってくれる人を探している親御さんも、けっこういるのではないでしょうか。
英語ができなくても、しっかり暮らしていけます。グローバル、グローバルとシュプレヒコールを上げているのは幻想です、と私は言ってあげて、安心させてあげたいです。
安河内:人間、いろいろな部分で生きているんですよね。
水野:でも、それでいいんですよね。
安河内:いいんですよ! 自分の立ち位置でそれぞれが社会に貢献しているんです。
水野:だから、やっぱり小学校から英語なんていらなくないですか?
安河内:……そこだけは平行線でしたか。
最後にもう一度はっきり言っておきましょう。小学校で週に数時間、英語をやったくらいで、英語がペラペラになるなどという幻想を持つと、また、英語教育に落胆することになるだけで、反動でめちゃくちゃになるでしょう。冷静に、じっくりと構えるべきです。
水野:これで失敗したら、もう立て直せないくらいの覚悟は必要。ここまで期待させちゃったら。
安河内:小学校で英語を学ぶようになったからといって、何か劇的な効果がある、ということではないですからね。そこまでではないはずです。今よりは、ちょっとよくなるくらいの期待はできるけれど、皆ができるようになるというふうに、国民的に期待すると、きっと落胆から来る反動で、またおかしな方向に行くでしょう。過度の期待によって振り子があっちに行ったりこっちに戻ったりして、めちゃくちゃになる可能性があります。
読めば分かるとおり、安河内哲也は東進ビジネススクールの講師なので商売のために「小学校から英語を勉強する方が良い」と主張しているだけで、説得力のある説明はできていない。
文科省が安河内哲也のような利害関係者を委員として集めて「小学校の英語教育の要否」を検討・議論させるのはおかしい!
安河内哲也のような利害関係者は、このような議論に参加させてはならない。
ちなみに、安河内哲也は、なぜか「韓国語能力検定試験1級」だ。

(その他参考)
【正論】お茶の水女子大学 藤原正彦 学ばせるべきは誇り高き日本の文化
2004/03/29, 産経新聞
■英語教育を小学校に導入する愚