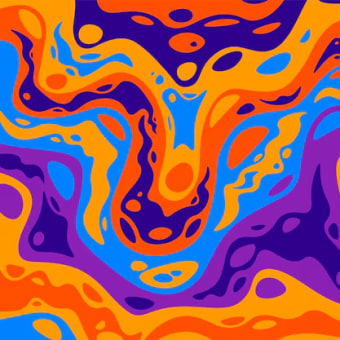▼▼▼
>昭和初期の日本人は「テロ犯」に同情した…「犬養毅首相の射殺犯」が死刑にならなかった危険すぎる空気
として、PRESIDENT ON LINEの記事をYahoo Japanニュースは、コレを取り上げた。
▼▼▼
昭和期に、軍部のテロ事件として1932年の515事件、青年将校に影響を与えた1935年「相澤事件」・相澤中佐が任地の仙台に向かう途中、東京で、統制派の永田鉄山少将・軍務局長を執務室にて、惨殺する事件がある。
515事件では、同情論があってか、極刑は免れたが、相澤事件では単独犯行という背景もあってか、銃殺刑になる。
この明暗が、後の226事件の決起将校の心理の片隅で共有されていた可能性は否定出来ないはず。
さらに、515の首謀者の一人は、戦後実業界(建設)に身を投じるも、1961年には、クーデター未遂事件になる「三無事件」で警察当局の摘発を受けた。
▼▼▼
「テロ犯」への同情の風土的要素には、日本三大仇討ちとして、「曽我兄弟」「赤穂浪士」「荒木又右衛門」があって、これがやがての時、いつからか、縁起物の「一富士、二鷹、三茄子」という言葉に残されたと言われている。
奈良の事件で、起きている同情論は、現代社会では如何に、軽薄浅慮なことかは、昭和のはじめのテロと比較できても、「一富士、二鷹、三茄子」に及ぶ範疇のものではないのは明らかで、冷静さを保つべきだ。
▼▼▼
相澤事件では単独犯行で死刑、515事件では同情を集めて極刑無し。
— katsukazan@世界は価値観対決による衝突➡激突に化学変化中 (@asanai106) November 15, 2022
226決起将校はこの空気を認識していたかも知れない。
昭和初期の日本人は「テロ犯」に同情した…「犬養毅首相の射殺犯」が死刑にならなかった危険すぎる空気(プレジデントオンライン)#Yahooニュースhttps://t.co/v1FyPc7zaa