なにかと、雑用というか、雑文の執筆に追われる日々で、生来の怠け癖と、やる気のなさと、ルーズさの所為と、そんな状況にあっても、チャンスがあれば速攻、旅人になりたい性癖とが相まって、ズルズルとブログをご無沙汰してしまった。
ありがたくも、こんなしょうもない拙文を読んで下さっている方々には、本当に申し訳ないと、思っている。(いつも言い訳ばかりで生きている私です。)
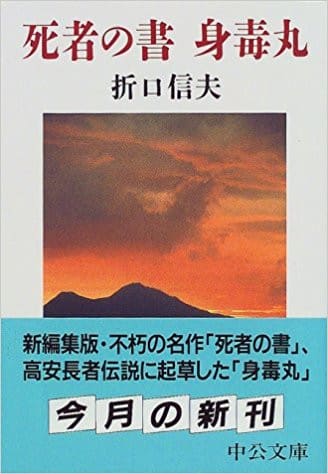
いつか、『死者の書』について、
〈まれびと〉について、
書いてみたいと思っていた。
折口が『死者の書』で綴っている、大阪府太子町と奈良県葛城の境にある二上山には、何度も登った。
二上山は、葛城の都から見ると西方になり、大津皇子のお墓がある。
その山麓には、中将姫の曼荼羅で有名な当麻寺がある。
中将姫は、藤原郎女と言われている女性である。
『死者の書』は、この二人のドラマティックな悲劇を語っている物語である。
当初、『死者の書』を読んで、二上山に行ったのではない。
なんとなく、二上山が、黄泉との結界の山だいうことを、認識していたように思う。
仕事で太子町に、数年にわたり何度も訪れて、知人のお子さんの小学生2年生だった女の子に伴われて登ったのだった。
太子町では、小学校の遠足で、二上山をホイホイと登るというのだ。
ゼイゼイ言いながら、登ったら、山頂に、大津皇子のお墓があった。
東の方向に葛城があった。
それから、暫く経ってのち、折口信夫の『死者の書』を読んで、私は衝撃を受けた。
7年ほど前まで、10年間ほど毎年のように行って登りもしたあの二上山の、大津皇子の物語で、当麻寺の中将姫の物語だったのだ。
そんなこんなで、この度、〈まれびと〉について、評論を書く機会があり、あらためて10数年ぶりに、折口の『死者の書』を、読んだ。
あらためて、新鮮な感じで読んだ。
そして、今年は、久しぶりに太子町を訪れてみようかという気持ちになっている。
あの時の小学生だった少女は、高校生になっているらしい。
<余談>
中将湯というものがある。
漢方の煎じ薬だ。
私の子どもの時に、家の戸棚の中に、中将姫の絵が描かれた紙の封筒が入っていた。
その封筒の煎じ薬は、いつもストーブの上の土瓶で煎じられていた。
その匂いが、今でも思い出される。
当麻寺へ行って、かの有名な曼荼羅よりも、中将姫が描かれた図に、驚いたものだった。
戸棚の隅に置かれていたあの中将湯の絵だったのである。














