各国を旅して(英語教師しながら)言語体系の地域ごとに分けた 体験記を出したら面白そうだな。 タイトルは 言語と見え方 。抽象的。
日本語には日本語ならではの視点・世界観がある 文化態度伝統歴史なども含まれている 英語にもあるだろう。 スワヒリ語にもあるだろう。 視点こそが本質ではないか。そしてその本質を取り出すのは困難だが、挑戦し甲斐がありそう。そしてその本質は、究極的に言えば、翻訳不可能なもので、その本質が生み出される場所で、体験的直接的に理解するほかない。と思われる。
言語と態度の関係っていっても 具体的に何に対する態度なのか? そこを明確にしないと 修論の問いを立てられない。
英語を使うと 態度がもっと 積極的になるんだよね、 という感覚があったとする。何に対する態度が変化するのか? 人に対する態度? 人とのコミュニケーションに対する態度? すごくあいまい。たとえば知らない人に話しかける抵抗が少なくなる、という印象はあるかもしれない。けどそれって言語の影響なのか?英語を使うことで、シンプルで直感的な表現を使うことで、一般に人々のもつ話しかけられることに対する抵抗感の少なさを仮定して、Hiの一言で扉が開く的な、それは文化によるものなのか? 日本語で知らない人にいきなり話しかけずらいといえるか? もしそうだとしたらなぜか? そもそも日本では文化的に知らない人に声をかける習慣がない? 変な人かもしれないから危険な行為(いきなり話しかける)は慎むべきだから? 大阪と東京ではまた話が違う? なぜ違う?
たとえばアフリカにいる現地の住民にインタビュした映像があって、現地の言葉を話すのだが、時折英語が混じる。これは英語で表す単語(例entrepreneurなど)に相当する母語が存在しないためと考えられる。日本でもcommunicationという言葉は日本語的にコミュニケーションという言葉で広く普及している。これもこの単語に相当する日本語表現がないため、また、そういった内容を表す概念、考え、態度自体がないため、ともいえる。逆にアフリカの言語における◎☆△という単語があったとして、それに対応する訳語が英語や日本語など他の言語に存在するとは限らない。そもそもそれに相当する概念がないから。英語で、「いらっしゃいませ」「お疲れ様です」などを訳すのは難しいのではないか。"Next Please?"は違うだろうし、"You hard working man"もなんか違う。いらっしゃいませを 無理やり 日本語直訳すると ご来店ありがとうございます ぐらいになるとして、 それを英語にすると Thank you for coming to the shopぐらいになるのか、英語として不自然な気がするし、そういうことを言う、表現する、習慣、文化が、たとえばロンドンのスーパーマーケット、レストラン、デパートにないと思われる。
つまり「いらっしゃいませ」、その言語表現以前に、相当する態度文化規範がない環境のなかで、その言語を理解してもらうのはとても難しいし、必要もないかもしれない。しかしだからと言って その表現が価値がないというわけではない。たまたまある文脈から出た言葉が別の文脈にはなじまない場合があるというだけだ。 ただ英語が支配的なこの現代世界では 英語を頂点とする言語間階層があることは否定するは難しいかもしれない。 英語が世界におけるビジネス政治経済学問における中心言語となっている以上、英語のもともと持つ規範価値観文化態度も必要以上の価値をもって見られる場合があるかもしれない。 たとえば、スワヒリ語話者が何か話すとき、母語にない概念を話すときに、どうしても英語を部分的に使ってしまうことになりやすいだろう。英語に合わせなきゃいけない状況。逆のパターンが想定しにくい。言語が価値づけされ、効率の名のもとに滅ぼされてしまう可能性がある。英語話者がなにか話すときに 英語にない概念・単語を話すとき、スワヒリ語にその対応表現があったとして、スワヒリ語を部分的に交えて、話す、というような状況もあってよいはずだ。だが現実には前者の割合が校舎に比べて圧倒的に多い。
日本語話者が何か話すときに 人とのやりとりが大事だよね。とか言ったときに、人とのコミュニケーションが大事だよね。と言った方が(なんとなく)受け入れられやすそうな感があるのではないか。なんかプラスのイメージがあるような。「危険性を考えて、計画を立てましょう」もしくは「リスクを考えてプランニングしましょう」これもなんだか後者のほうが現代風というか、できるビジネスマン風が漂ってないだろうか?考えすぎかな。 ひとつ面白いのは かわいい Kawaiiという単語が英語圏でも通用することである。(Sushi, Ramen, Manga, Akihabaraなどもそうか)こういう特異な文化的特徴が元となって言語そのものが国外に輸出される場合もある。ただやはり取り込む量が多い気がする。
17:58 ひとす 外来語で塗り固められた母語は悲しい。経済効率はあがるかもしれないが単純に悲しい。文化や精神性が失われる可能性がある。僕はこの文をなるべく英語を使わず表現しようとしてきた。英語を使うなら 韓国語 アラビア語 スワヒリ語 フランス語を同じように交えたっていいはず! (実際そんなことしたら混乱を生むだろうけど)アフリカにおけるいわゆる知識人や国の指導者たちが現地の人向けにスピーチしているのをみると、やっぱりところどころ 英語(もしくはフランス語)の表現が混じっているのが聞き取れる。それは多くの国が英仏の植民地だったからという歴史があるのだが、国の発展の基礎を 自国起源の母語でなく 他国起源の外国語 で説明してしまおうとするところに なんともいえない気分になる。英仏の後を追って、世界の多様性がまた一つ損なわれるだけといったら心配しすぎだろうか。
多様性と言っても 制限は必要かもしれない。なんでもありというわけにはいかない。過激なテロ組織はやはり、許されるべきではないし、過剰な憎悪表現、ヘイトスピーチも一定の規則は守るべきである。でないとすべてを許したら、なんでもありの無法状態になってしまう。
いろんな考えがすばらしいね。とかいってても。やはり同じ教室に武器を大量に持ち込んで授業を受けようとする学生がいたら、やはり、帰ってほしいと思うし。公共のルールというものは存在する。最低限の規制は必要だけど、どこで線を引くかは難しいところだよね。
"











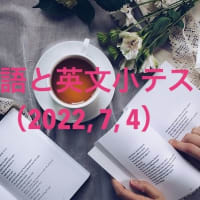

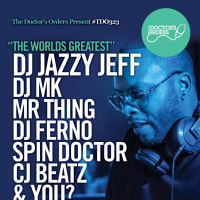

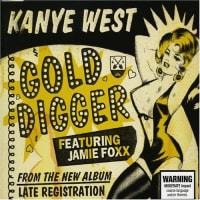




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます