東京から茨城へ引っ越す前、
骨董市(門前仲町、目黒不動尊、新井薬師、東郷神社などなど)で
値切りながら買い集めた「古民具」や「農民具」たち。。
その中の一つ「滑車」を取り付けました。

何の滑車かと言うと水を汲み上げるための
「つるべ井戸」。
なぜなら、
地下水が低下しているから。
東京から茨城に引っ越して11年。。
これほど地下水位が下がったのは初めて。
普通なら、冬が一番水位が下がると思うのですが、
茨城地方はここ1ヵ月位雨がまとまって降らないことが原因か?
それに伴い、30年以上使用してきたと思われる浅井戸用ポンプが
水を汲み上げようとすると同時に
地底に溜まっている泥や砂が詰まってしまい、
水を吸い上げなくなり、使用不可能に。。




ここで試されるのが
「百姓力=生きる自給率1%Up」

浅井戸の本来の使用の仕方?滑車で汲み上げる「つるべ井戸」にしてみたり、
ハシゴを縄ロープで3脚つないで8メートル下の井戸の底に入ってみたり、
ホームセンターやポンプのメーカーに勉強しに行ったり、
2週間かけて、
命と生活の源「水」と向き合いました。

地下水位を測る、地盤の構成、ロープの素材、長さ、滑車の力学、
身体の使い方…地理、物理から身体論体育まで、まさに
「Agriculutural Active Learning(AAL)
アグリカルチャラル・アクティブ・ラーニング」
(問題解決型の学習“農”力)※Jinendoの造語
こども百姓「じねん童」いろは&ふうかにとっても、本当に
「生きることに直結した」夏休みの宿題となった
ことと思います。
本当に他人事ではありませんよ!
水のこと、地球のこと!!
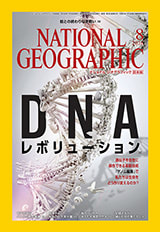




使い古された言葉としてではなく、
普遍的な古典の言葉として
Think Global,Local Adct!!
「百姓力=生きる自給率1%Upをはじめよう!」

こども百姓「じねん童」いろはの
“学校に提出する”夏休みの宿題「立体作品」には、
新たに『つるべ井戸』が加わったようです。。 





















