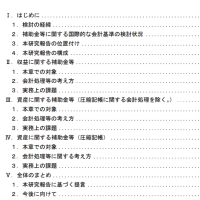(前編)9億円超が着服された可能性…!「史上最悪のマンション管理費横領事件」犯行のヤバすぎる手口
(後編)9億円超の着服が確認された「令和のマンション管理費横領事件」実は、あなたのマンションも狙われている可能性
マンション管理組合から預かっているマンション管理費の着服事件を取り上げた記事。
最初に挙がっているのは、上場会社である「ビケンテクノ」の事件です(→当サイトの関連記事)。
「巨額の着服は、どうして発覚したのか。本誌の取材に対して、同社の従業員が当時の状況と発覚の経緯を明かす。
「Xさんは長年この会社に勤めていたベテランです。60歳で定年を迎えた後も管理職待遇で再雇用されて、マンションの管理組合と向き合う仕事を担当されていました。そのXさんが、'23年の10月頃に突然『調子が悪い』といって会社に来なくなったんです。
その直前に、何人もの従業員がXさんから投資の勧誘を受けていた。だから欠勤が1ヵ月を超えた頃、Xさんと完全に連絡が取れなくなると、『カネがらみのトラブルが起きてるんじゃないか?』と疑いが生じ、社内で調査が始まりました」
調査の結果、同社が管理している複数のマンション管理組合口座から、管理費が引き落とされていることが発覚した。その総額は、約9億1000万円。」
不正の手口は...
「着服手口は現在調査中だが、おおよそ以下のようなものだ。
マンションの管理組合から印鑑と通帳を預かっていたX容疑者は、「払戻請求書」(各マンションで修繕などが必要になったときにおカネを下ろすために銀行に提出する書類)を偽造し、印鑑を押して銀行に提出。現金を受領していた。定期的に行われる住民との「管理組合総会」では、口座残高の部分を偽装した報告書を作成し、おカネが減っていないように見せかけていたという。」
マンション管理コンサルタントの話。
「...別の事件では、こんな手法が採られました。管理会社の担当者が『マンションの水道の給排水設備の修理にこれだけのおカネが必要です。だから、管理費から出しますね』と、伝票を書いてマンション管理組合に提示する。組合は疑うこともせず『定期的な修理は必要だし、このぐらいの金額は必要なんだろう』と、管理会社の提案を了承し、組合の承認印を押してしまった。
ところが、管理会社の担当者は伝票の金額部分を『消せるボールペン』で記入していたんです。管理組合の承認印をもらったあとで、その金額の桁を二つ書き換える。それで銀行から、本来必要な修理費より二桁も多い金額を引き出したのです。ポンプ修理に必要な代金は支払って、残りを自分の懐に入れてしまった」」
管理組合理事長による不正も...
「悪事に手を染めるのは管理会社だけではない。平成最大の着服事件としてマンション業界で語り継がれている「南魚沼着服事件」は、住民たちでおカネを管理していたのに巨額の横領が発生してしまったケースだ。
'16年冬、新潟県南魚沼市の大型分譲リゾートマンション「ツインタワー石打」の組合理事長が、総額11億7800万円の管理費を着服していたことが判明した。
理事長はそれを金融商品の購入や株への投資に使っていたが、結局投資に失敗。組合の預金が底を突いたところで住民らに着服を告白した。その後、組合が警視庁に告訴状を提出したことで、逮捕された。
この件も手口は極めてシンプルで、理事長は自分が管理していた組合の預金通帳と印鑑を使い、銀行に「修繕のために必要」と言って繰り返しおカネを引き出していた。」
この理事長は、当時、会計士で、大手監査法人Sの元パートナーだったといわれています(→当サイトの関連記事)。11億円という記録はまだ抜かれていないようです。
専門家によると、管理会社や理事会まかせなのが問題なのだそうです。
「マンションのトラブルなどの相談業務を行う「マンション管理組合支援センター」の有馬百江代表理事は「着服する側に問題があるのは言うまでもないが、区分所有者である組合員がマンションの管理を『面倒くさいから』と、すべて管理会社や理事会任せにしていることが根本原因」と指摘する。」
具体的な防止策は...
「マンション管理コンサルタントの土屋輝之氏は、「着服等の不正を防ぐためにも、少なくとも通帳の残高確認は住民たちで定期的に行ってほしい」と提言する。
「毎月とは言わずとも、年に数回は住民の方々が通帳を確認する機会を作るべきです。それもコピーや『報告書』のような形ではなく、原本で。
一番良いのは、管理費の運営にもデジタル通帳を導入することです。おカネの出し入れはできないように設定して、残高はアプリ等で住民全員が簡単にチェックできるようにする。こうして管理会社、あるいは理事会に対して『いつでも住民に残高を確認されている』と思わせることで、着服を防ぐ抑止力になります」」
先日の日経でもマンション積立金の横領問題を取り上げていました。具体例は、ビケンテクノの事例です。
狙われるマンション積立金
管理委託に潜むリスク、信頼逆手に横領後絶たず(日経)(記事冒頭のみ)
「マンション修繕積立金の横領事件が後を絶たない。共働き家庭の増加や入居者の高齢化に伴い、管理組合業務を外部委託する需要が高まった。不正リスクを排除し資産を守るには、住民自らチェックを担う仕組みが欠かせない。」
そもそも積立金が足りているのかという問題もあるようです。
「修繕積立金が不足」36%(日経)(記事冒頭のみ)
不正でなくても...
第三者管理のマンション、修繕での「割高な身内発注」防止(2024年)(日経)(記事冒頭のみ)