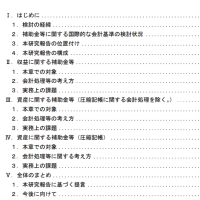財務省、公正取引委員会、経済産業省、中小企業庁、国土交通省は、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を、2022年1月19日に公表しました。
「このQ&Aは、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関し、事業者の方々から寄せられている質問、特に免税事業者やその取引先の対応に関する考え方を明らかにしたものであり、制度への理解を深め、必要な対応をご検討いただく際にご活用いただくことを目的としたものです。」
例えば、免税業者から110円で買っていたものを、インボイス制度導入で、仕入税額控除ができなくなるから、10円減額して100円にするというようなことが、独占禁止法などに違反しないかどうかが問題となりそうですが...
「Q7 仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか。
A 事業者がどのような条件で取引するかについては、基本的に、取引当事者間の自主的な判断に委ねられるものですが、免税事業者等の小規模事業者は、売上先の事業者との間で取引条件について情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定されます。
自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が、直ちに問題となるものではありませんが、見直しに当たっては、「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう注意が必要です。...」
「1 取引対価の引下げ
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施後の免税事業者との取引において、仕入税額控除ができないことを理由に、免税事業者に対して取引価格の引下げを要請し、取引価格の再交渉において、仕入税額控除が制限される分(注2)について、免税事業者の仕入れや諸経費の支払いに係る消費税の負担をも考慮した上で、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではありません。
しかし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を設定した場合であって、免税事業者が今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となり得ます。
また、取引上優越した地位にある事業者(買手)からの要請に応じて仕入先が免税事業者から課税事業者となった場合であって、その際、仕入先が納税義務を負うこととなる消費税分を勘案した取引価格の交渉が形式的なものにすぎず、著しく低い取引価格を設定した場合についても同様です。
(注2)免税事業者からの課税仕入れについては、インボイス制度の実施後3年間は、仕入税額相当額の8割、その後の3年間は同5割の控除ができることとされています。
...」
「仕入税額控除が制限される分」であれば、減額してもよいように読めますが、当然、経過措置を適用した上で計算するのでしょう。ただ、「免税事業者の仕入れや諸経費の支払いに係る消費税の負担をも考慮」するとなると、「仕入税額控除が制限される分」を一方的に減額するのは、免税業者に酷でしょう(免税業者は仕入税額控除ができないので)。
免税業者からすると、「仕入税額控除が制限される分」だけでも、大きな負担かもしれません。どさくさ紛れに、それ以上の不利な条件変更が押しつけられれば、さらに負担は増えます。
取引停止については...
「5 取引の停止
事業者がどの事業者と取引するかは基本的に自由ですが、例えば、取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対して、一方的に、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格など著しく低い取引価格を設定し、不当に不利益を与えることとなる場合であって、これに応じない相手方との取引を停止した場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあります。」
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事