自分なりに理想の音を出すべく38cmクラスのウーファー用の箱を作ったのは '80年前後のことだ。
かれこれ30数年前のことになってしまった。
当時のJAZZファンにはお馴染のJBLの43**系のシステムが欲しかったが今から見ても
普通のサラリーマンには高嶺の花みたいな値段だった。
なんとか、ユニット単体ならば買えそうだった。当時、並行輸入ものというのも出回るように
なっていたので、サンスイ経由だと5万円くらいのが、4万円弱で手に入った時代だった。
で、それ(JBL 2231A)を入手すべく馴染みの店に行ったら、見慣れぬメーカーのごついウーファーが転がっていた。
GAUSSというらしい、そのユニットは、店が手違いだかなにかで届いたそうだ。
店主いわく「ちょっと高いけど、頑丈でJAZZに向いているかも」という言葉に乗せられて
1本だけだったが買った。もう1本は日本の正規代理店になった シャープ・ブランドの
OPTONICAから購入できるとのことだった。OPTONICA経由だと、確か107,000円だった思う。
ということで、その珍しいユニットを手に入れ、いろいろあったが、赤坂工芸さんに世話になり
220Lの箱を作り、それに収めた。
が、そのGAUSSの5831というユニットは、なかなか手強くて苦労した。20年ほど格闘して
わかったことは、スタジオ・モニター用なので、度デカい音で鳴らさないと真価を発揮しないと
いうことだった。ということで、紆余曲折したが最終的にTADのTL1601系を入手した。これもなかなか手強くて
金田式のDCアンプを普通に使った場合の出力50-60Wでは制御しきれないことがわかり、
BTLで使うことでなんとか、8割くらいポテンシャルを引き出せたように思う。
いづれにしても、やっぱりスタジオやPAで使うユニットなので、一般家庭で鳴らすにはオーバー・スペックだ。
確かに会話もできない程の音量で鳴らすと スタジオ・ライクな音が出る。バス・ドラがちゃんと
床に据え付けられている感じまで出る。
が、それだけの音量で鳴らすことは稀だし、聴くのも疲れる。
仕事をリタイアしてからは家族からも 「こんな大きなBOXをこれからどうするの? 今後のことも
考えてね!!」とか言われたりしたので、ダウン・サイジングして 箱を120Lくらいにしたのが
数年前のことだ。
やっぱり箱を小さくしたことでスケール感は下がった。そして、暫くするとこの120Lの箱でも
嵩張る感じになってきた。物で溢れた部屋も整理したくなってきた。
ということで、以前から考えていた30cm径のウーファーへの取り換えということを本気で考えた。
が、今どきは小型、トールボーイTYPEが全盛の時代なので、30cmクラスのウーファーはあまり
見当たらない。ならばと、Car Audio用を捜してみた。こちらは豊富に揃っている。
米国からの直輸入の店を調べて決めたのがこれだった。
<< 先日、入手した カーオーディオ用のSUB Woofer GTO1214 >>
推奨サイズが50Lなので、手持ちの箱(70L弱)に組み込んでみた。
鳴らしてみたら、低域はかなり低い方まで出ているが、すごくボンつく音が出た。部屋のあちこちから
ビリつき音が出る。でも、なんとかなりそうな雰囲気もあるユニットのようだ。
下手な細工をせずに ウーファとして使うか、SUBウーファとして使うのがいいのか
暫く、試行錯誤することになりそうだ。
最新の画像[もっと見る]
-
 プレーヤー復活へ
2ヶ月前
プレーヤー復活へ
2ヶ月前
-
 プレーヤー復活へ
2ヶ月前
プレーヤー復活へ
2ヶ月前
-
 ORANGE社の小さなアンプ
2年前
ORANGE社の小さなアンプ
2年前
-
 MDギターの改造
2年前
MDギターの改造
2年前
-
 MDギターの改造
2年前
MDギターの改造
2年前
-
 MDギターの改造
2年前
MDギターの改造
2年前
-
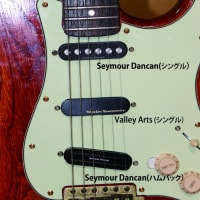 Schector改造記 番外編 その2
3年前
Schector改造記 番外編 その2
3年前
-
 Schector改造記 番外編 その2
3年前
Schector改造記 番外編 その2
3年前
-
 Schector改造記 番外編
3年前
Schector改造記 番外編
3年前
-
 Schector改造記 その5
3年前
Schector改造記 その5
3年前









