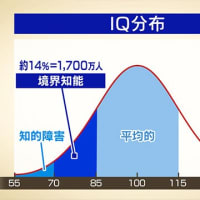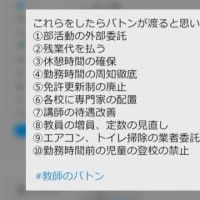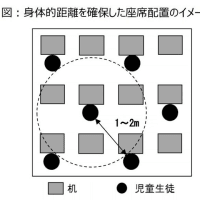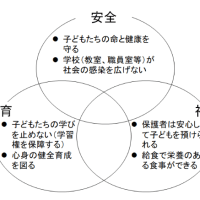重いランドセル 文科省が“置き勉”認めるよう全国に通知へ
各地の学校で新学期が始まる中、文部科学省は子どもたちのランドセルなどが重すぎるという意見を踏まえて、宿題で使わない教科書などは教室に置いて帰ることを認めるよう、全国の教育委員会に対して求める方針です。
小中学校では教える量の増加で教科書が分厚くなり、教材も増える一方、原則それらを自宅に持ち帰るよう指導しているところも少なくありません。
そのため、ランドセルなどの荷物は重量が増し、腰痛となる子どもたちも出始めるなど、対策を求める声が上がっていました。
文部科学省は全国の教育委員会などに、従来の学校の対応を見直すよう近く通知する方針です。具体的には、家庭学習で使用しない教科書や、リコーダーや書道の道具などについては、施錠ができる教室の机やロッカーに置いて帰ることを認めるよう求めています。
また、学校で栽培したアサガオなどを持ち帰らせる場合は、保護者が学校に取りに来ることを認めるとしています。
文部科学省は「子どもたちの発達の状況や通学の負担などを考慮し、それぞれの学校でアイデアを出し合って対応してほしい」と話しています。
「苦役のような通学は見直すべき」
子どもたちのランドセルの重さについて、大正大学の白土健教授が去年、小学1年から3年までの合わせて20人の児童を調査した結果、平均の重量は7.7キロでした。
小学1年生の平均体重はおよそ21キロですが、なかには体重の半分近い9.7キロのものもあったということです。
白土教授は「体重の20%から30%の荷物を長時間持つと健康に悪影響があるという話もある。子どもが毎日小学校に苦役のように通うことは見直すべきだ」と話しています。
(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180903/k10011605301000.htmlより)
実は、この件については、私はすでに自分の意見をブログで公表済みです。
こちらをご覧下さい。
その上で、今日のこの報道を踏まえ、いくつかコメントします。
まず、保護者が理性的な声を上げたことにより、学校の非合理が正される方向に動いたのは、とても良いことです。
残念ながら、学校は慣例・前例に弱いです。
「今までこうだったのだから」
「すでに定着している」
というようなルールは、何かよっぽど強い理由がないと、見直されません。
今回は、その悪習に打ち勝ったと言うことで、歓迎すべき事でしょう。
さて、この記事は、文科省の声明ではありません。
あくまで記事ですが、まぁNHKなので鵜呑みにして大丈夫だろうという若干の慢心のもとで、意見を書きます。
>>家庭学習で使用しない教科書や、リコーダーや書道の道具などについては、施錠ができる教室の机やロッカーに置いて帰ることを認めるよう求めています。
これ裏を返せば、資料集とかではない、家庭学習で使用する教科書は持って帰れって事ですかね?
この記事だとランドセルと書かれていることから、小学校を想定しているようですが
中学校は、普通の教科書だけで結構重いですよ?
そして、どこまでが「家庭学習で使用する教科書」なのかのライン引きが難しそうです。
>>文部科学省は「子どもたちの発達の状況や通学の負担などを考慮し、それぞれの学校でアイデアを出し合って対応してほしい」と話しています。
これは丸投げじゃないですかね。
こうなっては、文科省から「こういうルールに変更しろ」って出して欲しいです。
子どもの体格なんて、地域差無いんですから。
こういう言い方をされると、各学校で会議を設け、検討をしなければなりません。
そういうのが多忙化につながるのですが。
あと、実は地区ですりあわせるという必要性があります。
各校で検討した後、その結果を近隣学校の代表者が持ち寄り、大きな差が無いかどうかを確認し、あれば修正します。
そうしないと
「うちの子の学校はこれしか認められないのに、隣の○○中学校ではこんなに認められている!おかしい!!!」
と保護者の怒りをかうからです。
>>子どもが毎日小学校に苦役のように通うことは見直すべきだ
これには100%同意なのですが
実は、この通知文では、解決できないこともあります。
「重くて大変だけど、家で勉強したいから持って帰る」という真面目な少年少女がいるからです。
彼ら彼女らにとっては、「ルールだから持って帰る」が「自分のために持って帰る」に変わるだけ。体への負担は同じです。
また、今までは強いられていたから教科書を持ち帰っていて、それが少なからず家庭学習にプラスになっていたという中間層くらいの生徒が、
教科書を持ち帰らなくなることにより、家庭学習の質が低下する恐れがあります。
本当に勉強に興味が無い生徒・家庭のみ、デメリット無くメリットのみを享受できます。
ですから、この通知文は否定しないけど、もっと対応策出してよ、ってのが本音です。
私が思いつく限りの対応策は、以前の記事で提案済みです。
一番現実的なのは、分冊化なのかなぁ。
良いアイディアがあれば教えて下さい。
各地の学校で新学期が始まる中、文部科学省は子どもたちのランドセルなどが重すぎるという意見を踏まえて、宿題で使わない教科書などは教室に置いて帰ることを認めるよう、全国の教育委員会に対して求める方針です。
小中学校では教える量の増加で教科書が分厚くなり、教材も増える一方、原則それらを自宅に持ち帰るよう指導しているところも少なくありません。
そのため、ランドセルなどの荷物は重量が増し、腰痛となる子どもたちも出始めるなど、対策を求める声が上がっていました。
文部科学省は全国の教育委員会などに、従来の学校の対応を見直すよう近く通知する方針です。具体的には、家庭学習で使用しない教科書や、リコーダーや書道の道具などについては、施錠ができる教室の机やロッカーに置いて帰ることを認めるよう求めています。
また、学校で栽培したアサガオなどを持ち帰らせる場合は、保護者が学校に取りに来ることを認めるとしています。
文部科学省は「子どもたちの発達の状況や通学の負担などを考慮し、それぞれの学校でアイデアを出し合って対応してほしい」と話しています。
「苦役のような通学は見直すべき」
子どもたちのランドセルの重さについて、大正大学の白土健教授が去年、小学1年から3年までの合わせて20人の児童を調査した結果、平均の重量は7.7キロでした。
小学1年生の平均体重はおよそ21キロですが、なかには体重の半分近い9.7キロのものもあったということです。
白土教授は「体重の20%から30%の荷物を長時間持つと健康に悪影響があるという話もある。子どもが毎日小学校に苦役のように通うことは見直すべきだ」と話しています。
(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180903/k10011605301000.htmlより)
実は、この件については、私はすでに自分の意見をブログで公表済みです。
こちらをご覧下さい。
その上で、今日のこの報道を踏まえ、いくつかコメントします。
まず、保護者が理性的な声を上げたことにより、学校の非合理が正される方向に動いたのは、とても良いことです。
残念ながら、学校は慣例・前例に弱いです。
「今までこうだったのだから」
「すでに定着している」
というようなルールは、何かよっぽど強い理由がないと、見直されません。
今回は、その悪習に打ち勝ったと言うことで、歓迎すべき事でしょう。
さて、この記事は、文科省の声明ではありません。
あくまで記事ですが、まぁNHKなので鵜呑みにして大丈夫だろうという若干の慢心のもとで、意見を書きます。
>>家庭学習で使用しない教科書や、リコーダーや書道の道具などについては、施錠ができる教室の机やロッカーに置いて帰ることを認めるよう求めています。
これ裏を返せば、資料集とかではない、家庭学習で使用する教科書は持って帰れって事ですかね?
この記事だとランドセルと書かれていることから、小学校を想定しているようですが
中学校は、普通の教科書だけで結構重いですよ?
そして、どこまでが「家庭学習で使用する教科書」なのかのライン引きが難しそうです。
>>文部科学省は「子どもたちの発達の状況や通学の負担などを考慮し、それぞれの学校でアイデアを出し合って対応してほしい」と話しています。
これは丸投げじゃないですかね。
こうなっては、文科省から「こういうルールに変更しろ」って出して欲しいです。
子どもの体格なんて、地域差無いんですから。
こういう言い方をされると、各学校で会議を設け、検討をしなければなりません。
そういうのが多忙化につながるのですが。
あと、実は地区ですりあわせるという必要性があります。
各校で検討した後、その結果を近隣学校の代表者が持ち寄り、大きな差が無いかどうかを確認し、あれば修正します。
そうしないと
「うちの子の学校はこれしか認められないのに、隣の○○中学校ではこんなに認められている!おかしい!!!」
と保護者の怒りをかうからです。
>>子どもが毎日小学校に苦役のように通うことは見直すべきだ
これには100%同意なのですが
実は、この通知文では、解決できないこともあります。
「重くて大変だけど、家で勉強したいから持って帰る」という真面目な少年少女がいるからです。
彼ら彼女らにとっては、「ルールだから持って帰る」が「自分のために持って帰る」に変わるだけ。体への負担は同じです。
また、今までは強いられていたから教科書を持ち帰っていて、それが少なからず家庭学習にプラスになっていたという中間層くらいの生徒が、
教科書を持ち帰らなくなることにより、家庭学習の質が低下する恐れがあります。
本当に勉強に興味が無い生徒・家庭のみ、デメリット無くメリットのみを享受できます。
ですから、この通知文は否定しないけど、もっと対応策出してよ、ってのが本音です。
私が思いつく限りの対応策は、以前の記事で提案済みです。
一番現実的なのは、分冊化なのかなぁ。
良いアイディアがあれば教えて下さい。