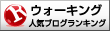紫陽花の花を見ようと宇治に出かけました。婆さんも一緒です。
四条から地下鉄に乗り京都駅まで。JR奈良線に乗って宇治まで行きました。土曜日ということもあり、車内は結構混んでいました。
宇治はお茶の町です。駅前の郵便ポストもお茶壺の形をしていました。

宇治橋通り商店街を歩き、宇治橋に出ました。交差点から見て右側の通りが縣神社に行くあがた通、左の通りが平等院に行く平等院表参道です。たくさんの観光客が平等院に向かっていました。

宇治橋の袂には、紫式部像があります。源氏物語の世界を作っていますね。



橋を渡って左手に京阪宇治線の宇治駅があります。右手の朝霧通りを行きます。途中に橋寺放生院があります。
放生院は、604年に聖徳太子の発願で作られたという古いお寺で、宇治橋を管理する寺となったことから「橋寺」と呼ばれています。




「さわらびの道」の道標もあります。源氏物語ミュージアムまで続く道です。

緩やかな坂道を上って行くと宇治上神社です。


緑の参道を進んでいくと拝殿前に出ます。


宇治上神社は世界遺産に登録されていて、今日も多くの観光客が見えていました。
拝殿は国宝です。


拝殿横には、宇治七名水の一つ「桐原水」があります。

本殿は、神殿建築として現存最古の遺構と言われています。

鳥居と青モミジが、お互いの色を引き立て合っていました。

来る時には気が付きませんでしたが、宇治神社に下りる手前に「早蕨(さわらび)」の古跡がありました。

宇治上神社から下りてくると、宇治神社の本殿の前に側面から入るようになります。


宇治神社の本殿は鎌倉時代の建築で、重要文化財に指定されています。


宇治川に向かって石段を下りて行きます。


朝霧通りにある宇治神社の鳥居です。こちら側が神社の正面です。

鳥居に前には、宇治十条モニュメント、対岸の橋島に渡る朝霧橋があります。

そこを過ぎて少し行った左手に、お茶屋さんがありその横から、今日の目的の中心である「恵心院」に行く参道があります。






境内の様子です。



恵心院は、平安時代からのお寺で、境内に様々な花が植えられていることから「花の寺」として知られています。今の時期ですと紫陽花が楽しめるのですが、今日は、まだ「咲き誇る」という状態ではありませんでした。






朝霧通りに戻り、川べりを歩き観流橋を渡って興聖寺に向かいます。対岸の十三重石塔も見えます。





直ぐに興聖寺への「琴坂」が見えてきます。参道はモミジのトンネルです。当然、秋には紅葉の名所となります。




坂道を上がって行くと、中国建築らしい竜宮門(山門)が見えてきます。


興聖寺は、江戸時代に再興されたお寺で、林羅山(はやしらざん)の銘が打たれている鐘楼は、「興聖の晩鐘(こうしょうのばんしょう)」と呼ばれています。







琴坂を下がり朝霧通りに出ます。



宇治神社の前の朝霧橋まで戻ります。

橋から見た宇治川下流、渡った先には平等院の屋根が見えます。


橋島から十三重石塔のある塔の島へと進みます。屋形船も出ていました。


鵜飼の鵜の檻がありました。産卵の時期なんだそうです。


十三重石塔は、高さ15メートルの日本最大の石塔です。1200年代、宇治橋再興の時に建立されたとのことです。



喜撰橋を渡り平等院側に行きます。


今日の平等院鳳凰堂は、入場するのに1時間程度待たなければならなかったようです。人気ですね。
私達は、平等院の裏側の道を歩き縣神社に行きました。
縣神社は、1052年に藤原頼道が平等院を建立する時に鎮守社としたものです。6月5日の縣祭りは、深夜から行われるので「暗闇の奇祭」として有名です。




宇治橋に向かって戻ります。お茶さんの前の花菖蒲が綺麗に咲いていました。


宇治橋の交差点の所にあった石の鳥居が見えてきました。そこまで行く途中に橋姫神社がありましたので立ち寄りました。
この神社は、かつては宇治橋三ノ間の張り出し部分に祀られていたのですが、洪水で流されたため現在地に移転されたそうです。橋姫は嫉妬の神としての伝説があり、それにちなんで「縁切りの神」として伝えられています。



鳥居の手前から表参道に入り、新茶を買ってきました。創業400年余りの老舗でした。


JR宇治駅に戻る途中、お昼を食べた「ゆば」の専門店のテーブルには紫陽花が飾られていました。

暑い最中の宇治散歩でしたが、見頃はまだとは言え紫陽花の花も楽しむことが出来ました。
気持ちの良い散歩が出来ました。
今日の歩数は、13,674歩。