9月に入って朝晩はめっきり過ごしやすくなりました。リーリーと聞こえてくる虫の音は自然のBGM。
さて、秋の夜長はどんな風に過ごしましょうか? 趣味の手作りをしてみたり本を読んだり・・・きっと、この方たちは疲れでバタンキュ~だと思います。^^
今週9月3日の月曜日から7日の金曜日まで、生産組合ではチャレンジ体験の中学生を受け入れています。
「生き方探究・チャレンジ体験」は平成12年から京都市が推進してきました。
地域の事業所で、興味や関心に応じた勤労・職場体験、ボランティアなどの社会体験をすることで、自ら学び、自ら考えるなどの「生きる力」を身につけ、集団や社会の一員として自分の在り方を見つめ将来の夢を育めるよう支援するものです。
また体験学習の場を地域に求めることで、挨拶などを通して地域とふれあい、結びつきを深め、地域で子ども達を育てるという機運を高めていく狙いも併せ持っています。
生産組合は春と秋に受け入れを実施、山に入って職人さんと山仕事をしたり、なかなかハードな体験をしてもらっています。

今回は衣笠中学校の2年生男子4名、全員野球部です。
8月31日に行われた出発式では「杉立くん」が決意表明をしました。何てここにピッタリな名前!と思いましたが、彼も野球部ですが残念ながら別の事業所で体験しているそうです。

場所は京北の山国。急な斜面ではなく、作業は案外しんどくなさそうです。
ところどころに人造絞のハシ(当て木)が巻かれています。作業は何かな、ハシほどき?

あ!いたいた。丸太を運んでいますよ。足元悪いけれど二人で息を合わせていっちに、いっちに。

現場の職人さんが伐採をしています。
これは「シケ木(しけぎ)」。光があまり当たらず弱い木、葉からの水分調整がうまく出来ていない木、うねりがあったりして絞りには適さないと判断された木。
このあたりだけで使われる言葉かも知れませんが、元気がない、お財布の中身が乏しい時に「シケてるよね」って使う、あの「シケ」です。

伐採は職人さんの判断。十尺竿をあてて裁断します。元末の差が小さいほど、磨丸太としての明るい未来が見えて来ます。

彼らの仕事は、この裁断した丸太の運搬作業。傷つけないように、トラックのあるところまで運びます。
最初は一人で運んでいる生徒もいましたが、二人の方が効率が良いことを発見。これも体験で得られた知恵です。
大事そうに扱ってくれているのが嬉しくもあり、次から次へと休む間もなく仕事をこなす職人さんを見る尊敬の眼差しは、この体験がとても有意義であることを語っているようでした。

こんなものを見つけました。「鹿の骨や。」と聞いて驚きの声があがります。
でもどんなアクシデントがあるかわからない、生と死が見え隠れする自然界。そんな厳しい状況の中で、北山杉も人も切磋琢磨して生きる道を見つけようとしています。

午前中にこれだけ運びました。年輪のつまった、20年くらいはたっている木。
「君たちよりずっと年上よ。」「え~っ?」
「どうしてこの体験を選んだの?」「先輩が面白いって言ってたから。」
もしかして、野球部に言い伝えられる伝説のコースになるかもです♪
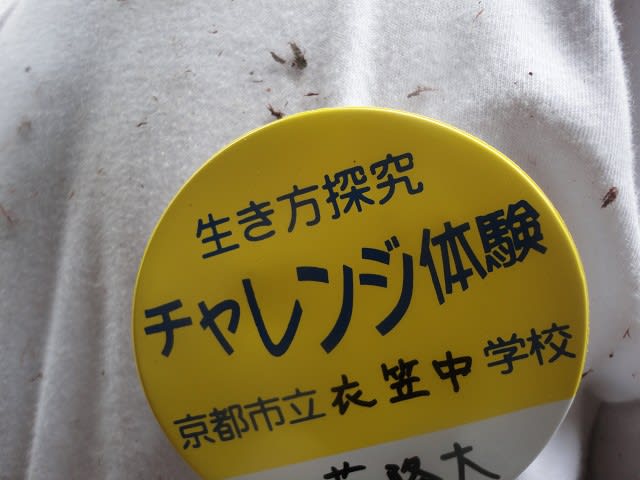
真っ白だった体操着もだんだん汚れてきました。
出発式で教頭先生が言われた「あへこじえ」は実行できていますか?
「あ」・・・あいさつをしっかりしましょう。
「へ」・・・返事は元気よく
「こ」・・・言葉遣いには気をつけよう
「じ」・・・時間を守る
「え」・・・笑顔を大切に

お昼休憩を前にちょっとドヤ顔。まだまだ午後も作業は続きました。
組合前に帰ってきた彼らに感想を聞いてみました。
丸太を運ぶのは大変だった、でも面白かった。
ムカデが出た。
職人さんはめっちゃ優しかった。
ハシを拾うのも面白かった、と手には一本のハシが。
午後4時のバスで彼らは衣笠中学校へと戻り、そしてクラブ活動です。全く元気な中学二年生。
「ありがとうございました!」と大きな声で挨拶して帰って行きました。「あへこじえ」の教訓もOK!
さあ、明日は今日伐採した丸太の皮むきです。上手に出来るでしょうか。
彼らがこの仕事に関心を持ち、興味を持って作業できるようにあれこれと準備をしています。
苦しみの果てに喜びが。その時、心地よい疲れが。少しは野球と似ているかも知れませんね。
まだまだチャレンジ体験は始まったばかり。頑張って下さい!




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます