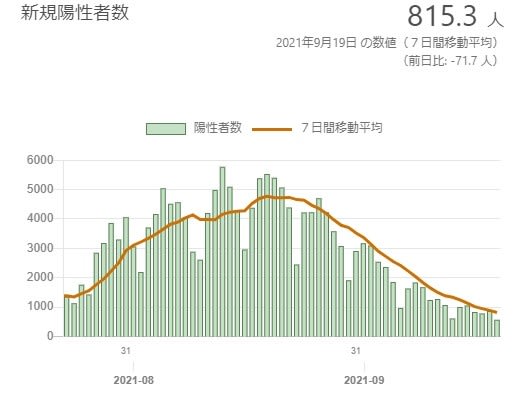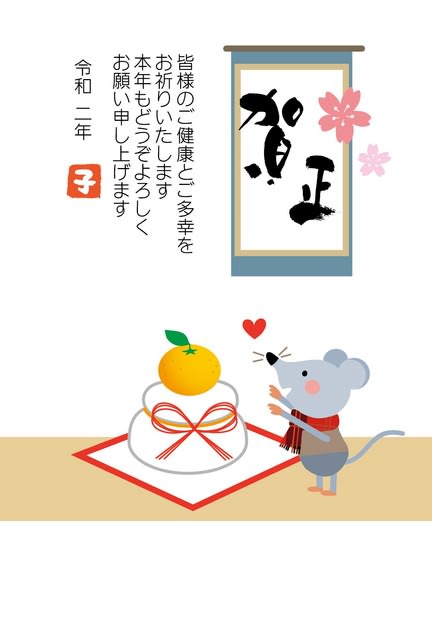みなさま(と言うほど、読者がいるとも思えないが(^^;)、あけましておめでとうございます。
それぞれに楽しいお正月をお過ごしのことと思います。
私はと言えば、紅白歌合戦見て、新年を迎えるとほぼ当時に爆睡し、元日の朝8時からビールを飲み始めるという、王道のような年末年始を過ごしております。
王道と言えば、年賀状ですが、最近は出さない人が多くなってきているのに加え、だんだんとご本人がご逝去されたというような便りも多くなり、最盛期の半分くらいに減っています。これから出す相手が増えるようなことも無いだろうし、正月早々寂しいなあと感じています。もっとも、新し好きの私としては若い人たちにLINEであけおめメッセージなどを送って喜んでいることを付記しておきたいと思います。まあ、「あけおめ」だの「ことよろ」だの、最近の子たちはもう使わないんだろうけどね。オジサン達が使い始めたら、その言葉はもう死語らしいです。
話は脱線しまくりますが、先日「絶滅危惧動作」というのがあるのを知りました。小指を立てて女性とか恋人とかを表すとか、指を回しながら電話をかけることを表すとか、そんな動作らしいです。ついつい、「え?!それってみんなまだやってるよ」と言いたくなりますが、それはこちらが既に「絶滅危惧種」側だからなんでしょう。やれやれ。
とまあ、年の初めからくだらないことを書いておりますが、正月らしく自分の年を実感しつつ、あれこれと思いを巡らすお正月です。
そんな相も変わらぬムーミンパパですが、本年もお見捨てなきようよろしくお願いいたします。
それぞれに楽しいお正月をお過ごしのことと思います。
私はと言えば、紅白歌合戦見て、新年を迎えるとほぼ当時に爆睡し、元日の朝8時からビールを飲み始めるという、王道のような年末年始を過ごしております。
王道と言えば、年賀状ですが、最近は出さない人が多くなってきているのに加え、だんだんとご本人がご逝去されたというような便りも多くなり、最盛期の半分くらいに減っています。これから出す相手が増えるようなことも無いだろうし、正月早々寂しいなあと感じています。もっとも、新し好きの私としては若い人たちにLINEであけおめメッセージなどを送って喜んでいることを付記しておきたいと思います。まあ、「あけおめ」だの「ことよろ」だの、最近の子たちはもう使わないんだろうけどね。オジサン達が使い始めたら、その言葉はもう死語らしいです。
話は脱線しまくりますが、先日「絶滅危惧動作」というのがあるのを知りました。小指を立てて女性とか恋人とかを表すとか、指を回しながら電話をかけることを表すとか、そんな動作らしいです。ついつい、「え?!それってみんなまだやってるよ」と言いたくなりますが、それはこちらが既に「絶滅危惧種」側だからなんでしょう。やれやれ。
とまあ、年の初めからくだらないことを書いておりますが、正月らしく自分の年を実感しつつ、あれこれと思いを巡らすお正月です。
そんな相も変わらぬムーミンパパですが、本年もお見捨てなきようよろしくお願いいたします。