
◆東急大井町線 等々力駅
昭和4年(1929)目黒蒲田電鉄の自由が丘~二子玉川間が開業、等々力駅は同時に開設された



◆ゴルフ橋
昭和6年(1931)に旧下野毛・等々力村に、東急電鉄が開発した「等々力ゴルフ場」に由来する。大塚古墳だけを残し周り一帯をゴルフ場として開業したが、昭和14年(1939)に廃止され、施設は空襲で焼失した。橋は昭和36年(1961)まで木橋であった。

◆等々力渓谷
武蔵野台地の南端を、谷沢川が浸食してできた延長約1Kmの、東京23区内唯一の渓谷。台地と谷との標高差は約10m。昭和49年(1974)渓谷沿いの一部を、世田谷区立等々力渓谷公園として開園、平成11年(1999)渓谷一帯の約3.5haの区域は東京都の「名勝」の指定を受けた。

崖の斜面ではシラカシ・ケヤキ・ムクノキ、斜面地上部ではイヌシデ・コナラが分布している。


玉沢橋では環状8号線が渓谷をまたいでいる

◆渓谷の湧水
30箇所以上の湧水が発生し、一部は窪地に集まって湿地を形成している。湧水が流れ出る、緩やかな斜面ではセキショウが、湧水が溜まる場所には、湿生植物が点在する。
流れ出る湧水は水路や遊歩道をつたい谷沢川に流れ込む




セキショウ トキワツユクサ


湧水が流れ込むため川の水も澄んでくる

◆等々力渓谷三号横穴
古墳時代末期から奈良時代に掛けて造成された横穴墓。6基以上発見されたが、昭和48年(1973)発見された3号横穴は状態が良好であったため保存された。奥行き13mで、内部は徳利を縦に半切したような形。等々力周辺を治めていた有力者の墓と推定される。

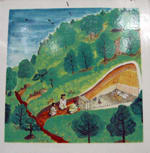
◆等々力不動尊
瀧轟山明王院(りょうごうざんみょうおういん)。真言宗中興の祖・興教大師が開いた満願寺の別院。5000坪の境内は、春の桜、秋の紅葉の名勝としても名高い


◆不動の滝
二条の滝、雄瀧、雌瀧の水が噴出している。古来より水垢離(みずごり)の場として滝に打たれる行者が絶えなかった。等々力の地名は、この滝の音が渓谷内に響き渡り「轟いた」ところからとも言い伝えられている。


◆役の行者神變窟
役(えん)の行者の像が岩穴にあり、役の行者が修行を行っていた。


◆御岳山古墳
石仏が据えられている

◆日本庭園
傾斜を活かした日本庭園は昭和48年に作庭された。昭和36年(1961)に建築された書院建物は休憩所になっている。
竹林

芳しい香りの蜜柑の花



◆野毛大塚古墳
大田区から世田谷区にかけて拡がる荏原台古墳群の一基。5世紀初頭に築かれた前方後円墳(帆立貝型)。三段に構築された墳丘には全体に河原石が葺かれ、円筒埴輪が各々の段にめぐらされていた。後円部墳丘上から4基の埋葬施設が確認され、多くの武具等が発見された。副葬品から、畿内政権と関係が指摘され、南武蔵の小豪族達の上に立つ大首長の墓と考えられている。

復元された前方部

4基の埋葬施設の図



◆谷沢川多摩川合流地点
等々力渓谷を流れる谷沢川は六郷用水(丸子川)の下を潜りぬけて多摩川に流れ込む。






















うらやましいな
役の行者って
あちらこちらで足跡を見かけますが
詳しいことを何も知らないので
一度 調べてみようと
思い立ちました
ツユクサみたいだけど
白いお花だわと思っていたのは
トキワツユクサなんですね
役の行者のこと、またお知らせください。
トキワツユクサは別名(どちらが本名?)が野博多唐草といい、南アメリカ原産の園芸種が帰化したもようです。
生命力が強く、茎が地面をはい、節から根を出して増えていきます。